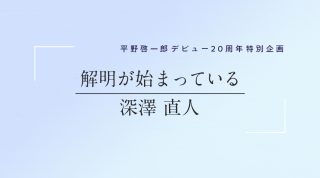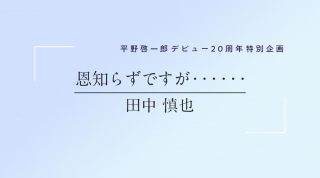2018年10月号の文學界に掲載された、平野啓一郎デビュー20周年記念企画「平野啓一郎の世界」。同誌に掲載されたエッセイ・作品論・対談記事を公式サイトでもお届けいたします。
「ある男」になりたいと願うことが、ぼくにもある。
平野啓一郎さんが提唱されている分人主義には、随分と救ってもらった。
分人主義は〝人間にはいくつもの顔がある〟ということに肯定的だ。
例えば、主婦向けのお昼の情報番組に出演している自分、深夜ラジオで話をしている自分。
プライベートで高校の同級生と話をしている時の自分。芸人の先輩と飲んでいる時の自分。
それぞれ違っていいのだという考え方が、分人主義である。
テレビの収録で「本音が言えない」と悩んでいた時に分人主義を知って、「どれも本音といえば本音なのかもしれない」と気が楽になった。
「ある男」は、その分人主義の究極の作品だという印象を持った。
本文中に〜人はなるほど、「おもいで」によって自分自身となる〜という一文がある。
例えば、日常の会話の何気ない一言でさえ、人はその「おもいで」の影響を受けているのかもしれない。
冒頭、バーにいる主人公が名前も経歴も嘘をついていたことが判明する場面から始まる。
この作品には、事情があって戸籍を売買・交換して〝自分ではない誰か〟になった男が数人登場する。
人が名前も経歴も偽って、別の誰かになりたいと願う理由とは一体どういうものだろうか。
どの分人でもバランスが取れなくなった時、〝別の誰かの分人〟を手に入れて、〝自分〟を取り戻そうとするのだろうか。
ぼくは、一人旅で海外に行くのが好きだ。
海外にいる時、外国人は当然誰もぼくのことを知らない。
海外で「ある男」=Xになることで、ぼくは空の色をいつもより青く感じられたり、スパゲティをいつもより美味しく食べられたりするのである。
一人旅ではない場合は、同行した人に対する分人を生きることになるので〝X〟にはなれない。
だから、ひとり旅でなければならないのだ。
〝X〟になることで自意識は縮小して、こんなぼくでも陽気に初対面の外国人に話しかけたりする。
そして、帰国の日が近づいてくると、東京という街の若林という人間に「ポジティブな部分もあるにはあるか」という想いがゆらりと立ち上ってくる。
帰国して空港で若林正恭に戻った時「またしばらくやってみるか」と重い腰を上げられるのである。
冒頭のバーの城戸という男も、城戸という体から一瞬でも抜けることで、楽になりたかったのではないだろうか。
ぼくも城戸も中年である。
中年になると、〝おもいで〟の量は増え、可能性の幅は狭くなる。
若い時は、その可能性の幅の広さに逆にやられそうになったことがある。
中年になると、狭くなった幅で生きていくことに退屈を感じてしまって、今自分が手にしている〝幸せ〟すらうっかり見落としてしまうことがある。
苦しみにはなかなか慣れないのに、なぜ人は幸せにはいとも簡単に慣れてしまうのだろうか。
城戸は自分以外の人間になることで、自分が手にしている〝見落としがちな幸福〟を相対化して再認識したかったのかもしれない。
ぼくは、芸人としての自分に対して後悔していることがある。
それは、芸名を付けなかったことだ。
別の名前が欲しかった。
若林正恭という本名の名残もないほどにかけ離れた芸名〝X〟を名乗っていれば、テレビでの発言もその〝X〟のコメントとしてよりハッキリと分人化できたのではないか、と。
収録中の発言は大胆になり、収録後のストレスは今よりは軽減されたものだったのではないかと想像される。
収録後、七三分けをシャンプーで落とし、ピンクベストを脱いでいる相方を見ていると「こいつは〝X〟としてテレビに出演しているから、こんなに呑気なのではないか」と疑いたくなる時がある。
そんな自分も、帰りのタクシーでドライバーに職業を聞かれた時、ふと「雑誌の編集者なんですよ」と嘘をついてみることがある。
住んでいる場所を知られたくないということもあるけど、違う誰かになることでささやかな快感を得るのは、ぼくも城戸と一緒なのかもしれない。
中年になると、どの分人にも疲れてしまうことがあるのだ。
自分を構成する要素。それには〝おもいで〟以外にも、自分のコントロールが利かない出自や環境の要素もある。
それによって苦しめられている「ある男」が、作中に登場する。
本人の気持ちなど想像することもなく、出自や環境で他者を〝こうだ〟と不当に決めつける差別。
それを受けている人の心情を、「ある男」を読むことによってより強く想像することができた。
差別を受けることによって苦しめられ、自分を構成する全ての分人を愛せなくなった人は、泣きながら公園の地面に頬を擦り付けるしかないのだろうか。
その描写を目で追っている時、胸が痛くて仕方がなかった。
〜愛にとって、過去とは何だろうか?〜
今のご時世、スペックなんていう言葉で他人を査定することも当たり前のようになっている。
「他者を愛している」と自分が宣言する時、その他者の〝どこ〟を愛しているのだろうか。その〝どこ〟に対する答えを「ある男」を読み終わった後、暗がりに手を伸ばしてかき回すように、ぼくはずっと探っていた。
分人主義の中で、〝真心〟という概念が成立するかどうかは分からない。だけど、愛するなら、愛されるなら、〝真心〟であればいいなと願ってしまった。

▶︎平野啓一郎による文学解説が聴ける「文学の森」についてはこちら