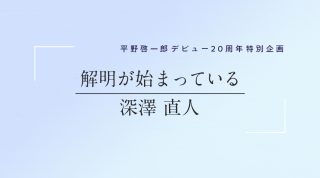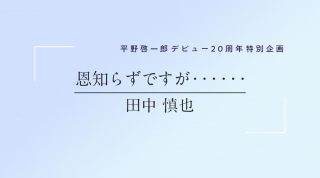2018年10月号の文學界に掲載された、平野啓一郎デビュー20周年記念企画「平野啓一郎の世界」。同誌に掲載されたエッセイ・作品論・対談記事を公式サイトでもお届けいたします。
Chute
『文明の憂鬱』のエッセイ「午後の真空」で平野啓一郎は中学時代の神秘な体験を回想する。「その時突然、私の中に真空が忍び込んだのです」――それは死を思い起こさせるというより、「何か神隠しのような突然の不在の溝への転落を想像させました」と。
ここに平野の原体験がある。
彼は何度でも、この真空、この不在への転落chuteに戻ってゆく。
新作長篇『ある男』では、原誠という男の「深手を負った物語」に、その墜落は転写される。
原の負った深手とは、父の小林謙吉が犯した殺人である。
三重県四日市市で一九八五年、ギャンブル依存症の父は、隣家の社長夫妻と一人息子を包丁で刺殺し、証拠隠滅のため放火、九三年、死刑に処せられた。
〝死刑囚の息子〟の汚名を負ったヒーローは、母方の原姓を名のり、ボクシングのジムに入って、東日本新人王トーナメントで優勝するが、「人間の最後の居場所であるはずのこのからだが地獄」、と自覚する深刻な苦悩を抱き、全日本新人王決定戦のリングに上がることを辞退した。
のみならずマンションのベランダから転落、ボクサーの夢も「パー」にしてしまったのだ。
これが『ある男』のchuteの物語である。むろん平野の愛読するカミュ『転落La chute』も含意されよう。ジムの練習仲間はこう語る。「なんかもう、どうしようもなくなって、何もかもから逃げ出したかったんじゃないですか?」。 『ある男』とならぶベストの長篇『決壊』(二〇〇八年)では、沢野崇はベランダから身を乗り出し、ドストエフスキーを思わせる独白で、みずからの飛び降り自殺を予告する。『空白を満たしなさい』(二〇一二年)の主人公にとって、彼の転落はオブセッションである。短篇集『あなたが、いなかった、あなた』(二〇〇七年)でも、そんな身投げが繰り返される(「『フェカンにて』」など)。
――『ある男』の転機となったヒーローの失墜が、いかに「新作を、前作を踏まえつつ」(同)錬成された、周到な熟慮の賜物であるかが、納得されよう。
もう一人の〈ある男〉
原誠の転落死未遂はしかし、彼自身の口から語られるのではない。『ある男』で原は一貫して客体objectである。原の〈背中〉を見つめる語り手がいる。 それは城戸章良、――弁護士だ。 城戸が原の死後、その足跡を追い、取材し、大部の報告書を作成する。 やがて、原の背中を追う城戸が、原の衝迫を背中に感じる瞬間が来る。
この神経の繊細な芥川的心性の持ち主は、妻の香織に「変なこと考えてない?」、同僚に「大丈夫、城戸さん?」と心配される。 「存在の不安」を抱えた、もう一人の〈ある男〉が、こうして長篇の〝目〟となり、一作をリードする。
「私」
城戸は作者とおなじ一九七五年生まれ。原も同年生まれらしく、まず生年により平野→城戸→原→城戸→平野と、三つ巴のサーキットが回転を始める。『ウェブ人間論』(二〇〇六年)でも、平野と対談する梅田望夫は、「一九七五年生まれの人はちょうど分水嶺に位置していますね」とコメントした。
城戸は横浜の都心に在住し、作家同様、プロで知的職業に従事する。『ある男』の「序」には、谷崎潤一郎『春琴抄』流の「私」も、ちらっと姿を見せる。平野の『本の読み方』(二〇〇六年)に、小説はマジックミラーのようなもの、「しっかりと目を凝らせば、向こう側に作者が見えるかもしれない。しかし同時に、そこに映し出された自分自身を見てしまうのかもしれない」。 「私小説が社会的に持っている機能に着目」(本誌二〇〇四年八月号のインタビュー、二〇〇七年『モノローグ』所収)した著者は、「私」という謎をターゲットにする。高橋源一郎によれば、主人公が次第に平野啓一郎に見えてくる、という意味で『決壊』は私小説なのだ(二〇一四年、『「生命力」の行方』)。本書の「序」にはマグリットの絵《複製禁止》に似た錯視も設けられる。――鏡を見る男がいて、鏡の中の男も、背中を見せて同じ鏡の奥を見る。重なりあう二人の背中。
さらに「序」は本篇の核を精確に指し示し、「読者は恐らく、その城戸さんにのめり込む作者の私の背中にこそ、本作の主題を見るだろう」。
消失点
主題とは『透明な迷宮』(二〇一四年)の一篇「Re:依田氏からの依頼」で、「肉体の遠近法の彼方に」かいま見られる「消失点」かもしれない。『マチネの終わりに』(二〇一六年)で章のタイトルになるヴァニシングポイントかもしれない。この甘美でロマンティックな味わいを持つ、クラシックな装いの小説は、ヒーローとヒロインがエレガントなフーガを奏し、「彼方の消失点で結び合っているように見える」。
谷崎の『夢の浮橋』との関連を思わせる『高瀬川』(二〇〇三年)の中篇「氷塊」にも、同一のテーマが読みとられる。上下二段からなるこの小説の明らかな構造主義に確認されるのも、少年を主役とする上段の物語で語られる、本当の母と今の母のあいだに開く、悲劇としての「空洞」なのである。
おなじ焦点/消点を、『ある男』に見る。 原誠の背中を追う、城戸章良の背中を追う、作者の背中を追う、読者の背中を追う、私の背中を追う、……つぎつぎと生起する追跡の背景には、『一月物語』(一九九九年)の「ここには何もありません。何も」、『かたちだけの愛』(二〇一〇年)の「[切断した恋人の足の先には]何もなかった」、――〈ある女〉ならざる〈ある男〉の、消えてゆく後ろ姿が浮かぶのである。
西へ
〈ある男〉が小説に初登場するのは第1章、九州は宮崎県のS市でのこと。 『日蝕』(一九九八年)、『葬送』(二〇〇二年)のフランス、『ドーン』(二〇〇九年)のSF的宇宙を別にすれば、作者は小説の舞台を西日本に設定するケースが多い。
平野は「還元主義的な」解釈が「好きではない」(『ショパンを嗜む』二〇一三年)とはいえ、北九州の工業都市で育った「田舎者であるということに強烈なこだわりがある」と言い(「毎日新聞」二〇一八年八月二一日夕刊)、古井由吉との対談で、自分は「ずっと西日本の人間だったんです」と強調することを忘れない(『「生命力」の行方』)。 『滴り落ちる時計たちの波紋』(二〇〇四年)の一篇「初七日」は作家が高校まで過ごした北九州市を舞台とするし、同書の「瀕死の午後と波打つ磯の幼い兄弟」も、九州地方の荒っぽい方言に光彩陸離たるものがある。関西弁『О嬢の物語』と称すべき『顔のない裸体たち』(二〇〇六年)の、「チンポ、しゃぶってや」といった平野ポルノの強烈なセリフにはド肝を抜かれる。
関東大震災以後、関西に移り住んだ谷崎への傾倒もあろう。『卍』の大阪弁を参考にしたい。十津川を舞台とする『一月物語』は、幻の女の「背」を追うflâneur(さ迷う人)の物語だが、平野の西への愛着が色濃く投影した作品だ。
変身
洗練の極み(『かたちだけの愛』、『マチネの終わりに』)と、野卑の極み(『顔のない裸体たち』)と。――二者の並在にこそ、平野の真骨頂は存する。 『ある男』はそうした両端の成熟した調和の成果にほかならない。
城戸の調査によると、原はボクサーを断念した後、九年の流浪の果てに、宮崎県S市の〝シャッター通り〟に姿を現す。リポーター城戸はこう推測する。「[ジムに入って来た]原誠が、S市で初めて里枝の文房具店を訪れた時も、確かそんな風だったのではなかったか」と。城戸のなかで二つの場面が溶けあうように混淆して、「それが、この世界の断片との、彼のいつもの、警戒心に満ちた触れ方だったのかもしれない」と。
里枝は本篇のヒロインの一人。離婚して横浜から宮崎に戻った中年の女性で、横浜時代に離婚の調停で弁護士の城戸と知りあい、前夫との間に悠人という息子、谷口大祐こと原誠と結婚して花という娘を儲けた。
原はそのときどきに「世界の断片」と出会う、つぎはぎだらけのアルルカンの衣裳をまとったペルソナで、出現するたびに姿を変える。平野に似た千変万化の男である。原が変わるように平野も変わる。両人は迅速な変化において遭遇する。原の短い生涯には数知れぬ欠落や穴やブランクがある。まさにブラックボックスの男というべきだ。〈空白を満たしなさい〉――そんな使嗾が聞こえる。北千住の寂れたジムのボクサーと、宮崎で林業に従事する静かな男を、同一人物と見抜くことができるだろうか?
近隣のスケッチを見せて里枝と親しくなり、結婚し平穏な家庭を営む谷口大祐なる男は、名前も職業も異にする、まるきり別人ではないか?
作家が主唱する「分人」ではないか(『私とは何か 「個人」から「分人」へ』二〇一二年)? 彼は「本当は違う誰か」ではないのか?『顔のない裸体たち』のベストシーン、その幕切れで、「お前は一体、誰なんや?」と誰何される、奇怪な和製O嬢の同類だったのではないか?
なりすまし
里枝と会う原誠は、林産業に勤める谷口大祐と名のって自己紹介した。このニセの大祐は里枝と婚姻後、わずか三年九ヶ月で伐採した杉の下敷きになって早逝。彼女は亡夫に厳しく禁じられていたのに、――一周忌を経て――群馬県で旅館を営む故人の実家に連絡した。
さっそく兄の恭一が宮崎へ飛んで来る。しかし仏壇に遺影の写真を見て、言下に「コイツは、僕の弟じゃない」と断言。「誰かが大祐になりすましてたんですよ」。
この不可解な出来事の調査を引き受けた弁護士の城戸が、谷口大祐になりすました〈ある男〉を、職業的な習慣でXと名づけ、その探索に乗り出したのだ。
平野が〈なりすまし〉を小説のモティーフとするのは、『決壊』を始めとして『ドーン』、『空白を満たしなさい』、『透明な迷宮』ほか、長短篇に枚挙の暇がない。『ある男』はその集大成である。
城戸は職掌柄「確定死刑囚の公募美術展」を観て、一家三人を惨殺した小林謙吉が描いた風景画に、見覚えがあると直観した。
Xがスケッチブックに描いた絵と瓜二つなのである。 すでに4章でXの写真を眺め、「どこかで見覚えがある顔のような気がした」。城戸は何かのメディアで死刑囚の顔を見たことがあるはず。遺伝的にもXの風貌は「哀れなほどに父親に似て」いるのだ。 「彼の純粋な心の反映のようなあのスケッチは」と弁護士は核心に入る、――「父親の獄中の絵とそっくりなのだった」。
小林謙吉には誠という名前の息子がいた。
こうして正体不明のXは、――まるで現像液に浮かびあがるプリントの画像のように――原誠の肖像とピタリと符合する。
しかし原が「身許のロンダリング」をして谷口になった経緯を解き明かすのは、城戸にとって決して容易なことではない――。
原はまず某と戸籍を交換し、その男になりすます。
仲介する小見浦なる戸籍ブローカーが、すこぶる生彩を有する。この「物悲しい、悪い冗談のような」詐欺師の男は、いかがわしくも愛すべき前代未聞のトリックスターで、丁々発止のやりとりが抜群にうまい。刑務所で城戸と面会するや、開口一番、「いや、こんなイケメンの弁護士先生に会いに来てもらえるとは!」。そしていきなり「先生、在日でしょう?」と切り出すのだ。
ついで原は小見浦を介して、谷口大祐の戸籍を買い、宮崎の辺鄙な町に現れて、里枝と結ばれ、「かわいそうに」と作中でくり返されるように、二〇一一年九月、仕事中の事故で命を落とす。
トライアングル
――東日本大震災で記憶される年である。
ここで原の数奇な運命は城戸のそれと微妙にシンクロする。
城戸は在日三世。この国が震災後とみに右傾化し、「反日」攻撃とシニシズムが蔓延、「排外主義やウルトラナショナリズムが跋扈する時代」(前出「毎日新聞」における平野の言)になり、政治的意見の相違もあって、セックスレスの妻の香織とのあいだに、一触即発の緊張が走る。
妻は「新しい上司」との浮気が怪しい。夫は「美人」の美涼にうつつを抜かす。
諍いは城戸がテレビでヘイトスピーチ特集を観ていて頂点に達する。カウンターデモの輪に美涼の姿をみとめたのだ。美涼はXの取材で親しくなったヒロイン。大祐(本物)の「元カノ」だった。――そのとき唐突にテレビが消え、妻が「リモコンをテーブルに音を立てて置いた」のだ。
香織は在日を扱うテレビ番組を、夫や息子の颯太に観てほしくなかったのか。それとも、「宮崎出張が発端だったので、彼はその相手を里枝だと思い、呆れていたが、その実、香織が予感していたのは、美涼の存在」だったのか。
夫妻のこうしたクライシスは谷崎の『蓼喰ふ蟲』以来のサスペンスだ。違いは、本作では二人の関係が終盤で修復される点にある。 『葬送』のショパンとサンド、『マチネの終わりに』の洋子とリチャード等、別離の瀬戸際にある男女を描いて平野の右に出る者はいない。
城戸、香織、里枝、大祐、恭一、美涼……の織りなす「三角形的欲望」(ジラール)は、平野練達の精緻な恋愛模様の華だろう。
Pandémie
――発端といえば、小林謙吉の殺人と死刑だった。 息子の誠は家郷との絆を絶ち、戸籍を〈洗浄〉して里枝と結婚、つかの間の「幸福」を手に入れる。
翻って里枝や、彼女の子どもたち、悠人と花の人生は狂わされてゆく。 里枝とか幼い花はまだしも、中学生になる悠人はどうか? 母親が離婚すると旧姓武本に変わり、母が〈大祐〉と再婚して谷口姓になり、それがまた城戸の尽力で武本に戻る。
自分の父は、自分は、誰だったのか?誰なのか?
悠人は名前に翻弄される。混乱する。自分で自分が分からなくなる。
この混乱は伝染性のものだ。
Xの追跡にはまってゆく城戸にも、おなじ混乱がうつる。城戸には「自分自身も不可解だった」。
この真空、この不在(前出)がXについてまわる。だれもが謎のXに感染してしまう。ロラン・バルトが『S/Z』で論述した、去勢する〈無〉の汎流行pandémieだ。
転落から不在へ、――『ある男』を私はこの流れで解した。
そして最後に新生がやって来る。
Vita Nova
最大の犠牲者は悠人である。悠人が一番「かわいそう」だ。
この災いから少年はいかにして救われるか? 死んだ義父の〈大祐〉を愛する悠人は、里枝が依頼した弁護士の報告を読み、長篇が着地するエンディングで、「蛻にいかに響くか蟬の声」という俳句を発表、全国紙のコンクールで最優秀賞に選ばれる。
この句は変身する〈ある男〉を寓意して間然するところがない。平野には「最後の変身」と題したカフカ+ランボーの文体模写がある(『滴り落ちる時計たちの波紋』)。芥川への親炙とあい俟って、悠人の遠い将来に『日蝕』で〝三島の再来〟と謳われた平野啓一郎その人を見る向きもあろう。
里枝が終章で「文学が息子にとって、救いになっている」と思うのは、その意味で解される。それは逆にいえば、文学を超える地平に悠人は出たということだ。
平野も、同様に。
――『ある男』で作家はキャリアのピークを極めたのである。
平野啓一郎最新長編小説『ある男』発売中!
https://amzn.to/2y7bkT4
平野啓一郎から直接あなたへメッセージが届く!
Mail Letter from 平野啓一郎の登録はこちらから
→ https://k-hirano.com/mailmagazine/