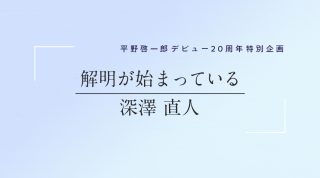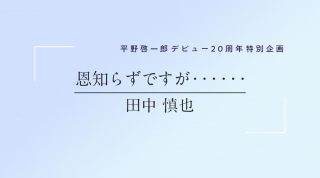2018年10月号の文學界に掲載された、平野啓一郎デビュー20周年記念企画「平野啓一郎の世界」。同誌に掲載されたエッセイ・作品論・対談記事を公式サイトでもお届けいたします。
改めて思い起こしてみると、平野啓一郎との付き合いは――もちろん書物を通してという意味だが――長い。
そのデビュー作『日蝕』から、最新長編『ある男』に至るまで、多くを発表直後に読んできた。一九九三年から二〇一一年にかけての文芸時評を集成した拙著『世界文学から/世界文学へ』(作品社)を引っ張り出して、索引を見てみると、『日蝕』から『ドーン』まで、平野作品は長短十四編を論じていることが分かる。若き天才が作家として成熟していく過程を最初から二十年以上にわたって見守りながら、同時代の文学をともに走り続けて来られたのは、幸せなことだった。
『日蝕』で登場したとき、著者は「三島由紀夫の再来」「神童」などともてはやされた。その呼称は決して過大評価ではなかったと思うが、私は当時ある紹介文で、少々エラそうに、こんなことを書いている――「前途ある若者のために申し添えておけば、日本の狭い文壇の中で「神童」扱いされて満足していてはいけない。
天才ならば目指すべきは世界。ライバルは、ルーマニアの宗教学者エリアーデやイタリアの記号学者エーコである」(『朝日新聞』一九九九年二月二十八日付)。
実際、その後の作家としての展開は期待を遥かに超えるものだった。長編『葬送』ではフランスを舞台にして十九世紀ヨーロッパ・リアリズム小説の高峰に再び上り詰めるという力業を成し遂げたかと思えば、『決壊』では一転して日本を舞台に、ドストエフスキーの向こうを張るような罪と悪の黙示録を提示した。
こういった大作の他に、手法や文体の高度なたくらみに満ちた短編の数々も生み出されていったのだが、これら短編の洗練ぶりはナボコフ作品を思わせるところがある。
この先、どこに行くのだろうか。最近の彼の長編は、初期の凝った晦渋な文体から明晰な現代的文体に転じ、プロットがエンターテインメント性を増すと同時に、その一方で作者自身の世界観や社会批判的姿勢を鮮明に示すようになってきている。その結果、より多くの読者に受け入れられ社会的に大きな存在になっていき、おそらく次の十年か二十年の間には、日本を代表する世界的な作家の一人として広く認められるのではないか。
じつはこの七月、ハーバード大学と共催で世界文学研究の集中セミナーを東京大学で実施した際、「現代日本文学の新しい声」と題して、百数十人の外国人研究者を聴衆とした特別イベントを行ったのだが、そこにゲストとして来ていただいたのが、平野啓一郎、小野正嗣、川上未映子の三人だった。これから世界の読者にもっと読まれるべきと私が考える三人の作家たちである。
平野啓一郎最新長編小説『ある男』発売中!
https://amzn.to/2y7bkT4
平野啓一郎から直接あなたへメッセージが届く!
Mail Letter from 平野啓一郎の登録はこちらから
→ https://k-hirano.com/mailmagazine/