平野啓一郎をナビゲーターとして、古今東西の世界文学の森を読み歩く文学サークル【文学の森】。
2023年9月都内で開催されたイベントでは、小説家の金原ひとみさんをゲストにお招きし、大きな影響を受けた3つの文学作品について語り合いました。
バタイユ、エリアーデ、ドストエフスキー……etc。過去の名作を語ることで、それぞれの文学観・人生観が浮き彫りになっていく、スリリングな対談となりました。

19年ぶりの公式対談!

平野:今日は金原ひとみさんをお招きして、お互いに影響を与えた3冊の本について話していきたいと思っています。お久しぶりにお会いしますね。
金原:はい、平野さんに最初に会ったのが、私のデビューしたての頃で、女性誌での対談だったのですが、その頃の平野さんは、今よりもニヒリスティックな方という印象でした(笑)
平野:そうでしたか(笑) 金原さんの芥川賞受賞作の『蛇にピアス』が非常にセンセーショナルで、当時、瀬戸内寂聴さんがすごく興奮して、「谷崎潤一郎の『刺青』が霞んで見えるわ!」と絶賛されていたのが印象的でした。僕も好きな作品なので、「瀬戸内さん気が合いますね」と話しました。
金原:大変嬉しいです。
平野:金原さんの『パリの砂漠、東京の蜃気楼』という本が文庫化された時には、あとがきを書かせてもらいました。エッセイのようにも一人称体の小説のようにも読めるような内容で、僕の大好きな作品です。金原さんのパリ滞在の様子が詳しく書いてありますが、金原さんが池袋で、酔っ払いに「ねえお姉ちゃん、そのピアス痛くないのー?」と絡まれた、という話があって、「笑ってしまった」とツイートしたら、読者から、「女性が男性に絡まれる怖さをもっと理解して欲しい」という反応がありました。そのことが心に残っていて、単行本の文庫化で解説を書くことになったとき、改めて深刻に受け止めて読み直しました。
金原:自分では、あの本は滑稽なつもりで書いたので、笑って受け止めていただいて良かったんですよ。ただ、平野さんに本当に深く、社会的な立場から読んでもらえたことは、意外でもあり、何か自分の作品が勝手に深まったような気がして、ありがたくもありました。平野さんの解説によって完結しているような作品なので、みなさんぜひ読んでみてください。
平野:では、まず1冊目、作家になる前に影響を受けた本として、金原さんはジョルジュ・バタイユの『眼球譚』(河出文庫 / 生田耕作訳)、僕はミルチャ・エリアーデの『鍛冶師と錬金術師』(せりか書房 / 大室幹雄訳)を持ってきました。
バタイユ『眼球譚』
小説という枠をとっぱらってもらった一冊

平野:金原さんはデビューの頃から、バタイユ特有の、生々しい描写が好きだとおっしゃってましたね。
金原:私はほとんど学校に行かず、小学校も行ってなければ、中学校も行ってないという状態で、本当に文学の「ぶ」の字も知らず、ただ小説を読むという読書好きの子供でした。体系的に捉えているわけじゃなくて、一つ一つの作品に出会うことが新鮮だったし、とにかく楽しむということだけを考えていました。父親が大学で創作ゼミをしていて、中2の時に一時期潜っていたことがあって、そのときに仏文好きの男子学生に、「バタイユは読んでおいた方がいいよ、『眼球譚』がおすすめ」と言われたので読んだら、グロテスクの権化みたいな、こういう世界観があるんだととにかく驚きました。文学はいろんなものをとっぱらったところに、自分の思い付きや衝動を自由に提示していいんだ、と。ちょうど小説を書きたいと思い始めた時期だったので、自分の中の「小説」という枠を全部とっぱらってもらった一冊だと思います。

平野:僕も大学時代にバタイユを読んで、影響を受けました。三島由紀夫を経由して、『エロティシズム』という理論書の方を読んでから、小説を読みました。「エロティシズム」という概念に、神との対面という過大な意味が込められているんですが、『日蝕』を書くときは、このバタイユ的な発想に影響されました。ただ、その後、瀬戸内寂聴さんと話をしながら考えたんですが、瀬戸内さんは、性について非常に世俗的なものとして話されるんです。僕自身、性行為の途中で神様が見えたりということもないですし(笑)、 性というものにそこまで形而上学的なものを期待するのはどうなのかと思うようになって書いた作品が、『高瀬川』でした。
エリアーデ『鍛治師と錬金術師』
この世界に価値を与え、現実を肯定していく

平野:入学したての頃は、大学デビューして爽やかな好青年になるんだと思って、小説を読むのはもうやめようと思ったんですよね。でも京大生協の書店に行ったら、面白そうな本がたくさんあって、その一つとして、宗教学の棚にエリアーデの著作集があったんです。それにたちまち夢中になりました。特に『鍛冶師と錬金術師』は高く評価され、エリアーデは宗教学者でもあるけれど、ノーベル賞候補になるほどの小説家でもありましたから、やっぱり文章がうまいんですよね。僕は90年代の閉塞感の中で、厭世的になるのではなく、この世界を価値化するような思考を求めていて。それが、同じく社会に不安が蔓延していた中世末期の、錬金術の話と重なったんです。

この本でエリアーデは、人間の不安の根源は、時間がとにかく一直線に流れて、いずれは死にたどり着かざるを得ない条件のもとに生きていることだと書いています。中世のキリスト教では地上の存在にも救いがあると考えられ、どんなつまらないものでも最後は善である神に至るような、目的論的な世界観に基づいています。錬金術は、その作業プロセスの体験が非常に重要で、目的論のプロセスに介入して、それを促進させ、単なる石ころを金のような存在にさせる技術で、時間の流れに介入することができる知的な体験と説明されています。賢者の石を使って錬金術を行えば、石が金になるように、無価値な世界を価値化することによって現実を肯定していく、それが当時、つまらない世の中をどう生きていこうかと思っていた僕の心にも非常に響いたところがありました。
ドストエフスキー『カラマーゾフの兄弟』
上巻は苦痛……中巻から転げ落ちるように読む
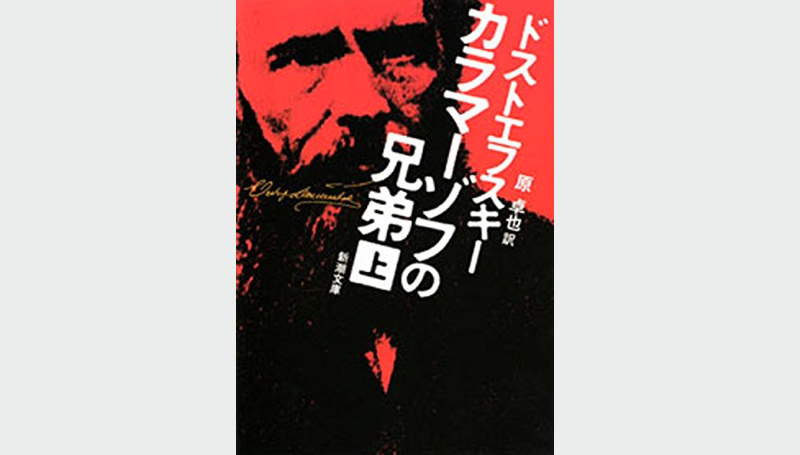
平野:続いてですが、金原さんがドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』(新潮文庫 / 原卓也訳)を、僕も実はドストエフスキーの『悪霊』を持ってきました。金原さんは、ドストエフスキー作品とはどのように出合いましたか?
金原:デビュー当時、編集担当者に、「ドストエフスキーを一切読まないままデビューしてしまったのはまずい」と言われたんです。20歳までに読むべきだと言われて、デビューしてすぐ読み始めました。上巻がすごく苦痛で「これなんの罰?」と思いながら読み進めるうちに引き込まれ、中巻から転げ落ちるようにどんどんその世界へ行くっていう体験をしました。超大作で、群像劇で、いろんな人間が出てきて、登場人物が意見を強く闘わせ合う、こういうタイプの作品を初めて読んで、すごくショッキングでしたし、登場人物たちと共に生きているような感覚を持って読むことができたんです。
平野:この小説を読んだ人に対する、よくある質問なんですけど、登場人物の中で誰が一番好きですか?
金原:私はこう聞かれると必ず、アリョーシャが好きと言うんですが、本当に好きなのは多分ドミトリーで、恐らく同族嫌悪的な気持ちがあって好きとは言えないんです。自分としてはイワン的な立場をとりたいと思っても、実際にはドミトリー的な感覚でしか生きられない。そういうふうに物語の人物を、話し手と共有して使えるのがとても楽しいなと思います。
平野:そうですね、海外の作家と会ったときにも、共通の話題になりますよね。僕もやはりドミトリーが好きで、圧倒的に迫力を持っていると思います。古井由吉さんとお話ししたとき、「西洋の文学をやってきた人間としては、イワンが話し出すとほっとする。けれど、ドミトリーにはやっぱりロシア的な曰く言い難いものを感じる」というようなことをおっしゃっていました。キャラクター造形がとても極端ですよね。
金原:そうですね。現代だとここまで盛り上がる設定は作れないだろうと思います。ただ、人物を書き分けて、それぞれ見えている世界の違いを表現するところは、自分の作品に影響を与えていると思います。
ドストエフスキー『悪霊』
「苦しい」物語は読めないけど、「悲しい」物語は読める
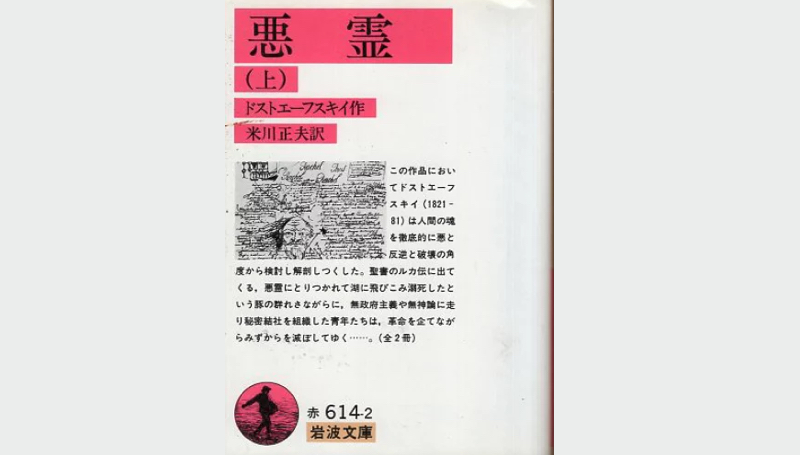
平野:僕は『悪霊』(岩波文庫 / 米川正夫訳)を持ってきました。パリに行った頃にずっと読んでいました。『決壊』という小説を書く時に、ドストエフスキーの技巧を意識して読み直しました。ドストエフスキーは、会話の合間に身体の描写が多いんですよ。歯ぎしりしてガチガチだったとか、手がブルブル震え出したとか、身体感覚の過剰な描写が魔術的な効果を持っているんです。読んでいると、読者の自律神経に影響がでて、ドキドキしながらのめり込んで本を読んでしまう、そのせいで具合が悪くなったりします。『決壊』ではその技巧を使って、身体の描写を増やしたんですよ。すると効果がありすぎて、読者から「読んでいると苦しくなる。」という感想をもらって、言葉の効果に感心もしましたが、それもさじ加減が必要だと思わされました。
金原:私も『蛇にピアス』(集英社)を書いたときに、スプリットタンを作るときの描写が生々しくて、「痛くて読めなかった」というようなことを言われたりしました。引き込ませる力があると同時に、人を排除してしまうところもあるので難しいです。拒絶されてしまうこともありうるんですよね。

平野:そうですよね。「悲しい」物語はみんな好きで読めるけれど、「苦しい」物語は読めない。僕たちが今の社会に生きていて書くべきことには、苦しみが根底にあるので、それを書かなければと思います。その苦しさがうまく悲しさのような形で描かれてると、みんな受け入れやすいのだけど、苦しさが苦しいままだと読むのが辛くなるんですよね。ドストエフスキーは、登場人物は苦しんでるんですけど、読めてしまう。
金原:そうですね。現代人が読むとかなりハードルの高い、苦しいものではあると思うんですけど、でもなんだかユーモラスな力があるんですよ。抜け感があるんですよね。ドストエフスキーは、女性の描き方も優れていると思います。女性の”わからなさ”や”手に負えなさ”というのを受け入れた状態で書いているのが潔いし、女性からみても嫌じゃないのが稀有だと思います。男性の欲望を安易に受け入れないところも魅力的ですね。
▶︎後編につづく
(構成・ライティング:水上 純)


