平野啓一郎の短編集『高瀬川』(講談社文庫)収録の短編「追憶」を、朗読と動画によって再表現する映像作品を公開しました。平野啓一郎が寄せた文章とあわせて、お楽しみください。
【『追憶』について(平野啓一郎)】
私の父はまったく健康な人でしたが、36歳の時、勤労感謝の日の祝日に、家族で一緒に昼食を摂り、畳で横になっていたところ、突然、心臓が止まって急死しました。
この事実は、私の思想に、今に至るまで大きな影響を及ぼしています。
母はその時、台所で洗い物をしていました。私は、母の手の中の皿を打つ水道水の一本の線を幻視します。最初に異変に気づいたのは、当時9歳の姉で、私は1歳半でしたので、その場の出来事については、実際はまったく覚えていません。多分、何も分からずに、その辺をウロウロしていたのだと思いますが、母や姉の記憶から、その時私がどうしていたのかは、すっぽりと抜け落ちています。
私はずっと、自分はハイハイをしていたのだと思い込んでいました。しかし、大人になり、自分で子供を育て始めて、1歳半ならもう立っていたはずだということに初めて気がつき、自分の想像上の記憶を修正しました。私は、1歳の子供が立つことが出来る、ということを、それ以前から知っていましたが、何故か自分の思い描いていた情景とは結びつかなかったのです。
当然、私は、生前の父のこともまったく覚えていません。
父がどんな人物だったのか、ということだけでなく、この突然死についても、私はその後、母や姉に繰り返し質問し続け、説明してもらいました。この経験は、言葉で不在の存在のリアリティを伝えようとする、私の今現在の小説家としての仕事と深く結びついている気がします。母と姉が、愛情を以て、愛する人の生と死を、何も知らない幼い私に語ろうと努力していたことに感謝しています。
父の死の光景を思い描こうとすることは、私にとって、母や姉の言葉が喚起したイメージによる、擬似的な、断片的な「追憶」の形を取るようになりました。私の記憶は、それらの言葉抜きに、直接的にその光景に至ろうとしても、完全な空白にしか辿り着けないのです。とにかく、この目で見ているはずなのに、その決定的な出来事について、私は何も覚えていないのです。
ただ、近くに沢があったために、「沢の家」と呼ばれていたその家は、母と姉と、2歳半で北九州に転居してからもしばらく維持されていましたので、その後、度々訪れる機会がありました。そのことはよく覚えています。従って、私の架空の「追憶」は、その少年時代の実際の記憶と混淆しています。
父の死については、後に『空白を満たしなさい』(2009年)で主題化しましたが、短篇集『高瀬川』(2003年)執筆時のこの変則的な形式の詩は、私が父の死という記憶のない原体験にどうにか到達しようとしていた試行錯誤自体の最初の作品化です。
この当時、創作に関しては、次のような発見について考えていました。
一つの作品を書く時、そこでは、使用可能な語彙群が自ずと定まります。これは、執筆の実践では、言葉の取捨選択という形を取るのですが、その語彙群から外れた言い回しや比喩表現を用いようとすると、非常に強い違和感を覚えます。この排他性は、かなりハッキリとしているのですが、同時に理屈では説明のつかない、多分に感覚的な判断です。
私は、その語彙群の同一性が何であるのかに関心を持ち、取り分け、その比喩の集合に着目しました。と言うのも、一つの主題を即時的に、また即事的に記述して行く表層の文章の語彙群の同一性よりも、原理的には自由であるはずの比喩群のプールの同一性の方が、遥かに不可思議に、神秘的に感じられていたからです。象徴派の詩人たちが、そこに魔術的な照応関係を実体的に見ようとしたがった理由がよくわかります。比喩にも、たとえ異化作用を狙ったものでさえ、明らかに、作品にとって不調和なものがあります。
この即時的/即事的な文章と、自由に奔出する比喩との双方に亘る語彙群の同一性は、恐らく相互依存的な性格のものでしょう。勿論、意識と無意識の関係とに擬えて理解することも可能でしょうが、そう単純化してしまうことで、零れ落ちてしまうものもあるでしょう。そして、この同一性は、表現しようとしている主題自体に由来するものであり、従って、その解明が主題全体の顕示に直結するのではないか、というのが、私の予感でした。
私はこの方法の実験として、私にとって最も語ることが困難だった父の死を主題として選びました。何故なら、それはどこまでもイマジナリーな領域で、即時的/即事的文章は、どこまでも比喩群と近接しており、両者の同一性は最も顕著であるように感じられていたからです。
私はまず、父の死について私が思い描いた情景を、隠喩に満ちた一篇の散文詩にしました。そして、その表層の文章と比喩群とを、両者の同一性に基づいて個々に交換可能な二つのグループと見做し、それらを恣意的に組み合わせて、表層の文章を比喩表現化し、また比喩表現を表層の文章化して、父の死の情景のイメージを断片的に変奏し続け、多層化しました。それは、その語彙群の自由な組み合わせによる、同一性の新しい具体的な提示の連続であり、その集積が、最初の詩単体よりも、そもそも到達不可能な父の死の情景に、私を(そして読者を)より接近させるのではないかと考えたからです。しかし、実際は、「事実」に接近しようとしつつ、長年、私が想像上の父の死を巡って作り上げてきたところのものが何だったのかを明らかにする、ということに他ならなかったでしょう。
方法として、最初の詩に用いられたすべての言葉を使用し、見開きごとに、その自由な組み合わせが明滅する仕掛けにしました。これは、印刷された本というメディアの見開きの構造に依拠した発想です。そして、この実験は、最初の思いつきよりも、遥かに成功したように見えました。何故うまくいったのか、私自身は、未だに説明しきれないところがあります。
既に18年前の作品ですが、以前から、この『追憶』を、ネット上で、動画と朗読によって再表現する可能性を検討してきて、今回、コルクの協力を得て、ようやく実現に至りました。
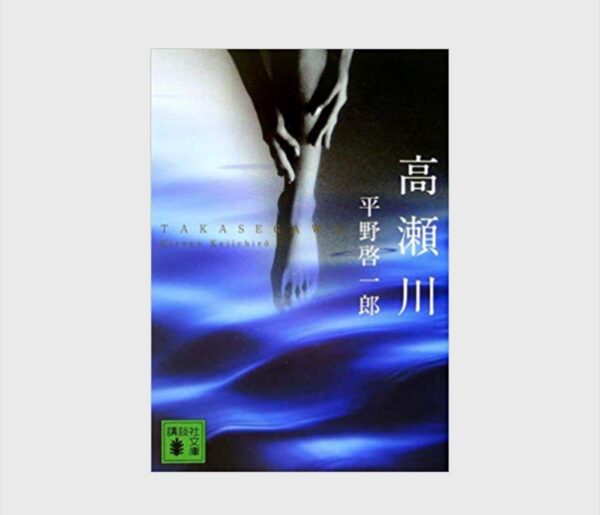
小説家と女性ファッション誌編集者が京都のラヴホテルで過ごす一夜を描き、現代の性という主題に対峙する「高瀬川」他全4篇を収録。実験的手法で文学の豊穣な可能性を開示する短篇集です。こちらより試し読みもお楽しみいただけます。ぜひ動画作品と併せてお楽しみください。


