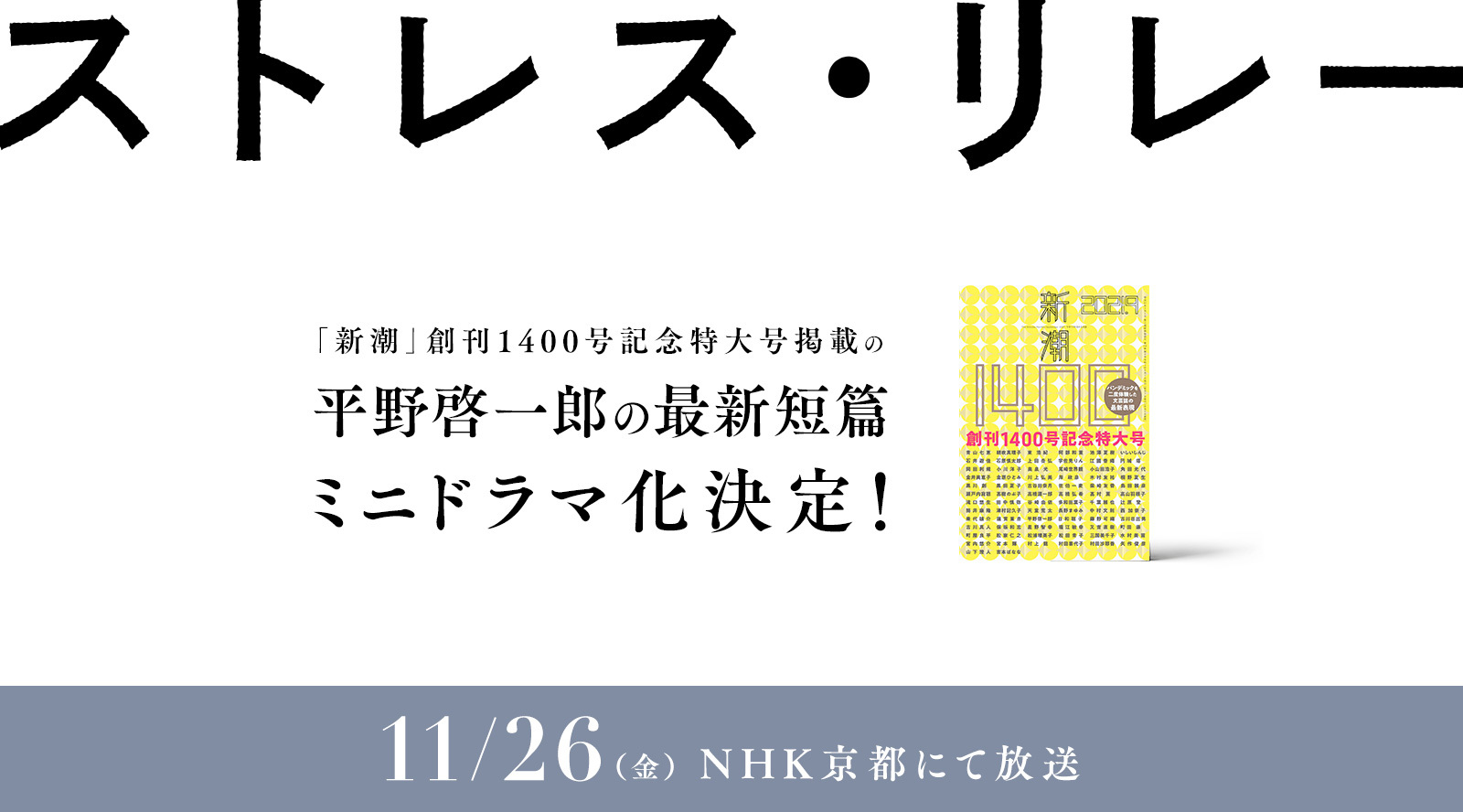人から人へ伝染し、アメリカから京都に持ち込まれた「ストレス」の連鎖と、それを断ち切った一人の英雄。
今年の夏に「新潮」創刊1400号記念特大号に掲載された短篇『ストレス・リレー』が、11/26(金)放送のNHK京都スペシャルでミニドラマ化されました。

ドキュメンタリーのような独特のテイストで、日常のストレス連鎖を非常にリアルに描いたドラマです。おかげさまで大変多くの方々から共感の声をいただいています。
出演は、川島海荷さん、近藤芳正さんの他、京都市在住の劇団の俳優の方々。
【NHKプラス】より11/29(月)〜12/10(金)期間限定で全国配信されますので、京都府外の方もお楽しみいただけます!

さて、ドラマ化記念!
ということで、こちらの公式HPで『ストレス・リレー』の全文原稿をお届けいたします。
もしこの小説を広めたい!と思ってくださった方は、SNSなどでもご感想いただけましたら幸いです。
それでは、平野啓一郎の最新短篇をどうぞお楽しみくださいませ。
『ストレス・リレー』 平野啓一郎
ルーシーは、英雄である。しかし、彼女はそのことに気づいておらず、周りの誰もそう思っていない。つまり彼女は、文学の対象であり、小説の主人公の資格を立派に備えているのである。
彼女の英雄性を示す物語は、どこから始めても、恣意的であろうが、ひとまず、二週間前のシアトルに遡るのが良いだろう。
1
小島和久は、ルーシーとは、縁もゆかりもない男である。多分、一生、顔を合わせることもなく、どこかで偶然、擦れ違ったとしても、お互いに何とも思わないに違いない。
しかし、追跡可能な範囲では、この物語の発端に相応しい人物である。
彼は、機械メーカーの社員で、今年四十四歳である。五年間の予定のシアトル勤務も、残り一年弱というタイミングで、「話がある」と急に本社から呼ばれ、一時帰国するところだった。理由ははっきりと告げられていない。が、いずれ、人事に関することであり、あれこれ考え出すと気が重かった。それとも、あの話だろうかと、こちらで隠している事柄が幾つか、思い当たらないでもなかった。
午前十一時半発のフライトで、今日は八時半に自宅を出て、タコマ国際空港まで自分で運転をした。妻と中学生の娘は、留守番である。
昨夜は、溜まっていた仕事を終えられず、深夜二時まで起きていた。機内で寝るつもりだったが、急なことで、エコノミー・クラスの真ん中の座席しか取れず、先が思いやられた。
搭乗手続きを早々に済ませ、税関を通ってから、彼は、飛行機が一時間遅れていることを知った。ラウンジを使えないこんな日に限ってと、わざと汚い英語で独り言を言った。搭乗口も変更されており、随分と歩かされた。
トローリー・ケイスを引っ張りながら、本社での話によっては、残り一年をそう楽しい気分では過ごせなくなるだろうということを考えた。
ロックが好きで、昔からアメリカ暮らしに憧れていて、赴任してすぐに、一人で、郊外のグリーンウッド・メモリアルパークにジミ・ヘンドリックスの墓参りに出かけた。
墓石そのものは案外、小さかったが、ドーム型の霊廟に蔽われていて、壁面の肖像画には、無数のキスのあとが残されていた。それを見て、アメリカだ、と感動し、FBで写真をシェアして、日本の昔のバンド仲間に感心されたのが懐かしかった。
恐らく、海外赴任はこれでお終いだろうが、日本の凋落は、外から見ると気が滅入るほどで、駐在員たちとは、酔うといつも「憂国」談義になった。妻も子供も、ここでの生活を気に入っていて、今回の一時帰国に不安な予感を抱いている。
仕事を変えてでも、アメリカに残る方法を考えるべきだろうか。……
搭乗時間まで、まだ二時間半もあり、小島は途中でフードコートに立ち寄った。カフェの前には三組が待っていて、メニューの表示を遠くから眺めつつ、最後尾に並んだ。
すると、大柄の白人の女性が、彼を押しのけるように、無言で割り込んできた。突然のことに面喰らって、「すみません、並んでたんです。」と後ろから声をかけた。女は振り返らなかった。もう一度、言ってみたが、やはり無視された。腹が立ったが、ひょっとすると、耳が不自由なのだろうかと、前に回り込んで、「すみません、僕が並んでたんです。」と身振りを交えて言った。更に一つ前の男性が、驚いて振り返ったが、しかし、彼女は、目を合わそうともしなかった。
こうなると、為す術がなかった。たかがコーヒーの順番くらいと思う余裕もなく、小島は、尋常でなく頭に来た。店員が、このやりとりを見ていたかどうかはわからなかったが、次を呼ばれると、彼女は何事もなく前に進み、一転して柔和な笑顔で会話を始め、クリームがたっぷり乗ったアイスラテを注文した。
搭乗便はその後、遅延の告知を繰り返し、結局、四時間遅れの出発となった。その時間を、独り無言で過ごした小島の憤懣は、疲労も相俟って大変なものだった。しかし、その怒りは、どこか力が入らないような、胸の奥底でいつまでも立ち上がれないような、激しい割に無力なものだった。
機内はさすがに日本人が多く、アナウンスも英語と日本語とで、そのことに安堵している自分に気がついた。
あれは何だったのか? シートベルトのサインが消えると、恐る恐る背もたれを倒し、肘置きに辛うじて触れる程度に肘をかけて目を瞑った。彼女の人格的な問題なのか、機嫌なのか、それともやはり、アジア人として差別されたのか。――わからなかった。それほどのことにさえ、確信を持てない自分の四年間のアメリカ生活を思った。動画でも撮影しながら、もっと強く抗議すべきだったのではないか。今なら幾らでも、その言葉が思い浮かぶのだが。
十一時間のフライトの後、羽田に到着したのは、夕方の七時頃だった。機内ではほとんど眠れず、映画を三本見て、仕事のメールにひたすら返事を書き続けていた。
頭がぼんやりしていて、疲れていたが、それよりも、胸に蟠っていた憤りが、時間をかけて増殖し、血の流れに乗って体の隅々にまで拡がってしまったような感じだった。勿論、熱もなく、どこか具合が悪いというわけでもないので、検疫は、彼がシアトルから厄介な「ストレス」を国内に持ち込もうとしていることなど、知る由もなかった。
小島は、お粗末な機内食のせいで、腹が減ったような、減ってないようなという感じだったが、手荷物受取所を出てから、空港の中の蕎麦屋に向かった。蕎麦と言うより、無性に天ぷらを食べたくなったのだった。
店内は混み合っていて、大きなスーツケースを入口で預け、端のテーブルに着席すると、作務衣にエプロン姿の若い女性店員が注文を取りに来た。
「ビールと天ぷら蕎麦。」
「あ、……すみません、天ぷら蕎麦が終わってしまいまして。」
「そうなの? なんだ、天ぷら蕎麦が喰いたかったのにな。……ま、いいや、じゃあこの鴨南蛮せいろ。」
「かしこまりました。少々お待ちください。」
短く黒い髪の、少しおどおどしたような店員を、小島は大丈夫だろうかと見上げた。
ビールは、いつまで経っても出てこなかった。携帯の充電も切れてしまい、イライラしながら、また、考えるつもりもなく、あのタコマ空港での割り込みのことを思い出した。自分を無視した女が、店員と談笑していた表情が頻りに脳裡をちらついた。
痺れを切らして、ビールの催促をしようと、先ほどの店員を呼びかけた時、彼は彼女が、別のテーブルで天ぷら蕎麦の注文を受けているのを目にした。
「すみません、ちょっと。ビールまだ? あと、天ぷら蕎麦、終わったんじゃないの?」
小島は、視線で促しながら尋ねた。
「あ、……えっと、すみません。……」
彼女は、叱られたようにその場に立ち尽くした。
「いや、すみませんじゃなくてさ、あるの、まだ?」
「……少々、お待ちください。」
店員は、急いで厨房に確認に行き、戻ってきた。
「すみません、やっぱりもう終わりだそうです。」
「いや、じゃあ、あっちのお客さんのは?」
「すみません、もう一名様分だったらあったみたいで。」
「ハ? じゃなんで、俺に言ってくれないの? こっちに先に言うべきじゃない?」
店員は、頬を紅潮させて黙ってしまった。小島は、『何なんだ、このボケた店員は?』と呆れながら、自分が、シアトルの空港とは、まったく違った状況で、またしても相手の無言の前に、為す術を失ってしまったのを意識した。そして、今まで経験したことがない類いの頭痛に顔を歪めた。
厨房から、蕎麦を早く運ぶようにと呼ばれて、店員は後ろを気にした。
「……すみません、あちらのお客様に言ってきます。」
「いや、いいよ! 悪いだろう、それも。――ああ、もういい。もういいよ!」
小島は、派手に椅子の音を立てて、出て行くつもりで立ち上がった。しかし彼女は、咄嗟に暴力を振るわれると思った様子で、後ろに飛び退くと、その場で到頭、泣き出してしまった。
2
竹下亮子は、朝から蒼白の顔色だった。
いつも通り、大井町からJRに乗り、寿司詰めの車中で、ドアの側に立って目を瞑った。立ったまま寝てしまいそうな気がしたが、どうせ熟睡できるはずもなく、少し眠った方がいいのではと思った。
昨夜は、娘がまた、酷く荒れた日だった。勤務先の羽田空港の蕎麦屋で、天ぷら蕎麦の品切れを伝えたところ、客が怒って、怒鳴りながら店を出て行ったらしい。その応対をまた、店長にしつこく叱られたらしかった。
娘は〝難しい子供〟だった。これまで、薄氷を踏む思いで、彼女の出来ることと出来ないこととを理解し、感情の揺らぎに付き合いながら育ててきた亮子は、接客業は難しいだろうと、最初から思っていた。
それでも、娘が自ら望んだことであり、頭ごなしに否定はしなかった。試してみて、もし少しでも出来ることが増えるならば、それは娘の生きていく可能性が広がるということなのだから。駄目だった時には、そこからまた長い回復期が必要だったが。――
目を開けて、携帯を覗き込む車中の人々に目を遣った。
疲労さえなければ、娘もほとんど、普通に生活することが出来る。
もしこの世界が、今よりほんの少しゆとりがあり、優しさに溢れているのであれば、娘は決して、特別ではないはずだった。
娘の性格的な偏りに気づいて以来、もう十年以上が経っている。正確には、診断名がついて以来と言うべきだったが。
人から見れば、過保護としか思えない親子関係だが、それを揶揄され、時には注意さえされる度に、彼女は反発し、傷つき、いつの間にか、友人関係も希薄になっていった。
昨夜の一件も、人に話してみたところで、誰がまともに取り合ってくれるだろうか? 接客をしていれば、質の悪い客もいるが、殴られたわけでもなければ、長々とクレームを言われたわけでもない。二十代にもなって、親に甘えすぎではないのか? 当の客も、自分の怒鳴った店員が、まさか夜中の三時まで母親相手に泣き続けていたなどとは、想像もしていないだろう。
それでも、そういう人間もいるんです、としか言いようがなかった。
元々、限界が近づきつつあったこの一週間ほどの悪いタイミングで怒鳴りつけられたために、娘はもう、その場で、何も考えることが出来なくなってしまった。頭の中が、全部、燃えてなくなってしまう感じと、いつか彼女は説明した。そういう時には、だからただ、静かな場所で休ませてやる以外にはないのだった。
車両が揺れる度に、二の腕を手すりが強く押した。ベッドに寝たまま起こさずに来た娘のことを心配した。今日は一日、仕事中に、急な連絡がないといいが。……
それから、窓に顔を向け、娘を怒鳴った男のことを考えた。四十代半ばくらいだという。そんないい歳をして、天ぷら蕎麦が食べられなかったくらいで、店員に声を荒らげるというのは、どんな人間なのだろうか?
願いの中には、決して叶わないと分かっているからこそ、強く願うことの出来るものがあった。
亮子は、その見知らぬ男を憎んでいた。シアトルから持ち帰られたストレスは、娘を介して、今や彼女にまで感染していた。そして、今朝の疲労のすべてを込めて、死んだらいいのに、と思い、何度も胸の裡で繰り返した。今、こうしている間にも、どこかで死んでくれたらいいのに。――そう思うと、少しだけ胸が楽になった。
死そのものを望んでいるのでは、多分なかった。ただ、この世界に最初からいなければ良かったのにと思い、今からでも、いなくなってほしかった。そうしたら、娘にもそのことを教えてやろう。……そう思った次の瞬間、彼女は、一つの考えに慄然とした。ひょっとすると、その男性客にも、性格的な偏りがあるのではあるまいか、と。
品川駅で一度、人に押し流されるようにホームに降りて、今度は、車両の奥深くに運ばれた。彼女が私かに、一人の人間の死を願っていたことに気づいた乗客はいなかった。
メッセージの着信を知らせる振動に、亮子は頬を強張らせ、首許に汗の蒸れを感じた。無視できずに、思い切って携帯の画面を覗いた。しかし、着信は娘からではなく、ここ数日、毎日届いていた高校の同窓会の連絡係からだった。
「何度もすみません! 会場の予約の関係があるので、出欠だけでも今日中に教えて下さい。忙しいのに、急かしてごめんね。よろしくお願いします!」
亮子はその文面を読み、「ごめんね。」のあとに付された絵文字を見つめた。特別、親しかったわけではなく、卒業以来、ずっと連絡を取っておらず、ただ、だからこそ、今会えば愛想良くお互いに会話を交わすであろう旧友の一人だった。
亮子は、そのへりくだった気づかいにつきあうことを、この時、酷く億劫に感じた。そして、昨日までは、返事をしなければ、と思っていたその連絡に対して、出来れば自分の不快感が、誤解の余地なくはっきり伝わってほしいとさえ願いながら、そのメッセージを削除し、返信しないことにした。
3
寺田佳代子は、職場の不動産会社でも、酒豪で有名だった。
若い頃にはその〝つきあいのよさ〟で随分と重宝されたが、四十歳を過ぎた頃から、却ってその〝つきあわせたがり〟が、殊に若い部下たちから疎まれるようになっていた。時代の変化もあった。
本人も、そのことは自覚しており、独身だからと思われるのが嫌で、近頃では、家で一人で飲むことも増えていた。これも、コロナ禍で身についた習慣だった。
それでも、この日彼女が、急遽、四人を引き連れて福山駅前の居酒屋に向かったのは、昨日来のストレスのせいで、どうしても、飲まずにはいられなかったからだった。
彼女は、来月予定されている高校の同窓会の連絡係を任されていた。幹事が親友で、手伝うことになったのだったが、あまり喋ったこともない旧友に、この歳になって急に連絡を取るのは、楽ではなかった。特に相手が、上京して活躍している、という噂を耳にしている時には。
佳代子は福山が好きで、附属高校から受験して広島大学に進学した。卒業後、福山で就職して今に至るので、他県に住んだことは一度もない。その「地元愛」を、ずっと自慢にしていたのだが、今回、連絡先の分からない級友たちを、ソーシャル・メディアで検索し、その生活の様子を――というより、人生を――眺めているうちに、何か奇妙な胸騒ぎを感じた。何と表現していいのかわからなかったが、これじゃないの?と、人から差し出されるように、「劣等感」という言葉ばかりが思い浮かんだ。
丁寧な、しかし、明るい口調で県外の六人に書き送ったメッセージには、意外にも、すぐに全員から返事が来た。参加可能なのは、二人だけだったが、それでも上首尾で、欠席の返事にも気づかいが感じられた。ただ、最後の一人だけは、「予定を確認して、すぐにご返事しますね。」という返信以降、連絡が絶えていた。佳代子は、幹事にせっつかれて、二度、メールを送信し、昨日、最後の確認を送っていたが、結局、音沙汰はなかった。
その無視には、多忙な人が、面倒臭いことに対して示す苛立たしさが、隠しようもなく表れていた。佳代子は努めて気にしないようにしていたが、その無視を通じて感染したストレスは、一日経って、却って症状が重くなっていた。
飲み会につきあったのは、同じく酒好きで、この日も問答無用で引っ張って来られた上司の吉岡、昔から彼女の押しの強さに弱く、子供の受験勉強の面倒を、急遽、看られなくなったと、妻に電話で謝った同期の斎藤、それに、二十代後半の女性の部下の織田と、三十代前半の男性の部下の田代だった。若い二人は独身だった。
吉岡と斎藤との間に、事前に話し合いがあったのか、一次会は、ほとんど吉岡が独りで喋り、それに斎藤が合いの手を入れて、楽しく二時間半を終えた。大方、今日は何となく荒れそうだからと、吉岡がその場を引き受けたのだろう。彼は、そういう人間だった。
それでも、あまり酒は進んでおらず、佳代子が注文を促すと、「いや、最近は、昔ほど呑めんようになってね。」と、すまなそうに笑った。佳代子は驚いたが、何となく、自分が取り残されてしまった感じがした。
彼女は勿論、それでは収まりがつかないので、更に皆を二次会に誘った。斎藤は謝りながら、織田はさっぱりと一次会で帰ると言った。田代もそのつもりだったが、「田代君はまだいいでしょう? ね? よし!」と逃げ遅れてしまった。
歩いて移動しながら、佳代子はうっかり携帯を覗いたが、やはり、竹下亮子からの返信はなかった。
彼女のストレスに、アルコールは明らかに悪く作用していた。
二次会は、バーのテーブル席だったが、彼女は乾杯して、ハイボールを飲み始めるなり、田代が今日、提出した資料で、パワーポイントのグリッドから、添付した写真が一ポイントズレていたことを蒸し返し、嫌味を言った。吉岡は、「まあまあ、」と宥め、「なんか、お前の飲み方も、昭和のオッサン臭が漂ってきたなあ。」と苦笑して、それとなく田代を庇った。
佳代子は、普段から悪洒落を言い合う上司のその一言に、この時、何となく傷ついた。そして、酔いはまた、一段と悪い方へと進んでいった。
田代は元々、こんな酒宴が大嫌いで、挙げ句に説教までされて、ほとほとウンザリしていた。
佳代子はそれから、到頭、胸にしまっておくことが出来ず、自分がこの一週間ほどの間に経験した同窓会の連絡係の話をし始めた。長い経緯の説明があり、自分の中に、附属出身だという十代のエリート意識と、東京に進学し、有名企業に就職した友人たちへの劣等感とが同居していることに、今回、初めて気がついたと自己分析した。そして、旧友に連絡をしながら、何となく、こちらの人生の時間が止まってしまっているような寂しさを覚えたこと、それにしても、幾ら忙しいからと言って、返事一つ寄越さずに無視するというのは、酷すぎるといったことを、一人で二時間近く、喋り続けた。
吉岡は、時々、ユーモアを交えて相槌を打っていたが、田代にとっては、その一言一句すべてが完全にどうでも良いことで、終いには、このままここで会社をクビになっても構わないので、彼女に罵詈雑言をぶちまけて、帰りたい気持ちにさえなっていた。
彼もまた、酔っていた。しかし、翌日酔いが醒めて思い返しても、その気持ちに変化はなかった。
お開きになった時には、もう午前一時を過ぎていた。佳代子は、まだ飲みたそうにしていたが、「もうええじゃろ、さすがに。」と、吉岡が宥めた。
田代のタクシー代も、吉岡が出してくれた。佳代子は足許をふらつかせながら、「遅くまでつきあってくれてありがとう! また明日からがんばろうね。」と笑顔で背中を叩いた。田代は愛想笑いも尽きて、それには返事しないまま車に乗り込んだ。
自宅の住所を運転手に告げ、携帯を取り出すと、彼は、ツイッターを眺めた。雪景色の中、凍結した湖に飛び込もうとして、意外と分厚い氷が割れず、背中を強打して、のたうち回る若者の動画が、リツイートで回ってきた。「爆笑!」とコメントをつけているのは、テレビでよく見るどこかの大学の社会学者で、田代は彼をフォローしていなかった。
その馬鹿馬鹿しさに、無性に腹が立った。佳代子から移されたストレスは、彼の中で忽ち劇症化していた。そして、普段はまずしないことだったが、「ヒマですね。しかも、人が苦しんでるのを見て喜ぶって最低ですね。それでも大学教授ですか?」とコメントを書いてやった。本当は、「それでも上司ですか?」と、寺田佳代子に言いたかったことだった。
そのまま、彼は酔いに任せて眠りに落ちた。運転手に起こされ、目を醒ますと、件の大学教授からは、既にブロックされたあとだった。
4
社会学者の久保田健司は、明後日の会議までに提出を求められている四十七ページからなる「私立大学等改革総合支援事業調査票」の項目を、早目の夕食を終えた後、黙々と埋めていっていたが、二十九項目目の「学部等又は研究科において企業等と協定等に基づき2週間以上のインターンシップ科目を実施していますか。」という項目に「実施していない。」即ち「0点」と回答したところで、ほとほと嫌気が差して手を止めた。絵に描いたような「【クソどうでもいい/ブルシット】」作業だったが、おまけにこんな露骨な金儲けの手先にされていることに我慢がならなかった。
『なにが、「Society5.0」だ、クソッ。文科省は経産省の犬か?……』
半ば気晴らしのつもりで、彼は、締切を二日過ぎている講演録の手直しの方に取りかかった。
「資本主義は、本当にもう限界か?」というシンポジウムで行った「ポスト資本主義社会の贈与論」という講演だったが、後日、会場で聞いていた論壇誌の副編集長から、素晴らしい内容で感動したので、是非、講演録を掲載させてほしい、とメールが届いた。
久保田の講演は好評で、その後のパネルでも何度か言及されていたが、些か準備不足で、掲載するならば、改めて事実確認をして整理する必要があった。その時間が取れるかどうか。……躊躇いながらも、最後は決断というほどのこともないまま、彼はその申し出を受け容れたのだった。但し、くれぐれも書き起こしそのままというのは止めてほしいと念を押し、出来れば短めにまとめてほしいと注文をつけた。
ゴールデンウィーク前に、早々に送られてきていたその原稿のファイルを、久保田は、今日まで開かずにいた。
メールは、最初の依頼文同様、改行の少ない長文で、改めて講演の感想が丁寧すぎるほどに書かれていた。久保田は、それにザッと目を通しはしたものの、とても詳しく読む余裕はなかった。時間的にも、肉体的にも、精神的にも。――スクロールバーを下げていくと、底の方にようやく添付ファイルの説明があり、それもまた回りくどかったが、要するに、講演録はPDFでもワードでも、どちらで手を入れてもらっても構わない、ということらしかった。メールには、PDFファイルが二つにワード・ファイルが三つ、更に謝礼の振込先を記すエクセル・ファイルの計六点が添付されていた。それだけでげんなりしたが、ワード・ファイルの一つは「執筆者登録用」となっており、「レイアウト」というファイル名のPDFを開くと、その通り、講演中の写真が挿入された誌面のデザインが表示された。しかし、文章はダミーだった。
PDFでの訂正は手間がかかるので、久保田は「久保田先生 ご講演書き起こし ご確認用」というタイトルのファイルを開いた。もう一つのファイルも同じようなタイトルだったので、そちらは見ないまま赤入れを始めた。
六十分の講演原稿はかなりの分量で、しかも、嫌な予感が的中して、あれほど言ったのに、書き起こしは未編集に近かった。三ページ目まで手を入れた段階で、彼は自分が、ほとんど一から原稿を書き直していることに気がついた。それだけで、もう一時間が経過している。一体、何時間かかるのか? 時計を見ると、午後十時だった。差し戻して、残りは再編集させようかと考えたが、締切を破ったのはこちらであり、その余裕はないだろう。あんなに言ってこの調子なら、やり直させても変わらないのではないか。……
結局、彼は四時間ぶっ通しでその講演録に手を入れ、終わったのは、午前一時頃だった。すぐに送信したが、あまりの面倒に、腸が煮えくり返るほどいらいらしていた。
椅子から立ち上がることも出来ず、気晴らしに、しばらくツイッターを眺めていた。そして、フィンランドの若者が、サウナから飛び出してきて、凍結した湖にダイヴし、氷で背中を痛打して悶絶する動画に失笑し、「爆笑!」とコメントをつけてシェアした。
それから、気力を振り絞ってシャワーを浴びに行った。
少し気分が落ち着き、戻ってくると、開きっぱなしのパソコンの画面で、またツイッターに目を遣った。さっきの動画は、その後、あっという間に三百人以上にリツイートされている。久保田は、普段はしないことに決めているが、コメント欄を覗いてみたくなった。「爆笑ですね!」、「なんか、オットセイみたい。」、「氷が割れたら割れたで、心臓に悪そうですが。……」といった絵文字付きの賑やかな反応の中に、こんなコメントが混ざっていた。
「ヒマですね。しかも、人が苦しんでるのを見て喜ぶって最低ですね。それでも大学教授ですか?」
彼は胸糞が悪くなって、そのアカウントを直ちにブロックした。せっかく鎮まりつつあった苛立ちが、また再燃して、手がつけられなくなってしまった。
『ヒマなのは、オマエだろう!……大体、俺は教授じゃなくて准教授だぞ、バカ。』
画面を閉じようとすると、メールの着信音が鳴った。待っていたのか、深夜にも拘らず、講演原稿を送った編集者からの返信だった。またしても長いメールで、中にこう書かれていた。
「……「久保田先生 ご講演書き起こし ご確認用」のファイルに手を入れて戴いたようですが、あちらは、万が一の時のために、参照用に添付した書き起こしそのままの原稿でしたので、編集したものは、もう一つの「久保田先生 ご講演録 入稿前」というワード・ファイルとPDFファイルの方でした。いずれにしましても、久保田先生に丁寧に直して戴いた原稿の方で入稿させて戴きます。」
久保田は口を半開きにし、ペンチで締め上げるように眉間に皺を寄せた。
四時間半前に確認してみなかったもう一方のワード・ファイルを開くと、冒頭の挨拶がカットされ、きれいに編集された講演録が目に飛び込んできた。
「紛らわしいんだよ!」
久保田は、机を拳で殴りつけて顔を伏せた。彼は普段、決して声を荒らげるような人間ではなかったが、基礎疾患のある人がコロナで重症化しやすかったのに似て、元々、苛立ちを募らせていたところに、あのツイッターのコメントを見てしまい、田代から移されたストレスは、忽ち激烈に発症してしまったのだった。
彼はすぐ様、キーボードを叩いて、編集者に猛然と抗議した。決して乱暴な言葉は用いなかったが、その分、儀式的なまでに理屈っぽく、相手の反論が予め封じ込められ、そのストレスの強調は執拗だった。ファイルが一度に六個も添付されていて、しかも、ファイル名が長く不明瞭なので、混乱するに決まっている。大体、書き起こし原稿まで添付してくるような編集者はおらず、丁寧なつもりなのかもしれないが、誤解の元だ。そもそも、メールが長過ぎ、重要な要件がどこに書いてあるのかわからない。一日に数十件、メールの処理をするのが普通の世の中で、自分のメールをそんなに時間をかけて読んでもらえると期待するのは非常識だ。お陰で原稿の見直しに、四時間も取られることになった!……
せめて一度読み返し、出来れば翌朝まで送信を待つべきだっただろう。しかし彼は、怒りに任せて送信ボタンに指を叩きつけ、そのまま消灯して、氷で背中を痛打した青年そっくりの呻き声を上げながら、ベッドに倒れ込んだのだった。
5
論壇誌の副編集長を務めている中岡知美は、朝起きてパソコンを開き、深夜に久保田健司から届いたメールを読んで、激しい動悸を覚えた。冷静さを装ってはいるが、激怒していた。すぐに謝罪のメールを書こうと椅子に座ったが、読めば読むほど理不尽で、最初の動揺が落ち着くと、腹が立ってきた。
あれだけ丁寧に説明して、自分が勝手に勘違いしただけなのに、なぜ、こんなにエラそうに相手を叱りつけられるのか? 大体、締切を二日過ぎているのに、謝罪の一言もない。こちらのメールが長くて読めないなどと言っているが、彼のこのメールこそ、とんでもない長さだった。
テレビでもよく目にしていて、新書を一冊読んだことがあり、好感を抱いていたので、彼女は甚だ幻滅した。難しい人なのだろうかと思ったが、恐らく、自分が年下で、女性でなければ、決してここまでの態度は取らないだろう。そういう男の書き手は、少なからずいた。
文字起こしまで送るというのは、彼女も普段はしないことだったが、しつこく編集を求められ、かなり手を入れたからこそ、念のために添付したのだった。
こんな次第で、久保田のストレスに感染してしまった彼女は、朝食を作りながら、夫に唐突に、「今日、晩メシ要らないから。」と言われた時、いつになく険しい顔つきになった。
「わたし今日、夜はいないよ。」
「なんで? そんなこと言ってた?」
「言ったわよ。見てよ。」
夫は、促されてカレンダーに目を遣り、言葉を失った。
「何とかならない?」
「無理よ。作家さんの書店イヴェントなんだから。前から言ってたじゃない。塾のお迎えもお願いしてたでしょう? 何なの、今日は?」
「ちょっと、……会食に誘われて。」
「断ったら。」
「断れないんだよ。」
「こっちは無理よ、絶対に。だから前以て言ってたでしょう?」
「言ってたかもしれないけど、大体、いつも色んなことを一度に言うから、わかんなくなるんだよ。」
知美は、その言い草に声を荒らげた。
「いい加減にしてよ! 無理だって言ってるでしょう? ちゃんと説明してるの! 自分が理解してなかったことを、どうしてわたしのせいにするの? いい加減にして!」
彼女は菜箸をシンクに投げつけると、これ以上、夫と口を利きたくなくてリヴィングから出て行った。
6
知美の夫は、結局、会食を断ったが、それが不服で、出先で呼んだタクシーが、待ち合わせ地点の十五メートルも先で止まっていた時には、乗り込むなり、運転手に悪態を吐いた。一人暮らしのその七十代の運転手は、アプリ自体の不具合とは敢えて言い訳せず、謝罪してやり過ごした。しかし、帰宅後、酎ハイを飲みながら、日中の生意気な客のことを思い出すと、腹の虫が治まらなかった。そして、前々から気になっていた隣の部屋のカップルの騒音に、今日こそは我慢がならなくなって、サンダル履きで、ドアをノックしに行った。……そこから、更に四人を経て、このストレスがルーシーに辿り着くまで、あと二人である。
古賀惣介は、東京から京都までの新幹線の車中でも、ずっと気が重かった。
昨日の午後、突然、取引先の京都の化学メーカーから、発注した工場の生産用設備の費用が嵩み続けていると強い調子のクレームが入って、東京から呼びつけられているのだった。
原料不足や中国での需要増加から鋼材価格が高騰しているのは何度も説明していたので、彼は急な電話に戸惑った。元々、気難しく苦手な社長だが、何か別の問題でも切り出されるのかもしれない。その心配をあれやこれやとしていたが、落ち着かないので、妻からせっつかれていた夏休みのタイ旅行の飛行機の予約をすることにした。
長年、多忙のせいで貯まる一方だった飛行機のマイルを、使用期限前に使うつもりだった。手帳を開き、航空会社のサイトを検索したが、特典航空券のビジネス・クラスの予約枠は、どの便も既に「空席待ち」である。彼は舌打ちした。「空席待ち」と言っても、一体、何人待っているのか示されないと、判断のしようがなかった。
京都駅からは、南区の会社までタクシーで二十分ほどである。
古賀は、念のために早目の新幹線に乗ったので、京都に到着後、駅のホテルのロビーでコーヒーを飲むことにした。少し心を落ち着けたかった。
入口で、「一名です。」と伝えると、若い女性の店員から、「そちらでおかけになってお待ちください。」と、外のソファーを促された。見ると、先に二組が座っている。
古賀は腕時計を見て、店内を見渡した。方々に空席があり、何故、待たされるのかわからなかった。
彼は、わざとらしく空いてる席に首を伸ばし、強引に近くのテーブルに向かった。先に待っていた客の一人が、不服そうな怪訝な目で彼を見ていた。
注文を取っていた先ほどの店員が、「あ、すみません、あちらでおかけになってお待ちください。」と、彼に改めて言った。
「空いてるじゃない、席。そことか、あそことか。」
「すみません、生憎と、すべてご予約戴いてます。少々、あちらでお掛けになってお待ちください。」
「どれくらいかかるの?」
「そうですね、……」と、店員は答えようがないという表情で、一応、振り返って席の状況を確認した。「二十分ほどお待ち戴くかもしれません。」
「二十分?」
古賀は舌打ちすると、順番待ちのソファーへと移動した。先に並んでいた二組が、彼の態度を盗み見ているのを感じた。
五分間、彼は貧乏揺すりをしながら、携帯を眺めつつ順番を待った。それから思い立って、航空会社に電話をし、空席待ちの状況を訊いてみることにした。
機械音声の応答の後、なかなかオペレーターに繋がらなかった。十五分待っても順番が来なければ、行かなければならない。時計を見ると、秒針に、胸を煎られるようだった。
ようやく女性のオペレーターが出ると、彼は手帳を見ながら、希望する便の座席を伝えた。しかし、やはりすべて、空席待ちだという返答だった。
「前後の便も、全然、空いてないんですか?」
「空いてません。」
「ないの?……マイル貯めるだけ貯めさせて、肝心な時に使えないんじゃ、話にならんな。」
彼は、そう不服を言ったが、オペレーターは黙っていた。
「まァ、しょうがないけど、空席待ちっていうのは、どのくらい希望があるんですか? 待ってれば空きそうですか?」
「まったくわかりません。」
古賀は、そのにべもない言い草にムッとした。しかし、会話は録音されていると最初に機械音声で断られていたので、余計なことを言って、責任を取らされたくないのだろうと察した。それで、今度は努めて気さくな調子で尋ねた。
「そう、……まあ、ハッキリとは言えないでしょうけど、こっちも予定の立てようがないから、経験的にというか、感触的に、どんなもんですか? 参考にするだけで、あとで、あの時、こう言っただろ、とか、そういう話にはしませんから。」
「まったくわかりません。」
古賀の携帯を持つ手が震えた。実のところ、この派遣社員のオペレーターは、昨日の電話応対のクレームで、つい今し方まで、ねちっこい〝指導〟を受けていたところだった。とにかく、余計なことは言うなと命じられたので、今日は一日、その注意に過剰適応してみせるつもりだった。古賀が怒っているのは感じたが、それが言われた通りの応対の結果なのである。そして、彼女を朝から執拗に叱責したその社員こそは、小島和久がシアトルから持ち帰り、長い経路でここまで運ばれてきたストレスの直近の感染者であり、結局それは、この女性オペレーターを介して、古賀にも移されようとしているのだった。
古賀は、勝手に気を回した分だけ、余計に彼女の無愛想な返答に憤慨した。
その悪いタイミングで、女性店員が座席が空いたことを告げに来た。丁度、二十分経ったところだった。
古賀は、腕時計を見て、もうコーヒーを飲む時間などないことを知った。そして、オペレーターに言うのとも、店員に言うのともつかず、「もういいよ!」と癇癪を起こして電話を切り、小走りでタクシー乗り場に向かった。
7
ルーシーは、浙江省杭州の出身で、京都大学の大学院に留学中の中国人だった。
都市環境工学を専攻し、今は修士課程の二年目である。元々の中国名は「羅森」といったが、上海の華東師範大学を卒業後、二年間、ニューヨーク市立大学に留学していて、その時以来、ルーシーという渾名が気に入っていた。
中学生の頃に、父親の仕事の都合で三年間、東京に住んだので、日本語は、言われなければ日本人だと信じてしまうほど達者だった。ただ、子供の頃に身についただけに、却って、自分は微妙に、少し失礼な日本語を喋っているのではないかと、いつも自問していた。実際、今日の午前中のホテルでのアルバイトでも、彼女は、順番待ちをしていた男性客に、よくわからない理由で、叱りつけられたところだった。
丁寧な表現を心がけたつもりだったが、何か気に障っただろうか? 彼女はそのことを、午後になって仕事を終えてからもずっと考えていたが、単に、日本によくいる〝怒鳴るオジサン〟なのかもしれない、という気もした。
古賀は実際、ルーシーが中国人だということには、気づいていなかった。
ルーシーには、免疫があったのだろうか? 彼女も確かに、古賀の態度にストレスを感じていたが、症状は比較的軽かった。なぜそうだったのかは、なかなか、単純ではない。たまたまその日、彼女が人と会う予定がなかったから、ということもあろうし、彼女が留学生だからということも、幾重もの意味で関係していよう。そもそもの性格もあれば、京都という環境もある。
ともかく、事実だけを記すならば、こうだった。
その日の午後、彼女は北大路通を少し上がった賀茂川の川縁で、先日買ったばかりのウクレレの練習をすることにしていた。去年、京都に来てから始めた趣味だったが、十ヶ月独学で練習して、遂に、これまでの合板の初心者モデルではなく、ケリーの単板のウクレレを買ったところだった。八万円の定価を六万四千円にしてくれた。
鴨川も、三条や四条の辺りは、当然に混雑していて、そのオーバー・ツーリズムを嘆く程度には、彼女も既に京都の人間だったが、北上して賀茂川に枝分かれし、植物園の辺りまで来ると、地元の人たちが、のんびり犬の散歩をしたり、昼寝をしたり、ピクニックをしたりしていて、ルーシーは真夏の暑くなる前に、ここでいつか、ウクレレの練習をしたいと思っていた。
桜の季節を終え、まだ梅雨入りには早く、土手は緑の草に蔽われていて、日差しが穏やかだった。風もなく、日曜日なので、家族連れも見かけたが、互いに目が合うような距離でもなかった。
護岸の石畳の上に腰を下ろすと、ルーシーは、すぐにはウクレレのケースを開かずに、しばらく川を眺めて過ごした。
月曜日の研究室のことを考え、杭州の家族のことを思い出した。
この日は、水の流れも穏やかだった。そよ風が心地良く、通りの車の音も遠い。京都は高い建物がないので、空が広く、上海よりも町は小さいのに、時の流れがゆったりと大きく感じられる。微かに曇りを帯びて、日差しの角が削られ、肌にやわらかかった。
不意にまた、今朝、怒鳴りつけた男性客のことを考えたが、意外と、もうその顔を曖昧にしか思い浮かべられなかった。ヘンな人だったなと思った。
真っ白な鷺が一羽いて、落差工と呼ばれる川床の段差の下で、じっと流れ落ちてくる川の水を見つめていた。ほとんど、哲学者風の顔つきだった。
何をしているのだろう?
白い水の泡立ちから、まっすぐに伸びた黒い二本の足が、超然とした気高さを感じさせる。
やがて、鷺はすっと喙を伸ばして流水に突っ込み、引き抜くと、何と小魚を銜えていた。ルーシーは、目を瞠った。頭良い! 泳いでいる魚を獲るのは難しかろうが、段差を流れ落ちる際に、一瞬、魚がコントロールを失う刹那を、じっと待っているのだった。そんなことをしている鷺は、その一羽だけだった。
彼女は笑って、携帯を取り出し、次にまた獲物を捕まえるまで、動画を撮影しながら待った。
川が流れていて、鷺は魚を待ち、彼女はその鷺を待っていた。そして、見事に二匹目をその黄色い喙で捕まえると、「おー、」と思わず歓声を発し、拍手して笑った。動画はそこで止めたが、彼女の声も、そよ風の音とともに録音されたはずだった。
それから彼女は、ようやくウクレレを取り出し、チューニングをして、『カイマナヒラ』の練習を始めた。部屋に閉じこもって弾くのとは違い、一つ一つの音が、発せられるなり稚魚を放流するように宙に飛び出していった。ハワイには実は、行ったことがなかったが、ウクレレはやはり、外で弾くための楽器なのだろうと、つくづく感じた。……
ルーシーはその後、ウクレレを弾いては休憩し、寝っ転がって空を見上げたり、おやつのマフィンを食べたりしながら、二時間ほどを、そこで一人で過ごした。
確認された限り、この後の一週間で、彼女から誰かへと、ストレスが感染した形跡はなかった。
古賀はその後、恐ろしいスーパー・スプレッダーとなって、計五人が彼とのやりとりを通じてストレスを抱え込んだ。そのうちの四経路では、以後もしばらく、市中で感染の拡大が続いた。しかし、ルーシーはアンカーであり、小島和久が、うっかりシアトルから持ち帰ったあのストレスは、流れ流れて、ようやく彼女の中で死滅したのだった。
ルーシーは、だから、さり気なくも、社会を守った英雄である。しかし、彼女はそのことに気づいておらず、周りの誰もそう思っていない。
つまり、彼女は、文学の対象であり、小説の主人公の資格を立派に備えているのである。
(終)
NHK京都で11月26日に放送される番組HPはこちら。
京都放送局で開催されるパブリックビューイング&トークイベントについてはこちら。