平野啓一郎が文学に目覚めたきっかけであり、最も大きな影響を受けた作家でもある三島由紀夫。その四つの代表作を精読することで三島の思想をスリリングに解き明かした『三島由紀夫論』が、第22回小林秀雄賞を受賞しました(詳細はこちら)。
今回は受賞を記念して、平野啓一郎自ら『三島由紀夫論』について語ったインタヴューを無料公開いたします。
三島由紀夫、大江健三郎、そしてその二人に多大な影響を受けた平野啓一郎。「虚無からの脱出」という共通する問題意識を持った三人が、それぞれに出した答えとは?
ぜひ最後までお楽しみください。
『三島由紀夫論』Amazonページはこちら
無料試し読みはこちら
※このインタビューは、平野啓一郎による文学解説が聴ける「文学の森」で行われたライヴ配信を一部テキスト化したものです。
三島を通じて、自分の文学者としてのルーツを探る

平野啓一郎(以下、平野):中学時代に『金閣寺』を読んで強い衝撃を受け、それが文学に目覚めたきっかけになりました。あれほどの衝撃を一冊の本から受けたことは、後にも先にもありません。あのときの衝撃がなければ、自分の人生は今と同じではなかったと思います。
『三島由紀夫論』は、構想・執筆23年に及ぶ作品です。これほど長く執筆の情熱が持続したのは、自分がどうして三島由紀夫にあんなにも強く惹かれたのか、ある意味、自分の文学者としてのルーツを知りたいという気持ちがあったからだと思います。
ただし、三島に対してはみな思い入れが強く、個人的な”我が三島”が語られることも多い。文学の読み方としては、それこそが重要だと思いますが、自分の仕事としては、自己投影が過多になることなく、三島を徹底的に他者として理解しようとすることを、心がけました。
四つの代表作(『仮面の告白』、『金閣寺』、『英霊の声』、『豊饒の海』)を精読し、三島の言わんとしてることを正確に理解して、そのような考え方に至った経緯を、時代背景と彼が影響を受けた思想を通じて分析する。自分の考えを書くのは、すべてその後にしたかったんです。
これは僕の小説のテーマでもありますが、他人とコミュニケーションを交わすとき、相手の本心は結局のところわからないが、その上でやはりわかろうとするというのが、重要です。文学作品においても作者の意図は、究極的にはわからないと言うべきですが、それでもそれをわかろうとすることに、読解の意味があると僕は思います。
戦後、人々は「生の実感」を何に求めたのか
平野:三島は戦後の日本社会に対して、非常に虚無的なものを感じていました。戦争体験はあまりにも強烈で、終戦後、日常生活を普通に生きることに戸惑い、「生の実感」をつかみ損ねます。
これは僕の『「カッコいい」とは何か』という本にも書きましたが、戦後、多くの人は国のためではなく、会社のために頑張るというような、一種の出世主義に生きがいを見いだします。

一方、仕事以外の享楽的な面では、生きる実感を身体的な感覚に求めていくのです。たとえば音楽だと、ビートルズへの熱狂、また体に響くジャズやロックのしびれるような音楽の陶酔感にそれを求めます。スポーツで体を動かすというのも生きる実感のひとつで、東京オリンピックは象徴的な出来事でした。
戦後は「アプレ・ゲール」と呼ばれる、無軌道になっていく若者たちが現れ、三島より十歳年下の世代の石原慎太郎や大江健三郎らは、若者たちの”性”を生きる実感の主題にしています。三島と大江健三郎は、虚無からの脱出という問題意識を持っていた点で、共通しているんです。
大江さんは、特に初期作品では「性」を通じて、日常生活に緊張感を回復し、生きている実感を取り戻し、虚無からの脱出を託そうとしています。『性的人間』や『われらの時代』がその典型です。
しかし、 三島は性的指向や恋愛感情などのセクシャリティーが非常に複雑で、 ストレートに表現できない点で、大江さんとは異なります。
虚無の上に美を打ち立てる三島の姿勢に共感した
平野:三島のニヒリズム(虚無主義)に僕は非常に共感しました。三島は、戦後の高度経済成長に大きな空虚感を持ち、自分の居場所はないと感じていたと思います。
一方で僕は、80年代後半のバブル経済のときに十代後半を過ごしました。北九州の田舎で育ち、東京のバブルの狂乱状態をテレビで見たときに、非常に空虚なものを感じたんです。 自分は何のために生きているのか、という問いが芽生えてきたときに、三島が戦後社会に感じていた空虚感と、だからこそ、その空疎さの上に美を打ち立てていく彼の文学者としての姿勢に非常に共感したのです。三島の言語芸術は、虚無の上に打ち立てようとしていた一つの大きな実体でした。
だからこそ、最終的に、自己のアイデンティティの空虚感を、「日本」とか「天皇」といったものに結びつけることによって下支えしてもらう発想になっていくところには、どうしても違和感があります。
大江さんが戦中の実体験を元に、反天皇性民主義者となったのに対して、十歳年上の世代の三島は、同世代の多くを戦死で失くしていたため、心情的にそれを否定できなかった。
そして、社会が虚無化していたら行動ができないので、天皇を中心とした世界を有意味化して、その上で三島は行動を起こそうとしました。
他者との関係性の中に、自分の生の基盤を見る
——三島が虚無感を克服するために出した答えが「天皇」だったとすると、平野さんはどういう答えをお持ちでしょうか。
平野:ニヒリズムの克服という観点では、僕の答えは「分人主義」だと思います。大江さんは、自分の故郷にある四国の森が豊かな文学的空間であり、最終的には孤独な現代人のたどり着く先だということを『万延元年のフットボール』以降、ずっと描き続けています。
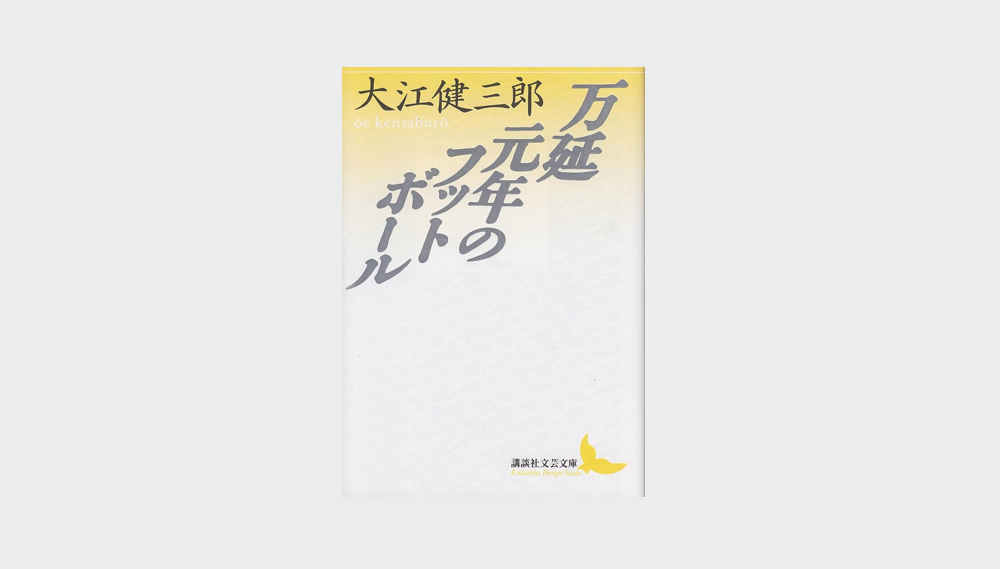
僕は北九州という都市部、労働者としていろんな人たちがたくさん流入してくる街で育ちました。だから地元の豊かな神話的空間が最後は僕を支えてくれるとは思えないんです。僕は天皇および日本の歴史にも自分を接続できないし、もっとローカルな土地に自分の位置や行きつく先があるわけでもない。
そのような中で、孤独に日常を生きるときに、人間は主体が分化していて、それぞれ他者との関係性の中に実体があるんじゃないかという考えに至りました。四国の森とか天皇とか、一なる大きな存在に自分を支えてもらうのではなく、具体的な複数の関係性の中に、自分の生の基盤を見るべきではないかという考えです。この分人主義という考え方は、尊敬する二人の作家を批評的に捉えて、自分なりに乗り越えようとした結論なんです。
文学は自分の悩みへの処方箋
──先日の講演で、平野さんが小説を書き始めたきっかけは自分の悩みへの処方箋だったという話が印象に残りました。
平野:現実の世界に完全に満たされて、今の社会で矛盾なく生きてる人は、そのまま人生をエンジョイすればいいと思います。現実の中で何か悩みを抱えたり、満たされないものがある人たちが、文学を読むのだと僕は思います。ある種の苦悩があって、その苦悩と戯れることが心地よいのであればそれでいいと思うのですが、自分の抱えてる悩みが切実だと、その痛みを「治したい」と思うんですよね。
僕の場合、「自分とは何なのか」というアイデンティティの悩みがあり、苦しかったので、その状態から脱したい、自分の症状から回復したいという気持ちがとても強かったんです。小説で単に苦悩を吐露するだけではなく、どういう思想が自分を救済してくれるのかということをずっと考えていました。
ただ、僕の苦悩は僕に特殊なものではなくて、この時代の日本という社会に生きていて、その関係性の中で生じてくる苦悩なので、ということは、同じ社会に生きている読者にも一定程度共有される苦悩ではないかと思います。 その僕に効く薬であれば、他の人たちにも効くのかもしれないという期待で、小説を書いています。
(ライティング:田村純子)
▶︎平野啓一郎『三島由紀夫論』(新潮社)
Amazonページはこちら
無料試し読みはこちら


