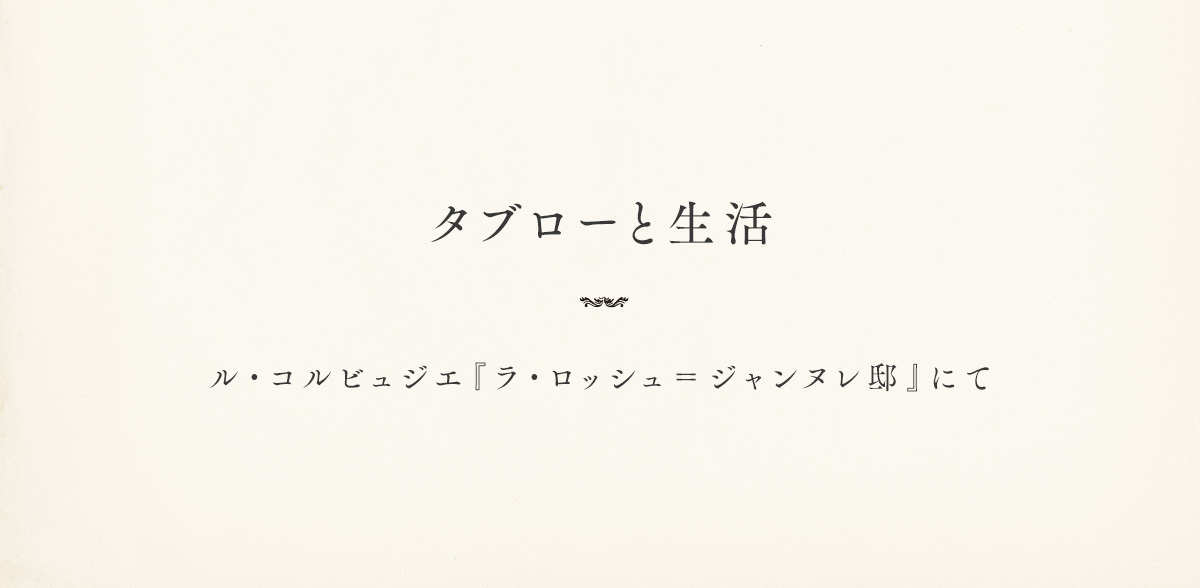最新エッセイ集『文学は何の役に立つのか?』刊行を記念して、2007年刊行の『モノローグ』(講談社)収録エッセイを公開します。『モノローグ』は電子書籍をこちらよりご購入いただけます。

タブローと生活
ル・コルビュジエ『ラ・ロッシュ=ジャンヌレ邸』にて
住宅建築には、常に一つの逆説がある。
もしそれを外部に於いて眺めるならば、その存在は、彫刻や絵画などと同じく基本的には「モノ」であり、その中心性は、周囲の多方向の空間に対して、常に一者として働きかける。しかし、内部に於いて見るならば、それは必然的に非中心的存在であり、一塊りの閉ざされた無としての空間に対して、多方向から、常に断片的に働きかける。道家の書物には、無の価値を説明するために、器だとか、車輪の中心だとかいった比喩が用いられるが、住宅も、人の生活を収める大きな器であり、またその生活の周りで機能する車輪であるとするならば、住宅建築とは、物質という有る「モノ」による無い「モノ」の創造に他ならない。
建てられた住宅は、遂にその意味の中心には存在することが出来ないが、しかしその中心は、物質的な造形によることなしには存在し得ないのであって、建築家は、常にその外殻を生み出すことに情熱を注ぐわけだが、最も重要な部分は、外殻そのものではなく、不可触である内部の空間である。この誠に奇妙な性格が、住宅建築というもののいわば逆説である。
ル・コルビュジエの初期の代表作であるラ・ロッシュジャンヌレ邸を訪れて、私は改めてそんなことを考えた。
ラ・ロッシュジャンヌレ邸は、元々は、彼の兄で、音楽家であったアルベール・ジャンヌレの家族と、独身の銀行家で、絵画のコレクターであったラウル・ラ・ロッシュの為に建てられた、今で言うところの「二世帯住宅」で、現在はル・コルビュジエ財団がその一角に事務所を構えている。今回、私が見学したのは、主にラ・ロッシュ邸の方で、ジャンヌレ邸の方は、残念ながら部分的にざっと見たという程度に過ぎないので、ここで語ることが出来るのは、前者の方のみである。
ラ・ロッシュ邸は、一言で言えば、若い仕事である。三十代の前半で建てているのだから、事実からしてもそうなのだが、それ以上に、作品の雰囲気として若い印象があって、これは、小説の所謂若書きの作品というのと同じことである。
実は、ラ・ロッシュジャンヌレ邸を訪れた翌日に、私は、ル・コルビュジエが最晩年まで住んでいたというナンジェセール・エ・コリ通りのアパルトマンにも足を運んだのだが、こちらは流石にというか、決して大げさなものではないものの、非常に円熟していて、そこはかとないユーモアがあり、素朴に、住み心地が良さそうだという感じを受けた。
ラ・ロッシュ邸の若いという印象は、これによって、幾分余計に強められてはいようが、ただ、その若いということが、悪いかといえば必ずしもそうではない。未熟は常に瑞々しさと、生硬さは冒険と、無粋は大胆さと、気負いは野心と、硬直は知性と、不徹底は甘美さと、不完全さは可能性と、表裏一体のものであり、それが魅力となるか、欠点として不快に感ぜられるかは、得てして紙一重である。
パンフレットによると、建築家と未来の住人との間では、「ラ・ロッシュ、あなたのような素晴らしい絵のコレクションを持っている人は、それに相応しい家を建てるべきですよ」、「分かった、ジャンヌレ、そういう家を建ててくれ」といった会話が交わされたそうだが、なるほどそれも納得されるように、この家は人の住みかであるのと同程度に、あるいはそれ以上に、絵の住みかである(因みに現在は、建物の壁は、すべてル・コルビュジエの絵によって飾られている)。最初に写真で見た時、私は、なんとも、味気ない建物だなとしか感じなかったが、実際に足を運んでみて、しばらくウロウロしていると、段々とどうも止ん事無きことのような気がしてきて、しまいには感心させられてしまった。ラ・ロッシュ邸にいると、元々は更地であった筈のこの土地の上に、所在なく、漠然と置かれていた一塊りの空間が、いかに巧みに切り分けられ、組み立てられたかということがよく分かる。それは、殆ど傲慢なほどの身振りであって、個々の空間は厳しく律せられ、だらしなく弛緩したような一角はただの一ヵ所もない。そのスタティックな構築の中でじっとしていると、自分自身までもがそこに絵のように嵌め込まれてしまったような感じがしてきて、つい足を動かしたくなる。けれども、そうして人の動きがあると、空間は息衝き、その動きのあとに尾を曳くようにして、幽かに血の通い始めるのが透かし見られる
ル・コルビュジエは、生涯に450点もの絵画作品を残しているそうで、晩年まで、午前中は自宅で絵を描き、午後は 事務所で建築の仕事をする、というのが日課であったらしいが、ラ・ロッシュ邸の設計の根底に絵画的な発想があることは、その事実を知らずとも明らかであろう。画家としてのル・コルビュジエは、やはり二流の印象を免れ得ず、恐らく、 彼自身もそのことは知っていたであろうし、またそれを知らしめたのがピカソの存在であったことも間違いないであろうが、ただ彼の建築を考える時にその絵画作品を参照しないことは不可能である(アイロニカルだが、彼の「線」に対する感覚が示す或る種の不器用さは、そのタブローに於いて最も顕著に表れている)。
彼の面白さは、もともと、二次元という限定された場所で三次元世界をいかに表現するかという問題の解決のための工夫であった絵画的概念を、再度、三次元世界へ逆輸入させる術を知っていた点である。彼の建築に於いて、しばしば空間をしきる壁は、真っ白なカンヴァスを走る線そのものであり、ヴォリュームの組み立ては、翻訳されたマッスの配置である。ただし、だからといって、完成した建物がタブローのようであるかといえばそうではなく、むしろそれは極めて複雑な額縁のようなものである。
ラ・ロッシュ邸の場合、その主題の特殊さから、そうした性格は如実であって、私が冒頭に記したようなことを考えたのは、その結果である。 ラウルラ・ロッシュの生活は、そこで彼が収集したタブロー以上に、一つの現代的なタブローではなかったか。
(「X-Knowledge HOME 特別編集 No.1」 ル・コルビュジエ パリ、白の時代 2004年4月)