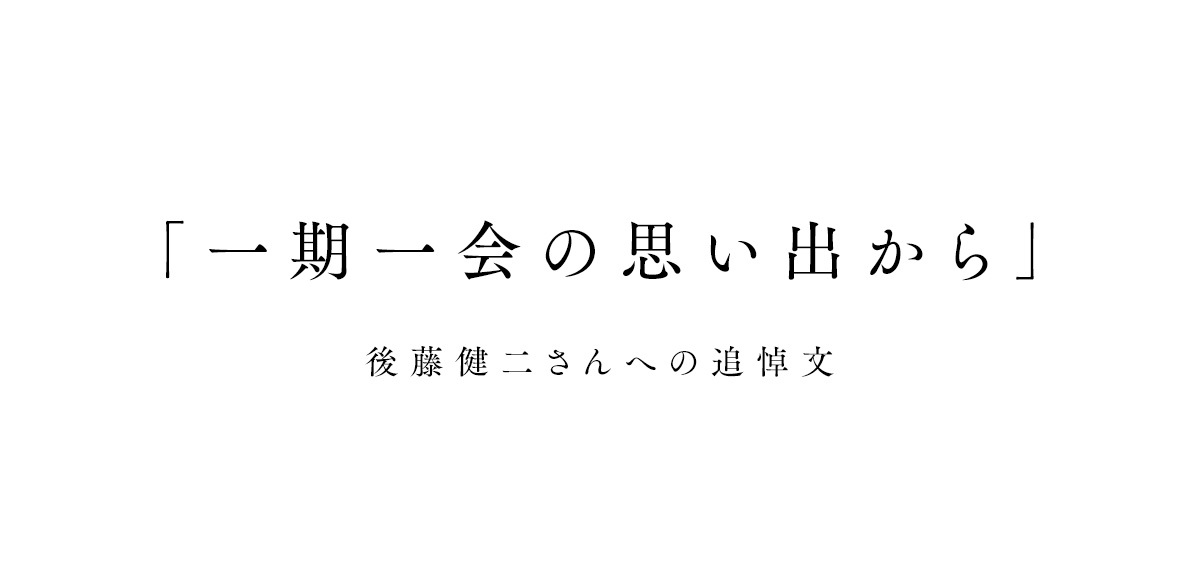今年1月28日に配信された「平野啓一郎 公式メールレター」では、7年前の1月30日にご逝去されたジャーナリスト・後藤健二さんへの追悼文をお届けしました。

平野啓一郎が『マチネの終わりに』執筆時の取材で出会った後藤健二さん。その記憶から感じること、そして「一期一会」という言葉について書き記した文章を、公式サイトでもお届けします。
これは、ジャーナリストの故後藤健二さんについて書いたものです。
後藤さんが亡くなって、もう七年が経ちました。後藤さんの死後、彼を追悼するフォト・エッセイ集の企画が持ち上がり、僕はそのあとがきを頼まれて、以下の文章を書きました。ところが、この企画は、頓挫してしまいました。理由は不明ですが、出版社の僕に対する対応は誠実なものでした。
そして、この原稿はしばらく僕の手許で眠っていたのですが、事件が風化してしまいつつある今、改めて皆さんに読んだもらいたいと、こちらで公開することにしました。一期一会の関係でしたが、忘れがたい、非常に素晴らしい方でした。
【あとがき ── 一期一会の思い出から ──】
後藤健二さんとは、どんな人だったのか? それを知るために、後藤さん自身の言葉をまとめた本書が上梓されることを、私は心から喜びたい。読み終えた人の胸には、様々な思いが去来しているだろうから、贅言は慎むべきだろう。
ここから感じ取られること。──それがすべてだと思う。 あとがきとして、私は幾許かの紙幅を許されているが、余韻を台なしにしない程度に、個人的な思い出話を少し添えるに留めたい。
*
私が、一読者として、後藤健二さんの存在を知ったのは、今から十年ほど前のことである。
当時、パリに住んでいた私は、フランスやその他のヨーロッパだけでなく、アフリカの存在を急に身近に感じるようになっていた。日本にいると、どうしても遠い印象だが、地理的にも、歴史的にも、また移民の多さからも、パリにいると、アフリカは、日常的な現実の一つである。
たまたま、私と同郷の親しい文化人類学者の友人が、マリでフィールド・ワークをしていて、隣国シエラレオネの少年兵の話などをよくしていたので、私はそれを題材に、「義足」(『あなたが、いなかった、あなた』収録)という短編小説を一つ書いた。その際に、参考文献として手に取ったのが、後藤さんの『ダイヤモンドより平和がほしい 子ども兵士・ムリアの告白』(産経児童出版文化賞受賞)だった。今でこそ、日本語で読めるシエラレオネ関連の書籍も増えたが、その頃はまだ、ほんの数えるほどしかなかった。
後藤さんは、テレビの報道番組などに本人もしばしば出演していたため、映像専門のジャーナリストという印象があるかもしれないが、私自身が最初に心を打たれたのは、その文章の方だった。実際、前掲書を含めて、後藤さんには五冊の著作があり、日本文藝家協会の会員でもあった。
著書を通じて感じたのは、後藤さんのジャーナリストとしてのバランスの良さだった。 弱者に対しては常にやさしく──さもなくば、あんな危険な場所にばかり足を運ぶはずはないのだが──、同時に現実を見つめる目は澄んでいて、キレイごとや思想的な偏向を排し、善悪の単純な対立構図を超えて真相に迫ろうとする誠実さがあった。
描かれているのは、両親を目の前で殺害された少年が、殺した人間たちに兵士に仕立てられ、顔に麻薬を埋め込まれて、「殺人マシーン」と化してゆくといった、想像を絶する凄惨な世界だが、後藤さんは取材者としての動揺を交えつつ、読者を選ばない、平易な文体で、その現実を深みを以て伝えていた。
参考資料のつもりで読んでいた私は、そうした彼らの生に存在を揺さぶられる一方で、著者である後藤さんにも頭が下がる思いだった。そして、『エイズの村に生まれて 命をつなぐ16歳の母・ナターシャ』や『ルワンダの祈り 内戦を生きのびた家族の物語』などの一連の著作も読みながら、しばらくは読者として、一方的な尊敬の念を抱いていた。
その後かなり経って、私は幸運にも、人を介して後藤さんの知遇を得る機会に恵まれた。昨年2014年のことである。 きっかけは、またしても小説の準備だった。私は、『マチネの終わりに』という毎日新聞の連載小説のために、イラクで取材経験のあるジャーナリストにインタヴューを続けていたが、その過程で、やはり後藤さんに話を聞くべきではないかと知人に勧められ、是非にと紹介してもらったのだった。
面会を請うためにメールで連絡を取り始めた時から、後藤さんは丁寧な方だった。 九月二日に、インデペンデント・プレスの事務所の一階で、初めてお目にかかった後藤さんは、長身で、がっちりとした体型で──高校時代は、一時アメフト部に所属していたらしい──、爽やかだったが、どことなく色気のある人だった。後ろで束ねた長髪やピアス、微かに漂っていたコロンか何かの匂いも、その印象を手伝っていたが、本書を読んで、後藤さんの音楽やワインの趣味などから、私は改めてなるほどと感じた。
メールでのやりとり同様、後藤さんは、とても腰が低く、お願いに伺ったこちらが恐縮するほどだった。大らかな、やわらかい笑顔で握手すると、二時間ほどのインタヴューに非常に丁寧に、真剣に応じてくださった。色々なことを質問したが、答えは常に明瞭で、複雑な事情を巨細に説明され、しかも、折々差し挟まれるエピソードには知的なユーモアが溢れていた。
私はそれを、後藤さんの人となりと思う反面、ジャーナリストとして、長年、海賊やゲリラ、難民やかつての少年兵など、非常にコミュニケーションの困難な他者と向き合ってきた結果だろうかとも考えたりした。
命知らずの正義感といった、戦場ジャーナリストの通念的なイメージとはかなり異なっていて、欧米メディアと日本のメディアとの比較分析などは、かなり現実的な洞察だった。作品のクオリティに関しては、厳しい基準を自らに課しているようだったが、それも、ビジネス的な視点と、自身の理想との両方からだった。
ジャーナリストは、どうしてそんな危険な場所に赴くのかというのは、どうしてそんな危険な場所に人が住んでいるのかというのと同様の愚問だろう。その上で、当然のことながら、私は安全管理についても質問した。後藤さんの答えは、多岐に亘ったが、基本的には、銃弾がまさに飛び交っている戦闘の最中というより、そこから少し下がったところにある人々の生活を伝えることを重視しているので、例えば、最前線に単独で突っ込んでいくようなタイプの欧米のフリーランサーなどとは、ちょっと違うのだという話だった。
本書の中にも、「見えない一線」という言葉が登場するが、それを侵さないことには細心の注意を払っているようだった。後藤さんのキャリアを振り返っても、いきなり、危険地帯のまっただ中に飛び込んでいったのではなく、経験を積みながら手堅く取材対象を広げていった観がある。
更に、ジャーナリストが戦場でどのように尊重されているか、取り分け、中東では、日本人がいかに好感を持たれているかを語り、それはやはり、第二次大戦後の復興と、「平和国家」としての歩みに負うていると説明した。当日の会話を具にここに記すことは出来ないが、それと関連して、湯川遥菜さんの拘束にも話が及んだ。事件後、様々な憶測が流れたが、私の理解した限りでは、後藤さんは湯川さんとは特に親しい間柄にはなく、しかし、一度その解放に尽力しているだけに、彼の再度の拘束を心配はしていた。
それだけの事情で、ISの支配地域にまで足を踏み入れるのだろうかと疑われるかもしれないが、私はわかるような気もする。取材目的もあっただろうが、後藤さんは結局、人並み外れてやさしかったのだろう。
たった一度きりの二時間ほどの面会だったが、私は、後藤さんのことが本当に好きになった。これを機に、長い付き合いになればいいなと期待し、最後にお礼を言うと、次回は、小説の取材とは関係なく、是非お食事でもとお誘いした。エントランスでの別れ際の立ち話で、後藤さんが聴きに行ったというサントリー・ホールのムターのコンサートに、実は私も行っていたと言うと、「ああ、本当に!?」とパッと目を輝かせた。次に会う時には、私たちはおいしいワインでも飲みながら、そんな会話で盛り上がるはずだった。
後藤さんから、最後にメールを貰ったのは、その後、一時帰国していた十月十五日のことである。面会の際、後藤さんは、紙袋一杯の貴重な取材テープを貸してくださり、私はそれを事務所に郵送で返却していた。その受け取りのメールだった。「新刊の広告を拝見しました! 書店で手に取りたいと思います。」とも書いてくださっていた。私は、過日の別れの挨拶と同様に、これからシリアに向かうという後藤さんに、くれぐれもお気をつけくださいと伝えた。後藤さんが拘束されたのは、恐らくその一週間ほど後のことだった。
*
後藤さんの死を巡っては、思うことは多々あるが、ここではあまり書きたくない。他の場所では発言してきたし、今後もするだろう。私は、死の瞬間の動画を見なかったし、その間、あまりにもグロテスクな様相を呈していたメディア上の言葉からも目を背けていた。ISによって動画が公開されて以来、拘束下の後藤さんの表情や心理があまりに生々しく想像されて、私自身も苦しかった。私でさえそうなのだから、ご家族の心痛を思うと、胸が張り裂けそうだった。
私は、「I AM KENJI.」というSNSのキャンペーンに参加した。お前は後藤さんじゃないだろうだとか、偽善的だとか、無駄だとか、あれについても色々言われていたが、私が考えていたのは、もっと単純なことだった。 私は、後藤さんの解放を願い続けていたから、もし彼が生きて帰国して、私がそんなふうに心配していたことを知ったら、喜んでくれるだろうと思っていた。ただその笑顔が見たかった。
もし逆の立場だったら、と私は考えた。私は後藤さんと、必ずしも長い付き合いの、深い間柄ではないだけに、自分が生命の危機に瀕していた時に、あの後藤健二さんまでもが、「I AM KEIICHIRO.」と表明してくれていたなら、うれしいだろうと想像したのだった。助からなかったとしても、何かの事情で、一瞬でもいいから、このネット上のキャンペーンが彼の目に触れることを祈っていた。それが、現実的かどうかといった意見は、私にとって、まったくどうでもいいことだった。
私は、拘束中の後藤さんの脳裏を、自分の存在が、一瞬でもよぎる瞬間があっただろうかと、何度か考えた。先程来書いてきた関係性からすると、無かっただろうと思うより他はないが、ただ、日本出国前のかなり長いインタヴューだっただけに、ひょっとすると、その会話の断片が思い出されることもあったのではないかとも考えた。しかし、それは永遠にわからないことである。
本書のあとがきを出版社から依頼された時、私は、断ることは考えなかったが、そんなわけで、後藤さんの魅力を語る役目としては、私よりも、もっと相応しい人がたくさんいるはずだとも思った。しかし、私たちが今後、後藤さんについて語り合う場所は、必ずしもここに限られるわけではあるまい。むしろ、始まったばかりである。私は、もっと間近で、後藤さんと接してきた人たちの言葉を楽しみにしながら、私自身の彼への献花のつもりで、その思い出を記すことにした。
一期一会という言葉を、私はこの先ずっと、後藤さんとの邂逅とともに記憶し続けるだろう。もう一度会いたかったと、心の底から思うが、私はそれを悲観しないことにした。後藤さんが、自らの危険をも顧みず取材し続けた人々も、後藤さんとの関係は、多くが一期一会だっただろう。後藤さんは、だからといって、彼ら一人一人との関係を、決して軽んじなかったはずである。私のように、直接、面会する機会のないまま、メディア越しに、あるいは取材映像や著作を通じて後藤さんと出会った人々も、同様に彼が大切にしていた人たちだった。
私たちには、愛する人を、ただ自分にとって大切な記憶によってのみ愛し続ける権利がある。彼を愛さない人々が、暴力とともに押しつけるどんな姿をも拒否して、その私たちに向けた姿だけを守り続けることができる。 一人の人間のうちの最も愛すべき部分を知る者は、それを知らない者たちとは、絶対に違うのだと、私は固く信じている。 亡くなった人と共にあるというのは、そういうことではあるまいか。
平野啓一郎
「平野啓一郎 公式メールレター」(無料)では、月に一度、平野よりお手紙をお届けしています。近況、新刊・メディア掲載・イベント出演のお知らせに加え、平野啓一郎が考えていること、作品の舞台裏もご紹介しています。より深く作品を楽しみたい方、この機会にぜひご登録ください!