この対談記事は、2021年8月20日、豊田市中央図書館オンラインイベントにて対談が実施された後、「すばる」2021年12月号に掲載されたものです。
対談のお相手は、医学史・文学研究者の小川公代さん。以前より平野啓一郎の作品群に大きな関心と共感を寄せてくださり、大きな話題になった著書『ケアの倫理とエンパワメント』でも、平野作品に言及してくださっています。

この対談では、最新長篇『本心』を軸にしながら、「文学は何の役に立つのか」、「小説の可能性とは何か」、「機械は人を幸せにするのか」といった普遍的なテーマについて話し合いました。
『ある男』『マチネの終わりに』『空白を満たしなさい』『ドーン』『かたちだけの愛』『カッコいいとは何か』……。平野作品を読み尽くしている小川さんだからこその、縦横無尽の展開。もちろん、これから平野啓一郎の作品を読み始めようとしている方にも、大きな示唆に富む内容になっています。
ぜひ最後までお楽しみください。
【ギグエコノミーと人間の未来】
小川公代(以下、小川):本日は「『本心』とは何なのか?」というイベントのタイトル通り、平野啓一郎さんの最新作『本心』に描かれているものをめぐって、作者である平野さんと議論を交わしていきたいと思います。
この作品は、コロナ禍で可視化されてきている格差や差別の問題を、非常に先鋭的に扱った作品です。平野さんは、これまでも命のないものに生命を吹き込んでいく、そんな要素を含んだ作品を書いてこられました。

一つ例を挙げれば、『かたちだけの愛』は交通事故で足を失った女性のために美しい義足を作る男性の物語でしたよね。『本心』でも、そうした作品と同じように、新しい命を作り出すという企図が描かれています。
物語は母親を亡くした主人公の石川朔也が、母親の死を乗り越えられずに、AIを駆使したテクノロジーでヴァーチャル・フィギュアといったものを製作してもらうところから始まる。つまり、ここで朔也が試みるのは、母に新たな命を吹き込むということです。もちろん、母は物理的にはこの世にはいない。でも、ヴァーチャルリアリティの技術を使って命を呼び起こすわけで、『本心』も、その点ではピグマリオン的な要素を備えた小説です。
とはいえ、本作は多面的に書かれている作品でもあります。例えば、朔也は母親の死後、彼女の元同僚の三好彩花と、金銭的な理由もあって共同生活を始めるんですが、二人の関係を巡っては、恋愛小説のような様相も帯びる。ただ、やはり一番力を入れて書かれているのが、母親が一体どんな人物だったのか、その正体を探り当てていく部分だと思います。重厚な推理小説を読んでいるような気にもなって、実に読み応えがありました。
ここから平野さんへの最初の質問です。作中で朔也はリアル・アバターという自分の身体を丸ごと貸し出すというケア労働に従事していますよね。この仕事では、依頼者から感謝されることも時折ありますが、馬鹿にされたりすることもある。かなり過酷な職業です。朔也は、もともと経済的に厳しい家庭で育った人物なんですね。シングルマザーとして朔也を育てた母親は、「死ぬまで低賃金労働者層に固定化されて」いたと書かれてもいます。平野さんは、物語のプロットをこうした設定の上で練っていくにあたって、現代の日本の状況のどのような部分に問題意識を感じていらっしゃったのでしょうか?
平野啓一郎(以下、平野):僕は、いわゆるロスジェネや団塊ジュニアと言われる世代の人間です。なので、基本的に自己責任論に強い反発があります。小説を書くときに、キャラクター性に偏重し過ぎてしまうと、小説内も自己責任論から逃れられない世界になってしまうんです。ある能力に恵まれた人はその力でどんな困難でも打開できる、あるいは、不幸に陥ってしまう人はパーソナリティに問題がある、みたいな描き方をしてしまうと、自分が抱いている反自己責任論的な感情に沿うものとはならなくなってしまう。そのため、やっぱり現在の社会状況だったり、そこに巣食う問題だったりを強く意識した上で書かねばならない、という考えを僕は持っているんですね。
AIやロボットの発展によって世界はどう変容するのかということは、この十年くらいの人々の大きな関心事項だと思います。特に仕事はいったいどうなってしまうのか、というのは切実な問題です。どんな仕事がなくなり、何の仕事が残るのか。僕自身、そのことは深く考えてきましたし、インタビューでも何度か答えてきました。ユヴァル・ノア・ハラリなんかの本を読むとかなり悲観的な予測も書かれていて、テクノロジー的には進歩をしていくけど、社会状況的にはかなり厳しい時代に突入することが考えられる。例えば、第三次AIブームが起こっている現在、ディープラーニング、すなわちパターン認識を学習していくAIが誕生していて、複雑な判断を要する仕事もAIに取って代わられうる時代がそこまできています。
その一方で、臨機応変に判断をしなければならない仕事に関しては、AIを開発するコストを考えたら人間を雇った方が安価で都合が良いと判断されるでしょう。だとすれば、そういった労働は今後もきっと残るかな、と。これは良い悪いを抜きにした予測です。加えて、気候変動や現在のようなパンデミックが起きた場合、外出が難しくなることもある。世間の多くの人々がリモートワークをせざるを得なくなったら、自分の代わりにいろんなことをやってくれる何でも屋さんの需要は増えるでしょう。そういった仕事はAIに任せるよりも、低賃金労働者がギグワークとして担っていくのではないか、ということを考えたときに、リアル・アバターという職業を思いついたんです。
小川:今のお話、すごく面白いですね。私は英文学を研究しているので、百年くらい前の知識人たちが機械についてどう考えていたか、みたいな議論をよく読みます。平野さんの翻訳されている『サロメ』はオスカー・ワイルドによる戯曲ですが、彼なんかは、その点に関して、なかなか楽観主義者で。

平野:そうですね。『社会主義の下での人間の魂』を読むとそれはわかります。
小川:ええ。あれを読むと、オスカー・ワイルドは、百年後には人間がしたくない仕事を機械が全部請け負ってくれる時代が到来するだろうと希望的に予測していたことがわかる。もちろん我々はウーバーイーツのようなギグエコノミーを両手をあげて礼賛できるような状況に現在いるわけじゃないんですが、当時のワイルドは、テクノロジーの発展が人間を解放すると素朴に信じていたようです。
他方で、ジョージ・オーウェルはワイルドを批判してますよね。きっとそんな明るい未来にはならないし、搾取は社会からなくなることはないんだ、と言っています。つまり、楽観論と悲観論の両方から、テクノロジーをどう使うのかという問題について議論されてきたわけです。すると、人間を機械のように搾取するギグエコノミーは批判の対象になりうる一方、さっき平野さんがおっしゃったようにアバターを使うことで生かされる命もあることがわかる。例えば、寝たきりになった人がカフェの店員のアバターになるっていうプロジェクトがあるらしいんですね。オリィ研究所が主宰・運営する「分身ロボットカフェ」というプロジェクトですが。そうしたイノベーションを見ていると、従来の環境では労働できない、例えば難病や重度障害で外出困難な人々がアバターを通じてそういうチャンスを得る機会が今後増えていくんだろうなとも思うわけです。
平野:そうですね。僕自身、極端な悲観論者でも楽観論者でもないつもりではいます。事実として、テクノロジーの進歩が僕たちの生活を改善していることは否定できませんし。特に僕たちの生活を取り囲む情報量は爆発的に増えているので、そこはAIの情報処理能力に頼らないと自分たちでは選択自体ができない状況になっているとは思います。
そういう意味では、AIやリアル・アバターが役立つということはもちろんあるわけです。異常に増えた社会の情報量を圧縮するAIだって必要だろうし、ウーバーイーツはコロナ禍で圧倒的に登録飲食店が増えて、生活に欠かせないものになった。『本心』を書く際に、車椅子ユーザーの方に取材をさせてもらったんです。すると、ウーバーイーツのおかげでアクセスできる飲食店が圧倒的に増えたとおっしゃってて。それは車椅子の方々だけじゃなくて、子育て中の人だとか、様々な事情ゆえに、なかなかレストランに行けない人たちの人生を楽しむ選択肢を増やすことにもつながっています。
そう考えると、『本心』で描いたリアル・アバターみたいな仕事は、確かに低賃金労働として搾取されることは問題ですけど、みんなから感謝される職業でもあるはずなんですよね。だから僕自身は、ワイルドの考えていたこともオーウェルの言っていることもよくわかる。ワイルドは寒空の下でするどぶさらいみたいな労働は人間のすべき仕事じゃないって言ってますけど、僕もやっぱりそれはそうだと思うんです。家事労働もテクノロジーがかなりの程度、解放してくれたことは間違いないですし。そういう意味では技術それ自体を全面的に批判するつもりはありません。ただ、社会の側で、倫理的にそれをどうコントロールしていくか考えていかないと、機械に振り回される社会になってしまうと思っています。
小川:生きている人間自体を効率・生産性・利便性といった資本主義の価値観で捉えてしまうようになっているのが現状です。どうしてそんな価値観が広がってしまったかをマックス・ウェーバーの概念を使って考えると、近代の合理的資本主義という社会において、人間が機械的に分化してしまったことに原因があると思います。そこは社会に属する人々がそれぞれリンクし合いながら組織化することで成立している。つまり、一人ひとりは全体として見られない。個人というのは、あくまでも全体にとっての手段に過ぎないという考え方が、知らない間に広く共有されてしまっている。そういう背景を踏まえて『本心』を読み直すと、楽観主義も悲観主義も両方あるものとしてアバターという表象を受け取ることができるんだと思います。
母が生前、朔也のリアル・アバターとしての仕事ぶりを見てみたいといって、彼を伊豆にある河津七滝(かわづななだる)に行かせますよね。七つ目の滝を見た後に、「やっと、朔也の仕事がわかった。あなたのお陰で助かる人がたくさんいるでしょうね」と母は言います。私、そこでグッときて思わず涙しちゃったんですけど、ここで、リアル・アバターは誰かの役に立つための仕事として朔也の母の目には映っています。
他方、ギグエコノミー的な搾取、人間を機械として扱うような利用をする依頼者も現れます。作中で、ある依頼者に知人の見舞いのためにメロンを買ってくるよう朔也は頼まれるんですが、四時間の契約時間の間、ずっと暑い中を無駄に歩かされる。途中で朔也も、これはただ、自分を嘲弄するためだけの依頼だと気づく。でも、依頼者に逆らえない朔也は、汗が滝のように流れるなか、ずっと歩き回る。あの場面、読みながら恐怖を感じました。「役に立つ」という言葉一つとっても、小説のなかでこうも多様に描かれると、読者はその言葉に込められた意味を考えさせられると思うんです。
平野:役に立つ人間であることに対して、人々はアンビバレントな感情を抱くものだと思います。つまり、資本主義体制下では、社会の役に立つと考えれば、自分自身の自尊心をある程度満足させられる反面、それが実は企業や資本家の役に立っているだけで、彼らの富を増やすために搾取されているだけだと思うと、役に立つ人間だとジャッジされることによって傷つく。
ただ、社会システムではなく、対人コミュニケーションの次元で考えると、誰かの役に立つのは喜びを感じるきっかけになり得るはずです。道で困ってる人を助ければ、それは自分自身の満足にもつながりますし。寝たきりの方がアバター的なロボットを使ってカフェで働き、人の役に立つことで自尊心が満たせる、といったオリィ研究所の「分身ロボットカフェ」のような事例もあります。
ただ、役に立たないなら生きているべきではない、みたいな言説には、当然、強い反発を抱きます。だから、リアル・アバターという仕事を構想したときに、道具としての存在と人間としての存在の根本にある違いを突き詰めて考えてみたかったんです。先ほど言及していただいた『かたちだけの愛』を書くにあたって、義足をどう捉えたらいいのか頭を悩ませたんですが、それは人間の身体が実はとても多義的だからなんですね。もちろん、人間にとって、歩く、座るといった機能的な動作は重要なので身体が機能的であることは大切です。でも、例えば、子どもがしがみつきたくなる場所とか、セクシーに見える部分とか、そういった機能性とは別種の役割も身体にはあります。だけど、義足は、あくまでも機能性重視なので、そういう意味では身体そのものの多義性をカヴァーしきれないんですね。そこが、ユーザーのストレスになる。だからこそ、今、3Dプリンターの登場と共に、道具的な義足が、一種の表現として発展しつつある。それは、『かたちだけの愛』で描いたことなんです。
決して同一のものになり得ない代替の存在を通じて、人生を前に進めていくことに、僕は興味があります。だから、ヴァーチャル・フィギュアのお母さんも、それに近い発想なんです。ただ、その場合のヴァーチャルのお母さんっていうのは、朔也にとって、自分の孤独を慰めてくれる存在で、それはやっぱり、合目的というか、道具的なんですね。でも、実在の母親はそうじゃありません。対人的なコミュニケーションで言えば、息子にとって「役に立つ」こともあるけど、でも、人間はそれだけじゃなくて、意味の束とでも言いますか、人間という存在は多面的であるので、自分が単一の意味だけで評価されたりすると、反発を覚えます。だから、複雑な意味の束としての自分を受け止めてくれる場所が社会に開かれているのであれば、自分がこの世界に生きていることを肯定的に捉えられるんじゃないかなと思うんです。
小川:今のお話は平野さんが小説家であることとリンクしていると思って聞いていました。というのも身体に機能と芸術性の二つの側面があるように、小説も芸術だけでなく、慰めや教育のための機能があるんだと思います。例えば、芸術を通じて貧困とは何かについて考えることもできる。十八世紀だと、それは絵画が担っていました。ウィリアム・ホガースは「ビール通りとジン横丁」という作品を描いて、貧しい暮らしを送る人の生活を絵で表現していた。つまり、芸術も多義的で、美だけでなく、そこから掬い取れるものもあるはずだと思うんです。
平野さんは『マチネの終わりに』でも、小説の有用性について書かれていましたよね。トーマス・マンについて触れて、彼は自分の主人公に身代わりになってもらったことで生き続けることができたんだ、と蒔野聡史は言っています。だから、小説って、読者にとっても作者にとっても役に立つものだと思うんです。ある意味では、小説は読者や作者のアバターなんです。『ケアの倫理とエンパワメント』でも書きましたが、私、マンとヴァージニア・ウルフってそういう意味では似てると思っていて。なぜかというと、『ダロウェイ夫人』のなかで、ウルフは、主人公ではなく、セプティマスというシェルショック症候群の元兵士を自殺させるんですね。確かに、ウルフは最終的に自分で命を絶ってしまったので、その点では生き延びたマンとは異なりますが、でも、なぜウルフやマンが登場人物を殺すのかって問われると、小説には自分の身代わりにすることで自分を慰める、アバター的な役割があるんじゃないかなって考えたくなります。
【アバターとしての小説の機能をめぐって】

平野:小説に自分だけでは気づけないことを教えてくれる役割があるというのは、その通りだと思います。『ある男』でも主題にしましたが、僕たちはそれぞれみんな自分なりの心の問題を抱えているけれど、そうした問題が一体何なのかわからないものです。でも、小説のなかに、自分が抱いていた複雑な感情が描かれていると、ハッとさせられて、慰められたりするわけですよね。そういった機能に興味があります。僕は十代の頃にトーマス・マンの初期作品を読んですごく感動していたけれど、よくよく考えれば、別にマンの登場人物と僕が似ているわけじゃない。彼が描くリューベックみたいな町に住む人々のルーツなんて僕とは無関係だけど、でもそんな人物を通じて映し出される心の機微が僕自身の感情に近い、というのが小説の持つ機能の重要な部分なんじゃないかと思うんです。
三島由紀夫はそのことをもっとはっきり言っています。ゲーテはウェルテルを殺したおかげで生き残ったと。彼は作中人物の死を、やはりそういう意味で捉えているんですが、彼自身は小説の結末と自分の人生のそれが合致してなければいけないと考えるようになる。だから、自分が生きようと思ってるときには、小説の人物も生きるし、自分が死を意識するようになれば、小説のキャラクターも死んでいく。僕は三島由紀夫には影響を受けてきましたが、作者と作中人物の運命を合致させるそうした方法には懐疑的で、両者を重ね過ぎてはいけないとは思っています。
小川:『ある男』で、弁護士の城戸が谷口大祐のふりをしていた謎の男の正体を暴いていくプロセスがまるで小説を読むことみたいだと比喩を使っていらっしゃいますよね。それって、まさに今、平野さんがおっしゃったことそのものだと思います。弁護士はクライアントの人生に自分を重ねることで、自分が歩んでいない人生を二重に生きているとでも言いますか。作中の言葉で言えば「誰か、心情を仮託する他人を求めている」わけで、自分の苦悩を自分だけでは処理できないってことですよね。そう考えると、やっぱり、『ある男』と『本心』は全く違う作品なのにつながっている。

三島とトーマス・マンの類似と相違も面白いですね。三島の『春の雪』では松枝清顕(まつがえきよあき)が死にますが、あれはシリーズ全体の主人公である本多繁邦の代わりに死ぬわけです。だから、戦後社会に生きていた三島が罪悪感で絶対に死ななきゃいけないみたいな心境で書いた作品だとして読むと、どこか清顕に自分の心情を乗り移らせていたところもあるんじゃないかって推察したくなります。トーマス・マン的なところは果たして『春の雪』にはあるのだろうかって思いながら、平野さんが「新潮」に連載されている「『豊饒の海』論」を読んでいるところです。
平野:そこまではそう言えると思います。ただ、第二巻になると飯沼勲という主人公が割腹自殺し、そのあたりが三島の政治活動や思想とあまりにも合致していくんです。飯沼勲の死はとても不可解で、昔はそれがよくわからなかった。今回、「『豊饒の海』論」を書くにあたって、かなりしつこくその辺を考察したんですけど、世間の理解を全て拒絶して死ぬってことに三島は価値を見出すんですね。そういう意味では、飯沼勲の心情に三島は自分というものを強く仮託していると言えると思います。
小川:平野さんは、ご出演された『100分 de 名著』で『金閣寺』を取り上げられていました。私があのなかで一番印象深かったのは、老師について論じていたところです。なぜ、老師という本来崇高でなければならない人物が、あれほどまでに醜く描写されているのか、その理由を考えたときに、老師が戦中の価値の対極にいる、つまり戦後社会を象徴する人物として三島が捉えていたのではないかと平野さんは言います。それはある意味では、歳を重ねることで人間が浅はかになってしまうネガティヴな変化に通じると思います。月日は魂を汚すと言いますか。確かに、『豊饒の海』には、『春の雪』から『天人五衰』まで、歳を積み重ねていくキャラクターがいっぱい登場するじゃないですか。昔、あんなに無垢で純粋だった飯沼茂之が右翼団体「靖献塾」の塾長になるところなんて、その最たるものですよね。
平野:飯沼茂之はビジネス右翼になってしまうんですね。
小川:ええ。でも、そのアイロニーの描写のされ方は実はオスカー・ワイルドとすごく近しいんですね。つまり、魂がいつまで経っても汚れないものであってほしいという願いが強過ぎて、初期作品でも理想的な魂を持つ登場人物には死が訪れている。
平野:ワイルドも『わがままな大男』とか『幸福な王子』を読むと、偽善というものに対して、ちょっとナイーブ過ぎるんじゃないかというぐらいの軽蔑があって、それは三島にも通じるところがありますね。『天人五衰』では、本多がただ生きているというだけで、果てしなく財産が増えていきます。三島はそのことをかなり分析的に書いていて、ストレートに資本主義批判を展開してるわけじゃないんですが、生きているだけで得をすることをアイロニカルに描き出している。三島には、未来を捨てて死んでいった戦時中の特攻隊員を始めとする戦死者に、コンプレックスと混ざり合った強い思い入れがあります。
小川:こうした問題意識は平野さんの著書『「カッコいい」とは何か』につながってくると思います。「カッコいい」というのは、社会全体で共有されるべき理想像が失われてしまった今の時代に個人がそれぞれ見出した模範的存在であるということを平野さんは書かれている。

だとするならば、本多もそうだったと思うんですね。結局、清顕という自分とは全く違う人物に自己を投影していて、そこにはいずれ自分もこうなりたいという願望が見え隠れしているわけです。だから、私には『マチネの終わりに』の新自由主義的なリチャードが本多に重なって見えてしまう。家父長的な価値観から、なんとか抜け出そうとはしている。そのため、近代の言わば負の遺産である「男らしさ」からどう脱却すればいいのかって考えるときに、『「カッコいい」とは何か』と平野さんの小説は、理論編と実践編として映ります。
『本心』では外国人のコンビニ店員が差別されているところにたまたま居合わせた朔也が立ち向かっていく、それこそカッコいい場面が描かれますよね。それを動画で見ていたイフィーという身体に障がいを持つ人物が、朔也に彼の理想像を見出す。イフィーは有名なアバター・デザイナーで、高層マンションに住んでるくらい裕福なので、投げ銭で二百万円もあげちゃうんです。自分にはお金はあるけど、身体が不自由だから苦しんでいる人を助けるなんてことはできない。だから朔也には憧れるということなんですが、反対に、身体に障がいを抱えながらアバター・デザイナーとして成功しているイフィーを朔也はカッコいいと感じる。お互い、こんな風になりたいという理想を抱くんです。
『本心』と「『豊饒の海』論」は同時進行で執筆されていたものだと思います。だから、「『豊饒の海』論」に、本多繁邦は清顕をアバター化しているなんて表現が出てくる。この辺は平野文学を考える上でとても重要だと思います。確かに、本多は『春の雪』の終盤で、清顕の代わりに、平野さんの言葉を借りれば、清顕のアバターとして月修寺の門跡に会いに行き、清顕のかつての恋人に会わせてほしいと頼む。でも、それは叶いません。清顕の代わりになることはできず、いわば化身できない情念を抱え込み、絶望に打ちのめされますよね。ここに「カッコいい」という言葉の本質があると思うんです。例えば、私も憧れの人を見たらカッコいいって思いますけど、でも、その状態からは決してその人たちに化身できない。距離があるんですね。
【「カッコいい」から読み解く『本心』】
平野:『「カッコいい」とは何か』で、僕はかなり真面目な議論をしてるんですが、小川さんみたいに僕の問題意識をしっかりと受け止めてくれる人は少なくて(笑)。あれは非常に真剣に書いた本なんです。というのも、二十世紀後半の文化を理解していこうとしたときに、「カッコいい」という概念を抜きにしては何も語れないはずなんです。マイケル・ジャクソン、エルビス・プレスリー、今だったら大坂なおみさんを、どうしてみんな支持するのか。それは「カッコいい」からですよね。にもかかわらず、「カッコいい」について論じた本が一冊もなかった。僕はそれ自体、すごく不思議なことだと思っていました。先ほど的確に要約していただいたように、ファシズムや全体主義的な体制のなかで価値観が一元化されていった後で、自由に生きなさいという時代が訪れたとしても、みんな戸惑ってしまう。それは戦後の「アプレゲール」の青年たちの問題であり、戦後を脱して高度経済成長期に突入する際、人々はみんなそれぞれの「カッコいい」を見出していきます。
カッコいいものに対する憧れは、人を努力させますし、成長もさせます。僕はそれ自体は肯定的に捉えて良いと思うし、それによって実にさまざまなものが生まれてきたことは間違いありません。ただ、悪用される可能性もあって、ネット上にインフルエンサーが溢れ返っている今、「カッコいい」は政治的に利用され得ることに留意しなければならない。倫理性をいつも問うていかないと、「カッコいい」への盲信は危険です。
そうやって考えると、個人が日常生活を営む上で、ポジティヴな向上心を維持しようとする時、「カッコいい」という概念は非常に重要なはずなんです。なのに、「カッコいい」について論じた本はこれまでまったくなかった。文学作品を「カッコいい」という概念を手がかりに読み解くなんて、論外ですよね。しかし、それも必要なことなのではないか。この問題意識は、『本心』の中で、イフィーという登場人物を通じて描いたことでもあります。
小川:私も『ケアの倫理とエンパワメント』では大坂なおみさんのエピソードに触れざるを得ませんでした。世界には彼女のことをカッコいいって思う人は一定数いるはずなんですね。でも、そんな彼女のカッコよさを否定しようとする人もいる。例えば、大坂さんはカメラの前で黒人差別の被害にあった方々の名前をプリントしたマスクをつけ、ブラック・ライブズ・マターの運動への連帯を示した。公の場で女性のアスリートがやるには、非常に勇気が必要だったはずなんです。でも、そんな大坂さんのカッコよさをスポンサーが否定してしまう。ここでいう否定というのは、大坂さんのスポンサーがTwitterで、大坂さんを応援するためにと言いながら彼女の「かわいい情報を置いておきます」などという投稿をし始めた、あの動きのことです。あれは言ってみればinfantilize、つまり、大坂さんを子ども扱いしてかわいく見せようとする試みですよね。それはやはり、ケアの視点から批判しなければならない。だから私は、あれは女性に小ささやかわいらしさを要求する言説の典型だと書きました。
『「カッコいい」とは何か』にも書かれていましたけど、男らしさには性欲と結びつく有害な男らしさだけじゃなくて、批判を恐れずに意見を述べるという肯定的な側面もありますよね。そうした男らしさには拍手を送るべきだと私も思います。ただ、それと同じくらい大事なのが、弱者に共感する力としての女らしさです。つまり、自立してはっきりと物を言う力と、周りにいる多様な人々に共感することができる力。双方を合体させた、ある種、両性具有的な能力を大坂なおみさんは持っているのではないか。むしろ、その両方から大坂さんを考えなければ、何かが見落とされてしまうんじゃないかと考えています。
平野:そうだと思います。付け加えるとすれば、「カッコいい」という概念はもともと男性中心主義と強く結びついているということです。そして、そこには「戦う」イメージが附帯している。僕は『「カッコいい」とは何か』のなかで、アラン・コルバンの『男らしさの歴史』に基づいて、古代ギリシャの「アンドレイア」という概念に注目しました。元々は、戦場における勇猛果敢さを意味する言葉のようです。
「カッコいい」と「かわいい」の違いは、後者には歯向かわないイメージがあることです。戦いのイメージがそこでは完全に削ぎ落とされている。だから、何かを「かわいい」化することには、社会にも個人にも歯向かってこない存在として去勢してしまう一面がある。
大坂さんは、強さと弱さを兼ね備えたスポーツ選手であることに新しさを感じます。スポーツ選手でありながら政治的なアピールをする、マイノリティに対して積極的に共感を示す。あるいは、彼女は試合後の記者会見を精神的に耐え難いと拒否しましたが、あれほどのアスリートでありながら、あるいはだからこそ、人間のヴァルネラブルな部分を一種の真実として見せる。そうした彼女の両羲性こそが新しい時代の魅力なんじゃないかって思います。
小川:十八世紀にエドマンド・バークが『崇高と美の観念の起源』を書いて、男らしさは崇高で、女らしさは美だと言いました。バークにとっての美っていうのは、端的に言えば、「かわいい」ってことなんですよ。私が研究対象にしているメアリー・ウルストンクラフトは『女性の権利の擁護』を書いた先駆的なフェミニストで、バークを痛烈に批判しました。男性が間違ったことを言ったとしても、女性は戦わずにかわいいふりをしていればいいんだ、というような言説に歯向かっていったんですね。メアリー・ウルストンクラフトも大坂なおみさん同様に厳しいバックラッシュに遭うんですが、それを考えると、十八世紀から現代にかけて結局、何も変わってないじゃないかってショックを受けてしまいます。「カッコいい」を突き詰めると、弱者やマイノリティへの配慮に行き着くのは当然なわけで、そこにはケアの問題が内在しているんだと思います。
平野:そうですね。時代的にもそれができないとカッコよくないとなりつつあるし、そうなってくれないと困ります。昔は俺に黙ってついて来いみたいなマッチョな男性性が賞賛されたけど、今はそれは通用しません。
【平野文学のなかでのケアの描かれ方】

小川:平野さんの文学を遡って読んで、どこからケア性のテーマが扱われているのかを探し当てるのは面白そうだなって思うんです。二〇〇九年に書かれた『ドーン』という作品は、近未来が舞台ですよね。主人公の明日人が宇宙飛行士になって、家族を地球に残した状態で宇宙へ行くんですが、そんなさなかにアメリカで大統領選挙がある。この物語では、二〇二二年に、憲法でLGBTの人たちの権利が制限されるようになったという設定がなされているんですが、候補者の一人がLGBTの問題で苦しんでいる人について考えてみてくださいって言うわけですね。それも「カッコいい」の一つの形なのではないかって読んでいて思いました。平野文学史的には、この辺りからケアを描き始めている気がします。
その後、二〇一二年の『空白を満たしなさい』では、ケアのアンチテーゼのような、利己主義を具現する佐伯という、ドーキンス的な進化論者を登場させますよね。そこには新自由主義の価値観に異を唱えるという平野さんの問題意識が色濃く反映されているように思いますが、いつぐらいからそうした考えを抱かれるようになったのでしょう。
平野:僕が育った北九州は工場の街で、共働きが普通でした。だから、女性だけが家で家事労働しなくちゃいけないという固定観念は、そもそもなかったんです。母子家庭で母が働いてたというのもありますが。
それと、僕がロスジェネ世代だっていうのも関係があると思います。僕たちの世代は、自分とは何かを散々問われてきながら、いざ、就職をしようと試みると社会の側から拒絶的な態度を取られた。結果として、望んでいた仕事に就けた人もいれば、そうでない人もいるという世代的な分断も経験させられてしまったわけです。それでも二十代の頃は体力もあるから、拘らなければ職にありつくことはできたけれど、三十代になるとはっきりと世代間格差を感じるようになった。その辺りからですかね、小川さんがおっしゃったようなことを考え出したのは。新自由主義に対しての強い反発を表明したのは、二〇〇六年から連載を始めた『決壊』辺りが最初じゃないかと思います。
小川:確かに『本心』の主人公の朔也も、『決壊』の主人公の崇とタイプは全く違いますが、どこか似ていますね。崇は頭が良いし、IQが高いのか、何でもこなせる。他方、朔也は高校を中退こそしていますが、読書量も豊富だし、地頭が良いんです。また、崇はコミュニケーション能力が高くていろんな人を魅了してやまないんですけど、朔也は逆に感受力が高い。三好さんが病気になったときにしっかりとケアをしてあげたり、どういうときにどんな言葉をかけてあげたら相手の慰めになるかもちゃんとわかってる。誰かを傷つけないというのは、男性視点では非常に大事なことだと思いますが、そういう意味では崇と同レベルのコミュニケーション能力を有しているんじゃないかって気もします。
その辺を考えると、タイトルにある「本心」とは何かという問いの答えも見えてくる。作中では朔也は、事故で亡くなった母親が、医者の認可を得て積極的に自分の生命を終結させる「自由死」を決断していたことの真相を探っていく。そこで大きなヒントになるのが、母が好んで読んでいたという架空の作家、藤原亮治の『波濤』という小説。母の担当医に彼女の死生観を知るためには、藤原亮治の小説を読んでみたほうがいいと言われ、朔也は『波濤』を読み始めるわけですね。
『波濤』の主人公はクラブで働く二十代の貧しい女性です。彼女は客にスカウトをされて、ネット番組にお笑い芸人へのドッキリの仕掛け人として出演することになる。朔也は読みながら、彼女のことをモーパッサンの作品に出てくるような人物だって言うんですが、すごい洞察ですよね。
この場面を読んだ次の日に、モーパッサンの『女の一生』をもう一度読んでみました。この小説のなかには、スタール夫人の『コリンナ』が出てくるんですよ。つまり、『本心』のなかには、架空の人物である藤原亮治が描く物語の世界があって、そのなかにモーパッサンのイメージがある。で、モーパッサンの『女の一生』を開くと、ロマン主義的なスタール夫人のコリンナが登場する。入れ子方式に、小説のなかから小説がどんどんと出てくる。
「本心」というタイトルの意味について考えてみると、そこまで深く潜れてしまう。いや、本当に驚きです。小説家が小説を書くというのは、その人がそこに至るまでに読んできたものの影響を、それが無意識であれ、作品に注ぎ込むことだと思います。だから、この作品にはモーパッサンだけじゃなく、三島由紀夫やトーマス・マン、ボードレールや、オスカー・ワイルドも入っているはず。だとするなら、朔也の母の本心というのは、平野さんが訳されているワイルドの『サロメ』と関係があったりするんじゃないでしょうか。この作品では原罪感覚が重要になってきますが、それは『サロメ』でワイルドが主題としていたものとつながっているのでは、なんていう推察をしたくなります。『本心』に出てくる女性は、みんな淫婦性があるように思えます。でも、本人たちは決して罪があるわけでもないし、汚れもなく、清らかな存在なんです。それゆえに、朔也の母、三好さん、そして朔也が高校生のときに中退することの原因となった女子高生もそうですが、彼女たちを見ていると、そこに、女性は生まれたときから原罪を背負わされている、というメッセージを読み取りたくなります。
平野:そうですね。モーパッサンの『脂肪の塊』にも、ブルジョワ社会の非常に醜いエゴによって、ドイツ兵と寝ることを強いられる娼婦が出てきます。僕はああいうモーパッサンがとても好きなんですね。今でもまったく古くない。ワイルドの『サロメ』を読んでいても、女性の淫婦性なんていうものは男性的な社会が勝手に思い描いているものだってことがわかります。それによってサロメって毒婦的な女性だとイメージされ続けているけど、大体、オリジナルの設定は少女的で、どこか愛らしい女性なんですよね。それが、いつの間にかカルメン的なファムファタールみたいな話になってしまった。そういうことを踏まえて、僕は『本心』では、この社会が女性に対して実際に強いてきた役割と、イメージとして付与してきた女性性のようなものの両方を、朔也の母や三好といった登場人物のなかにパーソナリティとして描いておきたかったんです。
本心ということに僕がこだわったのは、この社会のシステムでは、本心に則って自分で選んだってことになると、全てが肯定されるからなんです。男女関係も、今はお互いが合意してるかどうかが重要になっていますが、でも、そのときの本心は複雑です。自分では本心だって言ってるけれど、実は構造的に言わされているだけかもしれない。作中の「自由死」という制度も、本人が心から思っていればいいじゃないかって考えのもと作られたものですが、どこまで自分の意思なのか判断するのは難しい。これは、『マチネの終わりに』をはじめとして、ずっと考えてきたことです。だから、本心というのは、パーソナルで私的な問題であるにも拘わらず、社会システム全体に関わっているという意味でとても重要な概念だと思います。
【他者のわからなさを尊重すること】
小川:イベントをご覧になってくださってる方々から質問を頂いています。『本心』は最愛の人の他者性がテーマだと思います。他者性というのは、すなわち、相手の立場になって相手の気持ちを考えることだと思いますが、結局、真実なんてわかりませんよね。相手が生きていたとしても、本音で答えてくれるかどうかわからないし。平野さんは他者性についてどのようにお考えですか?
平野:僕は他者性とは何かといえば、わからないことを尊重するということだと思います。人間は、あなたが考えていることが全部わかると言われると、反発します。かといって、あなたが考えてることは全くわからないという風に切り捨てられると、それはそれで嫌です。
僕は他者性の問題が先鋭化するのは、死者に対しての態度を問うときだと思います。生きている人間ならば、勝手にこう思ってるんでしょうと断定されると反論できる。でも、死者はそれができないから、みんな死者に仮託して好き放題に言う。典型的なのは戦死者に対する言説です。僕は、亡くなった人たちに対しても生きている人間同様の配慮をするのが、死者の他者性に対する最低限の敬意の示し方だと考えています。
僕は普段、小説を書きながら、この人物はこの状況で果たしてどんな風に考えるんだろうと思いを巡らせるんです。彼だったらもしかするとこんなことを考えるんじゃないか、この場面ではこういうことを言うんじゃないか。で、書き始めの頃は、登場人物のキャラクターが明瞭でなく、わからないということがありますが、それが段々わかってくる。だけど、あるところを超えると、今度は、逆にわからなくなっている。でも、その段階に達すると、ある意味では、自分の創造した登場人物が他者として自立してくるということなんです。で、作者にとってはもう他者となってしまっている登場人物の心を考える。それは、自分勝手に書くよりも、人物が生きた存在になるということです。だから、最愛の人の他者性っていうのは、わかりたいしわかろうとするけど、それでも、やっぱりわからない部分が残る、その残った領域を尊重しながら向き合うべきだという考え方なんです。
小川:ありがとうございます。次は小説に出てくるガジェットについてです。作中で「縁起 Engi」という宇宙の時間を体験するアプリが出てきます。着想のきっかけはなんだったのでしょうか? 実は私も『群像』に書評を書いたときに「縁起 Engi」について唯識思想の方面から少し論じました。なので、平野さんの着想がどこにあったのかはとても気になります。
平野:人間の命とは何かについて、徹底して即物的に考えると、宇宙物理学みたいな話になりますよね。ビッグバンを始点にすると、命というのは百億年以上の間、続いているという具合に、随分と大きなスケールの時間で考えることになります。そのとき、今の人生が貴重だという気持ちを抱くかもしれないし、人を殺そうが殺されようが宇宙が経験している時間を前にしたらそんなことどうでもいいと、虚無感に苛まれるかもしれない。僕としては、だからこそ命は尊いと感じるのですが。 それから、「『豊饒の海』論」でも書きましたが、仏教思想の体系において縁起は最重要概念の一つなんですね。全ては相対的な関係性のなかで起きている現象の一部だと考えられていて、唯識という考え方が加わると、あらゆる現象とは阿頼耶識という識が生成消滅させているに過ぎず、客観的な実体がこの世界にあるわけではない、となる。「縁起 Engi」は、つまり、仏教思想と宇宙物理学を携帯のアプリのなかで融合させたイメージです。
小川:なるほど。私は書評で『本心』が新しい恋愛小説であることを唯識思想から読み解いたんですが、今のお話を聞いて腑に落ちました。最後に、この質問には答えておきたい。「小川さんが平野文学に注目されたきっかけはなんですか?」
えっと……、あれは私が大学院生のときだったから、二〇〇二年かな、刊行されたばかりだった『葬送』をイギリスに向かう飛行機に持ち込んで読み耽っていたんですね。私はそれまで政治思想を勉強していて、大学院で初めて文学に移行したんです。さぁ、これから文学をやるぞって意気込んでいたときに、この作品を読んで、ドラクロワとかジョルジュ・サンドが出てきて、私はロマン主義文学にすごい向いているなって確信を得たんです。それ以来なので、平野さんの文学とは二十年近いお付き合いをさせていただいています。そういう意味では、私がケアや感受性といったものを研究しているのは、遡ってみれば、『葬送』がきっかけなんですよね。
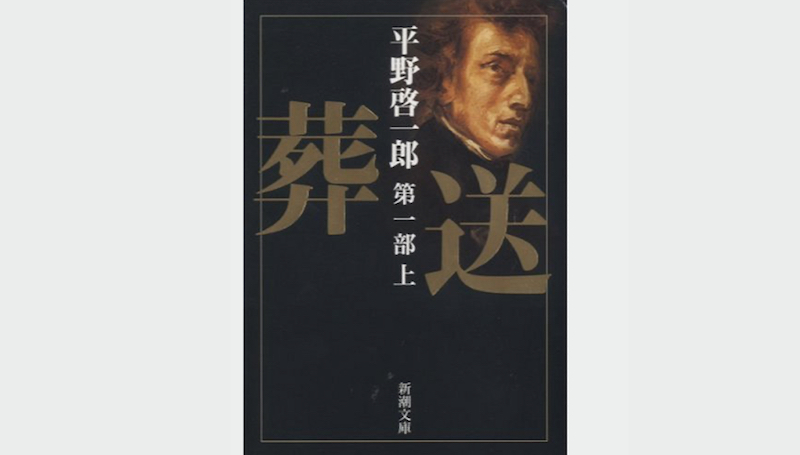
平野:恐れ多いです。ありがとうございます。僕は『葬送』を書いていた頃に、非常に多くのことを学びました。特にドラクロワの日記は芸術についてたくさんのことを教えてくれた。ドラクロワは印象派の先駆けとして、緻密な色彩理論を持っていた画家でした。赤と言っても、日差しや、物体の横に置かれているものの反映、あるいは影とかによって、相対的に変化するんだってことを言っている。
面白いのは、そんな彼が晩年になって、固有色の問題を熱心に論じていることなんです。あれだけ色を相対的に捉えている彼が、固有色の秘密に対する探求を彼の芸術的な主題の一つにしていく。そうしたドラクロワの考え方は、僕が分人主義と言いながら、一人の人間のパーソナリティとは何かを考えるようになったこととつながっているんです。
小川:今の色彩論は面白いですね。私は昔、ゲーテの色彩論に大きな影響を受けてから、人間の視神経や感覚印象に関心を持つようになりました。そこで学んだのは、人間って、先天的なものと、生まれてから相対的な価値を身につけていく後天的な部分の交わりで作り上げられているんだってことです。平野さんの小説からは、まさにそれが伝わってくる。そこにも平野文学の面白さがあると思います。
平野:その辺りを一生懸命書こうとしています。
小川:今日のお話を通じて、ますますこれから書かれる作品が楽しみになりました。ありがとうございました。
構成/長瀬海
【対談に登場した平野啓一郎の著作】
『本心』
『ある男』
『「カッコいい」とは何か』
『マチネの終わりに』
『ドーン』
『空白を満たしなさい』
『決壊』
『葬送』


