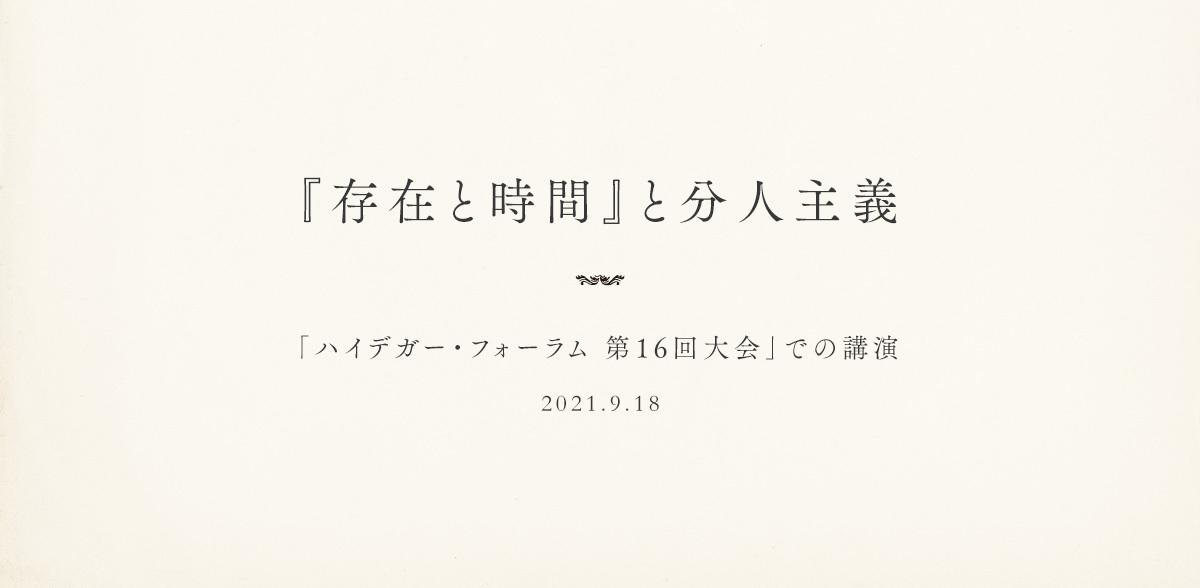この記事は、2021年9月18日に開催された「ハイデガー・フォーラム 第十六回大会」での平野啓一郎の講演を記録したものです。
父の突然死に端を発してハイデガーの思想に関心を持った平野啓一郎が、ハイデガーの名著『存在と時間』に対する共感や批判、自身の死生観について語りました。「もし今日死ぬとしたらどう生きるか」という仮定に対する考えが、一つのテーマになっています。
哲学的な論考から始まり、『日蝕』、『かたちだけの愛』、『ドーン』といった作品や、「分人主義」という概念を生み出すに至った経緯も、これまでにない切り口で明かされています。
読み応えたっぷりの講演録ですが、ぜひ最後までお楽しみください。
✳︎
「ハイデガー・フォーラム」は、20世紀ドイツの世界的哲学者マルティン・ハイデガーの思索に関心を寄せる日本全国の研究者たちの連絡組織で、ハイデガー哲学をめぐる議論を自由に楽しみながら、広く現代における哲学の可能性を追求しています。
ハイデガー・フォーラムHP:heideggerforum.main.jp/index.htm
電子ジャーナル16号:heideggerforum.main.jp/ej.htm
『存在と時間』と分人主義
ただいまご紹介いただきました、平野啓一郎です。宜しくお願いいたします。
ハイデガーフォーラムにお招きいただきまして、古荘さんや、森川さんからは、「ハイデガーにそんなにこだわらず、なんでもいいですよ」と非常に寛大なお誘いを受けたのですが、丁度、ハイデガー、とくに『存在と時間』という本のことがずっと気になっておりまして、何かの機会に再読したいなと思いながら、忙しさにかまけてずっとそのままになっておりましたので、これはひとつのチャンスかなと思いまして、改めて自分で精読し直す機会として、あえて「『存在と時間』と分人主義」という、自分の今の仕事に引き付けた大層なタイトルの講演の演題とさせていただきました。
多くの方にとっては釈迦に説法のような話も随分あると思いますし、ご疑問等抱かれる箇所も、多々あろうかと思いますので、講演後の質疑応答の時間には、活発なご意見を頂戴したいと存じます。これを機に僕のハイデガーの理解も少しは進むといいなと期待しております。あまり時間がありませんので、さっそく本題に入りたいと思います。
ハイデガーの存在自体は高校生ぐらいの頃から、倫理の授業を通じて知ってましたけど、僕はもう本当に田舎の文学少年でしたので、読む本というと岩波文庫に入っている、非常にクラシックな19世紀から20世紀初頭にかけての外国文学が中心で、あるいは三島由紀夫や谷崎潤一郎といった作家の作品を読むぐらいでしたので、思想関係の本というのはほとんど読んだことありませんでした。ただ倫理の授業ではチラチラ勉強してまして、僕はセンター試験を倫理・政経で受験しましたのでよく覚えているのですが、当時はハイデガーやサルトルぐらいまでが教科書の範囲でした。まあ非常にざっくりとした話しか書かれてませんでしたけど、なんとなく関心をもったんですね。
それからもうひとつ妙に印象に残っているのは、当時Z会という通信添削の教材を大学受験に向けてやったんですけども、その中にコラムのようなページがあって、なぜかハイデガーとナチズムの関係が詳しく書いてあった回があったんです。僕が大学受験したのは1994年ですので、その前年ぐらいのZ会ですけど、教材を作ってる人に研究者でもいたんでしょうか。
そういうハイデガーの概説的な内容で関心をもったのは、やっぱり死の問題だったんですね。と言いますのも、これはいろんなところでお話していることなんですが、僕は父が早くに亡くなっておりまして、僕が1歳の時、父が36歳の時でした。その死に方が、いわゆるポックリ病というんですかね、今だと「ブルガダ」という病名を耳にされた方もいらっしゃるかもしれませんが、非常に健康的な、ほとんど病院に行ったこともないような人だったそうですが、ある日突然心臓が止まって、死んでしまったんですね。
僕はそのときはまだ1歳だったので、全く記憶がありませんし、自分の直接の体験として、それが衝撃的にずっと残っているというわけもありません。しかし、こどものときから法事で、嫌でも三回忌、七回忌、十三回忌とか、色々な機会で死ということを考えさせられますし、父の死は突然死だったということがあって、悲しいとか寂しいとかいうんじゃなくて、ひとつの大きな謎として、自分の中に影を落としていました。
小学生の頃は割と平凡な子供だったんですけど、高学年になってきますとだんだん少し本なんかを読むようになったりもして、自分の父の死について考えるようになりました。急に心臓が止まって死ぬというのは、どういうことなのか。自分の心拍は、意識すると、どっくんどっくんと、ずっと心臓が鳴ってるわけですけど、次の一拍が鳴るって保証はどこにもないわけです。そんなことを考え出しますと、友達とテレビゲームしたり、漫画を読んで部屋でだらだら遊んだりしてると、非常に不安になってくるんですね。自分はもしかしたら次の瞬間に死ぬのかもしれないのに、こんなことをしていいんだろうか、何かもっと本当にしなきゃいけないことがあるんじゃないのか、というようなことを、実際はそれほど明瞭にではなくて非常に漠然とですけども、感じるようになりました。その頃から、だんだんと友達と話が合わなくなって、文学作品に魅了されていくことになります。
当時は、漠然と人間の死には、ふたつのタイプがあると考えるようになりました。ひとつは、80年、90年先に待ち構えている、寿命としての死ですね。それからもうひとつは父に訪れたような突然死です。これは交通事故だとか病気だとか色々な形で、その寿命に至る前のどこかわからない或る時点で突然訪れる死です。人間にはどうもこのふたつの死があるんだということを考えるようになって、80年先の死は小学生の僕にとっては、まだそれほど実感もなくて恐ろしいことではないんですけど、5分後に訪れるかもしれない、あるいは明日訪れるかもしれない死というのは、非常に強い恐怖だったんですね。
それから突然死というのは、もうひとつは予定が不可能なわけですね。つまり癌で「余命三ヶ月です」と宣告されますと、ある程度三ヶ月間という期間がわかりますから、その中で自分の人生のプライオリティというのを否応なく考えさせられます。しかし、突然死は、5分後に来るかもしれないし、5年後に来るかもしれない。そうしますと、自分の死の可能性として考えたときに、5分後に来るって思うのと、5年後に来るって思うこととでは、実際に何ができるのかという意味では、全然違うわけですね。5分後に死ぬとわかってできることというのは、本当に限られていますし、5年間と思うんだったら、その間にできることは少なからずあります。
つまり、いざ死を自覚したとしても、それが一体いつなのかというのが分からないことによって、何をしたらいいのかが根本的に変わってくる。これが、僕が当惑しつつ感じていたことのひとつでした。
そういったようなことを、正直に言いますと、六年生くらいの頃に、そんなにハイデガー的に整理して考えていたわけではありません。漠然と感じていたところでは、ハイデガーというのはどうも、人間は日常生活のなかで頽落していて、死に先駆することで本来的な生に目覚めるというか、連れ戻されるということを説いた哲学者なんだということを知って、関心を持っていたんです。
ところが、大学に入って、すぐにハイデガーを読んだわけではありませんでした。小野紀明先生の授業に出て、ゼミでもお世話になりましたので、小野先生の著作は当時ほぼ全て読んでおりましたし、そういう意味では間接的にもハイデガーという思想家に触れる機会があったのですが、なかなか、ハイデガーの著作には手が伸びず、学部時代はとうとう読みませんでした。
その時期に僕が関心持ってたのはむしろ、ミルチャ・エリアーデの宗教学でした。彼もハイデガーと同じように、人間は、死というものに直線的に接近してゆくことに存在の不安の根源があるという思想を説いています。ただエリアーデの場合は、それへの対処法として、一方では一種の神秘主義的な聖性体験を強調します。彼はインドで仏教の勉強をしてますから、解脱のイメージ、ニルヴァーナのイメージから強い影響を受けているんですね。ハイエロファニーという聖性が顕現している存在を体験することによって、俗なる時間を超脱すると。その或る種のエクスタシーの体験の中で、人間が直進的に、ユダヤ‐キリスト教的な時間の中で死に接近していくという不安から解放されるということを主張していて、僕はその発想に非常に魅了されました。
それからもうひとつは、日常世界の中に偽装されて埋め込まれている神話的なものを発見することによって、人間がただひたすら一直線に死に向かう存在ではなく、人類の大きな円環的時間の中に抱かれてると感じることが出来る、結果として、その時間の直線性の不安からも解放されるという思想も説いています。
どちらかというと、僕は自分が避けようもなく死に向かっているという不安の意識の解消として、そのエリアーデの思想に興味を持ちまして、『日蝕』という小説を書くことになり、また『一月物語』という第二作目を書きました。時間からの超脱が『日蝕』で、円環性の方が『一月物語』です。

『日蝕』を書きながら、当時はバブルも崩壊して、90年代というのは未来に明るい雰囲気もないような時代でしたので、或る種のニヒリズムに僕自身も陥っていました。阪神淡路大震災とかオウム事件とか世紀末的と言われるような事件も随分とありましたが、しかし、それでもやっぱりこの現実世界を生きていかなきゃいけないという、自分に襲いかかってくるニヒリズムをなんとか克服していかなきゃいけないという思いを抱いていたんですね。それで中世思想の中でも錬金術という物質世界を再聖化、再価値化しようとする思想運動に強い関心を持つようになりました。
そこで、文学作品による一種の聖性体験を通じて、日常性から超脱するということを『日蝕』、『一月物語』という二つの作品で試みました。それは、自分としては手応えがあったのですが、ただ、文学者として、やっぱりずっと神秘主義者で居続けるっていうことにも飽き足らないものがあり、やはり、この現実世界、地上世界を生きてる人間を、とくに現代の世界を生きてる人間を描かなければいけないと考えるようになりました。
第三作目の『葬送』では、19世紀の近代の大きな転換点を描いて、当時のポストモダニズムの流行の中で、自分なりの思索の足場を作って、その後はしばらく実験的な短編を書きながら、新しい時代を描くための方法を模索していました。
で、その頃に、実はハイデガーの『存在と時間』をようやく読んだんですね。2002年に『葬送』を書き終わるまでは、読むべき本も多くて、手が出なかったのですが、『葬送』刊行後、「やれやれ」というので、やっと手に取りました。
正直に申しますと、最初はなかなかピンときませんでした。というのは、とくにハイデガーの死についての思索に興味があったので、しばらく用具的存在とか、環境世界のなかでの配視的配慮の話が続く第一編にはもどかしさがありました。その辺の話は、難解すぎて分からないというわけではなく、用語はやっぱりかなり苦戦しましたが、何というか、すごく当たり前のことを書いてるんじゃないかという感じがしたんですね。道具というのは役に立つものとして存在していて、それに配視的な配慮で関わっていくっていうような話は、「まあ、そりゃそうなんじゃないかな」というような感じで、割とその辺はザーッと読み飛ばした気がします。デカルトの批判の辺りから、面白いと感じ始めたのですが。
それから、いよいよ死についての話が始まり、第二編に至っては、ある程度、すでに小野先生の本でも知っていたことでしたし、いろいろなところで断片的に触れていたハイデガーから予感していた内容でしたので、第一編よりは強い関心を持って読みましたが、ただ、どちらかというと当惑に近い感情を抱きました。僕自身は、自分自身のニヒリズムをどう克服すべきか、この世界をどう価値化して生きてゆくのか、ということを文学者として考えていた矢先でしたので、日常を生きる人間を、頽落や逃避、非本来性といったワーディングで語られると、そういう感覚は分かるけど、ちょっと今自分がやろうとしてることと違うんじゃないか、という感じを持ったんですね。エリアーデ流の「聖と俗」という二元論を吸収した後に、「俗」をどう生きるか、という点に関心が向いていましたので。いくらハイデガーが、「頽落」は、「何ら否定的な評価を表明するものでない」として、この「非本来的」な生に、「ある劣等な嘆かわしい存在的属性という意味をもたせ、それも人類文化の進歩した段階では匡正することができるなどと考えるとしたら、頽落の存在論的=実存的構造は、やはり誤解されたことになる」と強調しようとも、「頽落」、「逃亡」、「疎外」、「負い目」、「非本来性」といったその否定的なワーディングの故に、読者がこれを「ある劣等な嘆かわしい存在論的属性」と受け止めるのは、仕方がないと思います。やっぱり読むと、それに対して覚悟性における本来的な生や、自分の中の英雄性とかを求めて、決断主義の書として受け止める、ということがあったのではないでしょうか。
それでもその時に『存在と時間』を読んだことで、自分の思考やものの考え方には、一定の影響があった気がします。ただ、自分の『存在と時間』の読み自体が、非常にお粗末なものだという自覚もありましたので、あんまり堂々と「ハイデガーがこう言ってる」という言及の仕方は、その後もしませんでした。自分の考えていることと、『存在と時間』とを適切に関連付けていくことができなかったんですね。
その後2004年から2005年にかけて、一年間フランスで生活することがありました。そのときに、ああいう国ですから、建築だとか、デザインとかに非常に感動することが多かったんですね。例えばアール・デコ様式っていうのは、日本でも古い田舎の日本家屋の応接間とかに今もあって、うちの実家もそうなんですが、いいと思ったことなかったんですね。なんとなくダサい感じがしていたんですが、パリでアール・デコのバーとかカフェとかホテルのロビーとか見ますと、本当に立派に見えるんです。オスカー・ワイルドが亡くなったロテルというホテルが、その後立派に改装されて今は五ツ星ホテルになってますが、その内装のアール・デコは非常にカッコいいです。ああいう石造りの街ですから、歴史的な建築物、建築史が、常に都市の中に現前してる。ですから、新しい建物を建てるにしても新しいプロダクトを作るにしても、その現前している建築史なりデザイン史と具体的に調和するものでなければならないし、例えばヴィクトリア朝時代の椅子をモチーフにした、アクリルで作った新しい今時の椅子とかでも、それはデザイン史をただ参照して何か考えるんじゃなくて、実際にその辺の街に古い建物がいっぱいあって、そういう椅子も残っていて、その椅子を見ながら発想しているということを強く実感したんですね。その空間の中に歴史が現前してるから、やっぱりフランス人の服のデザインにしても物のデザインにしても、日本でそういうものを発想するのとは全然、違うものが出来上がってくる。
もともと、錬金術に興味を持っていたくらいですから、物の世界について考えていましたし、『X-KnowledgeHome』という建築誌で、ヨーロッパの建築探訪のような連載を依頼されたりして、建築もフランスだけでなく、ヨーロッパ一円を随分と見て回りました。
それから、もうひとつは、またちょっと違う話なんですが、フランスにいるとアフリカがすごく近くに感じられるんですね。日本からだとアフリカというのはどうしても遠い印象ですけど、パリにいると、アフリカから来ている人がたくさんいますし、バカンスでモロッコに行ったりする。
それで、たまたま文化人類学の研究者で、今は日本学術振興会のアフリカセンター長になってナイロビにいる溝口大助さんと知り合いになる機会があって、よく聞いてみると、僕と同郷の北九州出身だというので、当時、親しくおつきあいしていました。彼は、シエラレオネとかマリとかのフィールドワークを行っていて、当時はまだ日本であまり知られてなかった現地の少年兵の話なども教えてくれたんです。それは、反政府軍が村を焼き討ちにしたりした時に、皆殺しにするんじゃなくて、子供を誘拐して少年兵にする、その際に顔にアヘンを埋め込んで中毒にしてしまう、といった話だとか、住民の手とか足とかを切断して放置して帰って、そうすることで、社会に恐怖感を広めるだとか、政府の社会補償費用を圧迫する、といった大変な話を聞きました。で、足を切られてしまって、非常に粗末な義足で生活してる人もたくさんいて、僕もそれに対する寄付を今もしていますけど、政治的な関心と同時に、義足そのものに興味をもったんです。というのは、義足というのは、果たして身体の一部として捉えるべきなのか、それとも道具として捉えるべきなのかということを考えたんですね。それで、「義足」という短編を書いたんです。それはシエラレオネの或る青年が、反政府軍に足を切断された後、義足を付けているんですけども、ある時、義足が溝にはまってしまって抜けなくなってしまう。そうなった時に、その抜けなくなった義足を、身体の一部として捉えるのか、ひとつの道具として捉えるのか。この物質的な世界と人間との関わりの中で、僕たちは一定の輪郭を備えて、対象としての世界と接しているように見えるけれども、その義足が溝にはまってしまった時に、どこまで身体の輪郭として捉えるのかということを、その時に短編として書いたんです。それが、先ほど申しましたプロダクト・デザインへの興味と合流していったんですね。
その後、『決壊』、『ドーン』という小説を書いて、分人主義というのも考えだして、その辺から、「本質主義」を意識的に否定する立場を取るようになりました。唯一の「本当の自分」という問いの立て方は、やっぱり間違ってるんじゃないかということを考えだしたんですね。
と言いますのも、父の死以来、自分が非本来的な生き方をしてるんじゃないかという不安を、特に突然死の恐怖から抱くようになった僕が、じゃあ、どういうふうに考えていったかと言えば、「本来的な生」という言葉は使いませんでしたが、「本当の自分とはなにか」という問いに支配されていったんですね。
で、自分が将来、その死の不安を紛らわせられる、本当の自分が本当にやりたい仕事に就きたい、ということを考え出しますと、どうしてもそれは、職業選択の問題になってくる。職業選択の問題になると、終身雇用制というのが当時の基本的な前提でしたから、自分が40年間ぐらい、20代で就職して60歳ぐらいまでずっとひとつの仕事、ひとつのアイデンティティとして生きなきゃいけないっていうことになるわけですが、その時に、やっぱり本当に自分がしたいことをしたいという気持ちにどうしてもなります。そうすると、それに対応するものとして「本当の自分」とは一体なんなんだろうということを非常に考えさせられるんですね。ところが、この「本当の自分とはなにか」という問いが、僕にとっては非常につらいものでした。
まず虚偽意識を抱いてしまうということがあります。「本当の自分」じゃない自分をいま生きてるんじゃないか、と。そして、「その本当の自分って一体なんなのか」と考えるのですが、とくに就職という形で職業に対応するような「本当の自分」は、なかなか見つけることができない。そういうような「本当の自分とは何か」という問いを、『決壊』という小説で突き詰めたあと、やっぱりこれは「個人」という概念とひとつになっている。一なるアイデンティティとか、「本来的な生」といった発想自体が限界に来てるんじゃないかと考えるようになりまして、むしろ対人関係ごと、環境ごとに分化した自分の人格をすべて肯定して、自分を複数化していくことを主張すべきじゃないかと主体のモデルを転換していきました。それが、「分人」という概念の発端でした。

その考え方を具体的に書いたのは『ドーン』という小説だったのですが、この『ドーン』は2036年ぐらいを舞台にしてまして、非常にITが進んだ世界を書いてるんですが、世の中的にもWeb2.0とか色々言われたりしてまして、それまでの電話回線の遅いネットでなんとか情報摂取のために繋いでいたインターネットの世界が、常時接続になってひとつの「世界性」を備えていった時期だったと思います。
『ドーン』は、そこから想像される未来像を描いた小説でしたが、書き終えてみて、「これはフィジカルな世界に対する相当強い揺り戻しがあるだろうな」と感じました。つまり、当時はもう「Youtubeとかでこれだけコンサートとか観れるんだったら、本当のコンサートに行く人なんかいなくなるだろう」というような予想さえあったほどですが、フタを開けてみると、むしろリアルな体験というのが、その後も嫌になるほど強調されるようになりました。その気配は、既にあったんですね。
このフィジカルな世界とデジタルの世界との間の揺れ動きは、たぶん今後もシーソーのようにあり続けると思います。それでもう一回、身体とか、物質的な世界に関心を持ったときに、義足とプロダクト・デザインという、パリ時代から考えていたことを小説にしようと思い至りました。
その時に影響を受けたひとりは、プロダクト・デザイナーの深澤直人さんでした。当時は、プロダクト・デザインも、マルセル・ワンダースみたいな、それこそインターネットの時代になって、ネット上で情報として、非常にキャッチーでフォトジェニックな外観を備えたデザインが注目されていて、これは情報環境の進展の中での必然的な反応だったと思うんですが、その一方で深澤さんは、機能主義的なデザインの系譜に自らを連ねてらしたんですね。具体的にはディーター・ラムスという、今は電動シェーバーで有名なブラウンのデザイナーを務めた人ですが、彼からAppleのスティーブ・ジョブスとかジョナサン・アイブに至るまでの、一連の機能主義的デザインの系譜があって、その中にご自分を位置づけられている。
深澤さんと話していて非常に面白かったのは、深澤さんは、プロダクトの形というのは、コミュニケーションの中に内在しているんだという話をされるんですね。「何かこういうものが欲しい」という時、コミュニケーションの中でその欠落を漠然と感じているけど、それに物としての形を与えて、商品化することが出来ない。だから、デザイナーは、コミュニケーションに内在するその物の形を探り当てるのが仕事なんだと仰るんですね。
その時に深澤さんが参照されてたのが、アフォーダンスという話で、これはもともとジェームズ・J・ギブソンが『生態学的知覚システム』という本の中で書いた話なんですが、それをドナルド・ノーマンが『誰のためのデザイン』という本の中で、かなりデザイン寄りに再解釈して、それがデザイナーの間で広まったんですね。
単純に言うと、コップというのを、どうして僕たちはこうやって親指と人差し指でつまんだり、人差し指と中指で挟んだりせずに、今、普通に持つような持ち方で持つのかというのは、コップの形状自体が、持ち手にこういうふうに持つんだというふうにアフォードしているからなのだ、という話です。逆にそれを言葉で説明しないと分からない形状のプロダクトは失敗している、という主張なんですね。
ですから、深澤さんは、機能主義デザインの根幹として、人間が形状だけで、どこをどう触ったら用を為して、それが自分たちのコミュニケーションの中で生きた形で機能するか、わかるようにプロダクトをデザインしなければならないということを話されるんです。
それでその話が非常に面白くて、当時こういうSF的な設定を考えたんです。もし、この地球上から全人類が突然いなくなってしまったとして、どっかの宇宙の果てから宇宙人が来て、ここに住んでいた生物がどういう形状をしてたのかを調査しようとしたとしたなら、僕は、都市空間の中のプロダクトとか建築とかを実地に調査して行くことによって、かなり人間そっくりの形状を再現できるんじゃないかと思うんですね。
たとえば、階段の段差を見て、「ここにいた生物は、これ位の段差を登っていくことのできる足がついていたんじゃないか」とか、「足の長さはどれぐらいじゃないか」とか、階段と手すりとの関係から手と足の位置とかっていうのが想像できるとか、手すりの形状をみて、「物をこう掴む機能があったんじゃないか、しかもこれを丸くしてあるということは皮膚は相当柔らかいんじゃないんか」とか。
つまり都市空間というのは、人間の身体のありとあらゆる裏返しを、その動作の形で連続させることによって形成されているというイメージを抱いていたんですね。あらゆる身体の断片が、動きとともに連続していると言っても良いでしょう。しかもそれは、「標準的な身体」を前提にしているので、その空間自体が、また僕たちの動作にフィードバックされる。ですから、バリアフリーというのは、「標準的な身体」に基づいて作った都市空間が想定していなかった車椅子のユーザーなどを包摂するものですから、これは、宇宙人たちが身体の形状を想像する材料というより、ここに生きた生物の知性を想像する手懸かりになるのでしょう。結果、段差などがなくなっていく都市空間は、これまた僕たちにフィードバックされて、多様性を反映した世界像そのものの変更として経験されることになります。
こういう話を考え出した時に、思いがけず、またハイデガーのことを思い出しました。最初にお話ししました通り、僕はもともと、ハイデガーの『存在と時間』の第二編の死をめぐる話に関心を持っていたのですが、あの第一編の用具的存在とか配視的配慮とかいってたあたりの話が、急に面白く感じられてきたんですね。
それでとくに、「世界を構成する有意義性の指示関係の総体」が基づいている「主旨」という言葉に注目をしました。プロダクト・デザインに於けるアフォーダンスというのは、人間がいて、目の前に物があって、その物と人とのミニマムな関係性の中で考えることなんですが、その物が形作っている世界の全体は、一個の「主旨」に基づいて構成されていると、ハイデガーは言うわけですね。そして、この「主旨」こそは、政治的に議論されるべき概念なのではないかと考えるようになりました。それは資本主義なのかもしれないし、共産主義なのかもしれない。総動員体制であれば、当然、その「主旨」に則った用具的世界の構成があるはずです。ですから、プロダクトを巡って考えていたことを、ハイデガーの議論にそのように接続させると、社会全体の構造の政治性という議論を基礎づけられるのではないかと考えました。
そういうことを考えるようになったもう一つの理由が、やはり、義足だったんですね。日本に帰って、『かたちだけの愛』という小説を書くために、改めて義足について詳しく調べたのですが、義足が発展したのは、第一次大戦後に傷痍軍人が非常に増えて、しかも19世紀までの戦争と違って、爆弾とかマシンガンとかが登場しましたから、手足を欠損して帰還した兵士が非常に多かったんですね。その時に、義足・義手というものが求められていった。
更に、もうひとつは、整形外科の分野でのリハビリテーションの発展です。これは、従来の医学は、怪我した人を治すというところまでで終わっていたのですが、それだと帰還兵は短期間で回復させて再度、戦地に投入できない、或いはもう一度、日常空間に労働者として復帰させることができない、というので、リハビリテーションを行って健常者と同じように動けるところまで医学がサポートすべきだという考えになったようです。僕たちは今、リハビリテーションで怪我や病気になった人が回復してゆくプロセスを完全に肯定的に捉えていますけど、もともとは戦争への動員と結びついたものとして発展しています。そうした中で義足という道具は、歩行という目的に一義的に対応してデザインされているわけです。
難しいのは、誰かが足を怪我して失った時に、怪我の状況によって足をどの長さで切断するかが違うという点で、だから断端が長い人もいれば、非常に短い人もいます。基本的には保険医療で賄おうとするので、大量生産によって義足のコストをおさえようとする。しかし、ひとりひとりの断端のサイズが違うということで、苦肉の策として、太ももの断端を収めるソケットという部分はオーダーメイドで作るけれども、膝下はチューブと呼ばれるパイプで作られていて、それをカットして長さを調節することになるわけです。
この義足とリハビリによって、確かにその人は社会復帰できるわけですけども、これは「歩行」を一義的に目的とした一種の道具です。一方で生身の足は、もちろん歩くためのものでもありますけど、人を魅了したり、子供が「お母さん」と言って抱きついてきたり、物を持ち上げる時に踏ん張ったり、布団を蹴飛ばしたり、......と、人間の身体の一部として、非常に多義的なものなんですね。従って、一義的な歩行に特化した道具としての義足は、そういった複雑な意味の束としての身体からは懸け離れている。
美観においても難があります。義足のユーザーは、身体の一部であるはずなのに、道具的に一義的で、しかも工業製品としての必然に則って作られてたその外観にストレスを感じています。

それで、『かたちだけの愛』では、普通の足よりももっと魅力的な義足を作ろうとするデザイナーの物語を考えました。それは、義足という道具が歴史的背景として持っている、人間を兵士として戦場に、或いは労働者として都市に返せばいいとする思想から解放して、生身の足が持っている多義性へと開いてゆくということです。さもなくば、身体の各部位だけでなく、一人の人間がそもそも備えている多義性までもが、義足の一義的な目的性に矮小化されてしまうからです。
つまり、義足の思想そのものを変えることであり、その際、ハイデガーが言う「世界を構成する有意義性の指示関係の総体」の中で、用具的存在としての義足がどのように位置づけられているのか、そして、その指示関係の総体が基づく「主旨」とはつまり、どのような思想なのかを考える、ということは、まったく政治的な課題であるように思われました。
さて、時間がなくなってきたので、第二編の方をざっとお話しします。今回、改めて『存在と時間』をじっくり読み返して、スティーブ・ジョブズの有名な逸話のことを考えていました。ジョブズは、毎朝、鏡に向って、「もし、今日が人生最後の日だとするなら、自分は、今日これからしようとしている仕事をしたいと思うだろうか?」と自問していたというんですね。当人が語っていた有名な逸話で、彼の名言集などには、必ず収録されています。
僕にとって、この逸話が非常に印象的だったのは、2011年にジョブズが亡くなり、この言葉が話題になった時、僕の大学時代からの友人が、ツイッター上で、「自分なら、今日が人生最後の日だとしたら、仕事なんか放り出して家族や友人とのんびり静かに過ごしたいと思うだろうなあ。」と呟いていたからなんです。僕は、尤もなことだと笑って、リツイートしました。
このささやかな出来事が、未だに忘れられないのは、彼がその数ヶ月後に、自死してしまったからなんです。僕との関係は、さほど深いものではなかったんですが、それでもツイッターではフォローし合ってましたし、時々、やりとりもしていたので、その唐突な死には、大きな衝撃を受けました。まだ三十代半ばでした。
彼は、冗談半分でそのコメントを書いたんじゃなくて、自分がもうじき死ぬということを、非常に真剣に考えたんだと思います。で、本当にやりたい仕事をするというようなことではなくて、家族と静かに過ごしたいと心から感じたんでしょう。実際には、彼は自室で孤独な最後を迎えたのですが。そして、その前にしたことは、自分のソーシャルメディアのアカウントなどの消去です。ウェブ上に自分の社会的な存在が一切残らないようにして、自死しました。
ハイデガーは、こう言っています。
「先駆は現存在に世間的=自己への自己喪失を暴露し、現存在を引き出して、第一義的には配慮的待遇に支持を求めることなく自己自身として存在することの可能性へ臨ませるが、その自己とは、世間のもろもろの幻想から解かれた、情熱的な、事実的な、おのれ自身を確証させる、不安にさらされている《死へ臨む自由》における自己なのである。」(『存在と時間』細谷貞雄訳、92頁)
しかし、その死はまず一体、いつのことなのでしょうか? ジョブズの言葉には、一種のトリックがあります。
僕の友人が、「今日が人生最後の日だとするなら」という言葉を、後に実行する自死と重ねて、文字通りに考えてみたのとは違って、ジョブズは、実際には、「今日が人生最後の日」ではない前提の下で、猶且つ、恰も「今日が人生最後の日」であるかのような反実仮想の効果に期待しているのです。
何が違うのでしょうか? それは、可能なことの内容です。僕たちは、今日、自分が本当に死ぬとなれば、実際には出来ることはほとんどありません。それこそ、愛する人と静かに過ごすことくらいでしょう。今携わっている大きなプロジェクトを中止して、別のプロジェクトを立ち上げる、iPhoneを発売する、Apple Watchを作る、といったことは、所詮は、今日死ぬかも知れないという緊張感と共に、明日も明後日も数ヶ月後も生き続ける人間にのみ可能な決断です。実際に、ジョブズが余命数ヶ月と宣告された時には、医師は彼に、ただ身辺整理をするように、とだけ伝えています。
しかし、その身辺整理が「本来的な生」なのでしょうか?
実は、『存在と時間』も、ジョブズと同じトリックを用いているのではないでしょうか?ハイデガーは、現存在が「人はいつかはきっと死ぬ、しかし当分は、自分の番ではない」と、死をひとごととして感じていることを批判しています。しかし、死に先駆し、覚悟した現存在が、「本来的な生」を生きるためには、結局のところ、一定の時間的な余裕を想定せざるを得ないのではないでしょうか? つまり、「人はいつかはきっと死ぬ、しかし当分は、自分の番ではない」と思えなければ、何も出来ないはずです。少なくとも、自分で何をすべきかを決めて、プロジェクトを立ち上げる、ということは不可能でしょう。
『存在と時間』を幾ら読んでも、では、一体、「本来的な生」に於いて何をすべきなのか、ということはわかりません。それは、個々人に委ねられているのでしょうが、その分からない理由は、死までの時間の想定に関して、ハイデガーの思索に欠落があるからではないでしょうか?一体それは、今日のことなのか、五年後のことなのか。
実際には、『存在と時間』では、個々人に委ねるというだけでなく、覚悟性の共同性についても言及されています。
「覚悟せる現存在は、自ら選びとった存在可能の《主旨》にもとづいて、自己をおのれの世界へむかって明け渡す。おのれ自身の覚悟性こそ、共同存在するほかの人びとをひとごとでない彼ら自身の存在可能において《存在》させ、この存在可能を率先的=解放的な待遇において共同開示するという可能性のなかへ、現存在をはじめて引き入れるものなのである。覚悟せる現存在は、ほかの人びとの《良心》となることができる。」(同上、158-159頁)
ハイデガーがどれほど誤解だと言おうと、この本が決断主義の書として読まれたことには理由があるでしょう。この「ほかの人びとの《良心》」となった「覚悟せる現存在」を、後にヒトラーに重ねた読者がいたのも想像に難くありません。
「頽落」として、日常性を屈辱的に批判されているかのように感じ取った読者は、しかし、先駆すべき死をいつのことと想定すべきかも分からず、従って自分に何が可能かを具体的に考えることが出来ませんでした。そういう彼らに対して、ファシズムの無窮運動の総動員体制は、いつでも準備なく飛び込むことが出来、しかも私的な「頽落」的日常と対照的な、国家的な危難の克服という「目的」を据え、「本来的な生」の受け皿として機能したのではないでしょうか。
もし、自分で何かをしようとするなら、そのプロジェクトが大きければ大きいほど、結局誰かとの共同作業が必要になります。そして、その共同作業を維持していこうとすれば、どうしたって非本来的な生とならざるを得ない。頽落は不可避でしょう。コミュニティの中でおしゃべりなんかしながら続けていくしかない。これは、コロナ禍の自宅蟄居生活で痛感させられたことですし、僕が一頃、インターネットのおしゃべりに、ノルベルト・ボルツの『グーテンベルク銀河系の終焉』を読んで、ハイデガー的な解釈の可能性を見出して興奮したことでもあります。
『存在と時間』を読んでいて僕がずっと気になっているのは、ここのところです。研究者の皆さんが今その本来性と非本来性というようなことを、どういうふうに解釈されているのかディスカッションの中でぜひ伺いたいと思っています。
先駆すべき死を、もしかなり遠いことだと想定すると、若い人にとっての覚悟性は、結局、職業選択というような形で具体化せざるを得ないのではないでしょうか? それは、十代の頃に誰もが経験していることです。
だけど、では、労働をしていない時の人間同士のコミュニケーションはどうなるのか?僕自身として、分人主義的に考えたのは、小説家というのはもうひたすら人間の頽落を描き続けていて、人間のおしゃべりを作品化してるような仕事ですから、やっぱりハイデガーのいってるほど人間は日常生活の中で何も考えずに付和雷同してばかりいるわけでもないんじゃないかということです。トルストイの『アンナ・カレーニナ』も谷崎潤一郎の『細雪』も、ひたすらおしゃべりばかりしていますが、個々の登場人物の考えることは複雑にして多様です。
何か大きな政治的なムーブメントに巻き込まれそうになったときに、そこから距離を置いて、どういうふうに自分として生きて行くのかを考えたときに、僕は本来性と非本来性という二項対立的な発想ではなくて、やっぱり人間が複数のことに分化して、それぞれに多重帰属していて、社会の一部に巻き込まれている自分を、常に相対化して批判的に見ることができるということが重要なのではないかと考えます。
決して何かひとつの大きな権力構造の中に飲み込まれてしまって自分を失うということにはならずに、「どこどこの会社に帰属している時にはこういう自分だけど、別な人と付き合ってる時はこうで」というようなことを自覚し、その分人の構成と比率をコントロールする自由を維持する、ということが重要なのではないでしょうか。
いくつもの自分を生きている中で、どれを本当の自分、どれを本当じゃない自分というふうに序列化せずに、全部本当だということを肯定していくのが僕の分人主義という考え方の根本です。
駆け足でお話しましたけども、『存在と時間』は、ある意味では、自分の実存感覚の根底にある、父が急逝し、その後、死というものがずっと自分の中にあって、......ということに非常にマッチして、またこの世界を分析する時に大きな道具を与えてくれたようなものでありつつ、自分の思想としては小説家としてやっぱり日常生活の中で生きてる人間の心情なり思索なりをずっと細々描き続けていますので、反発もあるという非常にアンビバレントな感情を抱いています。
©︎Heidegger-Forum vol.16 2022