平野啓一郎をナビゲーターとして、古今東西の世界文学の森を読み歩く文学サークル【文学の森】。
2024年5月は、小説家・吉本ばななさんをゲストにお招きし、デビュー作『キッチン』をテーマに対談しました。
▶︎「食べる」ことで回復していく物語
▶︎「さみしさ」を埋めるために広く読まれた
▶︎省略するコツは、どうでもいいことをたっぷり書くこと
▶︎登場人物にインタビューしながら書く
▶︎たった一つのことが言いたくて小説を書いている
「食べる」ことで回復していく物語
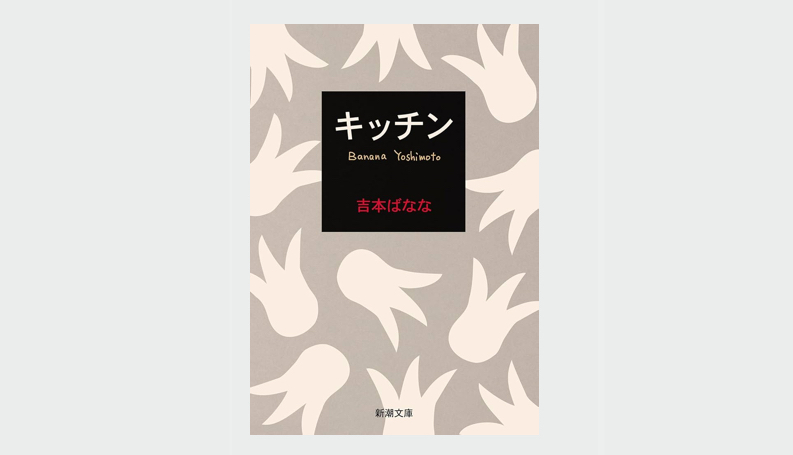
平野啓一郎(以下、平野):吉本さんのデビュー作『キッチン』をあらためて拝読しましたが、物語に出てくる様々な「食べ物」が印象に残りました。小説家が思っている以上に、読者は、登場人物が何を食べているのか気にしているんですよね。『キッチン』でも、様々な食べ物が、その場面や人物に絶妙にマッチしています。吉本さんは普段から食事や料理に深い関心がおありなのでしょうか。
吉本ばなな(以下、吉本):料理には関心がありますね。私は、『24-TWENTY FOUR』や『ミッションインポッシブル』を観ていても、食事のシーンがないことに違和感を感じるんですよ。途中でつまみ喰いとかしてくれたら、もっとリアリティがあるのにと思うんです(笑)。
平野:確かに、トム・クルーズがひと仕事終えて美味しそうに食事している場面とか、あんまり見たことない気がします(笑)。
吉本:あとは、人間の三大欲求のうち、性欲以外の欲に関する物語書きたかったというのもあります。『キッチン』の登場人物は、みんな弱っていて、コンディションの悪い人たちですよね。それどころじゃないというか、食べることでしか自分の状態を確認できないんだと思います。それくらい鈍いところが、現代の読者にとってはよかったんじゃないかな。
平野:人間の根源的な欲求としての「食べる」という行為が、登場人物が回復していく上で重要な意味を持っているということなんですね。
「さみしさ」を埋めるために広く読まれた
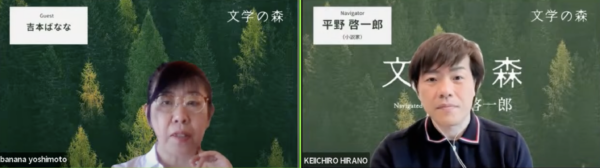
平野:文体は非常に軽快な一方で、内容は、「死」が作品全体にわたって書かれています。どなたか身近な方が亡くなった影響などがあったのでしょうか?
吉本:子供の時から、周りの人が亡くなるということはよくありました。それこそ三島由紀夫さんの自死をはじめとして、死が日常にあったことを子供心にもよく覚えていますね。
平野:吉本さんが生まれ育った80年代の東京はバブルの時期でもありますが、その影響はどうですか?
吉本:『キッチン』を書いた頃はバブルが弾ける少し前でした。一部の人は羽振り良く過ごしているけど、新規事業に失敗したり、借金のために亡くなったり、そういった死が身の回りでよくありました。私は下町の生まれ育ちで、「これは上品、これは下品」とか、「こういうことは言うもんじゃない」という確固たる価値観があったので、バブルに左右されはしませんでした。ただ、時代に置き去りにされていく人々を見て思うところがありましたね。
平野:それがこの作品の登場人物の造形にも影響を及ぼしたのでしょうか?
吉本:作風自体は、5歳くらいから変わらないんですよ。なんで人は生まれてくるのか、人生とは生きるに値するのかしないのか。目に見えないものはどのくらいこの世に力を及ぼしているのか。自分の中にはずっとあったテーマなのですが、バブルの華やかさの中でみんなが「さみしさ」を抱えていた時だったと思います。そのさみしさを埋めるために、多くの人がこの本を手に取ってくれたのかなと分析しています。
平野:「文学の森」に参加されている方からも、あらためて読み返してみて、発表当時とは印象が変わったという声を多く上がりました。今この時代に、もう一度この作品と出会い直したいと思うところがあるのも、そういった理由かもしれませんね。みんな、さみしくなっているというか。
省略するコツは、どうでもいいことをたっぷり書くこと
吉本:私の作品の特徴は、”大胆な省略”をするところなんですが、『キッチン』もかなり大胆に省略しながら書きました。だからこそ、普段本を読まない人たちも読んでくれたのかもしれません。
平野:これは、吉本さんの小説技法の中でも、僕が最も憧れる部分のひとつなんですよ。省略ってなかなか難しいんです。
吉本:どうやったら読んでいる人の心の中に空間を生み出せるか、ということを考えて、意図的に省略する訓練をしていました。文字でどうやったら余白を表せるのか。とりすぎてしまって骨子だけになって、肉付けしていくこともよくあります。
平野:大胆に省略しながらも骨子だけにならず、リアリティを失わないようにするために意識していることはありますか?
吉本:変なところをみっちり書くことですかね。どうでもいいようなところをみっちり書くと、意外とその前後を省略しても伝わるんですよね。
登場人物にインタビューしながら書く

平野:作品の中身の話についても伺いたいと思います。主人公のみかげは、唯一の肉親だった祖母を亡くして「天涯孤独」になり、自分の置かれた状況を把握できず、戸惑っている状態から始まります。そこから少しずつ回復に向かっていく、というのが書く前の漠然としたプランとしてあったのでしょうか?
吉本:なんでしょうね。急に世の中にポーンとひとりで出ちゃう、そういうときに頼れると思うものを直感として掴む。そういう危うさを書きたかったのだと思います。
平野:その時に絶妙な距離感でみかげに寄り添っていく雄一という青年がいます。その彼が、全然マッチョなところがなくて、性的なものも滲み出ていませんね。この男性像は、みかげのことを思って自然に出てきた人物像なのでしょうか。それとも、その時代の吉本さんの友達の雰囲気なのでしょうか?
吉本:いえ、この時代の友達は、みんなガツガツしてましたね(笑)。たいていの場合、私はインタビュー形式で書いています。「こんな場合はあなたはどうするんですか?」と登場人物に尋ねるんです。もし私がみかげだったら、親戚に頼るとか、料理の現場の寮に入るとか、なにかしら手立てを考えたり、現実的に人とのつながりを考えると思います。でも、みかげは私ではありませんから。みかげは、何も考えられない状態で、悲しいのか悲しくないのかもわからない、自分にお金があるかないかもわからない、できれば緩やかに自殺したい、というような人だったわけです。そういう気持ちで街を歩いていたら、同じような気持ちの人としか目があわないと思うんです。
平野:やはり吉本さんは、「自分のことを書きたい」というわけではなくて、あくまで小説の登場人物として距離をとって、物語の一人の人物を書きたいという意識が強くあるのでしょうか。
吉本:そうですね。現代の寓話みたいなものを書きたいので、あんまりリアリティに走っちゃうとそれが消えちゃうから、浮かせておきたいのかもしれません。例えば、この話を雄一の視点でリアルに書いたら、もっと薄汚れていると思うんです。男女関係が乱れていたり。でも、彼が自分自身の良いところを引き出してみかげに接するから、みかげから見たら、なんとなくよく見えてしまう。本当のところ、そういう物語だと思います。
平野:ある意味、そこがうまく省略されているというか。
吉本:一人称って、自分から見た勝手なカメラですから。その人たちの裏の裏とか、これまで何をしてきて、どういう感じでお金を稼いでいるかとか、そういうのを見ないで、乙女のカメラで切り取っている。しかし彼らの人生に暗い気配はある。だから妙な暗さが出ているんだと思います。
たった一つのことが言いたくて小説を書いている
ーー『キッチン』のあとがきに、「たったひとつのことを言いたくて」小説を書いていると書かれていたのですが、そのたった一つのこととは、何なのでしょうか?それは今も変わっていないですか?(参加者からの質問)
吉本:はい。確信を持って、人が自分で自分を成り立たせていれば、世の中が平和になるとか、人間関係が円満になるというのは感じてきたし、実践してきました。『キッチン』でも、そういうことを書いていると思ってます。
人って、本当はできるのにわざとしてないことが結構多いと思うんです。だから他人に対して、こう振る舞えば円満になるとわかっていながら、あえて複雑にしてしまっているという、「遊び」の部分がすごく多いと思います。『キッチン』の主人公みたいに、「遊び」の部分を出してる場合じゃないってなったときに、初めて気がつくことがあるように思います。
私が「あとがき」で書いたことは、人生というのは生きるに値するものだ、短かろうが長かろうが、とにかく意味のあることだということです。それをいろんな形で書いていて、意味のあるものにするためには、個人があらゆる意味で自立しているということが大切です。経済的な自立とかそういうことではなくて、人間として、自分の足で立っていて、自分はこういう人間であると、漠然とでいいから思っていられること。それが言いたかったんだと思います。それを今も書いてます。
平野:作中でも、「本当に捨てらんないのは自分のどこなのかをわかんないと、本当に楽しいことがなにかわかんないうちに大っきくなっちゃう」という台詞があります。日々の生活の中で流されていると、いろいろなことを見失いがちですが、「本当に捨てられないもの」という言葉はすごく印象的でした。これは「できるのにしないこと」という話にも繋がるのかなと思って、今聞いてました。今回は、『キッチン』についていろいろと質問攻めしてしまいましたが、一つ一つ丁寧に、予想していなかったような深い答えをいただき感激しています。とても豊かな時間をありがとうございました。
(構成・ライティング:水上 純)


