
平野啓一郎をナビゲーターとして、古今東西の世界文学の森を読み歩く文学サークル【文学の森】では、3か月ごとに「深める文学作品1冊」をテーマとして定めています。その作品に関し、1か月目は「平野啓一郎が語る回」、2か月目は「平野啓一郎がゲストと語る回」、3か月目は「読者と語る回」を開催します。
10月クールの「深める文学作品」は、平野啓一郎『ある男』。この記事では、10月28日に開催したライブ配信「平野啓一郎が『ある男』を語る」のダイジェストをお届けします。
映画「ある男」の感想、映画と原作の違いについて
──映画『ある男』が話題になっていますが、原作者から見た感想と、小説との違いについて伺えますでしょうか。
平野啓一郎(以下、平野):映画は限られた時間の枠に収めるために、小説とは別の映画的なロジックで場面を繋げる必要があります。ですから原作通りではありませんが、映画として見るとすごく納得できる作品になっています。『ある男』は複雑なテーマが絡み合ってる小説ですが、それを捨象しすぎずに、うまく生かそうとして取り組んでいただいたのがよく伝わってきます。才能のある俳優の方たちが集まっていいお芝居をしてくださったので、原作者として非常に喜ばしいですし、映画と合わせて、ぜひ小説も読んでもらいたいです。

平野:トーマス・マンの『ヴェニスに死す』はヴィスコンティが映画化して、非常に美しい作品になっていますが、やはり小説とは別物ですよね。原作では冒頭から、市民として生きることと芸術家の人生を生きることについての議論が続き、またヴェニスの海に向かう主人公の心模様の記述が数ページに渡っていて、トーマス・マンならではの読み応えがあります。一方、映画では、中年男が美少年に魅了される様子がフィーチャーされていて、同じストーリーだけど別の作品という感じがします。
──映画と原作、それぞれの良さがあるのはもちろんのこと、その上で「原作ならでは」の部分があるとしたらどういったところでしょうか?
『ある男』はかなり哲学的な小説でもあり、アイデンティティの問題や、なぜ死刑制度か間違っているのか、差別とは何なのか、といった議論がなされます。映画では、小説のように言葉によって徹底的に論じていくことにはならないので、その部分は原作を読んでもらわないとどうしても伝わらないと思います。
『ある男』ができるまで ー「アイデンティティ」と「過去は変えられるのか?」という主題
──そもそもどのような問題意識があって、『ある男』という作品を着想したのか、その経緯をお話しいただけますでしょうか。
平野:僕の小説は様々なテーマが複雑に絡み合っているので、インスピレーションが天から降ってきて感性で思いつくままに書くということはほとんどなく、思考していく過程で小説が形を成していきます。
前作『マチネの終わりに』では、”未来は過去を変える、あるいは変わってしまうのかもしれない”ということを主題として書きました。過去は、思っているよりも非常に脆弱で、僕たちは基本的に、記憶を頭の中で再構成しながら生きています。例えばトラウマ体験は、決して変えられないことのように捉えられがちですが、カウンセリングの現場では言語を通じて分析し捉え直すことで、そのトラウマ体験を克服しようとする試みが行われます。逆に、歴史修正主義のように、過去を都合よく変えてしまうという負の面もありますが、『マチネの終わりに』では、「過去は捉え方次第」ということをポジティヴな意味で強調しました。

平野:一方で、僕は小説家として、アイデンティティの問題を考え続けてきました。基本的に僕は、一人の人間を生まれながらに「こういう人間だ」と決めつける考え方に対して抵抗感があり、僕が提唱している「分人主義」も、本質主義に対抗する手段だと言えます。『ドーン』という小説を書いた頃から、そういったことを考え始め、「人間にとって、どうしても変えられないものとして残るのは何か?」という疑問を持ちました。
現代社会において、政府やある権力が人間を管理するとき使われるのは「個人」という単位です。「個人」を戸籍なり国家的IDに登録することを通じて管理するのが基本中の基本です。哲学者ドゥルーズは、『監視社会論』で、「分化した先で人間を管理していく」未来予測を書いていますが、少なくとも今はそうなっていないと思っています。分散化した人間をあくまでひとつの存在に統合していくことで管理していく。その管理圧と、管理されることから逃れたい欲動とは、ずっとシーソーのように揺れ続けている。
日本の場合、個人の管理は「戸籍」によって行われます。「親ガチャ」という言葉が流行っているように、生まれ育ちは選べないので、それを変えることはできないのが常識ですが、出自に悲惨なものがあって、どうしてもそれから逃れたい人たちが、過去を変えることを実現しようとしてもおかしくないし、実際にいるのではないかと思ったのです。オリヴィエ・ゲーズの『ヨーゼフ・メンゲルの逃亡』にあるように、戦時中、戦争犯罪に関わった人たちが身元を隠して別の都市で生きるという例もあります。インターネットが発達し、アンダーグラウンドなサイトも多々あるなか、戸籍交換という方法もありうるのではと思いついたのです。
愛する人の過去が嘘だったら?
そのようなことを考えている中で、「愛する人の過去が、聞いていた話と全然違ったとしたら、どういうふうに受け止めるのだろう?」という問いにたどり着きました。『透明な迷宮』という短編を書いたときにも、「人が人を好きになるきっかけは何か」ということを主題にしましたが、あるエピソードを共有することで恋愛が始まるというパターンが一つにはあると思います。
『ある男』でも、里枝は、谷口大祐だと信じていた「X」という男と出会い、その境遇や過去に共感し、エピソードを共有しながら徐々に好きになっていきます。家族として一緒に暮らした時間があったのに、ふたりを結び付ける上で大きな理由の一つだった「過去」が全く嘘だったとわかったら、どういうふうに感じるのかと思いを巡らし、これは物語の主題として面白いのではと思いました。
主人公を在日朝鮮人にした理由
アイデンティティの問題と関連して、ずっと書きたかったこととして、やはり差別の問題がありました。
『葬送』という小説でショパンのことを書きましたが、祖国をなくした亡命者としてのショパンの思いが彼の人生に濃厚に表れています。侵略された側の国民の気持ちを、ショパンの立場を通して考えさせられたのです。朝鮮半島の植民地化の問題にもそのころから関心を寄せていて、必然的に在日の問題もよく考えるようになりました。
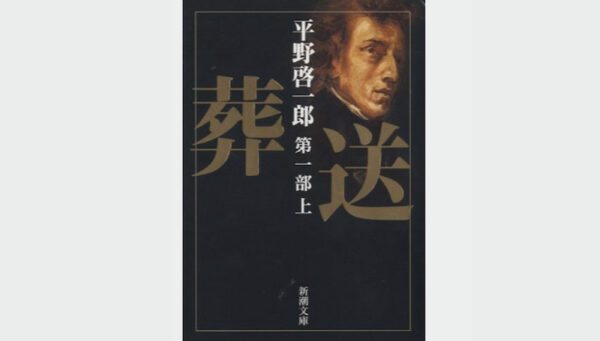
『ドーン』でアメリカの黒人差別の問題は主題のひとつとして書きましたが、日本の小説家として、国内の差別問題にはアプローチしていないことについて、これでいいのだろうかという思いもありました。
しかし僕自身は在日朝鮮人ではなく、当事者ではない人間が、自分の物語としてそれを書くというのは難しいのではないかと思っていました。部外者的な立場から、それに主体的にアプローチしていくことができるのか、最初は自信がなかったんですね。
アプローチの仕方に迷ってる間に、今度は東日本大震災が起こり、一致団結する中でナショナリズムの高まり、国の財政問題と絡めて、生活保護や生活習慣病の方へのバッシングや、排外主義的な言説が出てきて、国民を選別していこうとするような考え方が強くなっていった。今の時代の日本を描くときに、どうしても在日問題は避けて通れないテーマだと感じて、いよいよこの問題を書こうと思いました。
ただ相変わらず、自分が当事者ではないことが気にかかっていて、例えば、李恢成さんの著作を熱心に読みましたが、読めば読むほど自分には書けないのではないかと、ジレンマに陥りました。
ある時、在特会の過激なデモの映像を見ていて、僕は北九州で育ち、近くに朝鮮人学校もありましたし、朝鮮名で通学している友達や通名の子もいましたが、彼らのことがとても心配になりました。友達を心配するのは自分の中の偽りのない感情で、その意味では言わば、当事者です。
そこで、友達を心配するというアプローチだったら、感情的に偽りもなく、あるひとりの人間のことを、非当事者という立場ではない形で書き切れるのではないかと思いつきました。それで、僕と思しき語り手が、バーで知り合って仲良くなった在日三世の弁護士から聞いた話、ということを入り口にして、小説を書いていこうと決めました。アイデンティティの問題と融合させると、段々物語の全体像が見えてきました。
小説とは何かー「経由地」としてのフィクションの意味
──「アイデンティティ」や「人間にとって過去とは」ということに加えて、もう一つ、「他人の傷を生きる」ということも作品を通じて描かれる主題ですが、そのお話も伺えますでしょうか。
平野:自分の抱えている問題について自分だけで考えていると、どんどん落ち込んでいく場合でも、自分と近い経験をした人の話を経由して自分に戻ってくると、もう一度そのことに向き合えたり、自分の心の傷に触れたりすることができる。共感のお陰で慰められたりします。そのメカニズムに僕は興味があって、フィクションはある種の「経由地」として、大きな意味があるのではないかと思うのです。
僕自身も、学生時代にトーマス・マンの小説を読んで主人公に共感し、「まさに自分のことだ」と、すごく孤独が慰められたことがありました。特に初期の『トニオ・クレエゲル』や『ブッデンブローク家の人びと』は、芸術に憧れつつ市民社会にも憧れ、その両方のどちらで生きるべきかと思い悩む主人公が、小説家に憧れつつ普通に生きたいと思っていた自分の心情とすごくマッチして、とても魅了されたのです。

平野:その登場人物たちが僕に似ているかというと、むしろ違うところの方が多い。小説を書いていても思うことですが、読者は登場人物に共感したいと思っていることは間違いないけれど、読者と等身大の人物を書いたら満足かというと、必ずしもそうではない。むしろ、違う人の中に自分と同じものを見出すということが重要なのです。
この小説のメカニズムを『ある男』の作品の中に内在させようと思いました。城戸が在日という出自を3・11以降に意識しはじめて、「X」の正体を探るうちに、どうしても自分の出自を隠したかったという「X」の境遇に感情移入していきます。城戸の妻が「あなたとXとは全然違うじゃない」と指摘するように、死刑囚の子供と、在日三世とでは、何の接点もない。にもかかわらず、なぜか共感するということが、違う人の中に自分と同じものを見出し感動するというメカニズムと重なります。「小説とは何か」ということを、作中人物を通じて表現できるのではないかと思いました。
作者にとっての「クライマックス」はどこか?
──平野さんは小説を書き始める前に、その小説のテーマを象徴するようなクライマックスのシーンをまず思い浮かべるそうですが、『ある男』ではどの場面がクライマックスだったのでしょうか。
平野:『ある男』のクライマックスを物語的にイメージしたのは、森の場面です。原誠が事故に遭った森に、城戸が実際に行くと、その幻を見て、彼が振り返ったような気がしたというシーンです。
新約聖書の中に、百匹の羊がいてその一匹が迷子になり、それを探しに行く有名な話があります。ルカによる福音書です。僕はカトリック系の中学に通っていて、聖書の授業があったのですが、このことを自明のことのように教えられるとすごく不思議で、「いや、九十九匹ほっといて、一匹を探しに行くかな?仕方ないと諦めるのではないか?」と当時は思いました。しかし大人になると、信仰とは別に、やっぱり味わい深い話だなと思うようになったんです。これは、神と罪人との関係を表現したたとえですが、一匹を探しに行く方が、人間としての振る舞いとしても美しいと思います。
その話と重なって、人間社会の外側にポツンと置き去りにされているような名前もわからない存在を、城戸が探し続けて迎えに行ってあげる物語になるのだと、最終的に自分の中でイメージできたんです。そこで最後に声をかけるとしたら、「ずっと探してたんですよ」と言ってあげるのではないか。そしてそう言われたら、きっと嬉しいだろうと思ったんです。そこから小説の構図全体が見えて、これで書き始められると思いました。
(ライティング:田村純子)


