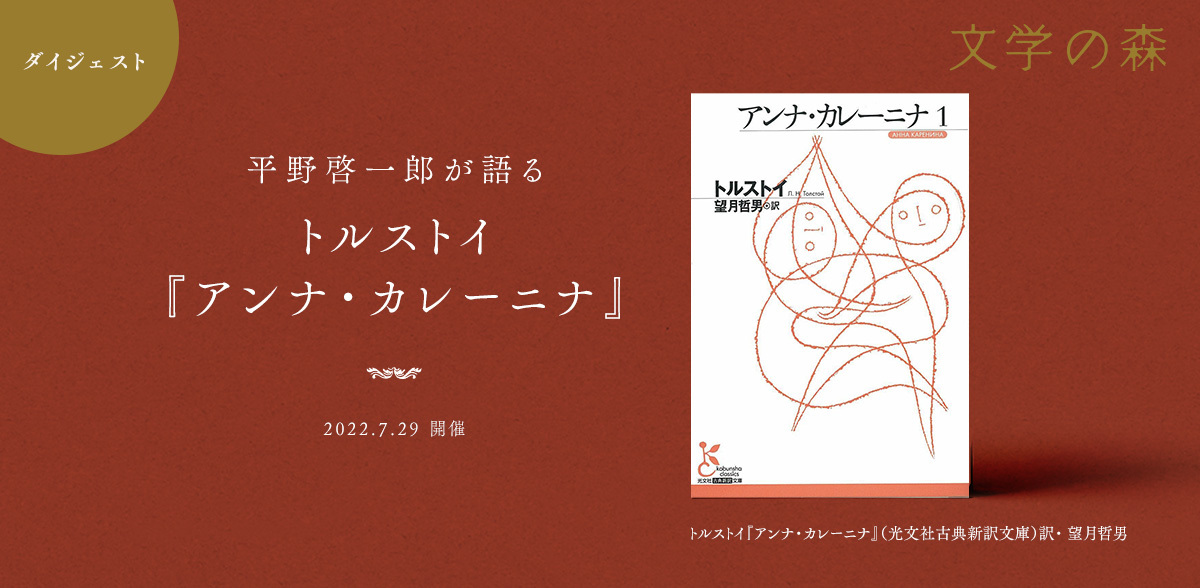平野啓一郎をナビゲーターとして、古今東西の世界文学の森を読み歩く文学サークル【文学の森】では、3か月ごとに「深める文学作品1冊」をテーマとして定めています。その作品に関し、1か月目は「平野啓一郎が語る回」、2か月目は「平野啓一郎がゲストと語る回」、3か月目は「読者とのQ&A」を開催します。

7月クールの「深める文学作品」は、トルストイ『アンナ・カレーニナ』(光文社古典新訳文庫/望月哲男訳)。
ドストエフスキーと並んでロシアを代表する文豪、レフ・トルストイ。中でも代表作の一つであり、後世の小説家に多大なる影響を与え続けている名作『アンナ・カレーニナ』をテーマ作に選定しました。
平野啓一郎が語る、トルストイの見事な「分人の描き分け」とは何か? そして文学が持つ「社会の価値観を柔軟にする力」とは?
この記事では、その一部をダイジェストでお届けします。
【トルストイの登場人物に見る「分人」】

平野啓一郎(以下、平野):僕はもともとはドスエフスキー派でしたが、作家になり分人主義的な観点から昔の古典的な名作を読み返したときに、トルストイの人物造形は分人の描き分けが非常に巧みで、これがトルストイの魅力だなと思いました。夫のカレーニンと過ごしている時のアンナ、ヴロンスキーと一緒にいるときのアンナ、あるいはカレーニンと暮らしながらヴロンスキーと一緒にいるときのアンナ、兄、子供といる時のアンナ、ドリーが来訪し二人で話してる時のアンナや、リョーヴィンといる時のアンナ、それぞれの描き分けが非常に巧みです。
これは、同じくロシア文学のドストエフスキーとの対比で僕が感じることです。ドストエフスキーの作品には、分人化していく人物もいれば、イデオロギーの権化のような枠にはまった人物も登場します。イデオロギーに一体化した『悪霊』のキリーロフはどこの場面でもキリーロフであり、対して『罪と罰』のラスコーリニコフは、分人化が描かれている登場人物です。彼が罪を認めていくプロセスで、分人の構成比率の変化があり、それがとても重要だと思います。具体的には、彼が人を殺すまでは、孤独に本を読みながらずっと自分の中に閉じこもっていた分人が、ソーニャと出会ってからは、彼の中でソーニャとの分人が大きくなっていく。このプロセスが彼の人格の変化に大きな影響を及ぼしていきます。
【トルストイのリョーヴィンとドストエフスキーの主人公との違い】

平野:望月訳を読んで改めて思ったのですが、『アンナ・カレーニナ』は、もう一人の主人公リョーヴィンの物語としても抜群に面白いと思います。ですがリョーヴィンの魅了が何かを表現するのは結構難しい。ドストエフスキーの小説に出てくるような、非常に強固な思想を持ち、イデオロギーを体現したような人物や、人殺しなど怪奇なことをする人物ではありません。またリョーヴィンは高邁な理想を持って突き進み、運命を切り開いていくというような英雄的なタイプの人でもなく、農村経営に乗りだしても、ドラスティックな改革を進めることはしませんでした。義兄はインテリとして農民と関わることが大事だと主張しますが、リョーヴィンは農民との生活を自分と一体化していて、農民との距離の取り方に悩みます。『ある男』でも引用した場面があるのですが、農民と一緒に日夜働いて、夜星空を見上げる場面の描写は陶酔感があり、大変美しい場面として描かれています。
年下の女性キティに純粋に憧れつつ悩み、いよいよ結婚するときは、敬虔なる信者でないことに罪悪感を感じます。リョービンは世の中の平凡な価値観に従って生きつつ、そのこと自体に疑いを持ち、細かいことにも誠実に考え抜いていくその連なりが、彼を非常に魅力的な人間にしています。ドストエフスキーの登場人物のように、暗黒世界の中で絶望的にもだえ苦しみながら悩んでいるのとは違います。彼は自殺の危機に瀕するぐらい、最後には非常に深い悩みを抱くのですが、人柄の良さが滲みでるというのか、平凡な人生を、悩みながらも意義あるものとして生きようとするまっすぐな姿に、大変感動的なものが感じられます。
図式的な対立ではない、何か表現し難いものを言葉にして表現するところに文学の良さがあるとすると、今自分がこう生きているという、生活自体を全面的に肯定するような思想を着地点にしているリョービンは、決して特別な人間ではないけれど、何かそういうものを非常に上手く体現した極めて類まれな登場人物だと思います。
【文学は社会の価値観を柔軟にしていく上で重要な意味を持つ】
平野:まずこの小説は、構成が非常に緊密な作品だと思います。アンナとブロンスキーとの出会いは人身事故が起きた列車で、それが反復される形で列車のモチーフが出てきます。小説の冒頭が主人公ではないオブロンスキーとドリーの夫婦喧嘩から始まっている点は不思議です。ドリーの心は深く傷つき、不倫は深刻であるけれど、実はよくあることとして描かれています。追い詰められたアンナとブロンスキーに対して、みんなが隠れてしていることを、おおっぴらにやったから責められているにすぎない、という描写があり、さらに小説の最後でカレーニンとアンナの確執が深まって、アンナが思い詰めて自殺してしまうことと、対照的に描かれていると思います。
—2019年日比谷での平野さんの講演会の時に、『アンナ・カレーニナ』を例に不倫についてお話されたことが印象に残っています。
平野:はい。みな自分の名において意見や価値判断を求められると、保守的な事しか言えず、価値観が硬直していくと思うんです。文学作品の中には、道に外れた人が出てきても、アンナなら、彼女が孤立してしまった状態や彼女の性格的な問題などを読者は思いやって考えたりすることができます。その人に共感する気持ちがあるから、不倫してるからだめだとか、さすがにそこまで硬直的なことは言わないと思うんですよ、それがいいかどうかは別にして。文学を題材にして、自分から少し引きはがした意見として言えるのが、文学を話題にするところのいいところだと思います。それが社会の価値観というのを柔軟にしていく上で、すごく重要だと思います。
【恋と愛を区別して考えること】

平野:僕は恋愛を恋という状態と愛という状態に分けて考えてはどうかということを提案しています。恋は短期的に激しく燃え上がり相手と結ばれたいと強く願う感情で、それに対して愛は関係の継続性が重視される概念だと考えています。人間は激しい恋の状態のときには愛の状態に憧れるし、穏やかにずっと結ばれてるような愛の状態が続くと、激しく誰かに恋し思いを寄せる状態にまた憧れる。この両方がシーソーのように揺れ動くのが人間の恋愛感情なのではないかと思います。
継続的な愛の状態にいることに退屈して、あるいは満足できなくて、激しい恋を時々することもあるかもしれませんが、その結ばれた相手とまた愛の状態に至って、ずっとその関係が継続することが幸福かどうかは、また別でわからないですよね。つまり配偶者と別れて不倫相手と結婚してみたけど、うまくいかなかったというのは、今でもよく聞く話ですね。結婚に限らずお付き合いの時にも、新しい人と付き合ってみたら前のパートナーの方が良かったということも結構あります。アンナの場合も、カレーニンとの愛が続きながら、ブロンスキーに恋をしている状態のときは良かったのに、ブロンスキーとの愛という関係が始まってしまうと満たされないというのは、非常によくわかる話です。
【『マチネの終わりに』では「大人の恋愛」を書こうとした。】
平野:少年少女の恋というのは、学校で勉強すること以外に社会的にしなければならないことはあまりないですよね。だから現代の若者の恋は、他者から好かれるかどうかという、コミュニケーションの問題や比重がとても大きいと思います。お互いに好きになったら、思い合うことで満たされることが理想的になるけれど、大人の恋愛となるとそれぞれに仕事や社会的な責任もあり、いつも相手のことばかり考えてずっと一緒にいるわけにはいかず、社会と個人のバランスの中で恋愛するのは、大人にとっての常識的な恋愛なのではないかと思います。
大人になって本当に全てを投げ打って、仕事も何もかも捨てずっと一緒にいようというのは逆に共感しにくいし、そんなことが可能なのかという疑問も抱きます。『マチネの終わりに』で「大人の恋愛」を描くにあたって、結構それは意識したテーマだったんです。それぞれに仕事やすべきことがありながらも、同時に、相手のことも好きだという思いや行動を貫くのが、大人の恋愛なんだと思います。
(ライティング:田村純子)

ご入会後は、これまでの配信すべてをアーカイヴ視聴していただけます。
小説執筆の裏話や近況のことなど、テーマ作の枠を超えた質疑応答、雑談も大歓迎。小説家の案内で、古今東西の文学が生い茂る大きな森を散策する楽しさを体験してみませんか?ご参加をお待ちしております。