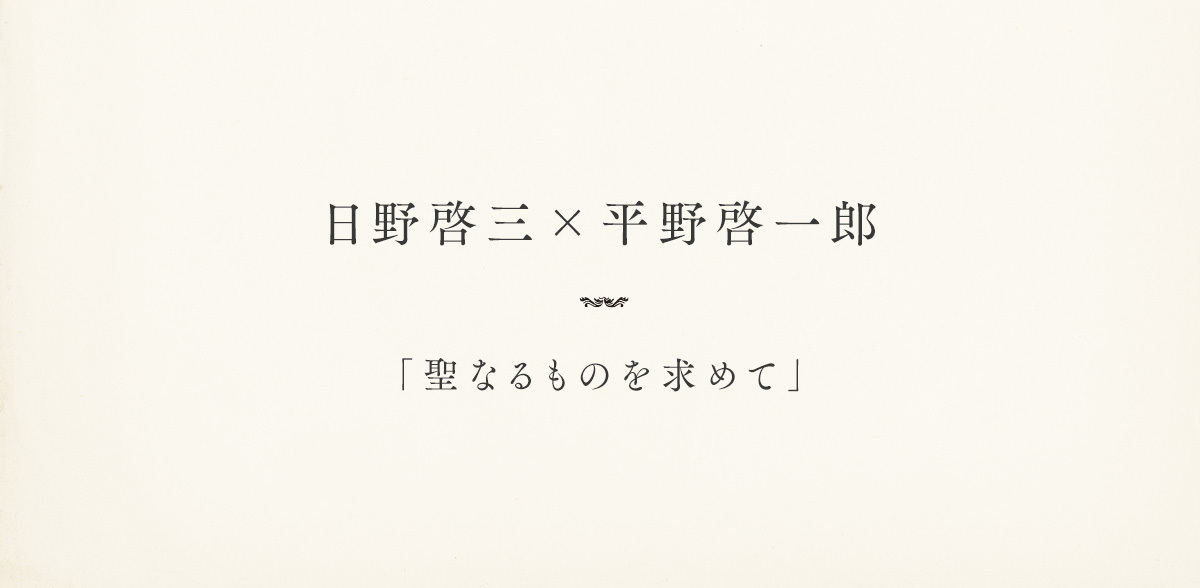最新エッセイ集『文学は何の役に立つのか?』刊行を記念して、2007年刊行の『ディアローグ』(講談社)収録エッセイを公開します。『ディアローグ』は電子書籍をこちらよりご購入いただけます。

日野啓三×平野啓一郎
──「聖なるものを求めて」
【エリアーデを手本に】
日野 今日の対談の参考にと思って、平野さんが「スタジオ・ボイス」の二月号に書かれた「小説の『現代性』とは」というエッセイを読んで来たのですが、特に後ろのほうの「私は、芸術作品を通じ得られる絶対の体験、我々の聖性恢復と存在の新しい次元の獲得とが、現代人を救済し得る可能性を信じている」というところを読んで、ぼくが何十年ひそかにやってきたことと同じ、これじゃ対談にならないな、と思いました(笑)。
平野 ぼくは日野さんのエッセイ集を読ませていただいて、僭越かもしれませんが、興味の方向が近いんじゃないかと感じました。ですから話しやすいというのはありますけど、対談にはどうなのかなと思っています(笑)。
日野 ただ、「絶対の体験」とは本当は言葉にしてはいけないことなんですよ。昔の禅の師匠だったら、そういうことに触れようとしたら相手の口をふさいだはず。少なくともエッセイとか対談でしゃべっちゃいけない。小説で表現することなんです。もう一つ事前に読んだもので、新聞のエッセイでエリアーデのことを書いてらしたけれども、エリアーデは論文だけじゃなくて小説も読んでいますか?
平野 はい、いちおう。
日野 そうですか。ぼくは、小説のほうは読まなければと思いながら読んでいないんです。 は、自分は宗教学者よりも小説家と言われたいと言っているけれど、彼の小説はいいですか。
平野 ぼくは好きですけれどね。ただ、甘いと思う人はいるかもしれません。ぼくは彼の日記が好きでよく読むんです。それを見れば、学者が片手間に小説を書いていたという感じじゃなくて、小説が彼の本質的な関心事であったことがよくわかります。
日野 彼はルーマニア人ですよね。フランス語や英語で書いているけれど。
平野 小説だけはルーマニア語で書いています。時間の問題がテーマになることが多いですね。
日野 ぼくは小説を書くとき、普通の意識状態から小説を書く状態に意識を転換するために踏み台を使うことがあります。たとえば誰かの著作の二、三ページを読んで、意識状態を高めて書き始めたりします。四十歳ぐらいのときかな、エリアーデをその踏み台に使った時期がありました。彼の言う「世界の中心の樹」はそれからもぼくの意識の中にずっとあります。九年前にガンで慶応病院に入院したとき、病室の窓から正面に東京タワーが見えるんです。全身麻酔から覚めかけたときとても意識が乱れて、幻覚や幻聴が次々と現れて、そのとき東京タワーだけが夜、真っ暗な空に銀色とオレンジ色でスッと立っているのが見えて、それで狂いかける意識を最後の線で食い止めてもらったということがありました。この世界には、あるいはぼくの意識の中にも本来一本垂直の軸があるんだぞ、ということを東京タワーが示してくれたみたいで。
平野 ぼくはエリアーデから決定的と言ってもいい影響を受けているという気がします。
日野 彼は変な人ですね。この人はべつに自分で世界じゅうを回っていろんな資料を集めたわけじゃないんだけれど。
平野 そうなんです。基本的には文化人類学者ではなくて、比較宗教学者ですから。やっぱり学者として出発する時点で、ルーマニアという辺境にいたという事実が大きな意味をもっているんでしょう。彼には、手に入る資料は全部読まなければ、ヨーロッパの学問の中心にいる人たちが持っている情報から遅れるんじゃないかという恐れがあって、結局そのコンプレックスがずっと尾を引いて、あの膨大な資料蒐集につながっているようです。
【聖性示現の表現】
日野 『日蝕』の中でぼくが最も気にかかった人物は、ブランコに乗っているジャンという嘘の少年でした。あれが一番気になります。
平野 あの少年の人物造形にはかなりいろいろな要因が重なっていて、なかなかひと口には言えませんが。ただ、基本的に主人公はトマス主義者ですから、理性によって世界は理解できる、記述できると考えるわけです。中世合理主義というのはアリストテレス受容以降のもので、常に何かの目的がある。ところが、ブランコ遊びというものは行って帰るだけで、何の目的もないですよね。それを見たときに、トマス主義者である主人公はゾッとする……そういうことは一つあります。
日野 ブランコの場面は、ニーチェの「永劫回帰」も思い出させますね。
平野 それも意識してました。
日野 そうですか。だから非常に魅力的で恐ろしい。登場する場面は短いけれど、あれは作品構造の中で軸の一つを担っている要素だなと思いました。
平野 実は『日蝕』を書こうと思ったときに、十九世紀のロマン主義者たちのように「暗黒の中世」としてロマン化するのではなく、可能な限り当時の実態に迫りたいという気持ちがありました。それで中世のものをいろいろ読んだのですが、結局人間は思ったほど変わっていないなという印象がすごく強かった。たとえば『薔薇物語』にみられるような、恋愛を一つの戦争にたとえて権謀術数を尽くして攻略しようとする感覚は、スタンダールまで基本的には変わっていない。
日野 『日蝕』は、書かれている思想も面白かったけれど、それ以上に物語り方が面白かった。クライマックスの場面でページを白くしているところがありますね。ああいう究極の場面、無限と有限が接する本当に書き難いところは、真っ白にしてもいいんです。ぼくもそういう場面をどう書くかいつも考えていて、『光』という長篇小説では、月面で宇宙飛行士が太陽光をじかに見るところはごく自然に、カタカナと漢字だけになってしまった。ただ、『日蝕』を読みながら「ああ、これやっちゃったか。あとで困るぞ」と思いました。あれは二度と使えないですから、次にああいう聖性示現の場面と書くときにどうするんだろうと思いました。
平野 ぼくは、小説とは言語表現不可能なものの表に浮かび上がってくる現象のようなものだと思っています。『日蝕』では、あの場面で、その現象を少し破ってその彼方のものを覗かせる手法をとっています。ただ、芸術も人間的な限定を受けている以上、宗教儀式や偶像と同じように、その内部において聖なるものを完全に表すことは出来ないという気持ちはあります。
【存在の不確かさ】
日野 人間そのものが有限だから、人間の行なうこと、考えること、つくること、すべて有限ですね。けれども、有限さを思い知らされるのは、誰にでもある体験ではない。たとえば、ぼくは十六歳のとき外地で終戦を迎えてすべてをなくしたり、ベトナム戦争の特派員に出たり、歳をとってからガンで死にかけたりした経験があって、少しずつ人間的なものすべては有限だということがわかっていった。これは、必ずしも頭で考えてわかるというものではない。平野さんの場合、何かそういう体験がありますか。
平野 自分の過去を探っていって、自分の考え方を規定する原因が唯一あるとすれば、それは父の死だと思います。父は病気には縁のない人間だったんですけど、ぼくが一歳のときに、ある日突然心臓が止まって死にました。そのことはぼくの中では二つの意味がありました。一つは、ぼくの実存感覚の本質的な部分がそれで形成されてしまったことです。自分の心臓の鼓動を一つ、二つ……と数えるときに、三つ目が鳴っても次の四つ目が鳴る保証はどこにもないという気がして、特に十代のころは、たとえば友達と遊んでいても、ふと自分の心臓のことを考えると、こんなことしてられない、という気になりました。それから存在論的な次元で言えば、ぼくの物心がつく前に父が死んだことで、確かに存在はしたんだけれども記憶がない父ということがあります。
日野 記憶はないけど、その実在感覚は家のなかに満ち満ちているはずですよ。
平野 ええ。だから、存在と無という二元論にあてはまらなくて、非存在というかたちで、つまり「ある」ということと「ない」ということの中間的な存在として常にぼくの中に父はあり続けていたんです。ある意味ではそういうイメージが神に対するぼくの感覚と連続性を持っているのかもしれないですけれど。
日野 でも、多少特異な経験から「だからこういう文学が出るんだ」と単純に言ったら間違いだと思う。それは幾つかのきっかけの一つに過ぎないし、もともとそういう気質があるからそういうふうになるんですよ。
平野 そうだと思います。存在の不確かさについては、日野さんのエッセイ集でも思い当たるところがありました。ぼく自身は、言葉がなくても、色彩とフォルムと、それから触覚とで存在の確かさは十分に保たれているんだという感覚はあったんです。ところがあるときから、隣りにいる人間の顔を見て、自分とこいつは鼻の形も違えば顔も全く違う。体のどこをとっても一つとして同じものはないのに、視覚器官だけが全く同じにできているとはとても思えないと考えるようになったんです。たとえば自分が見ているコーヒーカップとこいつが見ているコーヒーカップとでは、実は全く違うものを見ているんじゃないか、という具合に。 形而上学的な合意を全く排して、肉体に認識をすべて委ねたとき、われどんどん共通のものから遠ざかっていくという不安はありました。いま自分が見ている世界というのは、人間の器官がそういう具合にできているからそう見えているにすぎないのであって、いま見えているものの奥にあるのは何かということを考えると、存在の不確かさは自ずと強く感じられました。そして、そういうこと考えている自分自身も危険だと思いました。
日野 これはずっと後になって経験したことですが、全身麻酔のあと本当に幻覚を見たんです。あなたは今、隣りの人と違うものを見ていると言ったけれども、自分が見ているコーヒーカップだってある意識状態で見ているので、その意識状態の中心点がずれると、見えるものが消えて、見えるはずのないものがはっきり見えるのです。あれはショックでした。目に見えているから本当だ、というのは嘘で、むしろ触覚のほうが幾らかマシという気がします。
平野 それはありますね。西洋人はやはり視覚偏重のところがあって、そこが基本的につまずきのもとだと思います。
日野 日本人に限らず、ほとんどの人が一日の多くの時間をテレビに費やしてるから本当に視覚偏重の時代なんです。視覚というのは理性に近いでしょう。「このごろよくものが見えるようになった」という言い方は頭がよくなったと言ってるんですよね。「おまえはものが見えていない」とか、「よく見えた」とか「見えるようだ」とか。文章についても、理性的、意識的で、存在の不確かさをあたかも確かであるように見せる文章を、明晰な文章とか、目に見えるように書いている文章という。たとえば三島由紀夫や大岡昇平の文章が「明晰な文章」と言われたわけだけれど、ぼく自身も触覚的な文章が書きたいと常々思いつつ視覚的に書いてしまう。
【文学の原風景】
日野 ところで平野さんは、二十歳の頃に文学の風景はどう見えていましたか。ぼくのことを言うと、中学の頃までは小説はあまりよく読んでいなかったけれども、芥川龍之介の「歯車」とか「或旧友へ送る手記」が大好きで、終戦で内地へ引き揚げてくるとき、リュックしか持てない中に、全集の中から「或旧友へ送る手記」だけ千切って持ってきたぐらいでした。旧制高校に入ると、寮には志賀直哉の文章をしっかり原稿用紙に写す変なやつがいたし、そのころ現れてきた太宰治や織田作之助らの新戯作派について「これが文学だ!」と興奮してる連中もいた。ちょうど戦後文学のはしりの時期で、野間宏とか椎名麟三、埴谷雄高なんかが新進作家で、さほど認められてなかったけれど、一番ぼくは身近なものとして読んでいた。外国文学では、その頃一番流行っていたのがサルトルの『嘔吐』で、カミュの『ペスト』も、戦後ヒューマニズムの流れのなかで読まれていた。ただ、ぼくはカミュは少し読んで、これは先がないと思ってすぐやめたし、サルトルは『嘔吐』は面白かったけれども、ほかのものは「この人は学者で小説家じゃない」と思ったんです。ぼくにとって親しかったのは、トーマス・マンとアンドレ・マルローです。『荒野の狼』のヘッセも近かったし、ロシア文学も、ドストエフスキーをよく読んだ。とにかく、そんな偶然の風景の中でぼくは自分の文学的目覚めがあったわけです。あなたの場合、十五歳でも二十歳でもいいけど、 文学を意識したときにどのような遠近法があったんですか。
平野 ぼくはいわゆる文学少年ではなくて、絵や音楽に対しては興味があったんですが、文学は、小学生のころは誰でも読むもの、たとえば『坊っちゃん』などを読む程度だったんです。でも中学生のとき、三島由紀夫の『金閣寺』を読んで、大げさに言えばちょっと衝撃を受けたんです。ただ、ああいうもののモチーフの意味がわかるようになったのはずっと後になってからですが。そのときは、たとえばルーブル美術館でダヴィ ドの『ナポレオン一世の戴冠』を見て、モチーフはどうでもいいけれどある種の荘厳さに圧倒されて感動するように、三島に圧倒されたわけです。それ以降、三島を読みながら、三島が言及している作家を読んで、自分の読書の幅を広げていきました。勿論、ある程度読書を続けていれば、自然とその範囲は広がってゆきますが。 大学に入ってからは、古典的な教養を積極的に身につけようとしてましたから、同時代の作家について目を向けるようになったのは最近のことです。
日野 三島はどういうところが近かったんですか。
平野 三島に対しては、気質としてすごくシンパシーを感じます。基本的に三島という人はロマン主義者ですが、表現においては一定の秩序志向をもっています。 そういう芸術家の系譜はありますよ。たとえばショパンは死ぬまでバッハとモーツァルトを敬愛していたし、ドラクロワにしても、新古典主義には反発したけれど古典主義に対してはシンパシーを持っていて、文学ではシェークスピアよりラシーヌという人でしたし。初期のニーチェなんかも、ディオニュソス的なものはアポロン的なものの仮象のもとにしか眺め得なかったという立場です。
日野 秩序がないと怖いんですよ。 ある意識タイプの芸術家は枠がないと自分がどこへ行っちゃうかわからない。
平野 ぼくも、表現においては一定の秩序を求めますが、それは自分の中にあるものを全部解放してしまったらどうなるかわからないという恐怖感があるからです。 現代アートなどには、奔放な表現が たくさんありますけれど、解放することへの恐怖感が表現の際にない人に対してはちょっと不信感がありますね。
日野 よくわかる。フォルムに対する感覚をかなぐり捨てて、自分の中のドロドロしたものを垂れ流すと、逆に薄まってしまいますね。少なくとも、意識の上で枠がないと、表現が弱くなると思います。その意味では、二十世紀後半の諸芸術について、そう単純に時代が進歩したとは言いにくいとあなたも書いていたけれども、絵とか音楽についてはそう思いますね。
平野 ぼくもそう感じます。
日野 個人の行動にしてもそうです。たとえばキレたから、ムシャクシャしたからといって犯罪を犯す例が増えてきていますが、それで自分が全的に解放されるはずはない。キレた状態で瞬間的に暴発しただけで全的な解放になるほど人間存在は単純ではないですよ。自分を本当に生かしたい、自分自身を本当に感じたいというのは、手続きや自己訓練や時間をかけなければとてもできないことです。
平野 先ほど、芸術は絶対的なものを完全に描くことはできないといいましたが、それでも芸術に信頼を寄せているのは、芸術というものが現世の個物を通じての無限の開示みたいなことを、アルカイックの社会からずっと積み上げてきたからです。
【言葉と意識】
日野 この世界、この宇宙には、一回限りで後戻りできない出来事が幾つかある。ビッグバンのことは別にしても、三十五億年前の海の中で化学変化が起きてDNAができてしまったら、生命は後には戻れない。同じように、十万年ほど前、文法の基本をもった言葉ができてしまった以上、言葉がない昔にはもう戻れないし、言葉にしなければあらゆるものが認識できなくなります。「言語を絶したもの」ということすら、言葉がなかったら言えないわけだから。言葉に縛られていくわけで、不自由と言えば不自由ですね。さらに、死の意識というものも同じように出てきます。死体なら猫でも感知するけれど、死という形而上学的事実というか、個々の死体じゃない死一般、私もいつか死ぬという意味での「死」、そう
いう書き言葉的な認識はネアンデルタール人ではなく新人になってからですね。それから葬送儀礼が出てきて、もう少し秩序立ってくると、プリミティブなかたちですけれど宗教的儀式と芸術というものが急に生まれる。こういう幾つかの要になるものを越えると、もう後戻りできません。 言葉のなかったとき、意識がなかったときにどうしても憧れますけど。
平野 結局現象学などもその辺で行き詰まったようなところがあると思います。やはり意識が生まれた瞬間から、 人間はほかの生物と完全に違う次元に行ってしまいましたね。
日野 大脳皮質の前頭連合野が勝手に大きくなって、意識を持たされてしまったわけ。
平野 動物にとっては、認識する際には、必ずしも言葉は必要ではないですよね。たとえば犬に骨を投げても、地面と骨とを一緒に噛むことはしない。骨を個物としてちゃんと認識しているんです。でもわれ がそれを認識しようとすると、どうしても言葉が介在してしまう。
日野 ほかの動物はみんな言葉なしに生きている。仲間同士愛し合ってるし、友達もいるし、ケンカもしてる。だから言葉はなくてもいいんですけど、われわれにとっては言葉のない状態への郷愁さえも言葉でしか言えない。
平野 死の自覚も、意識が生まれなければありえないわけですからね。ぼくは存在か無かという二元論はもう通じないと思っていて、死のあとの、要するに物質としては無なんだけれども存在の余韻のようなものがある状態は、完全に無になるまでの間にかなり長く続くと思っているんです。神というものは、もともとの存在の実体がなくても余韻がある存在として、存在と無の中間的な部分に位置していたと思いますが、人間が死のあとに尾を引いている余韻の感覚を持ったときに、それに霊的な意味をこめたというのは、神に対する感覚とその余韻に対する感覚とがどこかで連続していたからじゃないかと思います。
日野 霊的な感覚というのはぼくにも経験があります。北極圏の湖のほとりを歩いていたときに、ふと五十億年前の岩そのものだと思えるぐらいの断層が見えた。動物も植物も一切いないところなんだけれども、何かがいる気がして、これを霊と言ったんだな、と思いました。もしかしたら、ぼくらが言葉による認識以前に、世界を丸ごと感じとっていた能力の名残りかもしれないですね。
【思考の究極としての小説】
日野 平野さんたちの世代に期待するのは、世界を全体で見て、さらに意識のメタ次元でも見て、メタレベルのロジックを考えて、メタレベルの知覚を創り出して欲しいということです。ぼくは、小説を書き始めたときに「小説というのは酒と女だ」「女を描けなきゃ小説じゃない」とか、イヤになるほど言われたけれど、そんなだったら楽ですよ。確かに一つ一つの領域と一定のレベルに限って、しかもそれ以上のことを予感しないで書くと、書きやすいし、非常にりっぱな結論が出ます。
平野 そういう結論はわかりやすいですしね。
日野 けれども少し横のものと一緒にして考えたら、すぐ矛盾が出てくるんです。だから一つの問題に限定しないで全体を描いてほしいし、それが一番できるのは小説だと思います。論文やエッセイは、結論らしきものをつけないと格好悪いでしょう。小説は結論がいらないんですよ。小説というのは、人類の発明した最も新しい、とても柔軟で豊かで便利な思考の方法だと思います。いろんなことを重層的に書ける。結論なしでいい。カフカの『城』には終わりがないけれども、十分に美しいです。 対立するものの両方を良しとすることもできるし、あらゆるものを否定することもできる。このごろよく「小説が衰えた」とか「文学はダメになった」と言うけれども、実はわれわれは小説というすごいものにまだ慣れていなくて、使いこなせていないんです。 技術的にも、まだ臆病なくらいだと思います。
平野 ぼくもそうだと思います。無意識の発見によって、伝統的な「理性と感性」のような対立が相対化されてしまった時代にこそ、小説は一つの思考の究極としての存在意義を大きくしていくと思います。
日野 そうですね。 ぼくらは戦後ずっと、勇ましいスローガン的評論、スローガン的小説をあれこれ聞かされ読まされてきたけれど、そのときはカッコよく、一元的に正しいとされてきたものがどんどん時間の中で相対化されていってしまった。逆に、濃いリアリティをそっくり持った、割り切れないもののほうが残っているんです。新しそうなものほど古くなる。新しいところから古くなっていく。近代小説は終わりだ、なんて言われて、周りを見渡すと何となくそんな気がする状況でもあるし(笑)、寂しいなと思っていたところに、あなたのような人が登場してきてくれて非常にうれしいです。
平野 ありがとうございます。
日野 ぼく個人の気持ちに限らず、小説というものの本質を考えたとき、あなたのような人が出るべきだと思いますし、必然だという気がします。ヘンなのが入り込んできた、どこかから降ってきたと思う人もいるだろうと思うけど。
平野 そうでしょうね(笑)。
【宗教とモラル】
日野 同志社大学教授の落合仁司という人が『〈神〉の証明』という本でとても面白いことを言っています。トマス・アキナス以後のローマのキリスト教では、トマス主義によって神と人間が離された、遠くなったというんですね。グレゴリオス・パラマス以後のギリシア正教のほうでは、瞑想の中で人間はほとんど神に近くなり得るのに、ローマでは人間と神が遠ざけられ、神の声が聞こえなくなってゆく。他方アジアの大乗仏教では「煩悩即涅槃」という、この「即」のために余りに仏が近くなりすぎた。遠くなりすぎたほうと近くなりすぎたほう、どちらでも神と人、絶対と相対、無限と有限のバランス感覚がおかしくなって、西欧世界とアジアの新興経済諸国は、二十世紀になってひたすら俗化して、それに対してギリシア正教圏とイスラム圏がまだ神と人との関係を保っていて俗化していないというんです。ぼくもアジアの「即」というのは前からいかがわしいと思ってました。西田哲学も「一即多」でしょう「即」という漢字を一字挟むと何でもくっついてしまう。「煩悩即涅槃」で神と人がほとんど違わなくなってしまうと、金を儲けようが賄賂を取ろうが、甘ったれた私的体験をイージーに書こうが、何をしても救われる。おかげで東北アジアは経済的に発展できたけれど、精神的なものを底深く失いつつある。特に日本についてはいまいろんなことを言われますけれど、今後は絶対的なものにつながる垂直軸を、われわれの文化に、また個人の中にもきちっと立てて、無限との関係をきちんと見定めていかないと、ズルズルと「煩悩即涅槃」 ままになってしまう。
平野 ぼくは、「煩悩即涅槃」という考えを否定しても現代のモラルに宗教がどれほど力を持つかはわかりませんが、ただ宗教にとってモラルの防波堤としての意味は付帯的なものにすぎないと思います。
本質的には、人間が身体を有している限り、そういう絶対的なものへの感覚は失われないとぼくは思います。ただ、物質文明の進歩とともにそうした自覚は鈍っていきますから、聖なるものが存在しているにもかかわらず意識されないという非常に危険な状態になるわけで、芸術を通じてそういうものに触れることは重要だと思っています。
日野 ぼくも危険だと思いますね。宗教はモラルとは別の次元のことですからね。
【「運命的な作家」】
日野 小説というものは、そのときそのときの時代現象に添い寝するというものだけでは、すぐに古くなっていきます。もちろん小説は詩とは違うから、具体的な個物、日常の現象に即さなくては書けないけれど、言葉を持って以後のわれわれ、ホモ・サピエンスの、最も根源的で簡単には解決されない矛盾の悲しみを描かなければならない。ただ、そこに居直って「悲しみ即救い」になってしまうと困るので、意識を深めてより高いレベルを目指していくわれわれの生きる意味を小説によって考え、シミュレーションしなければならないと思います。
平野 ぼくもそう思います。
日野 そのためには、いろんな方法を使うべきです。場所をどこにとってもいいし、題材も何でもいい。最近は方法的、つまり技術的に不勉強な作品が多いです。せっかく二十世紀には様々な文学的実験がなされているので、それを文章にも構成にも貪婪に利用していろんな書き方をしてほしい。不思議なことに、いい小説を読んできている人たちは、たとえ作者がどんなことをやったって、「この小説には何かがある」ということがわかるんですよ。 すぐにではないにしても、必ずわかってもらえます。
平野 ぼくも、『日蝕』を発表したとき、出す以上は自作に対して多少の自負みたいなものは持っていたんですが、こういうものが今の段階で果たして受け入れられるのかという不安は相当強かったんです。でも日野さんのエッセイを読みまして、僭越かもしれませんが、問題意識の近い作家がいたということに、うれしい驚きを感じました。
日野 ぼくの好きな言葉では「職業的な作家」ではない「運命的な作家」ということになるかな。それは、書かずにはおれない、書くことが生きることだという、私小説作家という意味ではなく、小説を書くことでしかうまく表現できない問題を抱えこんでしまった人間という意味だけれど、そういう「運命的な作家」はその時代においては孤独だけれども、ある種の人々にはわかるんです。「あっ、ちゃんと光っているよ」と。どこかでそういう人が見ていると信ずるから書くんですよね。先行する時代の、あるいは外国の文学を読んでいて、「なんだ同じようなことを考えていたのか」ということが何回もありますから、どこかの誰かが「おまえもそんなことをやってたのか」と、いつか言ってくれるであろうものを
書けばいいわけです。
平野 ぼくもそういう考えに近いです。
日野 この歳になって、また三度もガンで死にかけてから、自分が小説を書いてきてよかったと本気で思っています。ぼくは若いときには、小説という大それたこと、危険なことにはできるだけ近よらないほうがいいと思っていました。初めに文芸評論を書いて、そのあと小説を書きはじめて、芥川賞をもらったのは四十五歳のときですから。いつの間にか少しずつ魅せられていったわけですが、時間をかけてきていまはよかったと思っています。
【言葉の普遍性】
日野 平野さんはまだ二十三歳でしょう。遥かなる未来があるけれど、あと四十年も五十年も書かなくちゃいけないのは大変だなあ。
平野 やりたいことの数を考えれば、全然足りないですけれど。
日野 それはいいですね。
平野 もちろん一方では、やはり大変だというのはあります。『日蝕』 書き終わったときも、「快い達成感」とはほど遠い感覚でした。とはいっても、もう書かなくなるかといえば、結局書かざるを得ない。
日野 作品って貪婪に母体のエネルギーを吸い取るから。ところが、多感な魂はまた自然に妊娠するんですね。ぼくは一旦書き終わったら、その作品のことは忘れてしまいます。いとおしんで何度も読み返すこともない。一つの小説で無限をあらわすことはできないんだから、出来がいい悪いということとは別に、常に不満ですけれど、もう次のことを考えている。でも、書くことがなくなっている人もたくさんいるからね。
平野 書くことがなくなる、なくならないというのは、作家のタイプにもよりますよね。
日野 私小説作家は材料がなくなるだろうなあ。
平野 日本の私小説の伝統って、根深いものがありますね。ぼくは私小説とは全然違うところに身を置いていますけれど、敵に回して戦う気にはならないです。これだけ続くと、意味を考えてしまいますし。
日野 日本でこれだけ私小説が続いているのは、書かない部分までお互いにわかったつもりになれるからなんでしょうね。たとえばアメリカだとルーマニアから来た移民、ポーランドから来た移民、アイルランドから来た移民といて、お互いに相手がわからない。私小説を日本ふうに書いたとしても、多くの人には伝わらないでしょう。
平野 それは会話とか、日本人の言葉全部に言えることでしょうね。たとえば「善処します」と言ったときに、日本人なら顔色を見れば、よほどのバカじゃない限り、善処してくれないということがわかりますけれど、外国人は口に出さないとわからない。
日野 日本は少なくともこの二千年、島国で鎖国状態だった。もし元寇のときに台風が吹いていなかったら、知らない人種と出会ってどう話をするかというのを苦労して考えて、ある種の普遍性が出てきたはずだけれど、二回とも神風が吹いちゃった(笑)。
平野 そうですね。本当に単なる偶然ですけれど、それが歴史的にはこれだけの意味を持つんですから。
日野 この島国の鎖国状態は胎内瞑想に近いですよ。 生まれ出たくないんですね。けれども、もう許されないです。日本人が生活水準を徳川時代のレベルにまで下げるつもりならいいですが、今の生活水準は外と関係しなければ保てないし、そうなると以心伝心では通じないから、変わっていかざるを得ない。そういうことが小説の文章にもある種の変化をもたらしていくと思います。
平野 以心伝心といえば、日本のなかでも京都は特にそうですね。わざわざ言うことがはしたないという感覚があります。
日野 ただ、大阪弁や沖縄方言を使った小説でも、会話は方言でも地の文は標準語でしか書けない。普遍性を持つ方向には向かっていると思います。私小説の伝統も、長い歴史から来る必然だけれど、私小説というレベルでは対応できないような多層的な現実になりつつあるし、私たちの無意識を含めた意識全体、知覚の質も不気味なほど多層化しつつあるということでしょうね。
【「私」を語る】
日野 実はぼくは、私小説だけでなく 「随筆」も嫌いなんです。エッセイなら書きますが。 「エッセイ」 とぼくが言うときには、その中に思考が入っているわけですが、随筆、随想というのは気分を書いている。「私、こんな気分」「あっ、私と同じ気分ね」というので通るわけです。どんな気分でどんなことをして、たとえばペットが死んで悲しいなんてことなんかが、ぼくに何の関係があるかと思う。
平野 ぼくはトーマス・マンが好きなんですが、それはたとえ個人的な問題から発していても普遍的なレベルまできちんと象徴化されているからで、少しも普遍化されないまま、個人的な問題を文字として提示されても、「べつにおれの知ったこっちゃないよ」という感覚はありますね。ぼく自身もそういうものは人に見られたくないという気持ちがあるし。
日野 そうです。マンが、それを意識してやっているのか、自然にそうなってしまうのかは分からないけれど。
平野 マンは意識していると思いますけど。
日野 マンの育ったリューベックはハンザ同盟の港町で商人の町だから、異なる文化の人間にも伝わる普遍性が自然に身についていたのかな。スイスなんか、山国だから少し違うでしょう。ヘッセやユングはスイス出身ですよね。
平野 そうです。
日野 ぼくはユングの自伝が好きで何回も読みましたけど、奇々怪々ですよ。 子供のときに空から大きなウンコが降ってくる夢を見たなんて。けれども西欧では、小説やエッセイはきちんと垂直軸と普遍性への志向のあるものしか残っていかないでしょう。日本の場合は日常的な「私」にべったりな小説でも残してしまうし、『枕草子』以来随筆というものも連綿と残っている。
平野 おのれを語るということにはそれなりの苦痛が伴うかもしれないけれど、それはストリップ劇場で女の子が裸になるときに感じる苦痛と変わらないですよ。創作において芸術家が本質的に感じる苦痛とは全く別もののはずで、それがとり違えられているのではないでしょうか。
日野 私小説を擁護する人たちは私小説には自己があるとよく言います。自己表現がある、つまり「私」を語っていると。私小説でない小説は「私」がないからつくりもので、「作者の血のにじむ自己がない」と言う。「つくりもの」という日本語は悪い意味でしょう。
平野 結局それは、自我がないことへのコンプレックスの裏返しじゃないですか。自我が「あるかのように」ではないかと。強烈な自我に苦しんでいる人は、かえってそういうものを露にしない方向を目指したくなるように思います。
日野 私小説に対する批判は、議論ではなくて、日常的個人的経験を直接題材にしなくても「私」を表現できる作品をつくることですよ。私小説の伝統的基本線をはずれると、とめどもなくエンタテインメントになってしまうんじゃないか、という不安が日本の文壇には強くありますから。
平野 はあ・・・。
日野 この問題になると、いつも二者択一になるんですね。私小説か、「私」のないつくりもののエンタテインメントすれすれないし問題小説か、というふうに。でも問題の立て方が間違っているんで、むしろ「私」のあるフィクションのほうが近代小説の本道だと思いますよ。文体さえもつくる。
【個性の表現】
平野 私小説作家といっていいかどうかわからないですけれど、志賀直哉は、ぼくは特に好きというわけではないですが、ある種の天才だと思います。志賀の倫理の判断基準は好きか嫌いかでしかない。でも、個人的な好き嫌いというのが普遍的な善悪にぴったり合致しているから志賀はすごいというわけですが、そういう人が、特に教育において、小説の理想として存在し続けたというのは、ある意味で悲劇ですね。
日野 その志賀直哉の文章を十回原稿用紙に写したのが、昔は本当にいたんですよ。しないよりいいと思うけど・・・・・・。
平野 「私」のあらわれということで言えば、「個性的な表現」は面白いけれど、その人の「個性自体」が表現されても何の共感もないですね。
日野 「私」は他人との違いの係数ではない。
平野 今の日本人は個性という妄念にとりつかれているようなところがあると思います。西洋では、絶対王政のあとに革命が起こって、政治体制としてはようやく自由になれたと思っていたところに、今度は産業革命が起こってしまった。その時彼らは、機械の一つみたいになって自由を奪われている人間を見てゾッとしたと思うんです。それで個性ということをやかましく言うようになったんでしょう。西洋人が日本に来たときに、たとえばサラリーマンがみんな同じような格好をしているのを見てゾッとする感覚は、彼らがかつて覚えた感覚と同じだと思いますけれど、ただ日本人の均一性というのは、彼らが恐怖の対象とした産業革命以降の均一性とはまたちょっと出どころが違うと思います。にもかかわらず、外国人に「日本人は個性がない」と言われると、文部省なんかは戦々恐々として、個性の教育とか言うわけです。
日野 ぼくはヘロドトスの『歴史』を三、四年前に初めて読みましたが、個性の表現とは違う非常に客観性のある記述で、しかもユーモアがあるんです。客観性にはユーモアが伴うというのは発見でしたね。
平野 日本文学には、質のいいユーモアが本当に欠けていますからね。
【恩寵としての経験】
日野 このごろはもう答えないようにしてますが、作品はつくるものか、体験を描くものかと二者択一で聞かれることがよくあります。確かに小説の材料になるから、いろいろな体験をしたほうがいい。ただ、体験というのはいろんな次元で言えます。たとえばぼくはこれだけ生きてきて、おそらく何万回と夕陽を見ているはずです。ところが小説で夕陽を書くとき、そのうちの三回か四回、本当に夕陽そのものに出会ったと思った、その魂の経験としての夕陽しか書いていない。女性もそうでしょう。そういう体験は、自分で探してできるものではない「恩寵」のようなものですが、本当に深い経験というのはそういうものだと思う。
平野 そうですね。
日野 小説に書いて、読む者の心を深く打つのは、そういう経験なんです。だから、小説は作者がつくりあげるものではあるけれど、本当に全部はつくれないし、むしろつくれない部分に作品のリアリティがあるとも言える。つくれないからおもしろいとも言えるし。それなのに、よく「この小説で何を書いたのですか」とか聞かれる。あなたも聞かれたでしょう?
平野 聞かれますね。
日野 そのたびにぼくは怒るんです。もし書く前にこのぼくが思っていたことしか書いていないのなら、そんな小説は読む必要もない、と。 前に考えていなかったことが、書いている途中で一種の霊的体験として出てきたら、それはいいものだし、何を考えて書いたかなんて質問は無意味ですよ。あるいは書き終わっても気がつかなくて、人から言われてはじめてわかることもあるでしょう。作者自身でさえも気がつかないことを作品そのものから読み取ってくれる、それが本当の文芸評論家だと思うけれど。
平野 エリアーデは、彼の最高傑作といわれている『妖精たちの夜』について、自分は書き終わったあとにこの小説に含まれている意味を理解して愕然とした、というようなことを書いています。日野さんと同じような経験だと思います。
日野 「なぜ小説を書くんですか」ということの答えがそれです。世のため人のためだったら、もっと役に立つことがたくさんあるもの。
【芸術家の生活】
日野 あなたが京大の法学部で、しかも四年生だと聞いて、実は少し心配になったんです。法学部だから大企業に入れるかもしれない。もしかしたら大蔵省に入るかもしれない。そうすると小説はなかなか書けなくなる。考えてみると、あなたが考えているような小説を書いて、それで楽々食えるとは思えない。けれども、就職先がそこそこにプライドと誇りと収入の持てるところに行くと、小説を書くのがばからしくなります。あなたはもう間もなく卒業するかどうか知らないけれども、どういう生活をするかというのも重要です。それは俗っぽい、どうでもいいことじゃないんですよ。
平野 ええ、それはそう思います。
日野 大富豪の息子ならいいけれどね。
平野 どこかの大企業に就職するというつもりはいまのところはありません。若さに任せて、食うのに困ったらアルバイトでもして、ぐらいのことしか実は考えていないんです。ただ、文章一本で生活していて、食うのに困って筆が乱れるよりは、全く別の仕事をしているほうが自分の好きなように書けるんじゃないかという気はします。
日野 一番いいのはね、金持ちの女をつかまえるの。
平野 それはいいですね(笑)。
日野 いまは働いてる女性で、自分の仕事に働き甲斐や生き甲斐がないと、芸術家を養うというのは悪くないんじゃない。
平野 パトロンですね。
日野 だって、芸術家にはパトロンがいなきゃね。芸術というものは余剰なものなんだから。だけど何となく、なくてはならないものだから。
平野 ワーグナーなんかパトロンでもっていたわけですからね。
日野 冗談みたいに言ったけれども、せっかくの才能を持ちながら小説が書けなくなることもあるから。
平野 肝に銘じておきます。
(初出「文學界」 1999年3月号)
●日野啓三(Hino Keizo)
1929年東京都生まれ。東京大学文学部社会学科卒業。小説家。1974年『此岸の家』で平林たい子文学賞、1975年「あの夕陽」で芥川賞、1982年『抱擁』で泉鏡花賞、1986年『砂丘が動くように』で谷崎潤一郎賞、『夢の島』で芸術選奨文部大臣賞、1993年『台風の眼』で野間文芸賞、1996年『光』で読売文学賞を受賞。著書に『夢の島』『砂丘が動くように』などがある。2002年死去。