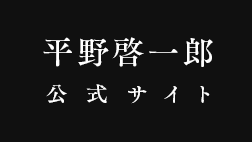このイベントはアンスティチュ・フランセ日本の主催による第13回『読書の秋』の一環として2020年10月31日にアンスティチュ・フランセ東京にて開催されたオンライン・ライブイベント『対談 ローラン・ビネと平野啓一郎』の書き起こしです。歴史的、社会的問題に妥協せずに取り組んできたローラン・ビネ氏と平野啓一郎が本イベントで出会いました。
彼らは、既成概念を超えて、そこに新しい視点から光をあてることを試みています。
ローラン・ビネ(パリ)+平野啓一郎(東京)+司会:佐々木敦(東京)
【前作『HHhH』とは全く違う『言語の七番目の機能』】
佐々木:本日はオンラインで、フランスの作家ローラン・ビネさんと平野啓一郎さんの対談をお送りします。私は司会を務める佐々木敦と申します。オンラインでの対談というのはなかなか奇妙な感じはしますけれども、丁度ローラン・ビネさんの小説第二作目の『言語の七番目の機能』の翻訳がでましたので、平野さんには後ほど感想を伺うとして、まず作者であるビネさんから少し執筆の経緯をお話しいただきたいと思います。
ご存知のように、ビネさんの前作の『HHhH―プラハ、1942年』はナチスドイツを扱った独創的な歴史小説で日本でも大変話題になり、二作目の翻訳を期待する声も多かったと思います。今回は読者の予想を大きく裏切って、ロラン・バルトの死をめぐるミステリー仕立ての作品で、いわゆるフレンチセオリーの代表的人物たちが実名で登場します。前作と大きく異なる二作目をどのようにして書かれたのでしょうか?
ビネ : みなさんこんばんは。まず日本に行けずにとても残念ですが、こういう形でもイベントができることを嬉しく思っています。
おっしゃるように『言語の七番目の機能』は前作とはかなり違う作品です。おそらく平野さんもそうではないかと思いますが、実際私は毎回テーマを変えるのが好きな作家なのです。前作『HHhH』では、ナチスドイツについて十年間かけて書いたので、もうこのテーマでは書きたくないと思っていました。
今回なぜロラン・バルトについての小説を書いたかといいますと、ロラン・バルトは私の思想の形成に最も影響を与えた人物であり、私は歴史の勉強から始め、のちに文学を専攻しましたが、その時にテクストの分析の仕方を記号論者のロラン・バルトから学び、とても尊敬していました。ご承知のようにバルトは交通事故で亡くなってしまいましたが、奇妙なことにクリーニング屋のトラックに轢かれた時、彼は身分証明書も鍵も持っていなかったのです。私はこの事実は推理小説の題材になると思い、彼が暗殺され持ち物を奪われたという設定にしました。もちろんこの陰謀物語は前作のように第二次世界大戦中に起こるのではありません。一九八◯年代のパリの知的世界そして世界全体を舞台にしています。
【フランスでの受容】
佐々木 : 『言語の七番目の機能』、平野さんはどのように読まれましたか?
平野:まず大変面白く読んで、僕自身のフランス現代思想への知識の不十分さからどこまで理解できたか自信がないのですが、そういう人間にも楽しめて色々なことを考えさせられる小説でした。いろいろ話したいことがあって、どこから始めれば良いか戸惑うくらいです。僕はビネさんとほぼ同じ世代なので、扱われている人物たちが知的世界のスターたちで、全世界に影響を与えていた時代を知っています。ですから登場人物たちのパロディのされ方はとても面白いと思い、腑に落ちる部分がありました。そこで伺いたいのは、これを読んでフランスでは笑い転げた人がいるとともに、怒った人もいたのではないかということです。
それから先程言ったように、僕はビネさんとほぼ同じ世代で、八◯年代、九◯年代のフランス現代思想を一応その時代に生きていたのでよくわかるのですが、もっと若い世代だとひょっとするとバルトを知らないかもしれません。またドゥルーズやフーコーなどは今でも真面目に読み続けられていて、純粋にフーコーの理論を使って例えば生政治の分析をしたりはしますが、フーコーのキャラクターをいじるというか、扱うことにはピンとこない世代もいるかもしれません。そこでビネさんに、まずフランスでの世代によるこの小説への反応の違いを教えていただきたいと思いますが、どうでしょうか。
ビネ : 平野さんは謙遜されていますが、『日蝕』を読みますと、フランスとヨーロッパの十五世紀の思想についての平野さんの知識ははるかに私を凌駕しており、驚愕するとともに、自分の属している文化への無知を恥ずかしく思いました。平野さんの学識にまず賞賛をささげたいと思います。
おっしゃる通りフランスで、私の小説には様々な反応がありました。大笑いしてくれた人もいます、また私がこれらの思想家たちを深く学んだことを賞賛してくれた人もいます。実際私は言語学の教育も受けましたので、ロラン・バルト、ヤコブソン、ソシュールなどについてはよく知っていたのですが、いわゆるフレンチセオリーの哲学者たちフーコー、ドゥルーズ、デリダなどはあまり知らなかったので、この本のために勉強しました。問題が起きたのは二人の登場人物についてで、フーコーそしてフィリップ・ソレルスでした。
確かに私は、ジュリア・クリステヴァの夫であるソレルスについては小説中でかなり辛辣にからかっています、しかしミシェル・フーコーについてはからかった部分は全くありません。フーコーの生活について私が語ったことは、誰もが知っていることでもあり、フーコー自身が公言していることでもあります。彼は風変わりなパーティーに出たりすることなどを自ら包み隠さず書いているのです。実際、ソレルスはかなり怒ったようで、二◯一五年にこの小説がフランスで出た時、訴訟を起こそうという話もあったのです。フランスの文学界は狭く、サンジェルマンデプレ地区にソレルスの友人は多いので、彼らの間でも憤懣を引き起こしました。ただし文学の本がこれほど騒動を巻き起こすことは珍しく、作者としては色々な人に読んで欲しいので、むしろ嬉しいことでもありました。
【メディアの変化と「言語の七番目の機能」】
平野 : 僕はこの小説は最近読んだので、今の時代の状況との関係、つまり言葉が現実を変えることができるのかという問題について伺っていきたいです。それについて、楽観的になることもありますし、悲観的になることもあります。例えばドナルド・トランプが、投票所をwatchしておけというと、重武装した支持者たちが、マシンガンを持って投票所に詰めかけたりしている。これはまさに『言語の七番目の機能』として小説中で書かれている状態で、彼の言ったことをそのまま真に受けて現実化するような状況が起きている。これはネガティブな例ですが、他方でグレタ・トゥーンベリさんのような人が、環境問題が改善しないことに対して、How dare you、というメッセージを発して、若い人がそれに反応し、世界中にムーブメントが起きている。これはポジティブな意味での言語の「七番目の機能」とも言うことができる現象だと思うんですね。
もう一方では、フェイクニュースが世界中に大混乱を巻き起こしていて、言葉が世界を変えられるということが、ポジティブなことではなくて、非常にネガティブな事例によって、世界を混乱に陥らせていると思うんですね。『言語の七番目の機能』は、今読むと、特に後半は、現実とは何かについて、あるいは言語と現実との関係について、非常に現代的に考察しているのではないかと感じました。
ビネ:おっしゃる通りです。『言語の七番目の機能』では最初に、言語は世界最強の武器と仮定しました。最良の場合と最悪な場合がありますが。
最初のアイデアでは、言語学でいう発話の行為遂行的(パフォーマティヴ)機能に関するもので、言葉を発することが行為そのものだということです。このアイデアが意味するのは、私は確かに原則を拡張解釈したかもしれませんが、言語を巧みに使用する者が権力を獲得するということです。例えば、軍隊の中でも権力を持つ人は、実際に武器を持つ人でも、戦車に乗っている人でもなく、指令を出す人、人々を服従させる人なのです。命令は言葉を通じて発せられます。フランス革命は、その前にヴォルテールやルソーなどの言葉がなければ起こらなかったでしょう。それがまさに小説を書き始める最初の仮定でした。現代はソシアルネットワークを通じた一種の戦争状態にあり、皆がソファーに座りながらキーボードの戦争のただ中にあると言えるかもしれません。そのような中で、トランプの言うこと、また彼の反対者の言うことは、現実に影響を与えており、私たちは対立のロジックの中に置かれています。
フランスの社会学者ピエール・ブルデューは「社会学は闘争のスポーツだ」と言いましたが、文学もまた、「闘争のスポーツ」なのです。ブルデューは権力に対抗する立場から書きましたが、私が思うに、誰でも書く時は常に、ある意味で何かに対抗して書いているのです。意識的か無意識的かはわかりませんが、私も書くときに何かに対抗して書いています。それは私の嫌いな種類の文学、賛成しかねる文学に対してです。私は歴史小説を書いたと言われますが、よくある歴史小説に対抗するやり方で書いたつもりです。人は常に言葉を用いる場合、この闘争の場に立たされます。特にフィクションを書くときは、必然的にこのような場に立たされるのです。
【ポストモダンの申し子】
平野:その意味で言うと、この小説の場合、フレンチセオリー華やかなりし時代はビネさんにとって叩くべき時代であったのか、それともその時代を神格化するようなイマージュ自体が闘争の対象だったのか、どちらでしょうか。
ビネ:フレンチセオリーはいわゆるポストモダンという潮流に属し、その定義は諸説ありますが、何れにしても、私はポストモダンの申し子です。私は、デリダなどが実践したように、近代的な思考の土台や、現実の根本を問い直す思想の潮流に属します。古典的な文学、バルザックの小説のような文学はかつて栄光に包まれていましたが、今日では私はそれらにそれほど興味を引かれません。私の意見では、ポストモダンは、それ以前の、セルバンテスの『ドン・キホーテ』にまで遡ることができると思います。つまりポストモダンの誕生は近代的な小説の誕生と同時であり、その意味ではモダンとポストモダンにそれほど大きな違いを設ける必要はないと思いますが、私はこの種の文学に興味をもっています。モダンな小説、それは自らを疑う小説、自己への反省を含む文学です。この自己への反省の方法は無数に存在します。私自身は、フレンチセオリーの思想家たちの末端へのつながりを感じています。彼らのやり方はとても健全だと思うのです。なぜなら彼らは当たり前のこと、偏見、前提を問い直したのですから。
まだ日本語に訳されていない最新作の『Civilizations』(以下、シビライゼイション)では、私は史実を逆転させました。その小説は、ヨーロッパ人がアメリカを征服したのではなく、インカ人がヨーロッパを征服したという、事実とは反対の歴史を書いているのですが、これは皆が前提としていることを問いなおすためで、そのようなアプローチこそ興味深く、刺激的に思えるのです。
【技術革新と権力】
平野 :もう一つ個人的に興味のあることですが、この小説ではインターネットもiPhoneもない時代が舞台になっていますが、現在とはメディアの状況が異なっています。小説の中でもちらちらと登場するレジス・ドブレがメディオロジーという学問を提唱していて、この小説でもデリダと一緒にミッテランにメッセージを渡す人として重要な役割を果たしています。そのドブレは、なぜある思想が伝わるかというと、言葉の中身よりも、メディアという物理的な実態があって、それが思想を伝えるのに重要なのだ、という話をしています。
トランプの言葉が影響を持つのは、言葉そのものが、何かのアイデアを伝えるということがまず一つあるとして、もう一つにはそれを伝えるメディアの力にも依っている。それがこの小説が書かれている時代から状況が大きく変わって、一番大きなものはインターネットですけども、そのインターネット環境がすごく広まった中で、今の時代の言語というものが、相対的に、影響力として変化しているのかどうか、つまりトランプの言葉が人を動かしているのか、それとも彼の映像あるいは彼のキャラクターの全体がメディアを通じて人を動かしているのか、ということもあると思います。そのメディア環境の違いから、この小説について少しお話しいただけますでしょうか。
ビネ:はい、その意味で私は、現代と十六世紀の類似性に驚かされています。私が十六世紀に焦点を当てますのは、私の最新の小説が十六世紀を舞台にしているからですが。十六世紀にはとりわけ二つの大きな出来事が起こりました。一つには貿易が世界規模になり、最初のグローバリゼーションが起こりました。もう一つはヨーロッパでルターの起こしたプロテスタンティズムです。プロテスタントたちは伝統的なローマのカトリックを批判しましたが、なぜプロテスタンティズムがこれほど広まったかというと、それは印刷術と結びついたからです。ルター自身も驚いたことに、彼が九十五箇条の抗議文を書き、教会の扉に打ち付けると、当時発明された活版印刷術によってすぐさま複製され、今日ならウイルス的と呼ぶべき広がり方で、人々の間に広まっていったのです。メディアが決定的な役割を果たしたのです。
私は、現代の革命とも呼ぶべきインターネット、ツイッター、フェイスブックはそれ自体良いものでも悪いものでもなく、単なるツールに過ぎないと思います。ですが、それは武器でもあるので、良くも悪くもそれを操る人、それを巧みに使う人が有利になります。それらが現在の闘争の場になっています。火薬の発明、銃の発明は、それを利用することができた人には権力の掌握につながりました。
【過去と現在】
佐々木:ビネさんの小説を読まれた方はお分かりだと思いますが、実際にはローマン・ヤコブソンは言語の機能を六番目までしか書いていなくて、七番目というのが重要な意味を持ってきます。この「言語の七番目の機能」は、実はメディアという形で実現したのではないかということかと思って聞いていました。多分小説が歴史小説である以上、常に過去を舞台にしているわけですけど。作者がそれを書いているのは現在であるわけで、書いている現在も何らかの形で表象していると思うんですね。
そこで、『言語の七番目の機能』では八◯年台前半を舞台に描かれていて、実際に原著が出たのが二◯一五年。年齢を見ますと、ビネさんはロラン・バルトが亡くなった一九八〇年には七歳で、そういう意味では全然リアルタイムではなかったと思います。過去のある時期を舞台にして歴史小説を書くということ、その際にどうやって現在と関係を持たせるのかということについてビネさんはどのように考えていらっしゃいますでしょうか。
ビネ:どのような場合も私たちが存在している現在を逃れることはできません。私は二十世紀に生まれ二十一世紀を生きている、その意味で二十世紀と二十一世紀の子供です。過去の歴史を描こうとしても、二十世紀及び二十一世紀の見方を通じてしか書けません。私は本によって過去を語る時には、メランコリックな関係を感じています。私は『空白を満たしなさい』を読んだ時、平野さんも同じ気持ちではないかと思ったのですが、私にとって過去を語ることはノスタルジックではなく、メランコリックなのです。ノスタルジックとは自分たちが生きた時代を振り返る態度です。人々にとって過去は過去であり、それを変えられないということはオブセッションになっていて、時にトラウマともなっています。平野さんの『空白を満たしなさい』はこのオブセッションをめぐる本になっていると思います。
表現方法は違いますが、私の『言語の七番目の機能』では、私はフランス人として、この時代に奇妙なノスタルジーを感じながら書いたのです。私が直接知らないこの時代は、フランスの知的社会が非常に繁栄し、刺激的で、世界中に影響を与えたおそらく最後の時代だったのです。それほど前の時代ではないのですが。それは私が知ることができなかったことが悔やまれる時代です。
現在のフランスの知的雰囲気に私は満足していません。それは重苦しく反動的です。デリダ、ドゥルーズ、バルトがいた時代に比べて力がとても弱いと感じられるのです。そのために私は、現代への不満のはけ口を過去に求めているのです。もちろん『HHhH』は違います。私は第二次世界大戦にノスタルジーは感じていません。『HHhH』は、ユダヤ人の大量虐殺が起こったこと、レジスタンスがいたこと、一九四二年にチェコ人のパラシュート部隊がラインハルト・ハイドリッヒを殺害したことなどを皆に知らせたいと思ったから書いたのです。『シビライゼイション』も同じです。私は敗者たちの歴史を書きたいという幻想を持っているので、両作品ともに一種のメランコリーを動機に書かれた、メランコリーを治療するための作品なのです。『HHhH』も『シビライゼイション』も歴史上の敗者の物語なのです。ただし『言語の七番目の機能』では、知的世界の最盛期を舞台にしました。
佐々木:ビネさんから三つの作品の舞台となる時代との関係をお話ししていただきました。
【フランス現代思想の黄金時代】
佐々木:『言語の七番目の機能』に関してですが、平野さんは覚えていらっしゃると思いますが、日本では、この小説の舞台の少し後、八三年ぐらいに、ドゥルーズ、デリダが紹介されて、その紹介者がメディアでスターになるニューアカデミズムと呼ばれる現象が起きました。僕はお二人より少し歳が上でその直撃世代です。その時の感覚からすると、『言語の七番目の機能』に出てくる登場人物の扱いはずいぶんショッキングだったりします。平野さんはフランス現代思想の日本での紹介に対してどういう感じの距離感でご覧になっていましたか。
平野 : 僕は九◯年代の半ばぐらいから、小説だけでなく思想にも関心を持つようになりました。それまでは小説ばかり読んでいたので、大学に入ってからですけど。日本でフーコーらが訳された頃は、ある種純粋な知的好奇心からだったとは思いますが、九◯年代に入ると、猫も杓子ものような、またファッション的な要素もあって、それが文学の読み方を貧しくした部分もあったと思います。一つの小説は、キャラクター、文体、構成、またほんのちょっとした言葉の使い方などいろいろな要素から成り立っていて、そういうもの全体を読まないとうまく読めないのですが、ある時期から、記号論的アプローチ一辺倒の読み方が小説の読み方をつまらなくしてしまい、読者も作者もそういう読み方に抵抗を示すようになったと思います。むしろ二◯◯◯年以降はその反動として、ナイーヴに読んだ批評が出てきたり、あるいは文芸誌が批評家でない人たちに書評を書かせて、作品へのアプローチを多様化することを行っていました。
僕自身も、結局はフーコーとか、その後に大きな影響を受けて、今でも尊敬していますけど、当時は現代思想ブームの最後の時代、それがだんだんファッションのようになっていく頃で非常に反発を感じていて、僕はボードレールという詩人がすごく好きだったのですが、この小説にも出てきますが、「ボードレール」というと、「ボードリヤール?」と聞き返されたりしました(笑)。「ボードレール」だと分かってもらっても「分かった。ベンヤミンから入ったんだね」と言われたりしました。
僕はボードレールが美術批評の中で「naïveté」、純粋さということを非常に強調して、一枚の絵の前に立ったときに純粋さから作品鑑賞をしなければいけないんだということを美術批評の中に書いていることに、かえって共感したんですね。ただ、その後日本では、フランスで哲学博士号を取ってきた人などによっても、ずっとフーコーなどは読まれ続けていて、特に生政治の話だとか、今の格差社会の中で活発に議論されているので、僕はそのブームが去った後で自分の思考に重要な本として読み直したし、読み続けたという経験がありますね。
ビネ:偉大な思想家の問題は、しばしばその弟子たちですね(笑)。
平野・佐々木:(笑)
【小説の様々なレベル】
佐々木:『言語の七番目の機能』を読んでいると、フランスあるいはフランス以外の綺羅星のような人たちが登場して、こういう小説は日本ではあまりないし、あったとしても、読者にある程度の知識とか、リテラシーを要求するので、知的なスノビズムみたいな受容になってしまう傾向があるので、フランスはすごい国だなあと思ったのですが。先ほどビネさんのお話を伺っていると、意外とビネさん自身も読者を啓発するような気持ちでこの作品を書かれたことがわかって新鮮な気がしました。
ビネ:私はフランス語の教師として十年間教壇に立っていました。この仕事の名残として私はしばしば教育的です。いろいろなことを伝えたい、教えたいというのが私の根本にはあります。『HHhH』では第二次世界大戦について紹介しましたが、『言語の七番目の機能』では、登場する思想家たちに出会い、鍵となる概念などは読者に伝えるべきものとして伝達しました。小説が成功したかどうかは読者の判断に委ねますが、この小説は様々なレベルで読むことができます。『言語の七番目の機能』は推理小説としても読めますし、冒険小説としても読めます。ジェームズ・ボンドのようなスパイも登場します。もし読者が望めばさらに深い読みもできます。
私は平野啓一郎さんの『日蝕』を読んで、『薔薇の名前』を思い浮かべましたので、例として用いますが、『薔薇の名前』は世界的な成功を収め、何百万冊も売れました。他の方はそうでないかもしれませんが、私は十四世紀のスコラ哲学には馴染みがありません。ベルナール・ギーなどのことは知りませんでした。しかし私は『薔薇の名前』を陰謀の話としてまたシャーロック・ホームズのような推理小説として読んだのです。ですから私は『言語の七番目の機能』をシャーロック・ホームズを読むように読んでほしいと思ったのです。私の小説の登場人物シモン・エルゾグのイニシアルのS.Hで、シャーロック・ホームズへの目配せなのです。私は優れた小説は論文のようなものであってはならないと思います。何かを証明したいのならば、論文を書くべきです。あるいはコレージュ・ド・フランスで講義をするべきなのです。しかしそれは小説ではありません。
【言葉の現実への影響】
平野:小説の最後の方で、ロゴスクラブでのファイトが巧みに組み込まれていて、最後にラスボスとして『薔薇の名前』のウンベルト・エーコが出てくるのが面白い場面でしたね。そのおかげでとてもエンターテイメント性が高まっていると同時に、最初にお話しした言語と現実との関係がとても生々しい形で描かれていると思いました。記号の組み合わせのゲームと現実が完全に切り離されているのかというと、ロゴスクラブでは敗けた方の人が小指を切断されたり、腕を切断されというフィジカルなダメージを負う。現実にそれが直結しているんですね。言語活動とかコミュニケーションが現実とどういう関係を持っているのかという大きな問いを、ロゴスクラブの戦いを通じてうまく描かれていて、この小説の一部だけを読んでいると、現実から切り離されたところで、言語でいくらでもできてしまうではないかという面白さを感じた後に、ロゴスクラブの場面になると、しかし結局言語とは現実と結びつかざるをえないじゃないかということが描かれている。そしてロゴスクラブと対立するように、大統領選の話がずっと出ています。結局政治も議論が僕たちの社会の全体を決める、政治に直結するという話につながっています。ロゴスクラブと大統領選の話が平行して描かれているところも、エンターテイメントでもありながら、この小説のテーマを巧みに表現していると感じました。
ビネ:ありがとうございます。おっしゃる通りです。私は言うなればレトリックそのものをドラマにしたかったのです。やや大げさなメタファー的演出ですが、論戦に敗れた者は、現実に影響を受けます。それは論戦が単なるゲームではなく、現実とつながっていること、つまり言葉の力を表現したかったからです。
またこのプロットのなかで、フランスの大統領選では、第二回目の投票に残った二名の候補者の中で論戦に勝利した方が大統領になるのですが、フランス語の教師という過去を持ち、作家でもある私は、言葉のプロとして、レトリックは現実とつながっているということを見せたかったのです。論戦は時に滑稽ですが、言葉は現実を創り出しており、文字どおり、現実に影響を及ぼすものなのです。すべての独裁者たちは言葉を巧みに操ることで権力に到達してきました。独裁者は常に優れた演説家でもあったわけです。トランプの言説はヒトラーやムムッソリーニに比べて滑稽なところがあるかもしれませんが、彼の演説は影響力を持っています。というわけで私の本は言語が現実に及ぼす力についての本でもあるのです。
【歴史修正主義と反事実的歴史小説】
平野:ロゴスクラブのシーンで面白かったのは、相手をどういう論理で説得するかという点が一つと、彼らが語っている文学的知識や教養が正確かどうかということが判定の中で重視されていて、間違った文学的な知識を話すと、それが減点対象になるということです。これが今の社会の中でも重要になってきていて、というのも今は世界中がフェイクニュースだらけで、何に基づいて議論するかという前提が不確実なものになっているからです。一方で相手を言い負かせば、勝ちだといっても、それがロジカルには言い負かしたことになっていないのに、相手を言い負かしたことになってしまい、それが問題になっています。歴史に関しても、修正主義というものが問題になっていて、例えば日本が第二次大戦中に大陸や朝鮮半島でしたことが次々に書き換えられてしまう。
僕も最近テーマにしていることなんですけど、過去はかつては安定的なものと見えていて、その安定化した過去を対象化して議論することができると思っていたのですが、良くも悪くも、過去は非常に不安定で、個人的なトラウマであれば、過去を語り直すことによって、固定されたトラウマの関係から、克服して、新しい自分を作っていくこともできるかもしれないけど、国の歴史としては、過去に行った悪いことというものを、日本においては日本軍がやった残虐行為というのを、修正していくような言説があります。ヨーロッパだとホロコースト否定論とかですね。
小説家としてのジレンマは、日本が中国大陸でやったことが何だったかということを書こうとして、それをフィクションという形で書いたときに、修正主義的な人たちに十分な力を持ちうるかということです。結局それはお前の作った話じゃないか、現実はこうだという風に言ってくる人がいるんですが、彼らの話自体、彼らなりのフィクションでもあります。むしろ事実をきちんと調べて正しく書く方が、修正主義的な人たちには力を持つんじゃないかと思うのですが、そうすると小説として何をなすべきかということにいつも苦しさを感じていました。
それが『言語の七番目の機能』は発想の逆転というか、ある意味出鱈目を書くことによって、歴史を書くことがどういうことなのかということを批評的に描いていて、ハッとさせらえたところがありました。フランスでもヨーロッパでも歴史の書き換えということが起きていると思いますが、そういう傾向にフィクションとしてどう対抗していくかについて、ビネさんはどうお考えでしょうか。
ビネ:とても興味深い、とても複雑な質問ですね。最近の私の『シビライゼイション』に関する議論で、反事実的歴史と歴史修正主義とがどう違うのかが話題になりました。実際には答えは簡単で、読書の契約の問題です。
私は『言語の七番目の機能』でバルトが暗殺されたと信じさせようとはしませんでした。私が提案しているのは一つのフィクションによる仮説でしかなく、バルトが交通事故で死んだことは誰もが知っていることです。私のフィクションの中で起こるのは事実ではなく想像力によって作られた多くの出来事なのです。『シビライゼイション』でも同じことで、インカがヨーロッパを征服したと思わせたいわけではありません。読者は実際に起こったことはその反対だと知っているのです。『HHhH』では事情は全く違います。その場合にはいかに事実を語るか、いかに史実に密着するかが問題でした。いずれにせよ、プロジェクトは正直なものであったと思われます。なぜならば読書をするときの契約は明白だったからです。
私はフィクションの真の危険は、偽造に手を貸してしまうことだと思います。フィクションは、自らが真実だと主張し始めると、偽造になってしまいます。ですから歴史修正主義に対する私の答えは、小説やフィクション自体のレベルにおいてではありません。フィクションであるという点では、歴史修正主義の小説とそれ以外の小説とを対立させることはできませんから。フィクションは何一つ証明することなどできません。例えば私はフィクションによってアウシュビッツが現実に起こったということを証明したわけではありません。
加えて一つ補足したいのは、メディアの話で、SNSによってフェイクニュースが増殖している状況についてですが、確かにSNSがフェイクニュースを作り出しているという状況はあるのですが、例えばテレビで政治家が何か嘘をつくと、SNSがすぐさまその嘘を暴くという状況も起きています。彼は何年にこういうことがあったと言っているが、SNSが情報ソースをあげて、それは違うと修正するのです。こうしてSNSはフェイクな言説が広まるのを防いでもいます。SNSは、かつて新聞記者のみが、時間に追われながら政治家の言説を報道していた時代に比べて、政治家の嘘を見抜く武器ともなっているのです。私たちはこうして非常に複雑な状況の中に生きており、闘争の場は現在では世界全体にまで拡大されています。誰もがそれに参加しており、SNSは世界の言論の競技場となっています。もちろん結果として多くの不快な言説、ノイズなどに満ちているのですが。SNSはその使用方法を身につけるべき武器であることだけは確かです。
【小説は何の役に立つか】
佐々木:奇しくも、数日後にアメリカ大統領選がある状態でこの対談は行われているわけですけれども。今の問いはトランプ時代におけるフィクションとは何かという問いでもあるとも思うんです。今ビネさんが言われたことも含めて、また平野さんのご自身の小説ということも含めて、何か感じられることはありますか?
平野 :最近、現実が小説の想像力を上回っているのではないかと、悲観的な含みで言われることが多いです。もし僕がトランプのような人が大統領になる小説を書いても、読者は反発したと思うんですね。しかし現実にはそういう人が大統領になっている。よく小説が何の役に立つのか、という人がいますが、その中で小説を何のために読むのかということがよく言われます。もちろん好きだから読むにきまっているんですけど、小説を読む習慣のない人には、何のために読むんだ、何の役に立つんだということがよく問われます。僕はこのクレージーな世界で、自分の正気を保つために小説を読んでいます。小説にはそういう機能があるし、特に今のような時代には。
ただ、小説もものすごく大きく分けると、現実の中で苦しんだり、迷っている人が、小説を読むことで束の間癒されるというか、美しいものに触れるということもあります。一方では現実に強くコミットする、読んだ人が現実をどう解釈してどう振る舞うかということを、強く後押しするような小説があって、もちろん両方兼ね備えていればいいと思うんですけど、僕もこの作品は現実から束の間解放されたい読者のために書こうとか、小説によって少し考えていると思うんですね。村上春樹という作家がよくコミットメント、デタッチメントという言葉を使っていて、今の話はそれに付随するかもしれませんけど、読むことで社会から引き離されるか、より社会に深くコミットしていくかという。僕は小説を読むことが社会に深く繋がっていくべきだと思うんですね。
【誰に向けて小説を書くか】
平野:その時にやっぱりどういう読者に、自分の作品が伝わっていくのかということも考えるんですね。文学を読む人は、結構僕の考えていることを僕の本を読む前から分かっているんじゃないかと思うんですね。差別してはいけないとか、暴言によって人を操ってはいけないとかですね。実はその外側にいる人たちに読まれることによって、社会が変わっていくきっかけになるのではないかと思って、最近の自分の物語の作り方では、小説を読まない人にもアクセスできるようなデザインを考えます。ビネさんの場合作品によっても違うと思うんですけど、どういう読者が自分の作品を読むかということを意識されたりしますか。
ビネ:その点に関しては二つのレベルが共存しているように思います。
まず私は自分が読みたい小説を書きます。読者としての自分を満足させるような小説。つまり私は自分が好きな本を書くのです。同時に私は楽観的で、すべての人に向けても書いています。例えば『言語の七番目の機能』のようなものを書くとき、ヤコブソンが言語の六機能について書いたことを誰もが知っているとは思えませんから、本のある箇所で皆がその考えに馴染めるように六機能を要約しています。私は読者が完全に自分を見失ってしまわないように、最小限の快適さを提供します。読者が、少しはわからないところはあっても、完全に理解不能にはしないのです。それが質問への答えでしょうか。
次に、この世の中の混乱に関して、パンデミックについて書きたいか、あるいはトランプについて書きたいかということですが、私がトランプについて書くかというとノーです。これはまさに事実がフィクションを超えてしまうという典型的な例です。私は『HHhH』で第二次大戦を描きましたが、非常に残酷なこと、英雄的なこと、悲劇的なことを書きました。なぜナチズムが起こったかに興味があったからです。
それから小説の役割ですね、小説家はアーティストと同じように、一つのオリジナルなヴィジョンを提示すべきだと思います。それは中心からはぐれた見方である可能性もあります。ピカソの絵は何を言っているのでしょうか。それは、ピカソはこのように世界を見ているのだ、ということです。そしてそれはオリジナルなヴィジョンなのです。そしてその視点が人々に徐々に影響を与えていきます。それが人間の感性を豊かにしていきます。私たちを刷新し、私たちに何か新しいものを提案します。こうして人類がある意味で前進していくのです。小説の役割は大きな問題について書くことであり、また小説家はアーティストと同じようにオリジナルな視点を持つべきです。現代のパンデミックやトランプについて書くよりは十五世紀や十六世紀について書く方が面白いのです。その中でペストの流行について書くことの方が、現代を捉え直すことにもつながります。作家に期待されているのはオリジナルなヴィジョンだと思います。
【ツイッターの言葉と文学の言葉】
佐々木:ビネさんありがとうございました。ここで、皆さんから質問が結構来ているようですので、お二人に質問に答えて頂く質疑応答の時間にしたいと思います。難しい質問が来ています。文学ではあえて抽象的、難解な語彙を使うことがありますが、SNSでは具体的な言葉を使った方が人気を得ます。人々がSNSに熱中すると言葉が単純になり、抽象的、難解な文学は人気を失うのではないでしょうか。今日作家はどのような語彙で創作をすべきだと思いますか?
平野:ツイッターでは百四十文字しかかけませんし、SNS上で難しいことを議論するのは限界があると思います。僕もツイッターもフェイスブックもやっていますけど、くだらないこととか書いてます(笑)。やはりインターネット上では早いテンポで情報がやりとりされていて、今人間がどういうことを考えているのか、感じているのかを考えようとすると、やはり本の形でまとまったものを読まないとダメだと思うんですね。本を読むのかネットをやるのかというのが大きく分けて二つあって、僕は両方やらないとダメだと思うんですね。本はどうしても数ヶ月、数年かけて書いて、それをゆっくり読むというようなペースで作られていますし、その中でしか深められないような思想もあります。
その一方でインターネットでは数秒で新しいニュースが来て、それはそれでその情報に触れておくというのも必要なので、両方やらないと世の中のことも、自分自身のこともわからないんじゃないかと思います。みんなインターネットの言葉に疲れているところもありますから、僕もツイッターとか見ている方ですけど、ずっと読んでいるとだんだん嫌気がさしてきて、僕はインターネットの言葉に触れているとむしろちゃんとした文章が読みたくなってきて、小説を読むとやっぱりちゃんとした文章はいいなあとつくづく思います。ネットばっかりやっていると小説が読みたくなくなるとはかならずしも言えなくて、むしろちゃんとした文章を読みたいという気にもなるんじゃないでしょうか。
ビネ:そのお気持ち、よくわかります。おっしゃるように三十分もインターネットの文章を読んでいるとうんざりすることもありますが、たまに匿名の作者が素晴らしいことを書いていたりもします。ツイッターの短い形式は、文学の形式にもあり、フランスにはアフォリズムの伝統があります。フランスではラ・ロシュフーコーやシオランなど、ツイッターで読むと素晴らしいものです。日本には俳句などもありますね。要は内容のクオリティーが大事で、SNSを我々がどう使うかが問題です。もちろんツイッターの大部分はそれほど良質のものではないですが、日に何度かはすばらしい匿名の書き手の文章に出会ったりもするのです。それはゲームの場でもあり、闘争の場でもあります。ただツイッター疲れで本を手に取りソファーに腰を下ろしたくなるという平野さんの気持ちは痛いほどわかりますよ。
平野:僕はラ・ロシュフーコーの言葉を紹介するツイッターのアカウントをフォローしていて、一日に二回ぐらい流れてきます。結構いいこと言うなあと感心しています(笑)。
【終わりに】
佐々木:バルトは日本でもずいぶん翻訳がある方で、新訳も進んでいるので、新しい読者を獲得している部分もあるだろうと思います。バルトは「人は愛するものについて常に語り損なう」と言いましたが、今日は愛するものについて語り損なうことなく対談を終えられそうですね。
ビネ:そうですね(笑)。まずこのような対談が可能となったこと、自分の本が日本語に翻訳されたことに感謝いたします。またこの場を借りて五十嵐一氏にオマージュを捧げたいと思います。彼は一九九一年に暗殺されてしまいましたが、サルマン・ラシュディの『悪魔の詩』を翻訳した勇気ある日本人です、心からの敬意を表したいと思います。現在フランスでは『悪魔の詩』からの連続性をもつ大変混乱した時期を過ごしております、そういうわけで五十嵐一氏にオマージュを捧げたいと思いました。
平野:本当にこの本は、語りたいことがたくさんあって、本当はあとでこっそり語りたいこともあるのですが(笑)。今日はとても楽しかったので、今度またパリか東京で直接ビネさんに会って話したいと思います。どうもありがとうございました。
ローラン・ビネ●1972年パリ生まれ。作家でありながら、文学の高等教育教授資格を持ち、パリの複数の大学で授業を担当した。『HHhH―プラハ、1942年』により2010年度ゴンクール賞最優秀新人賞を受賞。日本語版も出版され、本屋大賞・翻訳小説部門第1位、Twitter文学賞海外部門第1位となるなど話題を呼んだ。その他、『言語の第七の機能』によりアンテラリエ文学賞、『Civilizations』によりアカデミー・フランセーズ小説大賞を受賞。
Twitter