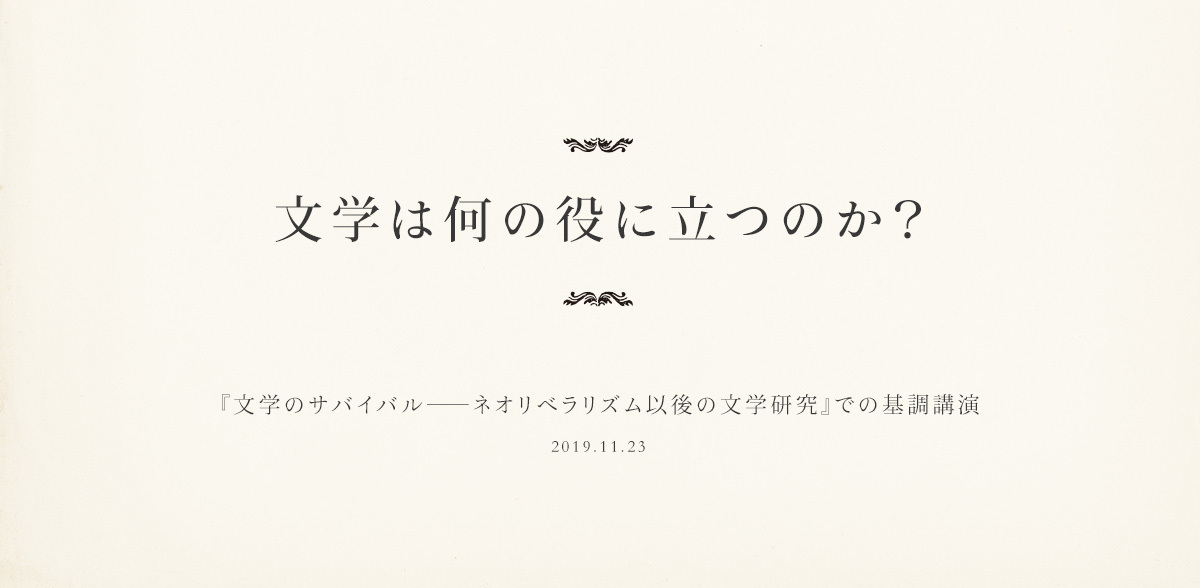この世の中で文学を問うこと
只今ご紹介いただきました小説家の平野啓一郎です。今日はこのような立派な場所にお招きいただきまして、ありがとうございます。
今日はあいにくの大雨です。少し前までは、雨が降ってもさほど気にしなかったんですが、台風の被害がまだ関東以北にかなり残っているので、これだけ降ると被災された方は大変なんじゃないかと、心配しております。
日本は自然災害も含めて、大変な状況にあると思います。そういう中で人はついつい、すぐに何か役に立つものを求めがちですが、今日はあえて「文学のサバイバル」という大きなテーマの中で、「文学は何の役に立つのか?」という身も蓋もないテーマを設定してみました。
小説家の悪い癖でして、最近本もなかなか売れない中、よほど刺激的なタイトルではないと、みんなが関心を持ってくれないのではないか、という強迫観念があります(笑)。僕の家には、自分で買う本や献本など、ものすごい数の本が日々新たに押し寄せてきていて——皆さんもそうだと思いますが——それが仕事机の周りにタワー化していき、非常に圧迫感があります。そうすると、その中で読む本と読まない本がおのずと分かれてきます。小説に関しては、正直に言うと、著者名もありますが、タイトルとあらすじがよっぽど興味を引かないとなかなか手が伸びません。タイトルを見て、なんとなく面白そうだと思い、帯のあらすじを見てさらにそう思ったら読む。さもなくば、必要に迫られないとなかなか読まないということになります。その感覚は、書店に本が並んでいる時の一般の人の実感とかなり近いんじゃないかと思うんですね。タイトルと帯を見て面白そうだと思い、なおかつ最初の数ページを読んでよっぽど面白くないと、そこまでは行ったけれど、また棚に戻されてしまう。そういう営みの中で、本は買われるか買われないかという運命を問われているのですが、まあ、そんなわけで講演のタイトル一つにしても、どう付けたものかと考えるわけです。
最近は自分で本を書いてインターネットで発表する場も増えてきたので、僕のところに原稿を送ってくる作家志望の人は少なくなりましたが、それでもまだ、たまにいます。だけどほとんどのファイルは読みません。なぜかと言うと、僕にそれを読んで欲しいと書かれた手紙が、全然面白くないんです(笑)。それからタイトルがやはり面白くなさそうなんですね。表現者はその時点から勝負が始まっていますから、本当に読んでもらいたいなら、「読むな」と言われても僕が読みたいと思うくらいの文章で訴えかけてくれないとダメなんじゃないか。数千人数万人の読者に自分の文章が受け入れられるかどうかの勝負は、僕という一人目の読者を獲得できるかどうかにかかっていると思うんです。
そういうわけで、「文学は何の役に立つのか?」という大仰なタイトルを付けましたが、これはもちろんアイロニカルな括弧付きの問いです。研究者の立場にある皆さんと、小説を書いている僕の立場は多少異なっているとは思いますが、いずれにしろ文学の世界にいると、しょっちゅう突きつけられる問いが、「いったい文学は何の役に立つんですか?」というものなんですね。
この問いは、答えるのに苦慮する問いでもありますが、最近僕は、この問いに答えるのに苦慮しないひとつの理由を見つけました。それは、"今の世の中で正気を保つため"です。僕は最近、ほとんどそのためだけに本を読んでいます。
というのは、世の中自体が本当に「キレイはキタナイ、キタナイはキレイ」を地で行くようになって、そういう言葉の中で社会を認識していると、ちょっと頭がおかしくなってくる感じがあります。だから文学作品を読むということは、僕にとっては精神的な健康を保つ、有効な手段になっています。
社会ではインターネットを中心に、フェイク・ニュースが世界的な問題になっていて、言葉が非常に大きな混乱状況にある。その中で、文学の意義は問い直される局面ではないかと思っています。
価値の見分け難さの原因
「文学は何の役に立つのですか?」と言われた時に、作家からの強弁としてこれまでよくあったのは、——非常にアーティスティックな態度ですが——「別に役に立たなくていいんだ、俺は役に立つものを書こうなんて思っていない、俺の表現なんだ」という言い方でした。これは一つの表明だと思いますし、僕はそう言うこと自体に意味があると今でも思っていますが、もう一方で、そもそも「文学は役に立つのか?」という問い自体にも一種の不思議さがあると思います。
というのは、どんな新自由主義者でも、あるものを評価する時には、"役に立つ"かどうかというより、"価値がある"かどうかを問うはずです。僕たちがお金を払って何かを手に入れる時には、役に立つかどうかではなくて、お金に見合うだけの価値があるかどうかを考えるのであって、役に立つかどうかは、価値の中の一つの基準でしかない。役には立たないけれど価値があるものは沢山あります。そういう意味では、「文学には価値があるか?」と問い直されるべきなのかもしれません。
ただ一方で、やはり「文学は役に立つ」と言えるのではないか、とも思うわけです。有用性の判断というのは非常に難しい。特に現在のように、未来のテクノロジーに関して、あるいはグローバル化によって、どこでどういうタイミングで何が起きていくかが分かりにくい時代になっていくと、何がいつ役に立つのかということの判断は非常に難しいです。
二〇〇〇年代の前半は経済の分野でも"選択と集中"ということがしきりに言われましたが、ほとんど失敗しました。というのは、選択し、集中するための未来像の予測が——特に家電などは——この一五年くらいの間の進歩が大きすぎたために、非常に難しかったからです。ではどうするかと言うと、マーケットをじっと見る、というのは、一つの重要な方法だったはずです。ところが、今の世の中、個人がお金を持っていませんから、活発に消費できない。長時間労働で余暇も気力もない。そうするとマーケットの動向も観察できないわけで、結局企業がどれだけ利益を上げても、次に何に向かって設備投資して行ったらよいのか分からず、そうしているうちに内部留保ばかりが増えていく、というのが今の状況だと思います。
文学についても、出版業界のピークは一九九六年から九七年と言われています。僕は一九九八年にデビューしたので、僕のこの二一年くらいの文学生活は、ちょうどこの業界が坂を転げ落ちるのと軌を一にしているんですが、それでもまだいい時期にデビューした方だと思います。その間、出版界では暗い面持ちで本が売れなくなった原因の議論が重ねられてきたわけですが、その際の内省のテーマは、「読者の読解力が落ちて、文学を理解できなくなっているのではないか」に関する話でした。また時間に関してはコンシャスで、インターネットの登場以降、相対的に本を読む時間が少なくなっているのではないかとも言われ、僕もそういう話はよくしました。
だけど蓋を開けてみると、結局個人の可処分所得が下がり続けていて、要するに、読者にお金が無くなっているというのが、本が売れなくなった非常に大きな理由の一つでした。このことは驚くほど出版業界の中で日常的な会話に出てきませんでした。本が売れなくなっているのは、要するに国民が貧乏になっているからじゃないか、ということは非常に大きな問題です。読書人が余暇と自由になるお金をもう少し多く持って、もう少し本を買うことができれば、やはり、どういう本が、どういう関心で今読まれているのかもよく分かるでしょう。また、「ハズレ」を恐れてベストセラーばかり読むのではなく、もっと何となく気になるような本にまで手が伸びていくはずです。
「いい物を作っても売れない」とずっと言われてきましたが、富裕層を見ていれば、ちょっと高くても少しでもいいものを買おうとするのですから、中間層以下の世帯でも、お金の余裕があれば必ずいいものを買おうとするはずです。それが実現できるだけの余暇とお金があれば、それに向けて商品を作っていくというサイクルになるはずなんです。今はとにかく、一人の人間が労働者としてこき使われることばかり考えられているので、消費者としていかに豊かにしていくかということが、全く蔑ろにされている。そうした中では、時間もお金も労働の方に搾り取られるだけ搾り取られて、なかなか文学を読むことにまでなって行かない。そうすると、いったい今の人間が何を考えて、どういう本に心を動かされるのかということの実態自体が見えにくくなってしまうという悪循環です。
社会の機能の一部であること
"役に立つ"という話をもう少し考えてみたいと思います。この言葉は何となく嫌な響きのある言葉ではあります。僕はボードレールという詩人がとても好きなんですが、彼は『赤裸の心』という遺稿集の中で、「役に立つ人間であるということが私には常に、何かしらひどく醜悪なことと思われた」という呟きを残しています。ここで彼は「utile(役に立つ)」というフランス語を使っていますが、僕は大学生の時にこの一文を読んで、非常に心慰められるところがありました。「そうだ! いいこと言うなぁ」と。
ここでボードレールが何を言おうとしていたのかについて、もう少し真面目に考えてみたいのですが、彼はこの言葉を人間について言っています。「役に立つ人間(homme utile)」と言っている。近代社会というのはご承知のように、機能的に分化して、分化した機能が緊密にリンクして社会が維持されています。それぞれの機能の中で働く人間は、ある意味ハンナ・アーレントが言うように、目的として扱われるのではなくて、全体の中の一つの手段として扱われることになる。しかも社会には格差がありますから、労働は共同体にとって良いことに繋がっているという実感よりも、むしろ資本家に搾取されているだけという感じになり、「役に立つ」ことが自分の存在承認に全然跳ね返らなくなるという問題が起きてきます。
一方で、世界的なベストセラーになったユヴァル・ノア・ハラリの『サピエンス全史』とか『ホモ・デウス』を読んでいますと、基本的人権が遍く国民に保障されて、教育の機会均等が保障される社会システムがどうして有効だったかということについて、労働力として万遍なく皆が教育を受けて、その人たちが機能的に分化した社会の中に絶え間なく労働力として供給されていくことが実利に合致していたからだとされています。フーコーの生政治の議論とも重なる話です。しかし、これからAIとかロボットが登場して仕事の多くを担っていくと、資産家階級のような人達と、仕事が無い人達の間で格差がどんどん広がっていく。そうした時に、社会的な格差を是正しなければいけないとか、教育の機会均等を維持しなければいけないというインセンティブ自体が失われていき、格差は格差のまま放っておかれるような社会が登場するのではないか。これが『ホモ・デウス』という本の暗い未来予想です。ハラリ自身は「そうなってはいけない」と言っていますが、その未来予測には嫌なリアリティがあります。
社会の機能の一部になるということは、僕たちは手段としてこき使われていて嫌だ、という感覚がある一方で、しかし、社会の中で自分が何らかの「役に立っている」という承認願望を満たしてくれるところがあります。それを極端な形で表現したのが、村田沙耶香さんの『コンビニ人間』だったのではないかと思います。
この小説は世界的なベストセラーになりました。最近、外国に行っていろいろな人と話をすると、村上春樹さんの名前も相変わらず出ますが、村田さんの名前を耳にすることも多いです。この小説は、自分が社会の中から疎外されているという意識を持った主人公が、コンビニの店員として役に立つことに唯一自分の社会との接点というか存在承認のようなものを感じ取ることができるという、非常にアイロニカルな小説です。海外の書評を見ていると、日本のぶっ飛んだ女の子の話というような評価もあって、ちょっと日本での読まれ方と違うところもあるようですが、とにかく、僕たちが数十年先に直面しようとしている問題の一つは、いったい人間のやる仕事がどれくらい残っていくのかということであって、そうすると、やはり労働を通じて社会の役に立っているという実感自体は、非常に重要なんじゃないか、と思えます。一つの機能として社会の中に埋め込まれていて、そのことを有難がられるということも、実は自分が生きている実感の中で必要なのではないか。
それから、対社会という大きな話ではなく、具体的な対人関係の中で役に立つことの良さもあるわけです。親兄弟、友達という他人の役に立つということには、相手のやりたいことの手段として自分が関与するのかもしれないけれど、そのこと自体は、必ずしも悲観的に受け止められるわけではない。自分が他人の役に立つことは嬉しいことであり、逆に自分が困った時に誰かが助けてくれると、「あぁ、良かった」ということがあるわけです。
社会全体の中で自分が一つの機能として役に立っているということと、対人的なコミュニケーションの中で自分が役に立っているかどうかということと二つがあって、その二つがどこかで結び付いているんじゃないか、というのが、言うなれば近代という社会だったと思います。
コスト社会論——冷たい否定/熱い否定
もう一つ言いたいのは、役に立つかどうかが問われる時に実は、最も意識されているのは、コスト意識ではないでしょうか。昨今言われているほとんどの問題はこれなんではないか。つまり、時間的なコストと財政的なコストに関して、対費用効果的に見合うものかどうかということが、「役に立つ」という言葉が発せられる時の根本にあります。
僕自身は、格差社会論の中で気になっていることがありまして、「新自由主義(ネオリベラリズム)以降」とこの研究集会のテーマにも掲げられていますが、ゼロ年代の格差社会論と一〇年代——東北大震災以降と言っていいかもしれません——のそれとに、変質があったと感じています。
ゼロ年代の格差社会論では、「勝ち組—負け組」という言葉が用いられるようになりました。この言葉は僕の記憶では、最初は新自由主義的な改革の中で、企業に対して用いられていました。個人も貯蓄をしているだけじゃなくて、できるだけ投資にお金を回しましょうと喧伝される中で、バブル崩壊後、株をどこの会社に投資したら良いのかについて、雑誌等が「勝ち組企業—負け組企業」という特集を頻りにしていた。
ところが、いつの頃からか、その二分法が人間にまで拡張されて、「あいつは勝ち組、あいつは負け組」と言われるようになりました。そのことを内面化してしまった人物による犯罪——例えば秋葉原の無差別殺傷事件のようなもの——も起こりました。『決壊』という僕の小説は、その予言のように受け止められましたが。その時は、まさに新自由主義的な雰囲気の中で、よく言われたのが、片山さつき的な、「努力している人が報われないのはおかしい」ということでした。勝ち組と言われている人達は努力をしていて頑張っているのだから金持ちになっていいじゃないか、という勝ち組擁護論が強かったと思います。貧困に陥っている人は努力が足りないとか、色々言われましたが、要するに「自己責任」として放っておかれており、その意味では、「消極的な、冷たい否定論」が貧困状況にある人達に向けられていたと思うんです。
ところが三・一一以降は——三・一一の際には一種の絆ブームがあって、国民的な一体感が強く主張され、ナショナリズムも昂揚し、それから、財政問題について、ゼロ年代よりも皆が遙かに意識的になり、国の借金問題がしばしば議論に上るようになりました。
人が皆、予算の使い道に非常に意識的になっていって、社会の中の貧しい人に対して「あんな奴等に金を使うべきじゃない」とバッシングするようになりました。予算を何に使うべきかという話の中で、使われるべき対象と、使われるべきでない対象とを選別する意識があらゆる所で見えてきました。貧しい人たちは、ゼロ年代の初めまでは自己責任論の中で無視され、放置されていたのが、一〇年代になると、社会保障費で国に財政的に迷惑をかけていると批判されるようになり、ある意味で「熱い、積極的な否定論」になっていきました。それは新自由主義というよりは全体主義的な風潮で、とにかく、選別する、セレクトするという意識が非常に強くなってきました。
しかも、それがあらゆる問題に関して厳密に適用されているかというとそうではなく、戦闘機など山のように買っても、税金の使い道としておかしいというバッシングの声はあまり上がらず、医療費や社会保障費に関して税金が使われる際に、ものすごく些細な問題に皆ががみがみ言って盛り上がる傾向があります。
こうしてコスト意識が一人の人間に適用される中で、例えばやまゆり園の殺人事件のように、一種の優生思想のようなものがそれに力を得て、「障碍者などを社会の中で生かしておくということに意味がない」という発想を持つ人まで出てきてしまいます。繰り返しになりますが、それはゼロ年代の初めにあった「冷たい、消極的な否定論」の単純な延長線上にはなく、存在していることが社会に迷惑をかけているという、積極的な否定論なのです。
コスト管理とリスク管理
それからもう一つ、リスク社会論という言葉をよく耳にされると思います。コスト管理と共にリスク管理をやっていこうという思想が、非常に社会的に強くなってきました。これはやはり、九・一一のテロ以降の感覚だと思います。恐らく最も顕著にその傾向が現れているのが、医療だと思います。
「サーベイランス医学」という言葉があります。これまでは、病気になって初めて病院に行き、その時点から医療費が発生するわけで、医学の対象は病気の人でした。ところが予防医学というのは病気以前から医療費が発生します。対象とされるのは病気になった人ではなくて、健康な人を含めて、全ての人です。健康な人を含め全ての人を二四時間モニタリングすることによって、リスクを防ごうという発想です。それが本当にコストカットに繋がっているのかについては否定的な議論があるのですが、この感覚はセキュリティの分野でも同じように起きています。
これまでは、犯罪が起きたら、捜査が始まって予算が必要になりましたが、リスク管理の観点からは、犯罪が起きる前に予防しなければいけない。それで、健康な人が医学の対象になったように、普通に生活している人全員が四六時中監視の対象になり、どこかに犯罪の芽が無いか、虱潰しに監視しなければいけなくなりました。
しかし、僕たちがアップルウォッチかなんか着けて、「今日は歩いた歩数が少ないな」等と個人的に管理するのとは違い、犯罪はネットワークに公権力が関わるために結局、リスク管理とコスト管理が両輪のようになり、そのために今、社会が圧迫されているのではないでしょうか。
さらに言えば、個人の自由と公共性との接点について、かつて僕らが日常感覚の中で感じていた結び付きとは、次元を異にしてきているように思います。というのは、ちょっと前までは、煙草を吸っていいかどうかは、全く個人の自由でした。「煙草は健康に害があります」と言われても、個人が自分の命に関して他人からとやかく言われる必要はないということを根拠に、「俺は癌になったっていいから煙草を吸い続けるんだ」と、そう言えたわけです。ところが先程言ったように、今日の財政問題に国民がシビアになっている状況では、「煙草を吸って癌になった奴の医療費を、なんで俺達の税金から払わなくちゃいけないんだ」というように変わってきました。個人の自由と思われていた領域の話が、すぐに国家の財政問題に直結するようになってきています。
個人の嗜好と公共性の問題は煙草のみならず、昨今では国家を越えて、環境問題として起こって来ています。ヨーロッパで今顕著になっているのは、一つは、「飛行機に乗らない」という運動、それから「牛肉を食べない」という運動です。牛肉を好きかどうかということは、少なくとも日本にいれば、ここ最近までは殆んど議論になりませんでした。しかしヨーロッパの友達と喋っていると、割と普通の会話の中で、「牛肉を食べる量を控えている」ということを言う人たちがいるんです。それはご承知のように、畜産の中でも牛を飼うことによる環境負荷が非常に大きいためです。それは、観念的な話ではなくて、代替肉をハンバーガーショップが開発するなど、かなり具体的なビジネスにもなってきています。
それから、つい昨日(二〇一九年一一月二二日)ニュースになっていたのですが、Coldplay(コールドプレイ)というイギリスの有名なバンドが、アルバムは出したけれどツアーはしません、と発表しました。何故かというと、ツアーに伴うCO2排出量が莫大だからだ、と言うのです。物凄い数のスタッフが飛行機で世界中を移動することに伴うCO2と、それからファンが各地から移動して来る際に排出されるCO2を計算してみると膨大で、それがプラスマイナスゼロになるような方策を考えつくまではツアーをしない、という発表でした。
ライブに行って音楽を楽しむことは、非常に私的な、個人的な趣味と考えられていた領域です。或いは「鶏肉よりも牛肉のが好き」だとか、「毎日炭水化物を食べないで赤身の牛肉を食べています」という話が地球環境問題に直結するという感覚は、僕達が今まで感じていた個人的な生と公共との関係には収まらず、次元が違ってきているような感覚を受けます。
文学の機能主義
さて、そうした現状における「文学」です。文学の場合も、以上話してきたような諸々が非常に複雑に絡み合って、「文学は役に立つのか?」という問いを恐らく突き付けられているのではないでしょうか。少し前に、漢文を学校で学ぶべきかどうかということが学界でもかなり刺激的な形で議論され、本にもなっていました。この場合も、漢文そのものが良いかどうかよりも、要するに、学校の授業時間の中で、漢文を教える時間的なコストを教育現場で取るかどうかがしばしば指摘されます。それから、大学で役にも立たん文学なんかを教えることに意味があるのかどうかということも、皆さん色々な形で突き付けられている問題だと思いますが、要するにこれも、個人が文学が好きだから勉強したいという問題と財政問題が、あるいは社会の中で本当にそれが役に立つかということが、非常に短絡して議論されているわけです。
その時に僕達は、やはり「役に立たなくても価値がある」と言い続けることが一つは大事なことなんだと思います。先程の人間の話に関しても、別に僕達は役に立つから社会に居ていいわけではなくて、基本的人権を認められていて、人間は存在するだけで、その存在そのものを尊重されなくてはいけない、という認識に立つべきですし、実際この国の憲法もそれを謳っています。だから、居るだけで価値がある、というのは非常に尊いわけです。そういう意味で、文学に関しても、役に立つかどうかはともかく、価値があるということを何らかの形で表現していくことは非常に重要だと思います。
と同時に、やっぱり文学は役にも立つのではないかな、という感じが僕はしています。最初に言った、「正気を保つため」という非常に重要な意味自体も含めて、そう思うのです。
ちょっと余談ですが、僕が作家としてデビューしたのは一九九八年で、その頃はちょうど文芸批評のポストモダン・ブームもいよいよ最後に差し掛かっていて、批評が役に立つのかどうかみたいな議論がかなりありました。状況論的に言うと、僕がデビューした頃は『批評空間』的な言説にちょっと皆が疲れていて、自分が小説が好きで読んだり感じたりしていることと、あそこで観念的に議論されていることが乖離し過ぎているように感じられていました。実作者の側にとってもそうだったし、読者の側にとってもそうでした。その疲労感の後、ゼロ年代以降は文芸雑誌なども、いわゆる文芸批評というよりも、もうちょっとブックガイド的な書評とか、新刊が出ても酷評したりする動きが少なくなって行って、割とマイルドな本の紹介になっていく傾向がありました。それから、専門の研究者や批評家に批評を書かせるのではなくて、日曜批評家というのか、他のジャンルで活動している人に書評を書いてもらうようなことが増えました。その時に、「批評の役割は何なんだ?」という話も当時ありました。その時に語られた一つが、機能主義的な意味なんです。
つまり、文壇というあるシステムの中で、機能として必要なんだ、という説です。その通りだと思うんですが、説明の仕方が良くなかった。誰とは言いませんが、とある批評家は、「批評家が抑圧的に振舞い、作家がそれに反発しようとすることによって、良い文学が書かれる」みたいな(笑)、非常に愚かな批評擁護論を展開していました。当時僕はデビューしたばかりでしたけれど、流石に馬鹿馬鹿しいのでつきあいきれませんでした。結局、そんな話は誰も真に受けませんでした。
ただ、僕たちはそうは言っても、この社会のシステムの中に生きていて、文学はそれでも求められてきたというのは、何かの機能を果たしているのだとは思うのです。今みたいな粗雑な話ではなくて、もう少しちゃんとした機能の説明の仕方も可能なのではないかと思います。
アートがアートである理由
ちょっと横道に反れますが、今、文学と同じように社会の中で、特に予算との関係で、政治的にも非常に難しい状況に陥っているもののひとつが、アートです。ご承知のようにあいちトリエンナーレでは大騒動になりました。それ以降、「国民感情を傷付ける」という名の下に芸術が非難され、政府が手続き上の屁理屈で公的資金の交付を停止したり、外務省がバックアップするはずだった企画から撤退したり、色々なことが起きています。文学について論じる時に、このアートの事例は参考になるでしょう。
分析美学という学問がありまして、これは六〇年代くらいから続いています。アーサー・ダントーという人の「アートワールド」という論文以降くらいから発展してきた学問のようです。この数年、『分析美学基本論文集』とか、色々邦訳が出まして、日本語でも重要文献が手軽に読めるようになりました。中でも、ダントーの語っている「アートワールド」という概念が、今の状況の中で効果的なのではないかと思います。
アートワールドというのは、論文自体は何とも言えないところがありまして、ダントーが元々六〇年代にアンディ・ウォーホルの展覧会に行ったところ、ハインツのケチャップだとか洗剤だとか、マス・プロダクトのパッケージ等が並べてあるのを見て、「こんなの芸術じゃない」と立腹している人たちがいて、なぜそれが芸術なのかを論理的に証明しようとして書いた、という経緯の短い論文です。その論文の中で例に挙げられているのは、ウォーホルだけではなくて、例えばラウシェンバーグがベッドを壁に立てかけて、それにペンキを塗っている作品などですね。それらがアートだと言われて、なぜそんな物がアートなんだ、という話になっているんです。
ダントーは何と言っているかというと、なぜそれがアートなのかは、「アートワールド」がそれをアートだと言っているからアートなんだ、と言うんです。アートワールドとは何なのかについて、厳密に構成員を定義していませんが、要するにアーティストがいて、キュレーターがいて、研究者がいて、ギャラリストがいて、批評家がいて、一般の美術愛好家がいて……という世界を総じて彼はアートワールドと言っているのでしょう。そしてその中にある——これが非常に微妙な言葉なんですが——あるatmosphere(雰囲気)がそのベッドをアートにしているんだ、と言うんです。或いは、アートワールドの中にある知識が、ベッドをアートだと認定している、と言います。
ベッドは一義的な物ではなくて両義的な物で、その辺の道路にポンと置いてあったら、ただの捨ててあるベッドなんだ、だけどアートワールドの人たちがそのベッドを展覧会場に展示していて、それをアートとして見せていることでアートになっている、というトートロジーのような、当たり前のような話をしています。
僕は最初それを読んだ時に、あまり感心しませんでした。当たり前なんじゃないの? と。一応美学的には、「美とは何か」とか「芸術とは何か」ということは、作品に内在する本質を問うことで答えを出そうとしていたのに対して、社会制度的なものを通じて究極の相対主義的な観点から、芸術とは何かを論じようとしたところが、非常に画期的だったと言われています。ただ集合的にはそうかもしれないけれど、個々のアートワールドの住人がなぜそれをアートとして認識し、それがアートワールド全体の認識になっていくかというと、結局、その作品に表われている美しさとか批評性とか、ある実体的な要素を評価してそれをアートだと認識しているのではないか。そして、その人が言語活動だとか展覧会を企画するなどして、アートワールド全体の中で影響力を及ぼしていって、アートだと認識されているんだと思います。個人的な作品鑑賞においては、相変わらず、ある種の本質が問われているんじゃないかと思うのですが。
アートワールドの自律性
それはともかく、アートワールド全体で議論しながら、或いは影響力のある人が推薦したり、高い値で売れたりという現象の中で、ある物はアートと認められ、ある物はアートじゃないとされ、しかもその基準も時代によって変わっていく。
MOMAなどパーマネント・コレクションと称してコレクションしているけれど、実際は、ある時間が経って要らなくなると、パーマネントと言っている割には、けっこうリリースして売ったりしています。ですから、何がアートで何がアートじゃないかということは、アートワールドが自律的に判断し続けているんだ、という、ある意味では当たり前の話なんです。
アートワールドの議論に僕はあまり興味なかったのですが、あいちトリエンナーレの一件以降、政治権力や暴力を背景に、「これはアートじゃない」という声を押しつけようという動きが社会の中に出てきた時、このダントーのアートワールドという議論は有効なんじゃないかという気がしてきました。つまり、何がアートで何がアートじゃないかということは、あくまでアートワールドの中で自律的に決定されなくてはいけないのであって、そのアートワールドの中でどのように人が影響力を行使していくかということは、説得力のある論文を書くとか、美術展を成功させるとか、非常に時間のかかるプロセスの中で決定されていくわけです。そこに一人の人間が突然やって来て、政治権力を使ったり暴力を背景に、「これはアートじゃない」ということをゴリ押ししようとするのは間違っています。
国家が自国の中にアートを制度的に抱え込むということは、アートワールドの自律性を信頼し、保護するということです。僕はその信頼性があるかどうかが非常に重要だと思います。アートというのは、人間がサルかヒトかようやく区別がついたくらいの頃から——それをアートと呼ぶかどうかはともかく——延々と続いてきた人間の営みです。それは国家の出現などより遙かに早くから始まって、何だかよく分らないけれど人間がとにかく必要としてずっと続いてきた営みなわけです。国家はそれを抱えておいた方がいいんだ、という発想の下に国家はアートを抱えている。だからこそ、その自律性を守って行かなければならない。
アートは国家より遙かに長いタイムスケールを人間の進化と共にしてきたし、国境を越えるような広い地理的ネットワークを持っています。そうすると、そこで考えられていることは、その時どきの政権の考えとか政策とは対立することは当然出てきます。出てきても、それでもアートを抱え込んでおいた方が、平たく言うと、国家にとっては得なんだ、そこから出てくる思想なり発想なりが中長期的には国家にとっては大きな活力になるんだ、という考えの下に、国家はアートワールドの自律性を尊重しながら維持していくべきだ、というのが基本的な考え方なんだと僕は思うんです。つまり、アートは、「役に立つ」ということでしょう。それを今の政権、今のトレンドの思想で矮小化しようとすると、結局、国家の今現在を超えていくような活力を共同体の中から失っていってしまう、ということが問題だと思います。
文学の救い
この考え方は、ある程度文学にもスライドさせることができるのではないかと思います。日本は憲法で、「健康で文化的な最低限度の生活」が保障されていますが、フィジカルな健康さえ維持されていれば国家の役目は十分だ、と解釈する風潮が昨今広まっています。とにかく食っていけるだけでいいじゃないか、と。そういう観点で、例えばNHKで相対的貧困に陥っている家庭が特集されて、その子の家にマンガが置いてあると、「貧乏とか言いながら、マンガが揃っているじゃないか、贅沢しやがって!」みたいな話になってしまう。だけど、「健康で文化的な最低限度の生活」を保障しなければならないのが国家なのです。これは、ドストエフスキーの『大審問官』の頃からずっと続いていることですが、人間は腹が満たされれば生きて行かれるのかというと、精神を健康的に維持しないと、どうやったって、生きて行くことはできないわけです。芸術も文化も何もかも抑制された中で、お腹一杯なんだから満足しろと言われても、どうしてもそれでは生きていけない、というのが人間です。それは、ファシズムやスターリニズムを見ても明らかです。
僕自身は、「文学は何の役に立つのか?」という根本問題を考える時に、やっぱり、自分は文学のお蔭で救われた、ということを非常に強く思うのです。僕は北九州という工業都市に育ちました。第三次産業の盛んな福岡に比べると、北九州は基本的に労働者の町ですし、しかも当時は製鉄所も衰退に向かっていました。同級生で本を読んでいる人なんて殆んどいませんし、子供の時にピアノを習っていると「女みたいだな」と言われるような土地柄です。そういう状況の中に生きている苦しさと孤独が強くあるわけです。その時に、僕は本を読み始めて、非常にそれに救われたんです。
なぜかと言えば、先ほどのアートの話と同じように、文学は、「今ここ」という自分の実存の限界状況から解放してくれるからです。僕はもともと、三島由紀夫の『金閣寺』という小説に感銘を受け、それから、三島が影響を受けた色々な作家の本を読むようになりました。その中で一〇代の時は、特に初期のトーマス・マンが好きでした。社会から一種の疎外感を感じている中で、人によっては太宰治を読んで慰められたりしたのかもしれないけれど、僕は三島由紀夫が好きだったから、何となく太宰治が好きじゃなくて(笑)、まぁ、そこまで付き合う必要もないんですが、たまたまトーマス・マンを読んだんです。
トーマス・マンに共感したのは、"世の中腐っている、俺はその世の中から疎外されている"という感じではありません。『トニオ・クレーガー』のような小説は典型的ですが、主人公は美的なもの、詩的なものに強い憧れを持っていながら、一方で——『ブッデンブローク家の人々』もそうですが——市民社会的なものに対しても非常に強い憧れを持っているんです。だから友達がクラスでフォークダンスをしているのを見て、「自分もあの輪の中に入れるような人間だったら良かったのになぁ」と思い、一方で、そういう市民社会的な世界では受け入れられないような美の世界にも耽溺しているという、揺れ動く心を描いている。その感じに僕は非常に共感したんです。
僕は北九州みたいな——北九州も良い所ですけれど(笑)——特に当時はヤンキー・ブーム真っ只中の「ビー・バップ・ハイスクール」とかが流行った時代ですから、一〇代の頃はまさに「サバイバル」だったわけです。ただ、僕の実家は公務員や医者が多い、固い家庭だったんです。その親戚達を見ていると、フローベールの小説に出てくるようなくだらないプチブルの俗物みたいにも見えないんですね。この人達はこつこつ働いていて、善良でいい人たちなんじゃないか、と。その市民社会的な感じというのが、トーマス・マンの世界観と近い感じがあったんです。自分も本当はああいう世界で健康的に生きて行くべきなんじゃないか、という感じと、でもやっぱり自分は絵が好きだし文学が好きだし……という中で、現実的には結局作家になりましたが、一〇代の頃、日本の田舎で過ごしていると、自分が将来小説家になるなんてことはあんまりリアルにも考えられないし……という中で、どうやって生きて行ったらいいのかという気持ちをずっと抱いていました。それが、『トニオ・クレーガー』とか『ブッデンブローク家の人々』を読んで、「分かるなぁ」という感じがしたんです。「まさにこれは、俺のことを書いている」と。
どうして二〇世紀の初頭のドイツ人が北九州に住んでいる一〇代の俺の気持ちをこんなに分かってくれるんだ、親よりも、友人よりも分かってくれると感激し、また非常に単純でしたから、トーマス・マンがノーベル文学賞を取ったことを知り、俺は下らないことでうじうじ悩んでいるような気がしていたけれど、実はノーベル賞作家と同じことを悩んでいたんだな、と思い付き、けっこう人類的に重要なことを悩んでいるんじゃないか(笑)、という気がだんだんしてきました。それで、悩んでいること自体を励まされるというか、心強い援軍を得た気がしたんです。
それで、僕は「今ここ」の場所から自分が解放されて、解放されるだけじゃなくて、別のネットワークに自分が接続されていく感じを持ったんです。自分がもっと心地良くなれる場所が世界に存在していて、しかもそれはノーベル文学賞作家など、高く評価される人たちがいる場所なのだ、と。皆さんも他の国に学会等で行かれた時に感じられるかもしれませんが、実際に僕は作家になってから、そういうネットワークが実在していて、その住人たちと同志的に対面したんですね。
北九州で中学生時代を過ごしている頃には、クラスに四〇人くらいの生徒がいても、三島由紀夫読んで「いいなぁ」と思っているのは僕くらいなものでした。そして文学の世界にのめり込めばのめり込むほど、一種の初期症状として、自分の見ている認識と友達の見ている認識がだんだん乖離してきて、ますます生き辛くなるというか、孤独が深まるという感じがありました。でも作家になって、今色々な国の作家と接したり研究者としゃべったりしていると、そういう経験をした人が、実は世界中にたくさんいて、しかもそのネットワークが数万人とか数百万人という大きなネットワークを形成していることが分かります。
今であれば、インターネットがありますから、「今ここ」の状況から解放してくれる世界は若者にとっては珍しくないかもしれませんが、当時の僕にとっては非常に大きなことでした。
しかも、各国で、「今ここ」から解放された経験を持っている人たちと出会って共感するにとどまらず——世界文学というようなものが、二〇世紀の半ば過ぎくらい迄にはある程度ラインナップが定まってきましたから——同じ本を読んでいるんです。ドストエフスキー読んだとか、バルザック読んだとか……そのように共通の話題にも事欠かないで話をすることができる。そうすると北九州で育った友達よりも、遙かに仲の良い友達が外国の見知らぬ土地にいた、という発見になるわけです。それは、大変な解放感でした。
三島由紀夫の『金閣寺』から本を読み始めたんですが、三島を読んだ時の僕の感動のひとつは、文体でした。それまで自分が知っていた日本語と全く違う、非常に煌びやかでレトリカルで、「あ、日本語にはこういう言葉があるのか」、と思いました。しかも三島の場合はそれがブッキッシュなくらい古典的な言葉と接続していて、それも「今ここ」の言葉から僕を解放してくれるものだったんですね。その文体が人工的で嫌だという人もいると思いますが、僕にはそれが非常に魅力的に感じられました。
同時に、主人公が非常に暗い、というところがまた良かった(笑)。それが、自分が教室の中で孤独を感じていることと重なります。『金閣寺』の主人公は皆さんご存知のように吃音で、社会とうまくコミュニケーションをとれなくて、金閣寺の美だけが心の拠り所だというところから話が始まります。その感じが、非常によく分る感じがしたんです。
暗ーい心情を、非常に煌びやかな文体で描いている、そのコントラストに心を打たれました。暗い心情をじめっと嫌な感じで描かれてそれに共感していると、「俺って本当に嫌な人間だな」っていう感じがしてくるんじゃないかと思うんですが(笑)、自分がうじうじ悩んでいたことがノーベル賞作家が感じていたことと同じだったんだと思った時と同じように、まさに、自分の悩んでいることや自分の状況に、その文体によって一種の価値が与えられるというか……それは個人的なものとして孤立して放っておかれるべきものではなくて、共有されるべきものなんだ、と感じたんですね。
普遍に至る個人
文学の良いところはまた、主人公があくまでも個人である、ということです。お門違いの質問に思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、よく僕がされる質問が、「平野さんの小説を読んでいると、非常に思想的だったり社会的な問題が出てきて興味深いんですが、なぜそれを小説という形で書くんですか? 論文で書いた方がいいんじゃないですか?」と聞かれます。論文が面白く書けたらそれもいいのかもしれませんし、ユヴァル・ノア・ハラリみたいな人は面白く論文風のああいう本を書いていますが、やはり小説の良さは、どこまで行っても話が一個人から始まることなんです。社会学とか哲学で扱おうとすると、どうしても或るカテゴリーを扱わなければいけない。Das Manとか、何年代の三〇代の人達の消費傾向とか……そうすると、どうしても或るマス(Mass)のカテゴリーを念頭に置かなければいけません。
しかし文学の場合は、何丁目何番地に住む固有名詞を持った一人の人間から始まるわけです。そうするとその人は、一般的な人間である必要は全くなくて、「そんな奴いるのかな」と思えるような、例外的な変人から話を始めてもいいわけです。大勢の人と考えていることが違うという感じを持っている人間からすると、一般論から始めなくていいという利点は大きい。それが、「俺の書いているものは誰も理解しなくてもいいんだ」と作家が嘯く一つの根拠になっていると思います。
ただ、やはり文学というのは本の形になって流通する形態としてはマス・プロダクトです。例えば僕が美容師なら一人のお客さんの毛質と頭の形に応じて自分の技術をカスタマイズするわけですが、本というのは一つの形を確定させた後、多くの人に読んでもらう。非常に多様な世界であるにも関わらず、或る一定の数の人が読んでくれることで成り立っている仕事なわけです。そうすると、或る変な奴がいる、「此奴俺と全然違うけれど、何なのかな?」と思いながら読んでいって、最後まで「全く俺とは違う奴で変な奴だ」で話が終わったら、変な奴が一人いたということしか残らない。だけど、読んでいるうちにどこか読者が「此奴は変な奴だと思って読んでいたけれど、何か分かるところがある」「自分もそういう気持ちになる時がある」とか、或いは、「ある変人についての話だと思っていたけれど、やはり人間にとって普遍的な問題に触れているんじゃないか」という感じを持つかもしれない。そういう体験があるかどうかが、一つの小説が成功するかしないかの賭けのようなものだと思います。
小説家は、一人の変人から話を始めたとしても、どこかで——これは括弧付きですが——ある「普遍性」や「一般性」に触れる瞬間が訪れるかどうかを考えながら書いています。考えながらというのは、そういう瞬間が来るかどうかということと、もう一つはタイミングが非常に難しいんです。
というのは、永遠にそのタイミングが来ないと、読んでいても主人公に共感できないとAmazonレビューに書かれることになって(笑)、途中で読むのをやめちゃうんですけれど、早すぎるとまた、読者は非常に反発するんです。或る登場人物がいて、彼の悩みは現代人一般の悩みじゃないか、みたいな感じが余りにも早く出ると、読んでいる方は「俺はこんな変な奴とは違う」と、気持ちが離れてしまう。だから、ぎりぎりまで「この人は他人なんだ」という感じを持たせながら、最後は寄り切られる形で、「これはやっぱり人間一般の問題に触れているのかもしれない」と——村田沙耶香さんの『コンビニ人間』もそうでしょう——どこかでその瞬間が来るかどうかということが、複数の人間に読まれるかどうか、ということに関わってきます。
それと、文学をずっと書いていて思うのは、読者は、自分のことがそのまま書かれてあると嬉しいかというと、必ずしもそうでもないんです。主人公に共感したいという気持ちはかなり強くあって、主人公に共感できないと物語を楽しめないのですが、全く同じがいいかというと、そうでもない。僕がそういうことを考え出したのは、『葬送』という小説でドラクロワという画家について書いた時に、多くの人が、「私はドラクロワみたいな大画家じゃないけれど、彼がアトリエに行って、仕事しなければいけないのに今日は仕事しなかった、みたいなことを思い悩んでいるシーンは、凄くよく分かるんです」という感想を語った時でした。それは僕の創作ではなくて、ドラクロワが日記の中にそう書いているから小説にしたのですが、つまり、読者は全く等身大の人物を描いてほしいわけではないのです。僕がまさにトーマス・マンの小説に感動したように、「ドラクロワのような大画家でも私と同じようなことに悩んでいた」と、共感にしても同一レベルの共感ではなくてちょっと顔が上を向いたような共感を、感じているわけです。そういう、自尊心を刺激する共感もあります。
人は皆自分の悩みをあまり価値があることと思っていないので、ちょっと憧れるような登場人物とか立派な人の中に共感を見出すと、心地良く共感できる。逆に、ものすごく下らない登場人物に「これ、俺と同じだな」と思うと、共感はするけれど嬉しい共感とは違うんだと思うんです。「やっぱり俺はこんな下らない人間だったんだ」とますます落ち込むことになる。
まぁ、その辺もそれほど単純には言えなくて、ミシェル・ウエルベックの小説を読むと、およそ共感したくないような人物が出てきますが、一種のヒーリング効果というか、あれはあれで不思議な癒やしもありますし、なかなか難しい問題です。
文学が個人を介する意義
同時に僕たちは、これは『ある男』という小説のテーマでもあったんですが、自分の問題を誰よりもよく知っているにも関わらず、なかなか自分自身では解決できない。クラスで孤立していることなんか百も承知しているのに受け止められない。それを小説や他人の人生を経由すると、改めて認識し直したり、共感によって孤独が和らげられるということがあります。
実際には、僕が一〇代に愛読したトーマス・マンの小説の登場人物なんか、僕に似ていないところの方が遙かに多いんです。小説は、似ていない他人の話だからこそいいんだ、ということもあると思います。自分の問題を他者を経由して考えるということが、本を読むときに非常に重要な意味を持っているのではないでしょうか。
人間は、他人と語り合う時に、自分の固有名詞と共に悩みを語り合うのはけっこう難しいんです。例えば「不倫についてどう思いますか?」ということを議論する場合、やっぱり、「不倫は良くないと思います」と(笑)、言うしかない。けれど、『アンナ・カレーニナ』という本を読んで不倫についてどう思うか議論をすると、「不倫する気持ちも分かります」とか言えるわけです。他人を経由することによって、僕達は、自分では引き受け切れないけれど本当は感じとっているものを言葉にすることができる。文学には、読んでいる時の他者への共感と、読み終わった後、読み終わった人同士が文学を介することによってより自由に、或いはより寛大に共感し合うという効果があると思います。
それから、あくまで個人から考えるということは、僕達が現実的に政治的な問題について考える時にも有意義なんじゃないか、と最近特に思ったことがあります。日韓の間で徴用工や慰安婦が、この間ずっと大きな政治的問題になっています。特に徴用工問題に関して、すごく議論がヒートアップして韓国バッシングが日本の中で起きて、嘆かわしいことですが、僕は韓国の大法院の判決文を日本語訳で読んだんです。判決文はPDFで四四ページくらいあり、最初は読めるかどうか心配でしたが、読んでみると非常に読みごたえがありました。一応法学部出なんで、「なるほど!」と思ったこともいろいろありましたし。それはともかくとして、冒頭に、今回訴えを起こしている原告の四人がどういう人生を辿ったかということが簡潔に書いてあるんです。それを読むと、悲惨としか言いようがない。
典型的な一人は、一七歳の時に「技術を身に付けられるから」と言われて日本の製鉄所で働き始めたものの、今の技能実習生と全く同じで、それは名ばかりで、危険な仕事で長時間こき使われて、逃げようとしたら散々暴力を振るわれた。朝鮮半島から渡ってきたのが一七歳、今の高校生くらいです。僕はそれを読んで、日韓の政治的な議論の中で、「元徴用工」というカテゴリーだけで、皆が一個人としての実感を持たないままニュース等で報道されているけれど、自分もかつては一七歳だった、という立場で想像した時に、やはりこの人達を足蹴にするようなことをしてはいけないと強く思いました。いきなり、国家利益の代弁者になって、カテゴリーによって考えるのはなく、飽くまで個人として考える。一個人の境遇を考えること——国境も違うし背景も違うし、お前の共感は根本のところでずれているんじゃないか、と思われるかもしれないけれど——でも僕は文学をそういう風にして読んで来たんですね。トーマス・マンの登場人物だって、リューベックに生まれ育った人が書いた登場人物とお前の共感は、本当はずれているんじゃないか、と言われるかもしれないけれど、でも僕はそれに非常に強い共感をして孤独を慰められたことがあった。同じように、一九四〇年代の朝鮮半島で育った一七歳の少年にも文学作品を読んでいる時のような共感を持ったんですね。
と同時に、僕は日本でこれまでずっと、石牟礼道子さんとか林京子さんとか大岡昇平とか、国家権力や大企業のような大きな権力に人生を踏みにじられ、翻弄された個人の物語を読んできたわけです。そして、それらの作品に非常に強い感銘を受けてきた僕が、日本の植民地支配下における大企業の中で一七歳の子が人権を蹂躙され、酷い目にあったという話を読んで、足蹴にできるはずないんです。文学を読んできた僕の立場からすると、石牟礼さんや林さんの作品の中で主人公が経験していることと徴用工の経験は、連続して受け止められないとおかしいんです。僕達が周りの国の人達と付き合う時に、政治的な課題はカテゴリーに基づいた議論がされていくけれども、その枠組みを解きほぐして、中で生きている人間はどうだったのかということを考えていく上で、非常に大きなヒントを与えてくれるのが、文学体験でした。
共感できない作者について考える
それから文学は、主人公への共感もありますが、他に色々な登場人物が出てきますから、その中で反対の立場だとか極端な立場だとか、色々なことを経験しながら、全体として問題を認識できるという点も重要です。
僕は三島由紀夫という作家に対しては、非常に複雑な思いを抱いています。自分が文学に目覚めたのは三島という作家のおかげですし、三島の『裸体と衣裳』等のエッセイや日記を通じて様々な作家と出会うことができ、戦後文学の中では好きな作家ですが、政治的な立場という意味では、凡そ対極的なところに今僕はいます。三島は最後は憲法改正を訴えて市ヶ谷で割腹自殺するわけですが、その彼の主張と僕の現在の主張は、全く反対です。だけど、彼の文学に対する共感と登場人物への関心を通じて、彼が何を言おうとしていたのかについて考えようという気持ちは未だに強くあります。ああいう小説、ああいう登場人物を書いた小説家が、なんでああいう最期に至ったのかな、と。それが無くて最初から拒絶反応だと、「俺とは考え方が違う」というだけになってしまうんですが、むしろ文学というのは作品を通じて、共感できない作者のことを考える、という一つの手立てにもなっている。
例えば『金閣寺』で言うと、文学はおかしなところに考え所があるというか、あの小説でテーマとして貫かれているのは、認識が大事なのか、行動が大事なのか、ということです。それを延々と議論している。世界を変えるのは認識か行動か、と。そして最後は、その二つが一致しなければいけないという結論に達します。しかしこの問題設定自体は、じっと考えていると不思議というか、変な気がします。普通に考えれば、どちらが先かはともかく、どちらも重要なんじゃないかと思うわけです。認識が先で行動が起きることもあるでしょう。あまり単純化してはいけないでしょうが、ルソーの本を読んでフランス革命に参加するのは認識が変化して行動が起きるということだろうし、サラエボでオーストリアの皇太子が暗殺されるという行動が起こった時に、それが何事かを言葉によって認識する、ということもあるでしょう。認識が先か行動が先かということは、認識が先のこともあれば行動とか出来事が先で、それが後で言葉によって認識されるという順番もあるだろうし、いずれにせよそれが世の中を変えていくことになるんだから、三島が『金閣寺』で頻りに言っている「認識か、行動か」という二者択一の問い自体は、何か変なんじゃないか、と思うわけです……思うんですが、三島はものすごくそのことに拘っていて、四〇年代に政治活動を始めてからも、認識と行動の一致ということをずっと言い続けている。その変なところに考え甲斐がある。
思うにそれは、第二次世界大戦下の危機的な状況下での彼の発想なんです。平時では、認識が変わって行動に移す人もいれば、行動が先だってそれを認識して社会が変わることもあり得ると思いますが、三島の考えでは大戦中は、「行動が先だ」と言った人は死に、「認識がまず変わるべきだ」と言った人は、結局いつまで経っても行動しなかったから生き残った、ということなのでしょう。その発想が、危機下において認識か行動のどちらかを選ばなくてはならず、それならやっぱり行動しなければいけないんだ、という発想の源泉なんだと思うんです。『金閣寺』という小説を読んでいると、そうした問いの設定自体、ちょっと考えるとおかしいと思うんですが、おかしいということを、間違っているとか稚拙だと思う前に、彼の人生とその前後の作品の中でずっと考えていくと、もう一つ奥の段階で、言っていることが見えてくるわけです。文学はそういうことを僕たちにトレーニングさせてくれます。
文学の矛盾をどう考えるか?
もう少し他の話もしたかったのですが、喋っているうちに時間が来てしまったので、まとめに入らなくてはいけなくなりました。僕自身の創作活動の中では、けっこう「役に立つ」ということを考えます。享楽として文学を読んでいる人もいれば、「生きるか死ぬか」という精神的にぎりぎりのところで文学を読んでいるという人も沢山います。僕自身大きなきっかけになったのは、『決壊』という小説を書いた時に——いろいろな所で何回も言っているんですが——これは「個人」という概念を使って書かれてきた近代文学に対して、「個人」という概念を中心にしたシステムでアイデンティティを把握しようとすることが可能なのかどうかということについて徹底的に突き詰めていった結果、非常に不幸な暗い終わり方をする小説です。そうしたら、読者の手紙や雑誌のインタビュアーから、「平野さんの小説にすごく感動したのですが、どうやって生きて行ったらいいのか分からなくなりました」ということを、切々と語られたんです。従来であれば、「それは自分で考えてくださいよ。それが文学です」と返事をするのかもしれないですが、僕は『決壊』の後、そこまで考えなければいけないんじゃないか、という気がしたんです。
周囲の情報環境も整ってきて、実体験もしているし、皆いろいろな情報を知っているので、文学は問いを突き付けるだけのスタイルだけだと、読者が満足しないというか……「それは分かっている、格差社会も、世の中の理不尽ももう何もかも知っている、じゃあ、どうしたらいいんですか!?」ってことを読者が切実に求めていると感じました。単に文学を「愉楽」を得るものと見ているのではなく、生きるために読むからです。
それからもう一つは、僕の実感の中で顕著なんですが、希望のある終わり方をものすごく読者が求めている。ボルヘスという作家は、「ハッピーエンドは通俗的なことのように思われるけれど、物語がハッピーエンドかどうかということを文学の世界では昔から皆真剣に考えてきたんだ」ということを『七つの夜』という本の中で書いています。社会が辛い状況になってくると、終わりにハッピーエンドを読者が切実に求めていると感じることがあります。
そういうことに作家がどう応えられるか、という問いの中で僕自身は、一方で分人主義みたいなことを考えて、「じゃあ、具体的にどうしたらいいのか」という方向性と、読んでいる束の間、現実を生きている苦しさから解放されるような文学的な恍惚感のようなものを描いていくという、両方をやらないといけないな、と思っています。
最後に、今僕が東京新聞に連載している「本心」という小説の中でテーマとして考えようとしていることの一つをお話しします。
カール・シュミットという人がロマン主義を批判する中で、メーリケの『旅の日のモーツァルト』という本の中の逸話に触れています。その中でモーツァルトはオレンジの木を見て、「互いに手をとりあって」というアリアを思い付くんですが、シュミットはそれを批判します。世の中には原因と結果があって、本来社会はその因果関係で動いているはずなのに、芸術家は、因果的な論理性が全く無い行動をとる。オレンジを見てアリアを思い付くなど、何の論理性もないように見えることを思い付くのがロマン主義者だ、と。彼はそれを「原因」に対して「機因」と呼んで区別するんですね。それのどこが悪いかというと、政治的に全く無力だから、と言うんです。現実的に辛いものを見たら、それに対して論理的必然的な行動をとるべきなのに、芸術家は同じものを見ても、とんでもない素っ頓狂なものを思い付くだけだ、と。
現実と文学体験との関係を考える際、例えば貧困などの非常に辛い状況にあって、僕の本を読むことで少し世の中の見え方が変わって、現状に耐えられるようになるとします。だけど、そうすると、現実に存在する貧困状態はそのままになるわけです。この格差社会にあって、格差があってもこのままの状態が続いてくれることが望ましいと思っている人にとっては、苦しい状況の人達が文学を読んで心を慰められ、おとなしくなってくれるなら、そのほうが好ましいでしょう。だから、辛い人の心の慰めになるようにと思って書いている作品が、実は社会体制自体の固定を裏側からバックアップしていることにもなりかねない、という矛盾があります。不幸だと思ったらその不幸を認識して行動に駆り立てなくてはいけないんじゃないか、不幸を「機因化」してはいけないのではないか。
だけど、本当にそこまで言っていいのかどうか、とも思うんです。やはり辛い気持ちをやり過ごして自分を維持することも必要だし、年齢によっても異なるでしょう。若い人はそこから行動に向かわなくてはいけないのかもしれないけれど、人生のある段階に至ったらそうとも言えないのではないか……否、辛かったんだという認識をして初めて政治的な行動が起きるかもしれないのに、辛いながらもささやかな幸福があったと思うと、結局何も政治的なアクションに繋がらないんじゃないか……そういう堂々巡りですね。
それはまさに、「文学は何の役に立つのか?」という一つの大きな問題です。文学を読むよりも政治行動に人々を直結させた方が社会は変わっていくんじゃないか、グレタさんと一緒に地球環境問題に参加する方が重要じゃないか、という発想もあると思います。そういう中で僕は、文学の意味が今どうなっているのかということを、新作「本心」を通じて考えようとしています。
非常に雑駁な話でしたが、僕の話はこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。
(ひらの・けいいちろう/小説家)
【注記】
本稿は、二〇一九年一一月二三日(土)、二四日(日)に明治大学、共立女子大学、二松学舎大学を会場として開催された日本近代文学会・昭和文学会・社会文学会合同国際研究集会「文学のサバイバル——ネオリベラリズム以後の文学研究」の基調講演(一一月二三日、明治大学駿河台キャンパス)をまとめたものです。音声記録の文字起こしは真文館の石井真理氏が担当し、講演者である平野啓一郎氏による加筆修正を行っています。
『日本近代文学』編集委員会
平野啓一郎の最新エッセイ集『文学は何の役に立つのか?』(7月16日発売)
Amazonでの予約受付はこちらから