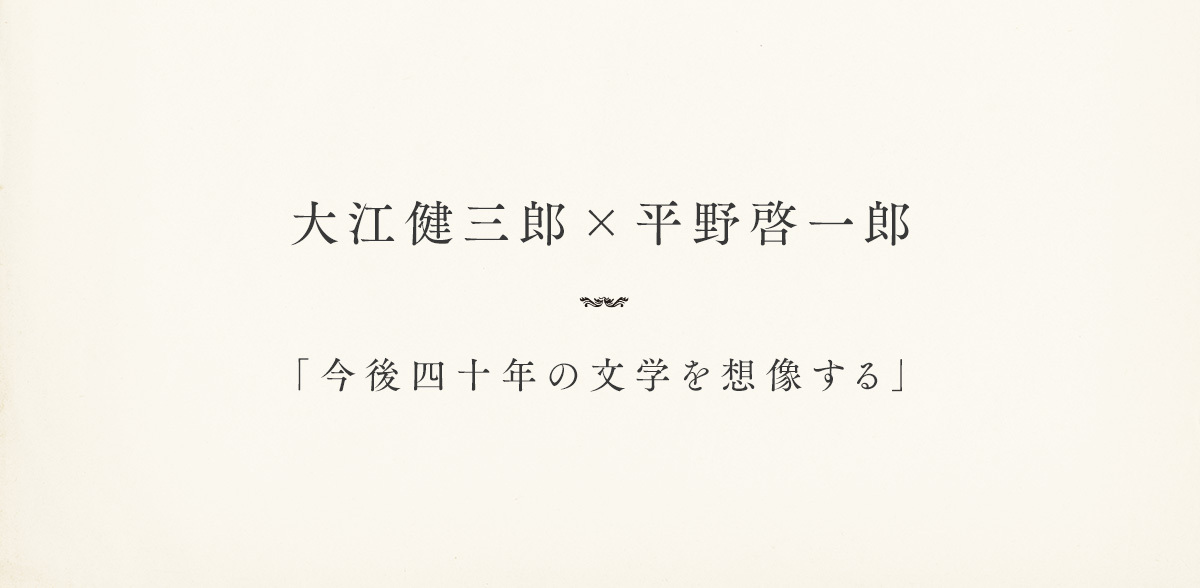最新エッセイ集『文学は何の役に立つのか?』刊行を記念して、2007年刊行の『ディアローグ』(講談社)収録エッセイを公開します。『ディアローグ』は電子書籍をこちらよりご購入いただけます。
大江健三郎×平野啓一郎
──「今後四十年の文学を想像する」
【「他者」の導入とナラティヴの問題】
大江 あなたの小説とはまた別に、今度あなたの音楽や建築の分野の本を読んで、新鮮なおもしろさでした。『TALKIN'ジャズ×文学』が興味に満ちている。『X‐Knowledge HOME』の編集にも引き込まれました。
平野 ジャズについては、マイルス・デイビスが自叙伝を書いていて、その自叙伝というのが抜群におもしろくて、もともとは僕もその辺から単に聴くという以上の関心が出てきたんです。彼自身が、ジャズがロックのビートなんかを取り入れて発展してゆく流れをずっと牽引してましたから。
これは小説の話にもちょっと絡んでくるんですが、僕がジャズを聴いていておもしろいなと思うのは、たとえばマイルスなんかは、死ぬまでに何度も音楽が変わっていくんですけど、どうやって音楽を変えていくかというと、結局メンバーを変えていくんですね。一緒に演奏している人たちをどんどん若くしていく。彼は四十歳ぐらいのころから、本当に名もない十代、二十代のミュージシャンとばかり演奏するようになる。彼らはそれぞれに全く違う音楽的な背景を持っていて、最初に何日間か、彼の自宅でリハーサルをして、一緒に演奏旅行に行くと、今の若い人たちがどういう音楽をどんなふうに理解しているのかが大体分かってくる。そういう中で、自分自身もそれに反応して新しい音楽のアイデアを模索していくんですね。もちろん、彼のディレクションは強力だったと思いますけど。こうした創作の方法は小説家がどうしてもできないことで、僕はいつもそのことを考えるんです。
いきなり本質的な話になってしまったんですが、小説家というのは本当の意味で「他者」というのを書けるんだろうかと僕はずっと考えてきました。ジャズの場合は、そういうふうにある人を連れてきて、一緒に一つの音楽を創造しようとする中で、幾ら共通言語としての楽典があると言っても、自分が絶対に考えつかないフレーズを相手が演奏することはあるわけで、それに対する反応によって自分を更新してゆくことも期待できる。そのコミュニケーションの過程そのものが作品化されるわけです。ところが、小説の場合、作品内の登場人物というのは、一人称的な視点で書こうと、いわゆる「神の視点」で書こうと、結局は一人の小説家が創造する他者なわけで、いずれにせよ、完全な他者にはなり切れていないのではないかと思うんです。
最近、古井由吉さんに中原昌也さんがインタビューされている中で、「(古井さんが)作中内の会話を括弧で括るのをやめた理由はなんですか?」という質問に、古井さんが「カギ括弧に入れて喋らせるほど、その人物が僕にとって他者になりきってない」と答えられてて、面白いなと思ったんです。大江さんも、カギ括弧で発言を括られませんけど。もちろん、言葉というものはそもそも他者的なものだし、僕は「己の血肉と化した唯一無二の文体」というようなものを信じない方だから、ある単語でもいいですし、言い回しでも口調でもいいんですが、出来るだけ自分とは疎遠な表現を小説の中に取り入れることで、言葉の方が僕を引っ張っていって、自然と他者を作品中に存在させてくれるかもしれないと信じてはみるんですが、その一方では、バフーチンなんかが言ってるような他者というのは、本当に小説の中に存在しうるんだろうかと、やっぱり懐疑的でもあるんです。どこまでいっても、自己の鏡像のヴァリエイションとしての他者しか描き得ないんじゃないかと。そうしたときに、ジャズ・ミュージシャンが音楽を変えたいと思ったときに、新しいメンバーを集めてきてやるというのは、ある意味でうらやましいなと感じてたんです。
大江 僕も若いころはジャズをよく聞いていた。息子の光が、それまでも嫌だったんでしょうが、抗議する態度を示すようになって、家でジャズのレコードを聞かなくなった。それが六〇年代の初めです。CDの時代になって、自分の部屋に小さい再生装置を置いて、それも古典というか、デューク・エリントンとチャーリー・パーカーの、それもごく古いものがCD化されたのを沢山聞きました。そして近頃、後期のジョン・コルトレーンを聞くくらいです。あなたのジャズの受容の時代とまったくズレています。
それでも、小川隆夫氏とあなたの対談でジャズクラブでの演奏家たちのまじめな話し合いの雰囲気のなかに、僕が聞いていたギル・エヴァンスやビル・エヴァンスが出て来る、懐かしい。チャーリー・パーカーのような人に新しい大切な人と思われていたマイルス・デイビスが、今度は老人として新しい人たちを集めて、おもしろい音楽をつくっていくという、高度の音楽的な転換が実際に行われた時代がよくわかる本でした。
文学においても、あなたがいわれる、本当に他者らしい他者を文学シーンに導入して、新しい文学をつくっていくという雰囲気がいまあるか、あるいは個人の内部においてそれができるかということですね。一緒に文学をつくる、ということでは、別のプレーヤーを連れてこなくても、新しい文学的な刺激を古典からも、同時代の外国文学からも取り入れることはできるわけですから、不可能ではないと思いますが。そこで自分はどうしているかということも、話したいわけなんです。
ジャズにおける奏法の転換が意識的に行われる。それも他者の導入によって行われる。それが作家にとって可能かという話なのですが、それを僕はナラティヴの問題ではないかと思う。
平野 そうですね。
大江 新しいナラティヴを僕たちはつくっていく、語り方にはいろんな語り方があるわけですが、結局どんなナラティヴをつくり出しても、それは一人の作家のナラティヴにすぎないのではないか。それ自体は他者の導入にはならないのではないか、というのがあなたの問題点なのでしょう。
そのことを僕も考えた。小説を書き続ける過程で、ナラティヴにしだいに意識的にならざるをえない。しかもナラティヴに意識的であることが、語り手とか人物とかに、自分とは違った他者を導入できるかという問題として、突き詰めていくことになる。書くべき人物と語り方ですね。その点、他者をどのように導入するかということを最初から考えていたのはあなたではないか、と思います。
あなたのナラティヴの、どのように物語を語っていくか、登場人物にどう語らせていくかということを、とても早く明瞭に解説している人は、四方田犬彦さんです。この四方田という批評家、あるいは表現者はあなたにとってとくに重要だと思います。今度あなたの編集した 『X-Knowledge HOME』 でも、四方田さんがおもしろい寄稿をしておられますが、まず、最初の頃の批評のことを話したいんです。
彼はどういっているか。『日蝕』という小説を、作者は今までにすでにあった物語の構造、人物、小説の場所を使って書いている、こういうものはもうあったじゃないかという批判があるということから始めている。彼はいう、「だが、こうした物語構造がいかに既存のものに多くを負っているからといって、それだけで作者を非難することは慎もうではないか」、それは当然のことです。今までに語られてこなかった物語、今までになかった語り方というものはありません。これまでにすべてが語られてきた、すべての物語が提出されたということから出発して、二十一世紀文学を、僕らはやっているわけです。
「というのもすでに物語のなかで主人公がみせる探求こそが、先行せる探求の反復である、それを意識的にこの作家はとらえている。そういって、「日蝕』に入っていくんです。 「蠟燭を片手に洞窟の真奥へと足を運ぶ錬金術師の探求を肩越しに眺めることでなされたものであるからであって、この肩越しという姿勢において、主人公と作者は重なりあっている」と彼は続けます。
僕は、この「肩越し」という言葉が非常にいいと思う。四方田さん独自の小説論のしっかりした発見、優秀な新発見なんです。作者であるあなたが、この錬金術師が語るように書いていく、その後ろにつき添うようにして、彼が語る物語として書いているんだけれども、錬金術師のすぐ後ろにくっついていて、肩越しに前を見ている、考えもしているという仕方でこれは書かれている。そのように主人公と作者が重なっている、と彼は書く。
それならば、この主人公は作者にとって他者であるかというと、他者ではない。しかし、まずひとりの作家が最初に小説を書くとき、彼がどういう人間であるかということを読者は知らない。むしろ作家自身も知らないわけです。だから、作家は自分自身を書いていいんです。自分自身を書くことが、文学世界に一つ新しい他者を提供することであるわけです。この作家は、しかしある工夫を持って、ヨーロッパ文学にこれまで当然にあった中世末あるいはルネッサンス初期らしい人物設定、場所の設定ということで人物と彼の場所をつくって、その人物と一緒に物語に入っていくという形でこの『日蝕』 書いた、それ自体で作家の独創だというわけです。僕も同意します。
そして『葬送』を読みますと、やはり肩越しに小説が書かれていく手法ではあるわけです。ショパンの肩越しに、ドラクロワの肩越しに。ところが、いうまでもなくショパンとドラクロワは違う。しかも読者はみな、ショパンもドラクロワも知っているわけです。音楽を聞き、絵を見ています。また、この若い作家が『日蝕』を書いた人だとも知っている。作者が人物の肩越しに物語っていくということは難しくなってくる、作者にとって本当にショパンは他人なのか、ドラクロワは他人なのか、ほかの人物たちだって他人なのか。作者がそのナラティヴを書いていきながら、客観的な書き方のナラティヴではあるんだけれども、本当に自分から離れて客観的であるのか、本当に他者を読者に提供しているか、ということに対する不安とか疑いとかはあるだろう。
『日蝕』と『葬送』という二つの作品には、仕事を始めて、これから仕事を続けようとする作家が、自分のナラティヴをどうするか、ナラティヴを書きつける作者と、自分の作中人物との間の肩越しの関係が二様に考え込みつつ書かれている。肩越しでいながら、これらの人物をいかに他者となし得るものかどうかという、集中した考え方がある、二つの大きいモデルとして作者が直面している問題があるわけです。
若い作家が自分の仕事を始めて、最初の作品『日蝕』が成功した。しかも、その成功した作品の書き方、ナラティヴ、人物像のつくり方をすっかり捨ててしまって、自分の作った資産を継承しないで、もっと難しい形で、こういう新しいナラティヴをつくり、新しい人物をつくり、新しい場所をつくり、最初の作品よりもっと客観化したナラティヴでやってみる。その難しい仕事をやろうとした、というのが『葬送』です。
なぜやろうとしたかというと、最初から、意識的な自分の作品あるいは文学に対する見方があってそれをやった。しかも文学に対するあなたの見方の中心にあるのは、作者は一体他人を書くことができるのかということだ。それが最初からあって書いた。しかもなおナラティヴと他者の問題ということが自分にある。すると、第二作は、こうであるほか書きようがない。そして、同じ問題をさらに持ち続けているというのは、現在、次の大きい展開に至ろうとしていることを意味している。それがあなたの作品をまとめて読んで、僕の考えたことです。
【ナラティヴの主格と作者の自分は切り離せるか?】
平野 まず一番最初に考えたのは、非常に基本的な問題ですけれども、やはり主人公の主語の問題だったんです。要するに、一人称体で書くか、三人称体で書くかということですね。それについては、特に『葬送』という小説を書いているときに、フランス語の資料を日本語に翻訳する上で随分と考えたことなんです。これは『私という小説家の作り方』という大江さんのご本の中にも書かれていたことですが、よくいわれるように、日本語の「私」あるいは「僕」というものと、「I」とか「Je」というのは同じかどうかという問題ですね。例えばドラクロワが社交界である女性としゃべっている場面を書こうとする。そうすると、「私は」という口調は余り違和感がないんですね。もちろん、そのとき、フランス語では「Je と言うでしょう。しかし、日記なんかで内省的なことを書いているときの「Je pense」 というような文章を、日本語で「私は」と訳すと、ちょっと違和感がある。
日本語の場合「私」「僕」「オレ」というのは、あらかじめ社会的な対人関係や状況を前提としているわけで、そうすると、自問のときに「私」という、オフィシャルな一人称代名詞を使うと、問いかけに最初から他者の目が挿入されてしまうことになって、内容は必然的に限定されるし、答え方にも衒いの気配が感じられてしまう。逆に「オレは」という一人称で内省できる内容というのもやはり限定的でしょう。「僕は」も同様です。前の二つに比べると一番率直かもしれませんが、ドラクロワのような五十歳を過ぎた芸術家の自問という意味では、あまり似つかわしくない印象です。
そういうふうに考えたときに、フランス語の「Je」を日本の小説で書こうとすると、結局、場面によって「僕は」といったり、「オレは」といったり、「私は」といったり、あるいは「自分は」といったりというのを書き分けなければ不自然な感じがする。そうすると、日本語で登場人物に単一の一人称代名詞を使える状況というのは、どういうものなんだろうということを考えたんです。
『日蝕』の場合、あれは異端僧の弁明の書のような体裁で、究極的には神との対話ですから、「私」というのを固定された形で書き得たと思うんです。『葬送』の方は、三人称体ですから、登場人物がその場面ごとの状況や接する相手によって、「私」や「僕」を使い分ければいい。
しかし、一人称体で、読者という広大な、多種多様な人々に向けて語るというときに、「私」や「僕」といった人称代名詞を統一的に採用するなら、それが前提としている作者と読者との共有空間とはどんなんだろうか。フランス語の「Je」だとか英語の「I」のように、どこに行っても誰に対しても同じというような西洋の小説に見られる主語の人称代名詞のあり方を、そのまま日本語の小説に適用すると、その意味はまったく別の、もっと複雑なものとなってしまう。そうして考えると、私小説作家の多くがそうだったように、三人称体の「彼」の方が、「I」や「Je」に近接してるんじゃないかなということを考えたんです。
僕は、僕なりに大江さんの作品をずっと拝読してきたんですけど、たとえば最近の「長江古義人」を主人公にした三部作でも、一人称体では書かれていないけれども、視点は常に主人公に固定されている。それは三人称というよりも、やっぱり、西洋の小説でいう「I」だとか「Je」だとかを連想させるんです。
大江さんが、たとえば、初期作品によくあったように、「僕」という一人称代名詞を使われるとき、それは、まず語りかける読者の具体像や主人公と読者との関係の具体的なイメージがあって、「僕」という主語が出てきたのか、それとも、大江さんが日本の私小説分析の中で、そこに見られる「私」というのは、一個人の多面的な自我をあらわしているという話をされていたように、「I」や「Je」と同じで、一貫したものであるが故に、他方で多面性を暗示したものとして使われているのか、というようなことを考えていたんです。そうした自分なりの問題意識が、『葬送』を書く動機の一つではありました。
大江 小説の中で人物がほかの人物に向かって、あるいは読み手に向かって発言する際、もちろん主語が必要です。そこでまず「私」か、「僕」か、「おれ」かと決めることが必要です。外国語の小説を訳そうとする時も、外国の人物たちが「Je」とか「Ⅰ」とかといっているところに、いわれたとおり特別に日本語的な、すなわち社会的に条件づけられたというか、それ自身によるというよりは、他者の存在によって決められた自己規定による代名詞を選ぶことになる。人物が「私」というとき、「おれ」というとき、ある程度、人物の位置も人との関係も決まってしまう。そういうことを自分の小説でどうするか、そういう日本語で翻訳することは正しいかどうか。それをまず考えたということですね。僕も本当にそうだと思います。小説をつくる場合も、翻訳する場合にも必要だし、外国の本を自分一人で読んでいく場合にもあてはまります。
それは、小説を書くナラティヴの問題として、日本語で西欧の諸語の達成した近代小説を書くことができるか、という問題にまで発展しうるものです。
まず人物の主格をどのような言葉であらわすか。そこに日本語としての特別な性格があるという認識が必要です。続いて、小説を書く場合に、自分のナラティヴの主語を「I」 とするか、あるいは「彼」とするか、「太郎」なら「太郎」とするかという問題が生じるということです。
そのことは僕にとっても大きい問題でした。 あなたは、四方田犬彦さんがうまくいっているように、人物の肩越しに作者が語るというやり方の巧みな人だ。最初もそうだったし、二十世紀後半の若い日本人ではないことがはっきりしている人物を書きながら、しかも、自分がつくった、仮想された登場人物の肩越しに語っている、肩越しに見てもいる、という小説として、一つの世界をつくり出したわけですから、大きい能力なんですよ。
さらには、最初の作品では一人の人物の肩越しに語っていたのを、今度は二人あるいはそれ以上の人物の肩越しに語ろうとする。ナラティヴの文章自体も、三人称の文章になるわけですね。ドラクロワが出てくる、ショパンが出てくる、あるいは彼らの友人たちが出てくるわけですから。
そこで、文章自体、「私はこうしています」というのではなくて「彼はこうしています」となる。ところがそうすると、とくに日本語では、「私」のナラティヴと違って、三人称のナラティヴを始めると何かよそよそしい客観的なものになってしまうという印象がある。永く僕が苦しんだのは、そのことでした。あなたの場合、ドラクロワの肩越しに語っているときの声と、ショパンの肩越しに語っている声は違うけれども、しかし、両方とも、「ショパン・プラス・作者」あるいは「ドラクロワ・プラス・作者」が語って効果をあげています。
僕の場合は、ずっとそこがうまくいかなかったんです。一人称を脱して、客観的な小説として書くこと自体に、僕は強い違和感を持っていたから。最初から僕は、なにより一人称で書きたかったんです。自分がナラティヴの主体だとして書きたいという気持ちがあって、僕は小説を書き始めたんですから。その点、「私小説」の伝統に抵抗したいといいながら、じつに「私小説」的でした。自分という書き手とナラティヴの主体の「僕」とを強い線で結んで、この作者の僕を裏切るようなことは、僕の小説の語り手にしたり、いったりさせないという、強い一体化を強制するかたちで小説を書いていたわけです。
例えば、最初の三人称で語る長篇『個人的な体験』で、主人公を「鳥」というニックネームで呼んだけれども、この鳥は三人称にもかかわらず、実は僕自身のニックネームなんです。ナラティヴの中で客観化されている主格は、実はナラティヴを書いている作者の主格と重なっている。そうした書き方の長所は、小説の主格が何かいったり、したりするということに、親身なリアリティーを与えることができるということです。 自分が書いた小説を自分で読んで、これは自分の言葉の世界だということを確信できる。それから、読者も「これは大江のナラティヴのリアリティーだが、すなわち大江のリアリティーの世界だ」と受けとめてくれるはずという一種の安心感がある。自分が自分のアイデンティティーをしっかりきざみ込んでつくり上げた世界だと確信して小説を書くことができる。それでずっとやってきたわけです。僕が三人称で書いたとしても、ナラティヴの中の三人称は、実は書き手からいえば一人称と同じだった。
そのやり方がしだいに、年齢によって、もっと小説作りにおいても成熟してきてはいますよ。ナラティヴの中で「私」と書く人物も、今度の「古義人三部作」がそうですが、小説全体から見ると、長江古義人という第三者であって書き手とは違うと設定して、そのとおりに書いているんだけれども、どうしても作者の僕は、自分が書いた長江古義人という人物に影響されていて、長江古義人が他人だとはいえない。長江はみんなから「長江さん」といわれるけれども、彼が「私」というとき、それは大江が「私」といっているのと同じようだ。そこに限界がある。たとえば私はあの三部作で長江古義人を自殺させられないし、他人に殺されることもできない。
そういう書き方によって、僕は自分の小説のリアリティーをつくってきたんです。あなたがドラクロワをつくったり、ショパンをつくったりしたようなことは、僕にはないんです。
これは僕が一生引きずった小説家としての欠陥ですよ。あなたの短い作品で、若い作家が女性の編集者とラブホテルで関係を持つ。橋の上から彼女の下着を捨てたりするという、あの人物が、作者に近い設定にされているけれども、あれを見て、読み手はだれ一人、あなただと思わない。外国語に訳されればはっきりしますが、あの人物を平野啓一郎という作家と同一視する読者はとくに外国の場合いないんです。
日本には、私小説の方法を巧妙に客観小説で使ったものがありますが、これは平野という作者じゃないぞという人物を自然につくり出してしまうところに、あの小説のおもしろさがある。そういうふうにあなたは書いてきた。ナラティヴの主格と自分自身を切り離すことに成功してきた作家なんです。
僕は、ナラティヴの主格と作者の自分とを切り離すことができなくて、いつまでもいつまでも、長江古義人は大江健三郎であるという形で小説を展開するほか、リアリティーを持たせられる自信が自分になかった。文章においても、人物においても、かれらの感じ方においても、あらゆるものにおいて。つまり僕は、トートロジー(同義語反復)的というか、自分のような人物をいつまでもいつまでも押し出して小説を書く技法に縛りつけられて七十一歳まで苦しんでいるわけなんです。
そこが、僕の小説家としての大きい過ちです。しかし、この過ちによる技法の他になかった以上、この過ちなしでは僕という作家もなかったわけで、僕はもう悔まぬことにしていますが。そこで僕の強い関心は、ナラティヴの主格と作者自身を切り離すということに成功してきた平野さんが、これから新しい長篇に進むことになってどうするか、そのことです。
今度は逆に、自分という書き手をナラティヴの主格に限りなく近づけて、今までよりももっと近くから肩越しに語る、左腕で相手の体を抱き締めているような感じに、自分に近づけてしまうか。あるいは、さらにすっかり切り離してしまうか。後者の方法は、もう幾らもモデルはあるでしょう。徹底して新しいドン・キホーテを自分でつくればいいのですから。あるいは、IT時代のジュリアン・ソレルでもつくればいいんですから。
ところが、二十一世紀前半に一人の人間が小説を書く。それに命をかけているときに、それをどのように自分自身から切り離すことができるかということは、なお残りうる問題ですね。同時に、それを切り離したものをつくり出すという冒険のおもしろさもあるわけです。あなたの場合、完全に自分から切り離した人物をつくるとなれば確実にできますよ。『葬送』を例にとればいいですが、自分の書こうとする人物と、その社会、あるいは共同体を作り出す、その方法をあなたはやってきた。
とにかく、徹底して客観的な他人の世界をつくり上げてきたんだから。この仕事は、具体的に文章を書いていく上で一番やりにくい仕事です。それをやった以上は、今度、全く不思議な人物を一人つくり出して、そいつに自由に「私」として語らせるということはできます。それとも、僕などが失敗しつつやってきたように、作者の「私」とナラティヴの「私」とをすっかり結びつけてみるという冒険を、あえてするか、その二つの道があるわけです。
【登場人物と死者──反論できない他者】
平野 今、非常に重要な論点がたくさんあったので、整理してしゃべるのは難しいんですけれども、まず一つは、やっぱり大江さんがおっしゃった作品のリアリティー、迫力ということで、これはまさしくその通りで、僕は自分と同じ年齢の頃に大江さんが書かれた作品を読んでいて、何が自分の書いているものと一番遠いかというと、主人公の言葉が即ち作者の言葉だという、あの圧倒的な迫力だと思うんです。それは、読者にとっても大江作品の大きな魅力だったでしょう。僕は僕なりに、非常に切実な主題について熱心に書いているつもりですが、僕の書き方だとなかなかあの感じは出ない。それをどうにかやろうとしたのが、「最後の変身」(『滴り落ちる時計たちの波紋』所収)という小説なんですが。
僕の場合、三人称体で書こうとしたときに、全く架空の世界ではなくて、ショパンやドラクロワといった、彼らの実際に書いた手紙や日記が残っている、実在の人物をモデルに小説を書くことにしたのは、一つにはやっぱり、小説家として自分が、「私」というナラティヴの形を取らずに、登場人物たちを書けるかどうかということに不安があったからだと思います。実際に、あの小説を書いていると、自分が作者であればこうするだろうというようなことを、彼らの残している日記や手紙がことごとく裏切っていくんですね。こういう出来事があった、この人物だったらこう考えるだろうと思ったことが、三年間くらいかけて書いていながら、その本当に最後の頃になっても簡単に裏切られてしまう。その経験が、未だに小説の登場人物に何か行動させようという時に、何時も僕の頭の中を過ぎりますね。
こういう話の時に未だに出るのが、サルトルがモーリアックを批判した例の「神の視点」という議論ですが、実存主義者のカトリック作家批判という特殊なニュアンスを除いて、小説家が、ともかくも作品世界を完全に等質な空間として眺められるような点に立てるかどうかという意味では、「アルキメデスの点」とでも言った方がいいか れません。そういう視点を作家が採用するかどうか、そもそも採用できるかどうか、という問題ですが。
僕は、小説の書き方としては、大体まず全体を構想して、その時点では確かにアルキメデスの点のような視点から作品世界を眺めていて、それから細部を順を追って書いていくという、まぁ、オーソドクスな書き方なんです。大江さんが、「リリーディング」という話をされるときに、再読したときに構造が見えてくるということをロラン・バルトを引用しつつおっしゃってますが、構造というものは、創作のモティーフとなる、一種の観想的な知なんだと思います。それが一方で律法的に存在していて、その後、順を追って書いてゆくうちに、状況や設定の中で、作家はより実践的な知に傾いて、前者を修正し、時には否定しながら創作の自由を得ていくんだと僕は考えるんです。 大江さんも否定的に言及されていま
すが、三島由紀夫の例の「最後の一文」というのは、後者の実践的な知を拘束するものだと思います。その意味では、タイトルというのも、同じように観想的な知に属するもので、それを最初に決めてしまうことは、最後の一文を決めてしまうこととあまり変わらないと思いますが。
そうしたときに、僕が幾らアルキメデスの点のようなところに立ったつもりになっても、結局は、 という人間が小説を書いているには違いなくて、「Je」だとか 「1 だとか、「私」や「僕」というナラティヴとしての一人称に強く結びつけられなくても、僕が書いているという事実は否定できないわけで、僕はそのことは、読者にもっと当然の前提として受け容れられているんだろうと割と信じていたんです。けれども、実際は、どうもそうでもないらしい。メタフィクションというような実験がさんざんやられた後でも、読者は必ずしも作家性というようなことを自然な形では受け容れないようだということを最近よく感じます。これは、絵や音楽の場合の作者と作品、それに鑑賞者との関係と著しく異なっていますが。
結局のところ、どんなに僕が、登場人物を距離を取って書いてみても、その描写の仕方や人物の扱い方に表れるのは、他者そのものというより、僕の他者観や他者との交わり方みたいなものでしかないでしょう。しかし、その関係性において、僕という小説家のリアリティーというものがにじみ出るのではないのか、僕が作者であるという事実のリアリティーを賭するのはそこなんじゃないかと考えるんです。
だからこそ、他者を描くというのは、例えばその内面的なことであろうと、あるいは表情や仕草といった外見上のことだろうと、それをどういう言葉に置きかえるかというのは、やっぱり暴力的なことで、どんなに神の視点やアルキメデスの点に立ってみたところで、作者である僕の主観性からは免れ得ないと思うんです。
僕は、「心理」と呼ばれるものを細かに書く方で、対人関係の中で、人がどう感じてどう行動したということのロゴスによる追跡は、一種の権力分析だと思うんですが、そういう書き方は、精神分析学的にというより、むしろ視点の問題として割と単純に批判されるんですね。けれども僕は、作者がそうして言葉の暴力性というものを明け透けに示しながら書く方が、ヘンな言い方ですけれども、読者に対して誠実なんじゃないかというようなことをずっと考えてました。
僕が特にこの問題を考えるのは、死者について考えるときなんです。他者の問題は、究極的には不可知であり、かつ、反論できない存在をいかにして書くか、いかにして言葉にするかという意味で、死者において特殊に先鋭化されると思いますし、言葉の暴力性は一番際立つんじゃないでしょうか。これは、僕の文学の大きなテーマなんです。個人的なことなんですが、僕の父は僕が一歳のときに亡くなっていまして、父の記憶というのは一切ないんです。それで、子供のときから、父親というのはどういう人だったんだろうということをずっと考えてきました。 「死者の声を聴く」とか「死者との対話」ということは、どんなに哲学的な重みをもって説かれても、どこか、どうしようもないほど通俗的な感じがしますが、個人的にはそれをやってきたつもりなんです。それは、主に母や姉といった実際に父を知る人が語る言葉から自分なりに想像した父との対話だったと思いますが、いつもどこかで空しい感じというか、結局はそれは実際に生きて存在していた父本人とは関係のない別の何かについての思索なんじゃないかということをずっと感じていました。逆の立場で考えると分かりやすい話ですが、俺が死んだ後、俺について語る人はいるだろうけれど、それについて俺自身はもちろん反論できないし、どんなに俺自身からは遠いようでも、語られた言葉は、たちまち俺を同一化してしまう。生きている今でも、どこかで昔の知人なんかが、アイツはこんなヤツだったと言うのを聞いたり読んだりすると、何とも言えない居心地の悪さを感じますし、イヤ、そうじゃないと言いたくなることもある。家族のような近親者が死者について語る際の「愛情」の問題についてはまた別に考えたいですが、彼らの言葉でさえ、取りこぼしは当然たくさんありますし、悲しいことですが、その言葉の暴力性は否定できないでしょう。しかし、にもかかわらず、 る。僕が拘りたいのは、そこですね。小説の登場人物というのは、そもそも作者に対して反論できませんし、その意味では、死者と近いような存在かもしれない。『葬送』で試みたように、死者をどう語るかというのは、僕が他者という存在をどう語り得るかということの根本にあるんです。
そして、僕という人間がどんな人間か、ということも、結局は他者との関係性を通じてしか本当には現れ得ないんだと思うんです。自分自身が他者に対する一種の暴力を免れ得なくて、他者による暴力からも逃れられない。そういう状況を拒絶した、引きこもりのような状況でだけ、「本当の自分」が出現するという実感も分かりますけど、それは架空の存在でしかないんでしょう。そうして他者との関係の中にあるときにだけ、初めて自分という存在がリアリティーを持つ。だから、小説に関しても、たとえ三人称で書いていようと、登場人物の描き方、その関係のあり方に、結局は作家は出現するんだろうと思うんです。
大江 小説を書くことの根本の問題は、やはりいつまでもその他者との関係という問題ですね。面白いことに、僕はいままでいったとおり、いつもいつも「私」ということを書きながら、それでいて、他人との関係性のなかで僕は「私」に重要性を与えられない、ということをやはりずっと自覚してきました。
といいますのは、小説を書き始めたころは、まず戦争中に子供で山奥にいて、ひどい目に遭った自分、戦後は占領中の国で青年に育って行き、田舎から来た学生として東京で生活して、社会から虐げられている人間としての自分を感じている。そのことを書いてやろうと思ったんです。そこで「私はこのように生きてきました」「私はいまこのように生きている」と私小説的に書くのではないけれども、とにかくこの社会で今、現に生きている自分を表に押し出していこうとする表現として、小説があったわけです。そのようにして小説を書いている間、まだ僕はでき上がった大人ではなかったから、子供がそういうふうに主張しているということの、若者が主張しているなということのおもしろみ、リアリティーはあったろうと思います。そういうことで青年期の終わりまで、小説を書いてきた。
ところが、さらに年をとり、壮年になってきますと、そのように小説を書いている自分に関心がなくなってくる。さらに今は、これから死んでいく自分というものに対しても、親身な関心はなくなってくるようなんです。そのかわり、他者を受け入れたり、話し合いをしたりする者として、すなわち文章でほかの人をとらえてみたり、表現してみたりすることのできる役割としての自分を感じている、なおも私を押し出す小説を書きながら。
今僕はまさに後期の作品を書こうとして、「私が」という主格を使ってみたり、三人称だけでも、実は「私」と置きかえることのできるような主格のナラティヴで書いたりして、数ヵ月、試行錯誤してるんですが、僕が書こうとしているのは究極の対象は自分じゃないと気がつく。そうじゃなくて、そこに書く自分との関係のなかの、何人かの他人が大切なんです。しかもその他人のモデルというべき者は、死んだ人間がほとんどです。 先生のこととか、長年の憎悪も愛もこもごもにあった友人とか……。
例えばそのように草稿として書いている友人を見てみます。その大切な友人も、生きている間は自分の外側にある存在として、決して自分が到達できない他者性を持っていたんです。僕が知らないうちに、こちらが目をそむけている間にどんな行動を起こすかわからないですから、その友人はね。他者、本当の他者なんです。自分から別のところにいる他者として生きていた存在なんです。そして、その友人が死んでしまう。さっき死んだ人間こそ他人である、他者であるという言い方を平野さんがされましたね。一つのモデルとして、死 父親という問題を考えてみながら。それは僕にも理解できます。
ところが、僕のように、これだけ年とってから友人に死なれる場合は、文章を書くことによって次第次第に、その死んだ友人を自分の中に取り込んでしまうんです。あるいは、自分がその死んだ友人という他人の中に入り込んでいくんです。そして、むしろその死者と自分との関係があいまいなものになってくる。非常に主観的な関係に、相手を取り込んでしまう感じ。その点で、暴力的といえば、死んだ友人のことを書くことぐらい暴力的なことはないんです。しかしそれをやってしまっている。
しかも、それを書きながら、長年小説を書いてきた人間として、僕は個人として客観性の豊かな人間ではないけれども、文章を書くことにおいて、あるいは文章を書き直すことにおいて、文学的客観性とでもいっていいものは技術のように持っている。それを文学を実践するうちにつくり出してきた。つまり文章を書くこと自体の力によって、死んだ他人に客観性を与えることができるという気持ちもあるわけなんです。
どうもその点に、恐しさとして自覚される要素がある。ものを書くということで、他者の中に入り込むという点で、手が死んでいると、入り込みやすい。 死者は、こちらに入り込まれやすい。また、生きている人間というものを書くときには、相手は他者であって「おれはおまえの書くような人間じゃない」とこちらを拒むこともできますしね、それが死んだ人間を書いている時にはない。そういうことで、自分が死んだ他者をちゃんと書いていると安心はできないから、僕がやっていることは、死んだ人間と自分との間の会話をできるだけ克明に思い出すこと、あるいは、もう一回、そういう人間として相手のキャラクターを考えながら、対話としてつくり上げていくことです。とくに相手のこちらに対する批判こそを含み込んでね。そういうことで客観性を与えるようにはしているんですが……。
とにかく、ものを書くということは、どんなに理屈をつけても「私」が書いていることです。サルトルが客観的な視点による小説を神の視点などといって批判しましたが、あれは小説の技法、小説の本質を考える上で、サルトルらしくないといっていいか、あまりにサルトルらしいというか、まだ若いサルトルの単純な理論なんです。驚くほど単純な議論です。
そこを、神という言葉を使うものだから、モーリアックがいらい たんだと思います。モーリアックとサルトルを比べれば、やはりサルトルは問題にならない複雑さの人間がモーリアックですのにね。大体、モーリアックには神があるんですから。神という存在と、あれだけ複雑な人間が、何とか折り合いをつけて暮らしてきたんです、小説さえ書いたりしながら。サルトルには神がいないんですから、世界は存在と無だけですから、サルトルの生き方は易しいんです。死ぬ直前まで苦しいアンガージュマンを続けましたけれども。モーリアックとサルトルが同じ場面で議論することは本当はできないんだけれども、サルトルはそれを知っていながら単純化してやってみせた、ということでしょう。
他人の見方、他人を見る関係として「私」にあるのは、あなたがアルキメデスの点ということを出されたけれども、私の言葉でいえば、一つは、遠近法的に見るということなんです。私はここにいて、他人たちをある距離を持って眺めるわけですから、そのときにあらわれる他人は、はっきり世界に位置を得ている他人ですね。遠近法といってもじつは、架空の視点ですよ。鳥瞰図的というのは、これもまた架空の視点です。しかし、鳥瞰図というのは、その見方をしている者が自由に動き回る、それこそ鳥か天使のように、翼を持った人間としてあらゆる場所を眺めることのできる視点です。
鳥瞰図には、遠近法は採用されていないと僕は考えます。鳥はとにかく上から見ているというだけ。それと鳥瞰図的に見ていて、ズームレンズを使うように勝手に近づいていくやり方があります。小説家はしばしばクローズアップ的にやるんです。鳥瞰図からすぐさまクローズアップになるんですから、世界のとらえ方が客観的であるかというと、それはあり得ないことです。非常に主観的です。自分と他人との関係ということを高みから見たり、一挙に近くから見たり、ズームレンズ的に、僕たちはそれをやる。
小説家は、他人との関係をズームレンズのメカニズムによっていて、近くしたり遠くしたりできる。まさに僕たちは暴力的といっていい関係に立って他人を書いているんです。日本にずっとある私小説の写生という技法によって書いているから客観的な小説だと主張する作家は、芸術院に行けばゴロゴロ居るでしょうが、実は遠近法というものほど主観的な技法はありません。あらゆる他人に線を引いて、それが自分のところに全部集まるように書 遠近法こそ主観的です。鳥瞰図というのは、ますます主観的。しかもズームレンズの目を持った鳥なんです。
そうすると、文学には主観からすっかり切り離した書き方とい ものはない。それを認めた上で、自分と自分自身あるいは自分と他人、自分と世界との関係を書くものであって、その関係の書き方にいろんな技術を総投入して、客観性の幻想をリアルに成立させることが小説を書くことだと僕は考えています。
【表現とは、自由の源泉に触れるもの】
平野 今のお話でおもしろかったのは、僕は『葬送』を書いて、ドラクロワという画家のことを色々関心をもって調べてたんですけど、彼がやった絵画の改革の一つが背景の処理の仕方なんですね。新古典派の画家なんかが、まさしく今のお話で言うと、きまじめな鳥瞰的な視点であらゆる細部をくっきりと鮮明に描いていくのに対して、ロマン派の画家たちは、主要な登場人物をバンと描いて、その他の人物は大雑把に描いておいてそれで良しとする。そういうことで、彼はアカデミックな画家たちからメチャクチャに批判されるわけですが。
ただ、作者の視点として、そういうふうに自分が関心を持っている人物がメインに描かれていて、端の方の人物は雑に描かれても、鑑賞者は、その関心の距離感を前提としつつ、必ずしもそれに従わなくて、作者があまり重視しなかった隅っこの方の人物と個人的に深い関係を結ぶことが出来るんですね。これは小説にも言えることで、作者と登場人物との関係の距離感は、必ずしも読者と登場人物との関係の距離感を拘束しないと思うんです。
大江 『葬送』を読んで、僕が感心したことの一つに、これはドラクロワ以後の画家たちを描く、あるいはショパン以後の音楽家たちに方向を見定めて、かれらを生み出す社会を書く、ロマンチシズムの時代の誕生をとらえているけれども、一方でアカデミズムの人物たちがうまく書けていることです。いかにもドラクロワを弾圧するような何人もが見られますが、じつは僕はロマンチシズムの世界を経験した後だから自分の目が作り変えられていることを認めますが、それでいて、僕がルーブルに行って、しばしば長い時間を過ごすのはアカデミズムの絵の前においてです。
ドラクロワがあらわれる直前の画家たちは、あなたはドラクロワが本当に天才的にデッサンがうまい人だと書いていて、僕はそれに賛成ですが、 アカデミズムの人たちこそ天才的にデッサンのうまい人たちだらけですね。
平野 アングルなんかそうですね。
大江 確実にそうしたものとしての絵を描く。そしてドラクロワが出てきたために、僕たちはアカデミズムの絵を自由に見る力を与えられたと思います。
平野 そうですね。
大江 ゴヤという画家が出てこなければ、スペイン、フランスのアカデミズムの絵を僕らは、かつて宮廷の人間が見たように視点も決められて、かしこまって見ていたに違いない。その絵を見ることによって自分が束縛されるような見方をしたに違いない。
ところが、一旦ゴヤがあらわれ、ドラクロワの仕事がありということになると、もう僕らはどんなアカデミズムの絵を見ても、それらの人たちが驚異的にうまいということもあって、自由に自分の見方でその絵を見ることができ始める。かれらの権力から解放されて、見るべからざるものさえ見出して楽しみます。それは美術史のおもしろい点であるだけじゃなく、表現の歴史というものはそういうもので、ラスコーの洞窟からピカソに至り、現在に至るまで、人間の主観性と客観性、あるいは実在と実在しないもの、人間の精神の動き、目の動き、心の動きというものの自由の源泉に、同時代的に触れることができる。そういうものだと思うんです。時々、僕にしてはめずらしく二十一世紀にかけて生まれてよかったと思います。
僕は人間あるいは人類としてはどうしても一度、完全にアカデミズム的な、これが世界を見、世界を描く一番ちゃんとした、一番技術を使ったものなんだというものを完成しようとし、それに成功したんだと思います。建築だってそうです。これこそが建築だというものを完成した。そして、それに対して、今新しいものをつくろうとする。でき上がった形に対して、これからつくろうとする自分との関係は千変万化であって、アカデミズムの時代もロマンチシズムの時代も現代のような時代も、どうも表現とい ものは主観的なもの、自分というものと他人との間の関係というものをどのように打ち立て、更新し、また再建し、破壊するかということにこそすべてがあると僕は考えています。文学も、もちろんそうです。
平野 そうですね。パリにいたときに、ピカソ美術館が「ピカソとアングル展」というちょっと意表を突くようなタイトルの展覧会をやっていたんです。アングルというのは、これまでの美術史の評価の中では、アカデミズムのラストエンペラーみたいな感じで、ドラクロワの登場によって、彼の特徴であった色彩表現の追求が印象派を経てフォーヴィズムあたりまで息の長い影響を与える一方で、取り残されてしまった古い画家だと考えられていましたけど、「ピカソとアングル展」では、ピカソがアングルのデッサンからどのような影響を受けていたか、ということを実証的に示して、アングルの例のオダリスクに見られるような、異常に背中の長いような女の描き方なんかは、実はピカソのような画家がモデルの身体を極端に歪曲して描いたりすることの先駆けだった ゃないかという視点による企画展だったんです。
それは要するに、アングルという人は、アカデミックな手法で、厳格に主観を排して、モデルとの個人的な関係とは別のところで絵を描いていたはずなのに、そこに、うっかりというか、そういうモダニズムの画家が持っていた対象との自由な関係のあり方を予告してしまっていたという話なんだと思うんです。そうした見方は、アカデミズムというものが自明のものとして受け入れられていて、一つの定まった見方しかなかった時代にはもちろん、不可能でしたし、今おっしゃったようなこととも重なるんじゃないかと思いますね。
【無信仰と風のそよぎとしての哀れみ】
大江 『葬送』のエピグラフに、ボードレールから引用しての一節がありますね。「堕落とは何か。仮にそれが 一元が二元になったことだとするならば、堕落したのは、神だということになる。言いかえれば、創造とは神の堕落ではあるまいか」という言葉をエピグラフとして引いていられますが、この引用は、『葬送』 書こうとしての、神という課題に対するあなたの答えですか。
平野 一つは、僕は二元というのを二元論というよりも多元論の最小単位だと考えていたんです。 元論対二元論というよりは一元論対多元論の最初の第一歩が二元論だろうと。それは、大革命以後の共和制を巡る当時の政治状況にも如実に表れていますが。『葬送』の中で描きたかったのは、さまざまな人物たちが、小説の中にも書いているんですけれども、本人たちは極めてマジメに生きているのに、結局は言葉を使ってコミュニケーションを取るがゆえに、いつもその関係に齟齬が生じてしまう。あるいは、自分自身とさえもすれ違ってしまう。世界の根本的な条件である多数性というものの不具合というか、不都合というか、それが一つの大きなテーマだったんです。完全に統一された絶対的な一者の世界であれば、そういうことは起こり得なかった。要するに、その困難が近代なんだというのが僕の一つの認識で、それをボードレールのあの言葉は非常に端的にあらわしているんじゃないかと思っていたんです。特に十九世紀という、神というものの存在がいよいよ実質的に人々 心の中から消えていこうとしていた時代ですから、あの言葉にはインパクトを感じました。
大江 僕はキリスト教徒になることはないと、いわば本能のようにして知っています。その本能のようなものを打ち壊すものがあらわれてきたらいたし方ないですが、とにかくキリスト教を尊敬しますが、自分からキリスト教に歩み寄ることはないし、僕と同じ仕方で、歩み寄ることはできないという考え方の人たちが好きなのでもあります。
しかし、ヨーロッパの文学をずっと読んできて、唯一つであること、ワンネスというかな、ワンであることがキリスト教の神であって、ワンネスということを「一つ」という言葉に翻訳すること自体が反キリスト教的である、と感じることがあります。
平野 なるほど、確かにそうですね。
大江 一つであるということは……。
平野 カウンタブルということですね。
大江 二つのもの、それよりほかのものがありえるということです。世界ということを考えた瞬間に非常に大きいもの一つがあって、目をちらっと、それより別の方向に向けた瞬間、僕らは根本的にこの宗教とは違うところに行く、そうしたものが、キリスト教の一つの神の世界だろうと僕は感じています。そして、二元的なものを考えるときに、完全な神の唯一性に対する考え方が揺らぐということは少しわかるような気がする。
そこで「神が世界を創造したということ自体において神は堕落したんじゃないか」という、ボードレールの深く強い考え方を扉に印刷した『葬送』という小説、そしてあなたという作家を考えます。ところが一方に、世界を創造したけれども、神は堕落していない、とボードレールに端的に反論する人が、シモーヌ・ヴェイユだと僕は考えています。シモーヌ・ヴェイユの大学教師資格試験のときの同じクラスにいた人で、シモーヌ・ペトルマンという女性が、二元論とキリスト教の最初のころ、グノーシスのころのそれとの相関を論文にした。それを僕らは知っていますが、このペトルマンは、ヴェイユの手紙や聞き書をうまく使った、大きい評伝を書いた人です。
さて、シモーヌ・ヴェイユはどのように神という唯一者とその創造した世界との関係を独自に考えていたのか。神様がまず最初に世界をつくったことは認める。しかし世界をつくった瞬間に、ロケットか何かで打ち上げるように、無限に速無限に遠く自分自身を打ち上げてしまった。神はこの世界からずっと遠いところにある。そして、我々、創造された者はこの世界にいて、苦痛を感じたり、不幸を感じたりするということがある。しかし、それは神とは無関係に、自分らの世界固有の必然性のメカニズムによってそうあるんだ。 もし神が私たちの不幸や苦痛、幸福についても、それと関係があるんだったら、神は創造した後、しかるべく身を引いたとする自分たちの信仰は成立しない、という。もし神が我々と一緒にいるんだったら、我々が神と一緒にいるということは、神の唯一性の中にいるわけですから、私たちは存在しない、という。
神はこの世界からはるかに遠いところに存在していて、そして我々は神がいないところにこの世界をつくっている。我々の世界が堕落しているとして、それは神が堕落したということではない、というのがシモーヌ・ヴェイユの考え方だと思うんですが、僕は、宗教についてこの考え方が好きです。
自分としては、死ぬまで、その遠い彼方の神様の方を見ないで、神様と無関係な、切り離された世界で生きて、文学をつくろう。死んだ後は、自分の作品について責任を感じない。僕はもう存在しないんだからというのが、僕の考え方なんです。
平野 シモーヌ・ヴェイユもボードレールも共通しているのは、彼らにはある種の新プラトン主義的な発想があって、キリストが不在なんですね。 大江さんの今のお話も、創造の後、神が永遠に遠ざかってしまったというのは、ハンス・ヨナスの分類によるなら、マニ教的というよりシリア・アレキサンドリア的なグノーシス主義の発想に近い印象を受けます。その「造られっぱなし」の世界にとどまり続けるというのは、グノーシスとは大きな違いで、非常に重要だと思いますけど。
僕は、ボードレールのあの「聖ペテロの否認」というのは、キリストの磔刑を描いた詩の中でも一番美しいものの一つだと思うんです。キリスト教の決定的な独創性は、キリストが人性と神性とを兼ね備えているという発想ですけど、あそこでも、キリストというのは神の子としては描かれていなくて、一人の男であるナザレのイエスという書き方をされている。それで、あんなヤツは知らないと言ったペテロに対して、ボードレールはよくぞ言ったというわけですが、結局キリスト教というのは、創造の後、神が永遠に遠ざかってしまったわけじゃないというのをキリストの存在を結び目として信じようとしていた宗教で、そのための初期のラテン教父たちの努力は非常にたくましいものでしたから、これは決定的な認識の変化だと思うんです。
僕はキリスト教が自殺を禁止している理由について考えるんですが、これは一つには、それまで多数的なものだった供犠というのをキリストの磔刑という歴史的一回的な事実のうちに回収してしまったからだと思うんです。贖罪のための供儀は、生け贄との一体化を通じての象徴的な自殺ですから。信者はワインを飲んで、パンを食べて、キリストの肉体と物質性を通じて同一化するわけですから、自分を苦しめる罪の意識から自己処罰を通じて解放される必要がなく、代わりに未来永劫にわたってキリストがそれを引き受けてくれたことになっている。逆に言うと、自分で苦しむ権利は、彼に奪われてしまっている。
その意味では、自殺を禁止するというのは、ナザレのイエスの唯一性、その絶対的な神聖さを侵害される恐れによるものだったと思うんです。 十九世紀になって、ボードレールみたいに、キリストの磔刑に全人類の原罪を贖う意味を認めない人が出てくると、ロマン派の画家や詩人なんかを中心に、贖罪の私有化が一気に広まってくる。芸術家たちは、私的に創造した自殺や殺人の場面を通じて、苦悩する権利を取り戻し始めるわけで、これは先ほどお話ししたような一元論から多元論へという大きな流れの中での出来事の一つだったと思うんです。特に近代の功利主義的な世界の中で、最も崇高な行為とは、その対極にある他者への献身であり、そのいわば究極の姿が他者のために死ぬということでしたから。この崇高さは、もともとはキリストひとりが独占的に担っていたものですね。
結局、ボードレールなんかにしても、自ら死刑囚にして死刑執行人なんだと言って、自分の苦悩する権利をナザレのイエスには絶対に移譲しない。詩の世界で、自己処罰として完結してしまうわけです。それはアイロニカルな自己崇高化とも言えるでしょう。そうしたとき、文学の作品の中での登場人物の死というのは、やっぱり、一種の贖罪として社会の中で機能していったんだということを、僕はずっと考えていたんです。
『ボヴァリー夫人』みたいに、作者があれは私だといっているような主人公が最後には死んでしまう。あるいはトーマス・マンの『ヴェニスに死す』でもそうですし、『ウェルテル』もそうでしょう。大江さんの作品の中にも、そうした形で象徴的に死んでいく登場人物たちがしばしば見受けられて、たとえば、『「雨の木」を聴く女たち』の中にも強姦事件を起こした少年の身がわりに死んでしまう高校教師がいますが、僕の関心から言えば、あのエピソードは、今のような主題の系譜に連なるように見えます。特に受難というのは、大江文学の非常に大切な主題の一つですから。贖罪というのは論理的な必然や義務関係があって誰かが身代わりに死ぬというのではなくて、そもそもの罪とは何か全く無関係なところで引き受けられる、不思議といえば不思議な死なんではないでしょうか。文学作品が十九世紀以降、繰り返し、殺人や自殺、あるいは死そのものを描いてきたことには、キリストの磔刑の唯一性を掘崩すようなところがあった気がします。
大江 僕はシモーヌ・ヴェイユにイエス・キリストはいると考えています。シモーヌ・ヴェイユは、我々の世界と神が遠い距離をへだてているということをまず確認する。そして、遠くにいる神に向かってお願いしたり、呼びかけたりすることはできない。こちらはこちらのつくられた世界の必然性の中で生きるほかはない。
ところが、向こうから、一番高いところからこちらに向けて一方的に哀れみの感情、哀れみというか慈悲というかグラースというか、そういう感情を持つ存在として神があるということは、シモーヌ・ヴェイユも否定しない。つくられた存在として必然性の中で生きている世界の我々と、それから無関係な神と結ぶ関係はないんだ、結ぶ関係があるとしたらば、一方的な関係であって、こちらから何かすることはできないけれども、イエス・キリストが、ある哀れみを我々に仲介してくださるということはあるかもしれない、それがシモーヌ・ヴェイユの考え方だと思っています。
僕はキリスト教の方たちとあまりお話をしたことがないのですが、渡辺一夫さんが、お友達のハーバート・ノーマンと、パウロが好きかペテロが好きかと話して、パウロが好きだと一致した、といわれて、じつは僕はペテロが好きだ、「おれは神の子を知らない」と否定しても、そのペテロに対して哀れみを抱く存在はあり得るというのがキリスト教の魅力だと思いつつ、信仰を持たない人間として生きてきました。
それでいて、確かに一つだけ考えていることは、大きい、高い世界に、どうも我々を創造したものがある。そして、我々はそれと無関係に自分たちの必然性の中で生きていく。この社会にあって、人間としての責任をとりたい。しかし、ある種、風のそよぎのようなくらいには、どうも自分たちを哀れんでいるなにものかの気配を感じることが、年をとるにしたがってあるようになった、というのが今の僕の状態です。
【将来の文学表現のあり方とその受けとめ】
大江 さて、僕たちは「群像」創刊六十周年記念を祝って話しています。僕の日本文学史観は、明治維新から自分に関わりのあるものが始まった、それは近代から始まったというものです。その明治維新によって始まった文学が、明治の初期の文学はちょっとまた別のものかもしれませんが、とにかく一九四五年まで来て、敗戦によって一つの分かれ目に来たと僕は考えています。 そして四五年から新しい文学の世界が始まった。それで、小説を書く人間としても、戦後の改革を重要に考えるという立場を保ってきました。
そして、この新しい文学の時である敗戦後の六十年がたったわけです。六十年、それを五十年プラス十年と僕はとらえる。大体戦後の文学は、五十年で分岐点を越えたのではないか。五十年目よりさかのぼる変化の動きもあるし、五十年から後まで持ちこたえたものもあるけれども、大体戦後五十年ということを一つの目安にしたい。それから十年たって今の苦況があると考えたい。
そしてさらに、戦後百年ということを考えるのです。五十年を一つの分かれ目とすると、機械的に百年が次の分かれ目になる。戦後百年のときになって、もう一度、「群像」百周年という雑誌が出るとしますね。そこで、年をとった側の人間として、記念の対談の責任を二分の一負う人はあなたなんですよ(笑)。今から戦後百年までは、あと四十年、その時あなたは七十一歳ですね。僕も今やはり七十一歳です。 僕はこの六十年からしばらくすれば死ぬんだけれども、六十周年記念号で僕とあなたとが七十一歳対三十一歳の人間として話したわけで、その縁から、僕の望みをいうと、あと四十年たったら、あなたが七十一歳の人間として、三十一歳の新しい文学者と話してもらいたい。
そのように考えますと、先にもいいましたが、遠からず死ぬ人間には責任のとりようがないけれど、これから四十年の文学というものを具体的に想像する資格もあるし、その責任もあるというのがあなたの年代なんです。僕は文学世代でいえば戦後五十年世代です。あなたは戦後百年と戦後五十年をつなぐ文学世代としてあるわけです。これからの五十年、具体的には四十年ですね。それについてどういう見通しをお持ちですか。
平野 一つに、環境の変化は非常に大きいと思うんです。 大江さんも『さようなら、私の本よ!』では、その問題を扱われていましたけれども、僕はやはり、インターネットの登場は人間のあり方を劇的に変えるんじゃないかという気がしてるんです。実感として、自分自身が、世界に対してひどくちっぽけになっているという感じをみんな持っているんじゃないでしょうか。昔は、たとえば、ちょっと足が速かったりすれば、彼はそのささやかな、愛らしい能力の突出によって、村で一番足が速い人として、共同体の記憶に銘記され得たかもしれない。それは彼のアイデンティティーにとって、決して小さくはない支えになったでしょう。けれども、今はそんな能力には誰も見向きもしない。ちょっと足が速いぐらいで
は、小学校程度では持て囃されるかもしれないけれど、県レヴェル、全国レヴェル、あるいは世界レヴェルで言えば別にどうってことない。そうした中で、一人の人間が他者から存在を銘記されるためには、何か途方もな ような能力を発揮しなければならないのかもしれない。と、同時に、そうした小規模の共同体の中では、見向きもされなかったような能力が、インターネットを通じて、世界のどこかでありがたがられる可能性もある。これは逆に、世界の広大さに対応するほど、自分自身を大きく感じさせるでしょう。言語の相違は、ネット空間をかなり明確に複数の領域に分割していますが、原理的には誰もが世界と直接つながって、世界から情報を受け取り、世界に対して物申したかったことが言えるようになり、地球の裏側の人とも苦もなくコミュニケーションが取れるようになった。これはたとえば、コミュニタリアンが考えるような身体性に拘束された共同体のイメージを破壊するものでしょう。これからの人間は、そうした共同体の言説空間とは別のもっと遥かに広大な言説空間にも同時に所属することになる。
そうしたときに、僕は一つ、『さようなら、私の本よ!』の中で非常におもしろかったのは、「ジュネーヴ」という例の『悪霊』の中の話をお書きになられていた点です。 僕は『悪霊』を読んでいてずっと考えていたのは、ジュネーヴというのは、要するにキリスト教における神のメタなんじゃないかということです。その意思は、結局のところ誰にもわからないし、そもそも存在しているかどうかわからないけれども、それを伝える媒介となる人間、メディアとなる人間がいるわけですね。それが預言者であるか、ピョートル・ヴェルホーヴェンスキイか、ということですけど。
また先ほどの話ですが、ボードレールは「火箭」という彼のノートの中で、「神は、君臨するのに、存在する必要さえもない唯一の存在だ」ということを言っているんです。そういう点ではシモーヌ・ヴェイユと大分距離があるわけですけれども、その発想は、まさしく『悪霊』の中のジュネーヴのようなもので、そうすると、結局あれは、世界革命を起こそうとしている青年たち、世界を変革しようとしている人たちが、極めて伝統的なキリスト教の構造に則って、つまり、ある得体の知れない、存在するかどうかも分からないところから絶対的な伝令が来て、それに従うというかたちをとっているところがミソなわけで、言ってみれば、キリスト教的な信仰観のパロディなんだと思うんです。 『さようなら、私の本よ!』の中でも、ジュネーヴというのは最後まで得体の知れない存在で、むしろ、それを伝えてくる媒介、メディアとしての人間の方が力を持つわけですね。現実的には、メディアこそが創造的に言葉を発していても、キリスト教やユダヤ教の預言者は、より大きな権威の言葉を預かっているに過ぎないわけで、しかもなおかつ、絶対的に権威づけられている存在です。
そうすると、僕はずっと、小説家というのは一種のメディアなんだろうかということを考えていたんです。つまり、何かある世界の現実、あるいはもっと言うなら世界の「真理」というようなものを言葉にして預かっておいて、それを読者に対して語る存在だろうか、と。しかも、実際には「真理」こそはジュネーヴであって、あるのかどうかも分からない、作家自身が捏造したものかもしれないのです。たとえば、日本の自然主義作家が、人間の性について赤裸々に語ったとき、彼らはメディアとして、読者に人間の「真実の姿」を語ったんでしょう。彼らの言葉そのものが、「真理」のような力を有している。そうした役割が、作家に期待された時代はあったと思います。
それは、僕はずっと起源をさかのぼれば、ユダヤ・キリスト教的な預言者というのと、もう一方で、プラトンの『ソクラテスの弁明』のような作品があるんだと思うんです。
『ソクラテスの弁明』に見られる、弟子が、「真理」を説く師が社会から迫害される様について語るというスタイルは、福音書と共通していますが、その意味では、四方田さんが言われるように、プラトンもソクラテスの肩越しに社会を見、語っているんでしょう。 ソクラテスというのは「真理」を説くわけですが、にもかかわらず、裁判では有罪判決が下され、しかも、刑に服する。あの作品は、アテナイ民主政治末期のピュシスとノモスとの矛盾、乖離という主題を、これ以上ないほどドラマチックに描き出していますし、プラトンの政治観の根底にある、なぜ敬愛する師は死ななければならなかったかという非常に人間的な問いが語られた傑作なんだと思います。
そうすると、結局あそこで何が起こっているかというと、ソクラテス本人はご存じの通り、著作を残していませんから、プラトンこそがいわばメディアとして、その決定的な出来事をアテナイ市民に向けて語るわけですね。媒介するわけです。しかし、実際に言葉を発しているのはプラトン本人であって、しかもそこには、堕落しきったポリスの市民に対して、かくあるべしという当為が既に含まれている。これを僕は、小説の一つの原型なんじゃないかと考えるんです。最近例えば高橋源一郎さんや島田雅彦さんといった人たちが、「作家というのは世間で顰蹙を買うようなことをこそ書くべきだ」と主張されていますけど、これは、現代の資本主義社会の常識の側からの「顰蹙」であって、作家はそういう功利主義的な価値体系からこぼれ落ちてしまった人間性をこそ救出し、描くべきだという態度表明なんだと僕は理解しています。そういう意味では、大江さんが今度書かれていた「老人の愚行」ということも、通俗的な言い方になってしまいますが、様々なレヴェルでの社会通念に対する抵抗という意味で、僕なりに強い印象をもって受け止めました。
そうしたときに、作家が、当為とすべき理念と人々との間のメディアであり得る可能性というのは、インターネットの登場により、これからは徐々に弱まっていくのではないかということを考えるんです。かつては、作家たちによって寡占的に語られていた人間の現実だとか、あるいはそこから導き出された当為というものを、今は「一億総表現者時代」なんていわれますけれど、インターネットの世界では、各人が各様に書いて、議論したりしている。言葉と個人との関係は非常に大きなものとなっている。「一億総メディア時代」といっでしょうし、要するに、メディアとしての小説家なんていらない、単に職人的に面白いプロットを紡ぎ出す「プロの作家」がいれば十分だという認識が、かなり悲観的に見ればですが、一般化しつつある気がします。
そうしたときに、それでもなお、作家が社会的な常識に抵抗して、一種の理念を説くとするならば、その言葉は読者にどう伝わり、どう受け容れられていくのか。建築のような一つのプロジェクトにものすごいお金がかかって、ものすごい政治的な能力が発揮される分野では、結局その担い手は、良くも悪くも、今後も一種の選抜を経た人たちに限定されるでしょうけど、小説のように元手のかからない表現分野だと、誰でも直接に参加自由ということになって、作家が一種のメディアであるという旧来的なイメージはもう意味をなさなくなるでしょう。僕はそれが悪いとは思いませんし、作家が権威として振る舞うのは滑稽だと思いますけど、その時に語られなくなる現実、届かなくなる声があることは簡単に想像できます。僕が関心があるのは、ある意味でその語られなくなる現実、届かなくなるであろう声だけなので、それをいかに書き、伝えていくかというのは、今後の課題だと思っています。
大江 今いわれたことと関係づけて、あなたが新しい建築に深い関心を持ってられること、しかも文学の場に残り続けていられることに、僕はとても力強いものを感じます。さて、「メディア」という言葉の僕の受けとめ方をいいますと、三年前にエドワード・サイードという永年の友人が死んでしまい彼の仕事をあらためて全部読む、それから彼の本になっていなかったものの刊行に、ごくわずかながら参加するということをしてきました。その再読したサイードの本のとくに楽しんだものに、日本でも『音楽と社会』という名前で翻訳されたダニエル・バレンボイムとの対話集「Parallels and Paradoxes」があります。「Parallels」 は「似たようなもの、並行するもの」の複数ですが、「Paradox」は「逆説」ですね。それを僕は身につまされる思いもあって読んだのですが、その中で彼が、我々が一冊の本を読むとき、人間の心に起こるものとして何があるかという基本的なことをバレンボイムにしゃべっているんです。 人は、根っからの教師でしたから。
自分たちが一冊の本を取り上げて読んで、何が我々にもたらされるかというと、それは伝えられたことではないと彼はいうんです。
自分の中に何かを呼び起こされるということであって、何かが自分の中にインフォームされる。こちらからいえば生きて動くものを受けとめるということであって、インフォメーションによって我々は自分の心が動き出すことを発見する。あるいは、本を読むことによって、本の内容が、一人の人間の精神として生きて動いているのを発見することですらある、と彼はいうわけです。
すなわち、本を読む水準でいえば、本を読んで私たちが刺激されたり、感動したり、励まされたりするのは何かというと、そこにある死んだ情報が我々に伝わってきて、ある物知りになれたりすることじゃなくて、読んだことによって我々の精神が動き始め、励まされ、加速され、そして強調され、ある動きを起すということだ。それが本を読むことなんだと彼はいうわけです。それが自分たちにとって一番重要なものとして、本を読むという単純な行為の中にある。
僕も、世界に対して発信するということの中心に、情報を伝達するということが確実にあると思います。しかも情報伝達ということの規模が大きくなる、情報を伝達する側の人間が限られるのじゃなくて、あらゆる人間が世界で発信し、あらゆる人がそれを受けとめることができるという点で、情報伝達の方法としての「インターネットが世界を変えた」といわれることに賛成なんです。
さて、その場合に、例えば先ほどの、ソクラテスの死をめぐる情報がある。アテネの政治機構がソクラテスの死を決定して布告するとすれば、それは一つの情報。それに対してプラトンという、もう一つのメディアが、ソクラテスという具体的な例にそくして表現をする。 ソクラテスという人間がこのように動いた、このように生きた、このように死んだということをそこに表現して、それまでの権力のメディアが伝えていたのとは別の次元の表現をしたのが、『ソクラテスの弁明』という作品ですね。
そういうふうにメディアを通じて情報が伝達されるだけというのではなくて、メディアから発信されるものをしっかり読み取る人間が、そこに人間の精神の動きとして動くものを呼び覚まされるかどうかということに、現在までそうであったように、将来の表現、その受けとめ、それから世界を変えるということなどもすべて含まれていくだろうと僕は思います。
その点で、僕は将来についても、文学表現あるいは文字の表現は生き続けるだろうと思う。しかも、それがこれまでと違ったメディア、インターネットという方法で行われるとき、文学の人間がどのように発信するか、また読み手としての僕らがどのように発信を受けとめて、そこに生きた精神の行為として、精神のあり方としての情報を自分たちのものにすることができるかどうかということが、かつてそうであったように、また現在もそうである部分があるように、将来の文学表現とその受けとめにおいても努められなければならないし、行われることになるだろうと考えています。
そのためには、どのようにインターネットという巨大化されたメディアの情報を、精神の動きという生きている存在として、実在として伝達することができるか、あるいは単なるコンピューターが記録するインフォメーションの展示としてそれが終わるか、その二つの道があるだろう。後の方の道だと、アメリカは現に世界国家を文化的にも経済的にも全部一括するような、サイードのいう文化の帝国主義を実現していますが、それがもっと徹底したものとなることもありうる。そうすると、人間の創造性、あるいは人間が一人生きることの意味というか、そういうことの表現と伝達の機能は失われていくだろうと憂えます。そこで、僕らが死んだ後も、そういう生きた精神をインフォームする、伝達する、呼び起こすものとしての文学という、いささか古めかしい考え方が新しい技法で伝え続けられることを祈る、というのが僕の辿りついている態度です。
(初出「群像」 二〇〇六年十月号)
●大江健三郎(Kenzaburo Oe)
1935年愛媛県生まれ。東京大学文学部仏文科卒業。小説家。1958年「飼育」で芥川賞、1967年『万延元年のフットボール』で谷崎潤一郎賞、1973年 『洪水はわが魂に及び』で野間文芸賞、1983年『「雨の木」を聴く女たち』で読売文学賞、『新しい人よ眼ざめよ』で大佛次郎賞、1984年「河馬に噛まれる」で川端康成文学賞、1990年『人生の親戚』で伊藤整文学賞、1994年ノーベル文学賞を受賞する。著書に『個人的な体験』『さようなら、私の本よ!』などがある。