昨年、デビュー25周年を迎えた小説家・平野啓一郎。大きな節目を記念して、これまでの平野作品を自ら振り返るトークイベントを開催しました。
芥川賞を受賞したデビュー作『日蝕』、映像化でも話題になった『空白を満たしなさい』、『マチネの終わりに』、『ある男』、『本心』まで。読者が選んだ印象的な「一節」から、作品のテーマや執筆背景を語りました。まだ平野作品を読んだことのない方に向けて、おすすめの「読む順番」も紹介されています。
平野作品、どこから読む?
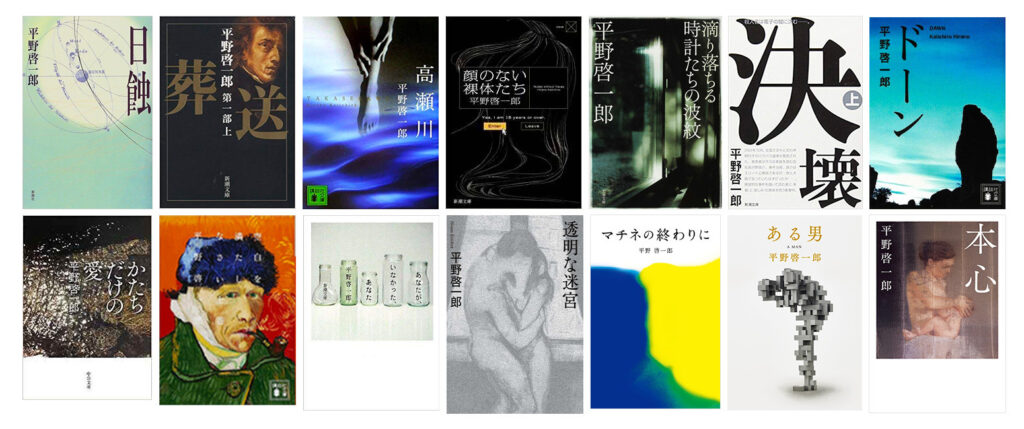
——作家生活25周年を迎えられましたが、お気持ちはいかがでしょうか。
平野啓一郎(以下、平野):デビューが23歳で、小説家生活25年ということは、小説家になる前に生きてきた時間よりも、なってからの人生の方がついに長くなったということで、感慨深いものがありますね。ここまで続けられていることはありがたいことですし、本を読んでくださる方がいることが何よりですから、本当に感謝してます。
——平野作品を読んだことのない方に向けて、まずはどの作品から読むのがおすすめでしょうか?
平野:SNSでも、「どこから読むとよいのか」というつぶやきをよく目にします。多くの人の意見を総合すると、「最近のものから遡って読んでいく」というのが、僕の作品の場合は良いようです。デビュー作の『日蝕』から読み始めようと取り組んでくださる方もいらっしゃいますし、それはそれで嬉しいのですが、やはり今やっていることから遡って読んでもらった方が入りやすいですし、全体の流れを理解しやすいと思います。
──それでは、まずは最近の作品から振り返っていただきたいと思います。
『本心』(2021)
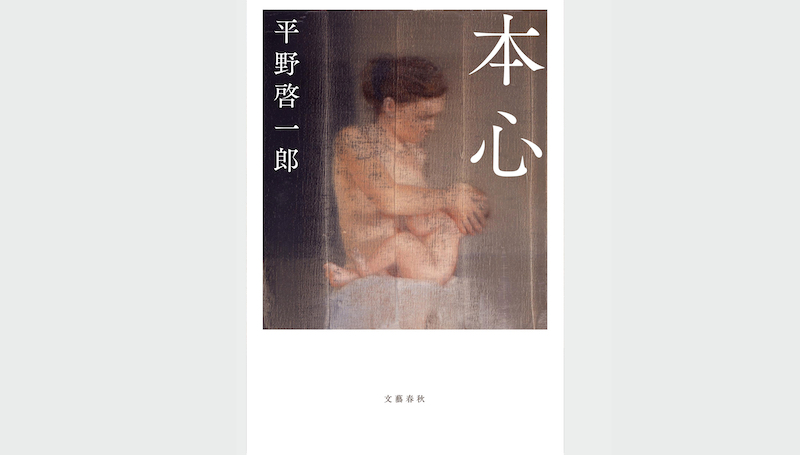
(あらすじ)
舞台は「自由死」が合法化された近未来の日本。最新技術を使い、生前そっくりの母を再生させた息子は、「自由死」を望んだ母の<本心>を探ろうとする。「最愛の人の他者性」を主題に、愛と幸福の真実を問いかける平野文学の到達点。
(引用)
僕は、彼女を愛さない。彼女から愛されることを願わない。ただ、今、僕の命が突然尽きるとして、その〝死の一瞬前〟に、彼女と一緒の自分でいられるならば、僕は、幸福とともに死を迎えられる気がする。つまり、宇宙そのものになることを、喜びのうちに受け容れる、ということだが。
▶︎▶︎▶︎
平野:私たち人間は、職場や家庭、SNSなど、環境や対人関係ごとにいろいろな人格に変化します。それは、中心にいる「本当の自分」が複数の仮面を使い分けているのではなく、複数の自分すべてが「本当の自分」なんだという考え方を、僕は「分人主義」という言葉で提唱しています。そして「分人」のなかには、生きていて心地の良い分人もあれば、非常に不愉快な分人もあって、できるだけ心地のいい分人の比率を高めていくことで、自分の人生が生きやすくなるのではないかと考えています。
この小説の主人公は、亡くなった母が生前に「自由死」を希望していたことを知り、その理由を知ろうとします。「自由死」、そして選んでいただいた一節にある「死の一瞬前」というのも、分人主義から派生したコンセプトです。僕たちは死ぬときも、やはり何らかの「分人」を生きているはずですよね。そうすると、できれば、愛する人に見守られて、死の恐怖を共有してもらいながら、心地のいい分人で死にたいんじゃないかと思います。非常に不愉快な分人で最期を迎えるというのは、嫌だと思うんですよね。
小説のなかの一つの思考実験として、人間が自分の死のタイミングを自由に決められるとしたら、その社会はどうなのかということを考えたかったんです。愛する人に見守られながら死ねるという、死に対する自己決定権を持つことができる一方で、例えば、経済的な理由や周囲からの圧力で、自由死を選ばざるを得ないという問題も出てくると思います。この問題を巡る両義的な可能性について書きました。
『ある男』(2018)
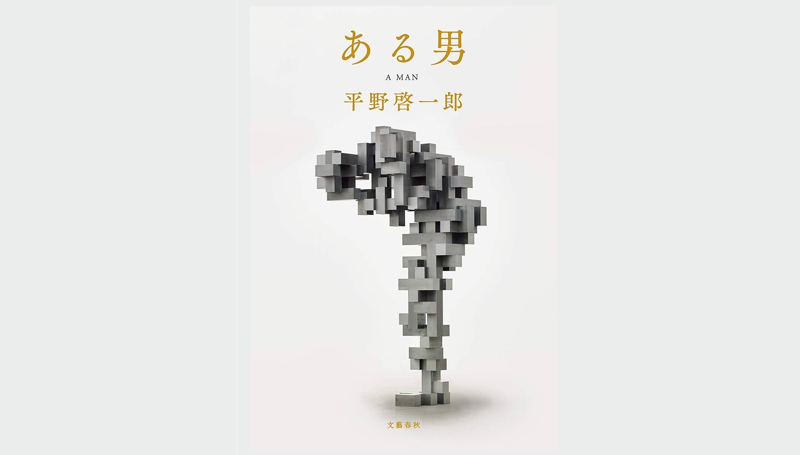
(あらすじ)
弁護士の城戸は、かつての依頼者里枝から、亡くなった夫「大祐」が実は全くの別人だったという奇妙な相談を受ける。調査を始めた城戸は、次第に明かされる謎の男への共感から、自らのアイデンティティを激しく揺さぶられてゆく。
(引用)
大祐の打ち明け話を、里枝は途中で口を挟むことなく、最後まで黙って聴いた。彼がこんな辺鄙な町に辿り着いて、よりにもよって林業のような危険な重労働に携わり、休日は独り絵を描いて過ごし、半年以上もかけてようやく、自分に「友達になっていただけませんか。」と告げたその心中を想像した。
▶︎▶︎▶︎
前作の『マチネの終わり』では、天才ギタリストと国際ジャーナリストという、私たちの日常から少し遠いような登場人物を書きましたから、次の作品では、ごく普通の身近な人物を書こうと思い、地方都市で生活している里枝という女性を中心に、人物設定をしました。彼女が愛していたはずの夫「大祐」が、事故によって亡くなったあと、名前もわからない全くの別人だったことが発覚します。
この小説は、「普通とは何か?」ということが重要なテーマになっています。「親ガチャ」という言葉もあるように、自分では生まれる環境を選ぶことができません。過酷な条件の下で育ち、劣等感や生きづらさを抱える人は特に、「普通」であることに憧れを持つと思います。ただ、「普通」には両義的な意味があり、そこに帰属できることで安心できる一方で、標準的な価値を押し付けて、一定の人を排除してしまう働きもある。この作品では、在日朝鮮人の差別問題を含めて書くことで、重層的な物語にしました。
選んでいただいた場面は、二人の不器用で訥々(とつとつ)とした会話なんですが、そこに相手の良さが表れていることを感じ取り、じきに深い仲になっていくという箇所の一節です。社会の優しさが失われつつあるような時代にあって、それでも人としての誠実さや優しさはどうあり得るのかを、文学的に書きたかったんです。
『マチネの終わりに』(2016)

(あらすじ)
天才ギタリスト蒔野聡史とジャーナリスト小峰陽子との愛と孤独を書いた長編小説。イラク戦争、難民問題、リーマン・ショック、東日本大震災、2000年代後半から10年代初頭にかけての世界的な事件を背景に、芸術と生活、父と娘、グローバリズム、生と死など、現代的テーマが重層的に描かれる。
(読者が選んだ一節)
「世界に意味が満ちるためには、事物がただ、自分のためだけに存在するのでは不十分なのだと、蒔野は知った。彼とてこの歳に至るまで、それなりの数の愛を経験してはいたものの、そんな思いを抱いたことは一度もなかった。洋子との関係は、一つの発見だった。この世界は、自分と同時に、自分の愛する者のためにも存在していなければならない。」
▶︎▶︎▶︎
平野:この小説を書いた時期は、日本の政治的な状況も含めて、日々のニュースにうんざりさせられて、精神的に疲弊していました。この世の中のいろいろなことを、つかの間でも忘れさせてくれるような、美しい物語を読みたい、そんな気持ちが高まっていたんです。ただ、僕の精神状態にフィットする作品がなかったので、自分で書いたんです(笑)。
選んでいただいた一節で伝えようとしたのは、抱擁し合うときの官能的な情熱よりも、「話が合う」という一見単純なことが、愛し合う上で一番重要なのではないかということです。この小説の主人公たちは、二人で話した時間がとにかく楽しかった、という思い出を共有し、互いに惹かれ合うことになります。
人間は経験したことを抱えているだけではなく、人に話して共感したくなる。これは人間の根源的な欲求だと思います。例えば子供って、何か発見したりした時に、自分だけの胸に秘めておくということはできなくて、「見て見て!」と、大人に見せようとしますよね。それはおそらく、SNSで今日起きたことをシェアしたくなるのとつながっているんじゃないかと思います。
そして、単に綺麗な花とかではない、もっと複雑なことになると、誰に言っても通じるわけじゃない。「あの人にこそ聞いてもらいたい」という話ってありますよね。そういう人が恋愛の相手であれば、この世界を幸福に生きていけるんじゃないかと思います。何を見ても、何を感じても、あとであの人に話したいと思える。逆に別離の悲しみは、その話を共有する相手がいなくなってしまうことではないかと思います。
『空白を満たしなさい』(2012)

(あらすじ)
ある日勤務先の会議室で目覚めた土屋徹生は、自分が3年前に自殺したことを知らされる。しかし、愛する妻と幼い息子に恵まれ、新商品の開発に情熱を注いでいた当時の自分に自殺する理由など考えられないとし、実は自分はころされたのではないかと疑問を持ち、事実を追っていく物語。
(引用)
「見守る、でいいんじゃないかな?いやな自分になってしまった時には、他のまっとうな自分を通じて、静かに見守れば。消そうとしても、やっぱり、深いところで色んなことが絡み合ってるんだよ、多分。また絶望的な分人が生じて、それが勝手に走り出しそうになった時には、俺と一緒にいる時の今の徹生君になって、まあ、そう考えずにって、腕でも摑んで引っ張り戻せばいいよ。──」
▶︎▶︎▶︎
この作品は、僕が36歳のときに書いた小説です。僕の父親は36歳で病気で亡くなり、その年齢を迎えることが、ずっと一種の恐怖でした。親より長生きする感覚がうまく想像できず、遺伝的な要因で自分も親の享年で死ぬのではないか、という不安感があった。そのため、父親の死を自分なりに文学的な主題にして、精神的に克服したいという気持ちがありました。
一方で、リーマン・ショック以降、年間3万人近くが自死し、特に若い人の自死は深刻な社会問題でした。僕の周りでも自死してしまった人が何人かいて、その問題——人が自死に至ってしまうメカニズム──を考えたいと思い、『ドーン』で考え出した分人という考え方を、内面的に深化させて書いた作品です。
自殺は自分自身に対する全否定的な感情です。自分は統合された存在、一個人だと認識すると、自分を否定する気持ちになったときに、自分の全部が嫌いになる懸念があります。一方で、現実世界で人間は分人化して、いくつもの自分を生きていると認識すれば、本当に辛い自分は、いくつもの分人の中の一つに過ぎないんだと思える。そのような相対的な視点が得られれば、最悪の手段を選ばずに、生を持続させていく具体的な方法を見出すことができるのではないかと考えました。
選んでいただいた一節は、嫌な自分を無理に消そうとするのではなく、自分が生きていて心地良い分人を通じて、その嫌な分人を「見守る」ぐらいの形でいいんじゃないかと、考え方を示しています。分人については『私とは何か 「個人」から「分人へ」』という新書で詳しく説明しています。
『ドーン』(2009)
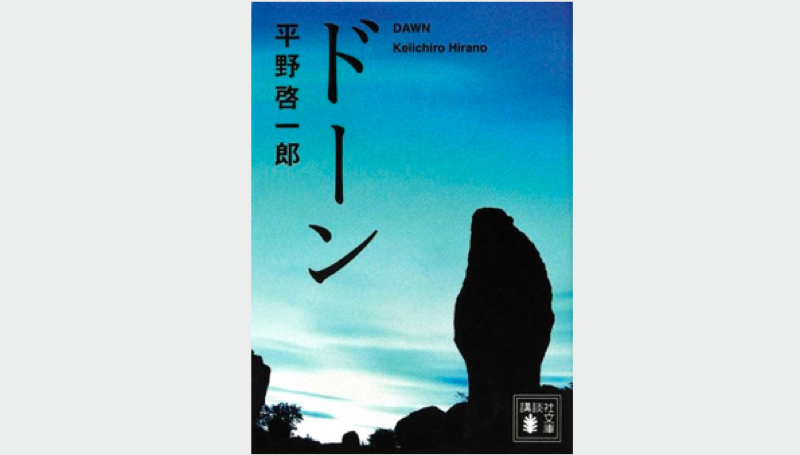
(あらすじ)
2036年のアメリカを舞台に人類初の有人火星探査に成功した英雄的クルーたちが、ミッション中に起きた「とある出来事」のために、熾烈なアメリカ大統領選に巻き込まれていく壮大な物語。顔認証技術と組み合わされた防犯カメラネットワーク「散影」など、現実的/哲学的な未来予測の数々が注目された作品。
(引用)
船体に亀裂が走った時に、そこを叩いて壊そうとする馬鹿はいない。しかし、人間関係の場合、必ずしもそうした抑制が利くわけではない。分かっていて、亀裂をさらに広げようとするかのような言動をつい取ってしまうのが人間だ。
▶︎▶︎▶︎
イラク戦争以降、日本は安全保障の分野でアメリカとの一体化が急激に進み、2000年代からは完全にアメリカ一辺倒の安全保障政策になったため、米大統領選のゆくえが日本人の国際的な立場にも直結してしまうようになりました。その影響の大きさから、米大統領選を文学作品として取り上げました。
また、平行して宇宙飛行、有人火星探査を舞台にしています。火星探査は行って帰ってくるまでに、地球と火星の周回軌道の関係で大体3年ぐらいかかるそうです。船体の閉鎖空間の中にクルー6人を3年間も閉じ込めておいて、精神が持つのかを考えると、多くの人はもたないと直感的に思うのではないでしょうか。
一節は、主人公のボスであるNASAの高官が、諭すように話す場面です。宇宙船はここではメタファーですが、同じクルーとずっと一つの人格を生き続けることが苦しいんじゃないかと僕は考えました。人間は、会社ではこういう人格を生きているけど、一歩、会社を出て別の人といると、別の人格を生きることができる。この小説を書くことで、複数の人格を生きるバランスの中で、人間は精神を保っているのではないかと考えるようになり、分人主義という思想に至りました。
『日蝕』(1998)
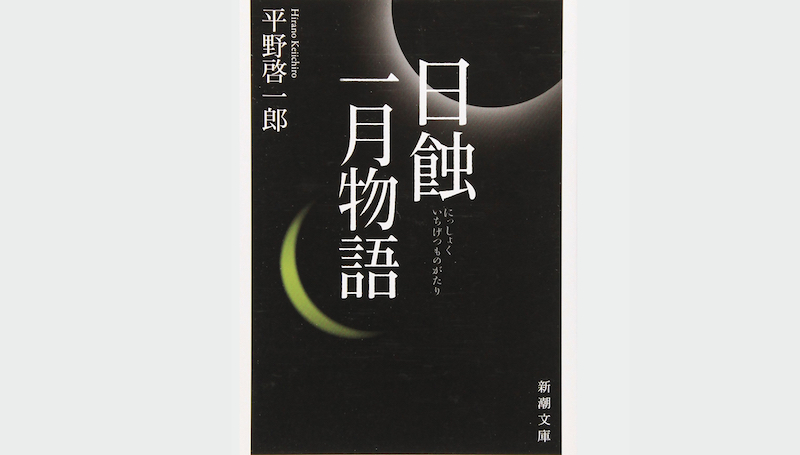
(あらすじ)
15世紀末、ペストの流行によって荒廃した南フランスの小さな村を舞台に、旅の途上の若き学僧の聖性体験を、華麗な文体で描き出し文壇に衝撃を与えたデビュー作。錬金術の作業過程と魔女裁判とが原始的に交錯する重層的な構造で、クライマックスの焚刑の場面は圧巻。累計48万部のベストセラーとなった。
(引用)
私の息は少しく荒かった。先に通った広い径から、再度狭路に入ってより、既に久しく歩いている。低い天井を伝わる水は絶えず私の頭皮を濡らし、地下川の細流は足下を濡らしている。深閑とした洞内には、石より溜る雫の音が、鼓動の如く、規則的に響いている。汗が冷め、私は俄かに悪寒を覚えた。
▶︎▶︎▶︎
90年代、世紀末の閉塞感が世界を覆うなかで、僕は厭世的になるのではなく、世界を価値化するような思考を求め、解放されたいという感情を非常に強く持っていました。当時大学の思想史を受講し、エリアーデの宗教史・歴史哲学、更に『中世思想原典集成』を読みながら、中世のキリスト教の神秘主義に関心が向いていきました。
錬金術は、その作業プロセスの体験が非常に重要で、目的論のプロセスに介入して、それを促進させ、単なる石ころを金のような存在にさせる技術で、時間の流れに介入することができる知的な体験と説明されています。賢者の石を使って錬金術を行えば、石が金になるように、無価値な世界を価値化することによって現実を肯定していく、それが当時、つまらない世の中をどう生きていこうかと思っていた僕の心にも非常に響いたところがあり、『日蝕』の創作に至りました。
デビュー作は、さすがに今の自分からは少し距離があります。文体のせいもあって、老成した作品のように見られるところもありましたが、若くないと書けなかった作品だと思いますね。
▶︎▶︎▶︎
──時間の都合上、すべての作品に触れることはできませんでしたが、デビュー作から最新作に至るまでの平野作品をざっと振り返ってきました。最後に、平野作品のファンの方、あるいはこれから一冊目を手に取る方に向けて、一言いただけますでしょうか。
平野:僕は読書の魅力に十代で目覚めて、文学が自分の支えになってくれました。読み出したらのめり込んで、自分の精神が保たれていくというプロセスは、『ある男』で悠人という少年の体験としても書きました。
本の良いところは、誰にも強制されないところです。本人が読みたい気持ちが少しでもないと、絶対に読まない。小説家も、読者に本を読む選択の自由があるからこそ、自由にものを書けると思っています。
今日お話を聞いていただいて、もし、ちょっと読んでみようかなって気になった方がいらっしゃれば、手にとっていただければ幸いです。本日は長い時間、どうもありがとうございました。
(構成・文:水上純)


