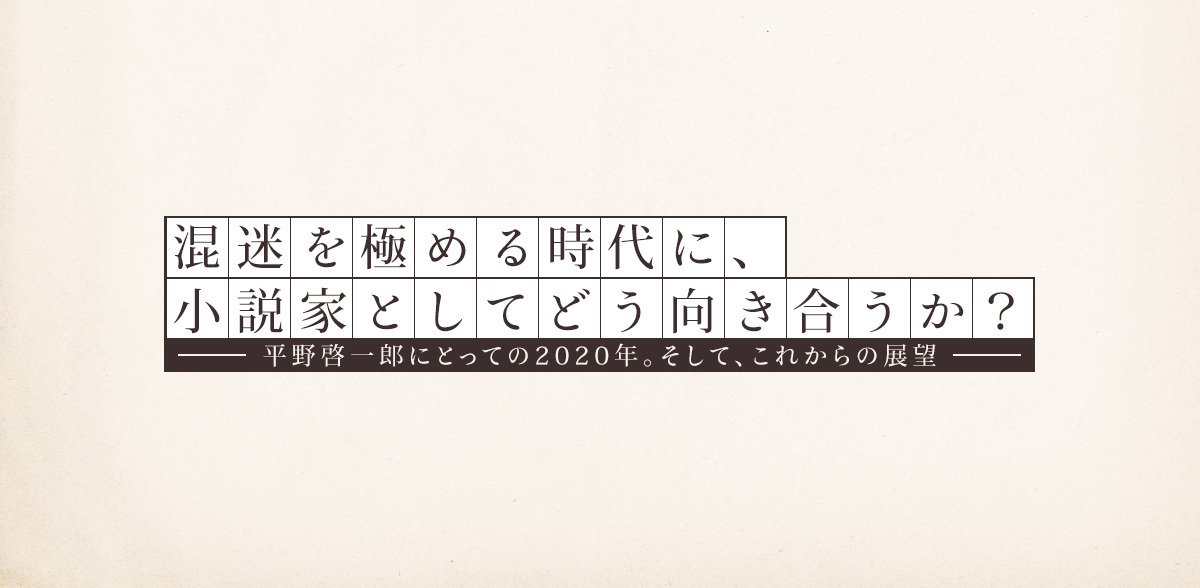平野啓一郎にとって、2020年はかねてから特別な年でした。文学の出発点となった三島由紀夫の没後50年であり、三島由紀夫の享年と同じ45歳を迎えるからです。他方、新型コロナウィルスの感染拡大により、2020年は世界を大きく変える一年となりました。混迷を極める時代に、小説家が果たすべき役割とは何なのか?平野啓一郎にとっての2020年。そして、これからの作家活動の展望について、話を聞きました。
『本心』の連載、そして『三島由紀夫論』の執筆
── 『本心』の新聞連載に、『三島由紀夫論』への着手と、2020年の執筆活動を振り返ってみて、いかがですか?
平野啓一郎(以下、平野):
まず、『本心』の連載が、予定よりもかなり長くなってしまいました。当初は春頃には終わるつもりが、夏まで伸びました。原稿も2ヶ月くらいの余裕をもって始めたはずが、一時は1週間分くらいしか余裕がないところまで追い詰められたりもしました。その度に、挿絵の方に苦労をかけてしまうのですが、菅実花さんには本当にお世話になりました。
その影響もあり、『三島由紀夫論』を三島由紀夫の没後50年である2020年のうちに出版する予定でしたが、叶いませんでした。三島が亡くなった11月に発売される『新潮』の2020年12月号へ、『豊饒の海』論の短期集中連載の第一回を掲載することだけは、なんとか間に合わせました。この連載も、想定より長くなりそうです。
三島を論ずるには、とにかく勉強しなければならないことが多く、考えも深まってきています。『本心』も単行本化に向けて、ゲラの見直しを進めていますが、新聞連載時より、かなりよくなりそうです。どちらも、2021年の晩春か、初夏くらいの刊行を目指しています。
── 『本心』は第4期(後期分人主義)の最後の作品と聞いています。作家として次の段階へと向かうなかで、ご自身の原点である三島由紀夫を改めて掘り下げることに、重要な意味を感じますか?
平野:
そうですね。僕は三島由紀夫という作家に対しては、非常に複雑な思いを抱いています。自分が文学に目覚めたのは三島という作家のおかげですし、三島の『裸体と衣裳』等のエッセイや日記を通じて様々な作家と出会うことができました。
ただ、政治的な立場という意味では、凡そ対極的なところに僕はいます。三島の最後は憲法改正を訴えて市ヶ谷で割腹自殺するわけですが、その彼の主張と僕の現在の主張は、全く反対です。
彼の文学に対する共感を通じて、三島由紀夫という作家がなぜあの最後に至ったのかを整理して考えたい気持ちが、常に自分の中にありました。そして、三島が亡くなった年齢に自分が達した時、本格的に取り組もうと以前から決めていました。
これまでに『豊饒の海』を何度も読んでいますが、今改めて読み返すと、若い頃には感じなかったものを感じます。同じ40代の肉体を持つことで感じとれることもあるし、作家として20年以上活動を続けるなかで共感できるようになったこともあります。三島由紀夫について考えることは、僕自身が小説家としてこれからどうありたいかを考える上で、確実に大きな意味を持っています。
想像以上の反響に驚いた『A MAN』
── また、2020年は『ある男』の英訳版『A MAN』が発売となり、アメリカ・デビューを果たしました。Amazonのレビュー数が2,500を超えるなど、大きな反響を得ています。
平野:
率直に嬉しいですね。これまでも様々な言語に翻訳し、海外の読者に作品を届けてきましたが、英語圏の読者にも届けることができました。出版元であるAmazon Crossingも、僕の作品を気に入ってくれて、プロモーションに力を入れてくれています。
── ご自身としては、アメリカの読者に受け入れられている理由を、どのように捉えていますか?
平野:
『A MAN』では、在日朝鮮人や戸籍ロンダリングなど、出自と差別の問題について書いていますが、Black Lives Matter運動を見てもわかるように、近年のアメリカでは問題が深刻化しています。そういう社会情勢も背景にあり、共感してもらえた部分もあるのではないでしょうか。
また、対人関係や場所によって、登場人物の人格を描き分けるスタイルに新鮮さを感じてとってくれた人も多いようです。
小説は文字だけで情報を伝えるため、読者に混乱をもたらさないために、登場人物の性格や振る舞いを、ある程度、固定化させることが一般的です。ですが、僕は「分人主義」の考えのもと、ひとりの人間が複数の分人を生きている姿を描いたほうが、生きた人間を描けると考えています。
『マチネの終わりに』でも、蒔野といる時の洋子と、リチャードといる時の洋子、イラクにいる時の洋子では、違う分人を描き分けるように意識しました。それによって洋子という人間がわかりづらくなったと言われることはなく、ひとりの人間としてリアルに描かれていると多くの読者から評価されました。この考えは僕が大切にしていることなので、その描き方が新鮮と海外で好意的に受け止めてもらえるのは、喜ばしいことでした。
── 『A MAN』のレビューを見ると、翻訳が素晴らしいという内容も多くありました。
平野:
そうですね。イーライ・K・P・ウィリアムさんが本当にいい仕事をしてくれました。
『A MAN』の英訳は何人かの翻訳者に一部だけ試訳してもらい、結果としてイーライさんにお願いすることになりました。その際に、谷崎潤一郎の英訳をしているアンソニー・チェンバースさんが、イーライさんの試訳について、「すごくクリエイティブに翻訳上の問題を解決していて、とても良い訳だ」とおっしゃっていました。チェンバースさんは翻訳にとても厳しい人だから、「これはいいお墨付きを得た」と僕も喜んでいたんです。
── 2021年4月に『マチネの終わりに』の英訳版『At the End of the Matinee』も発売となります。
平野:
はい。こちらの翻訳はジュリエット・カーペンターさんに担当してもらっています。ジュリエットさんは、何冊もの日本文学の英訳をされている翻訳者で、僕の知り合いの日本文学研究者のアメリカ人たちも、こぞって太鼓判を押すような人です。出版元であるAmazon Crossingも、是非彼女にお願いしたいということで決まりました。『At the End of the Matinee』も、海外の読者にどのように読まれるかが楽しみです。
新型コロナウイルスが作家活動に与えた影響
── 2020年は、新型コロナウィルスの感染拡大により、様々な変化を強いられる一年でした。平野さんの作家活動には、どのような影響をもたらしていますか?
平野:
新型コロナウィルスは後遺症として、記憶障害や集中力の低下など、思考力に影響を与えることが報じられています。僕のような職業にとって、それは深刻なことなので、感染してはいけないという恐怖が常にありました。
とはいえ、完全に外界と遮断することもできません。子どももいますし、家の中にずっと閉じこもっているのは精神的にも肉体的にも良くはありません。だから、感染対策を徹底しつつも、どこかピリピリとした緊張状態の中で、毎日を過ごしていたように思います。
もともと僕はメンタルは強い方ですが、年末に近づくにつれて、何となく体調が優れなくなり、気づかないうちに蓄積されているものがあると感じました。それで、増えてしまった体重を落とし、今はだいぶ落ち着くことができました。
今後、感染拡大が治っても、後遺症の問題があるとすると、後遺症に苦しむ人を多く抱えた社会が訪れます。新型コロナウィルスがもたらす影響は、10年くらい続くのではないでしょうか。
── 外出自粛でリモートワークが社会に浸透していく中で、平野さんもオンラインでトークイベントを開催したりと、新しい取り組みもはじめました。
平野:
そうですね。講演会などのイベントが中止となって、読者の方と会う機会がなくなってしまったので、何か代わりになるものができないかと思い、オンラインでのトークイベントを実験的にはじめました。また、オンラインでは国境を超えた対話もできるので、外国に住む作家や研究者と対談したり、海外の文芸フェスに登壇することもはじめました。
オンラインの良いところは、住んでいる地域に関係なく参加できることです。僕も地元は北九州で、美術展やコンサートがやってこないことに、いつも飢餓感を感じていました。オンラインで開催することで、「はじめて講演会に参加することができました」という地方に住む読者の声を聞き、この感覚を忘れてしまっていたことを素直に反省しましたね。
同時代を生きる作家として、未来の展望を語りたい
── 新型コロナウイルスの感染拡大や、気候変動による自然災害の増加など、先行きの見えない社会に不安を抱える人が増えているように思います。これからの作家人生において、平野さんが小説家として果たしていきたいと考えていることはありますか?
平野:
僕自身にとって文学とは何かを考えると、「自分は文学のおかげで救われた」ということを強く思い返します。
僕は三島由紀夫の『金閣寺』から文学を読み始めましたが、その時の僕の感動のひとつは、文体でした。煌びやかでレトリカルで、「日本語にはこういう言葉があるのか」と驚きました。同時に、主人公が暗いとところがまた良かった(笑)。自分が教室の中で感じている孤独と重なりました。暗い心情を、非常に煌びやかな文体で描く、そのコントラストに心を打たれました。
僕はその後、トーマス・マンも好きになりましたが、自分がウジウジと悩んでいたことと、ノーベル賞作家が感じていたことは、同じだったんだと思った瞬間、それは個人的なものとして放っておかれるべきものではなくて、共有されるべきものなんだと感じられるようになりました。
僕は、読者と同時代を生きている作家です。同時代を生きる読者が感じる不安や孤独の受け止め先として、自分の作品が読まれたらと思って、これまで小説を書いてきました。そして、その想いはこれからも変わることはありません。
分人主義の考えも、個人という概念でアイデンティティを捉えることに生きづらさを感じる人への、僕なりの提案として書いてきました。小説家として、ますます混迷する時代に向き合い、未来の展望を語るような作品を書いていきたいと考えています。
── 第5期として、これから平野さんがどのようなテーマで作品を書くのかが楽しみなのですが、既に構想は決まっているのでしょか?
平野:
持続可能性という言葉を目にする機会が増えましたが、地球や人類がどうサバイブしていくかを真剣に考えないといけない状況に達していると思います。特に、地球環境においては、毎年、世界のどこかで大規模な自然災害が発生していて、日本でも夏から秋にかけて大きな水害に見舞われています。
政治も混乱していて、なかなか事態が好転しないなかで、冷静に考えると悲観的な未来しか思い浮かびませんが、そういう時代に作家として何を書くべきかをすごく考えています。
アイデアは既にいくつか出来上がっていて、2021年の後半は、それらを試す意味で短編小説の執筆に取り掛かるつもりです。第1期(ロマン主義三部作)が終わった後もそうでしたし、第4期(後期分人主義)に入る時もそうでしたが、短編を書くことで、次の長編で書くべきものが見えてきます。
今を生きる読者の声を聞く『文学の森』
── 最後の質問です。2021年は、オンラインで読者の方々と作品について語りあう『文学の森』という新しい取り組みも開始すると聞きました。その背景を教えてもらえますか?
平野:
僕にとって、読者の声を知ることは非常に重要です。商品の売り手として、買い手がどう思っているかを知るマーケティング的な意味合いではなく、読者の声は今を生きている人々の生々しい声なんです。好評であれ、不評であれ、自分の本がどう読まれているかを知ることは、今の時代とは何かを考えるうえで、とても大きな意味を持っています。
そう考えた時に、Amazonレビューのような自由な書き込みができる場で、読者の声を知ることも大切ですが、僕の作品を読み続けてくれている読者だから感じたことも知りたいと思うようになりました。そして、オンラインを活用すれば、それが実現できます。
同時に、昨年からオンラインイベントを開催したことで、読者の方がとても喜んでくれていることを感じました。僕自身、様々な地域に住む読者と接することに価値を感じています。そういった経験も重なり、オンラインで読者と双方向につながることのできる場をつくることは、重要かもしれないと思うようになりました。
『文学の森』で具体的にどんな活動をするかの構想はまだ固まっていませんが、せっかくなので、文学を通じて、参加者同士がつながっていくような場になればとも考えています。
文学好きな人に話を聞くと、日常的に文学について語れる仲間が身の回りにいないとよく聞きます。僕自身、北九州で中学生時代を過ごしている頃、クラスに40人くらいの生徒がいても、三島由紀夫を読んで「いいなぁ」と思っているのは僕くらいなものでした。そして文学の世界にのめり込めば、のめり込むほど、孤独が深まる感じがありました。
でも、作家になって、様々な国の作家と接したり、研究者と話したりしていると、そういう経験をした人が、実は世界中にたくさんいることがわかりました。そして、ドストエフスキーを読んだとか、バルザックを読んだとか、違う国で育った人間にも関わらず、共通の話題に事欠かないで話をすることができます。そうすると同じ地元で育った友達よりも、遙かに仲の良い友達が外国の見知らぬ土地にいた、という発見になるわけです。
文学とは、そういう人と人を繋ぐ媒介にもなりえると思います。『文学の森』が、どういう場に育っていくか、僕自身、楽しみにしています。
(聞き手・ライティング:井手桂司)